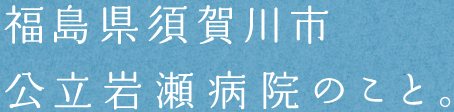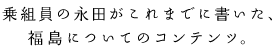![]()
「このまちは無駄には人を死なせない。」
「安全というのは、科学的な根拠で示すこと。
安心というのは、自分たちの心でつくること。」
公立岩瀬病院の三浦純一院長は、
震災後の活動をとおして、
多くの理念、ポリシーを、
自分のことばとして獲得してきた。
三浦院長は、震災の直後、
須賀川市にローカルな情報が
行き渡っていないことを問題視し、
須賀川市内のホテルと
引っ越したばかりの新しい病棟をつかって
臨時のFMラジオ局を開設する。
 後日、新しい建物にも放送の設備が整えられた。
後日、新しい建物にも放送の設備が整えられた。非常時だからこそ必要とされたラジオ局だけれど、
非常時だからこそ、手続きや機材の調達がむずかしい。
けれども、須賀川市民の持ち前の
「自分たちでなんとかする」精神によって、
驚くべき速やかさでそれは達成された。
「一般のメディアから必要な情報が
流れてこないものですから、
自分たちでラジオ局をつくることにしました。
じつは、この院長室をつかったんですよ。
私がラジオをやろうと提案すると、
いろんな人たちが協力してくださいました。
その連携の速度はすばらしいものでした。
まず、須賀川商工会議所の青年部が、
群馬県の館林市から発信機を調達してくれました。
開設にあたってボランティアを募集したところ、
商店の人やお世話になっている会社の役員の方など、
たくさんの人が参加してくださいました。
また、電波を飛ばすために、
震災後、営業していなかったホテルの
屋上にアンテナを立て、10階のフロア全体を
放送局としてつかわせてもらいました。
エレベーターが動かない状態でしたから、
みんなで階段をのぼって、機材を上げました。
アンテナの設置は、須賀川市の消防署の
通信司令室の人が指導し、
そのまま放送局長となってくれました。
公共の電波として流すわけですから、
さまざまな手続きが必要なんですけど、
須賀川市長が総務省に直接電話を入れてくれて、
それですぐに放送の許可がおりたんです。」
 ラジオ局の開設をはじめ、三浦院長の震災後の活動をバックアップしてきた
ラジオ局の開設をはじめ、三浦院長の震災後の活動をバックアップしてきた
須賀川市の秋山さん(左)と関根さん(中央)。
「すかがわさいがいFM」と名づけられた
そのラジオ局は震災後2ヵ月にわたって
24時間体制の放送を続け、
須賀川市民に多くの情報を提供する。
公立岩瀬病院は「病院ラジオ」という番組を受け持った。
そして、その放送のなかにも、
三浦院長のはっきりとしたポリシーが
打ち出されることとなった。
「病院からのお知らせや、被ばく対策など、
自分たちで企画して、いろんな放送をしました。
その場、その場で、内容を考えて、
どんどん放送していったんですが、
ひとつだけポリシーがあって、
それは『批判しない』ということでした。
国を批判しない。東電を批判しない。
したくなるんですよ、正直。
でも、批判しない。そう決めました。
それは、ルールとして定めたというよりも、
私がお願いした、という感じです。
いろいろ思うことはあるでしょうけど、
批判はしないでくださいね、と。
難しいんですけどね。」
批判しない、というポリシーは、
論争に巻き込まれたくないから、という
事なかれ主義から提案されたものではなかった。
三浦院長は、背景をこんなふうに説明してくださった。
「たくさんの人が協力しなければならない、
というときに、やっぱり、
『心』が大事になってくると思うんです。
でも、人は、生まれも育ちもDNAも違うから、
心をひとつにすることは
なかなかできないと思うんです。
でも、心をひとつにすることはできなくても、
『こころざし』というか、
『心のベクトル』は合わせることが
できるんじゃないかなと思ったんです。
それには、『批判しない』ことが大切だと思いました。
そうすると、ベクトルをつくりやすくなる。
たしかに、ああいう状況でしたから、
批判したくはなります。
でも、それを抑えて、いまできること、
自分たちにできることに集中する。
そうすることによって、
『心のベクトル』がそろっていくんじゃないかと。
逆に、なにかを批判をすることで団結する、
という方法もあるのかもしれないけど、
自分には、そういうやり方は合わないですね。」
それは、震災があったからというより、
もともと三浦院長が心の真ん中に置いている
ポリシーのように思えた。
思えば、長くうかがっているお話の中にも、
批判めいた性質のことばはまったくなかった。
批判しない、というのは、
三浦院長の根本的なスタンスに思えますが、
それは、考えた末にたどり着いたものですか、
それとも自然とそういうふうに
物事をとらえるようになったのですか、と訊くと、
思いがけないことばが返ってきた。
「癌の患者さんと、
ずっと付き合ってるからじゃないですかね。」

「きつい言い方になりますが、
絶対助からない人って、います。
その人たちと、ずっと会話するんですよ。
で、医師の役割って、最後に、その人に、
『ご臨終です』って言うんですけど、
そのときは、もう、
その人は亡くなってるんで、意識もない。
でも、その最後の会話まで付き合うんですね。
誰が悪いわけじゃないんですよね。
本人が悪いわけじゃない。
でも、そういうことになってしまった。
誰が悪いというわけじゃないのに、
病気になって、死んでいく。
そこで誰も批判できないからこそ、
その亡くなる人が出るたびに、
自分の技術がもっとあれば、とか、
心のケアももっとしておかなければ、とか、
人を治すことと向き合って
自分を積み重ねていくことができるんです。
そういう経験をずっとしてきたので、
批判することに意味を感じなくなってきたというか。
何十年も、そういうふうにやってきましたから、
今回の震災でも、変えられないんでしょうね。
その人が、病気になったときに必要なのは、
誰かを批判することじゃなくて、やっぱり、
『治してほしい』ということだと思うんですよね。」
でもね‥‥と三浦院長は言って、
同じ自分を、違う視線から語りはじめる。
それもまた、切実な「自分」だ。
「ほんとに絶対助からない人が、亡くなると、
私の心もダメージが大きいんですよ。
30年、外科医をやっていると、
そういうことが何度もあります。
たとえば、消化器外科で
自分が手術をした患者さんが、
経過がよくて、よろこんで帰ります。
でも、5年後に転移して、再発して来ることがある。
そのとき、言われることばあります。
『私、これで死ぬんですか?』って。
訊かれて、そうなる可能性が高いとわかっても、
それは、言えません。
『努力をさせてください』
と言うしか、なかったりします。
そのとき、以前の自分の手術がどうだったかは、
じつははかなり記憶に残ってます。
この人は、リンパ節が腫れてて、
手術で完全に取ったけど、ひょっとしたら、
その奥にあったのかなぁ、とか、
どうしても、考えます。
そういう気持ちが、つぎの人を看るときに
活きたりもします。
もう、同じ思いはさせたくないから。
そういうふうにして、経験を重ねるごとに、
手術の技術って上がっていくわけです。
誰も批判してない。責任は自分にある。
ひとつひとつ、重ねていく。
そうすると、自分だけじゃ医者はできないな、
っていうのが、だんだんわかってくる。
いろんな人に関わってもらって、
ひとりの患者さんに、精一杯のサービスを提供する。
そういうことをやるんだよって、自分に言う。
しっかり生きる術を、みんなで磨いていく。」
三浦院長のことばは、さらに広がる。
提示されるコンセプトは、さらに大きくなる。
「人は、死にます。
どうせ死ぬんですから、それまでのあいだ、
心豊かに生きられるかどうか、ですよね。
つまり、『クオリティ・オブ・デス』だと
私は思っています。
『クオリティ・オブ・ライフ』じゃなくて、
『クオリティ・オブ・デス』、
『いかに死んでいくか』、だと思うんですよ。
終わりに向けて、自分がどういうふうに生きていくか。
あなたは、ずーっと批判して、死ぬんですか?
って、問いかけられたらどうするか、ですよね。
批判をすると、いっときは人が集まってくる。
でも、集まる人は限定されてしまう。
自分の『クオリティ・オブ・デス』を考えたら、
批判なんかしてられないですね。
だって、あさって死ぬかもしれないじゃないですか。
病院という場所にいると、そんなふうに思うんです。
今朝まで元気だったんですけど‥‥っていう人がいて、
その人をどうやって助けようか、というのが
自分たちの毎日の仕事ですから。
急に倒れた人がいて、その人の20年後とかを
イメージしながら判断して手術する。
だから、ほんと、批判なんかしてる暇がない。」
2007年6月17日、三浦院長は、
長く追い求めていた自分の理念を
はっきりと、ことばとしてつかんだ。
「このまちは無駄には人を死なせない。」
それは、いまも、自分の
『クオリティ・オブ・デス』に役立っていると
三浦院長は言う。
「理念がことばにできたのは、
震災よりもずっと前ですが、
これがあってほんとうに助かりました。
『このまちは無駄には人を死なせない。』
この理念がことばにできてなかったら、
自分の余裕がどんどんなくなったと思います。
そうすると、ほかの人の苦しさを
受け止められなくなってしまう。
おかしな言い方ですが、私は、
『ごめん、いま俺、忙しい』って
言おうと思えば言える立場にあって、
しかも、実際に、忙しいんです。
だから、自分にいまできることはなんなのか、
つねにしっかり考えてないといけない。
自分をプロデュースしてないといけない。
そういうときに、理念を持っている強みって
ものすごくあると思うんです。
『このまちは無駄には人を死なせない。』
もっとも責任の思い、
命を預かっている仕事ですから、
『無駄には人を死なせない』と思っていたい。
そう思っている人間が、
このまちに、たとえたったひとりでも、
いたほうがいいんじゃないかと思うんです。」
「このまちは無駄には人を死なせない。」
三浦院長がことばにした理念に、
三浦院長自身が助けられている。
なんというか、それは、
ひりひりするようなバランスで、
ようやく成り立っているようにも思えた。
そうしてぼくは、三浦院長にも、やはり尋ねる。
──疲れは、溜まりませんか?
なにしろ、あれから4年が過ぎている。

「‥‥私は、何度も、参ってます。
やっぱり、疲れるというか、体は、壊れますね。
何度も、ひどい頭痛になりました。
休まざるを得ないような状態にも、なります。
私は、自分の体のことですから、
だましだまし、休めることもできますけど、
やっぱり、メンタル面で参ってしまう人も増えてます。
たとえば、役所関連の人たち。病院の職員なんかも。
同じ被災者なんですけど、
窓口に座らなければならない人たち。
タフな上司のもとで働く現場の人たち。
そういった人たちの心に、少しずつ、
ほころびができてきているように思います。
静かに、潜在的に、溜まっている人たちが多い。
あと、親が疲れを溜め込んでいくと、
子どもさんの具合が悪くなるんですね。
そういうふうに、疲れが、社会に対して、
ボディブローみたいに効いてきているんじゃないかと。
だから、震災から時間が経って、
ひとりひとりの市民を助けることは、
みんなで力を合わせて考えてきたんですけど、
『市民を助ける人への支援』が
できてなかったんじゃないかという気がしますね。」
そう、4年が過ぎて、
見えないところに疲れは溜まってきていて、
それは明らかなのに、
該当する人たちは、おそらく声があげづらい。
病院に勤める人たち。
役所の窓口に座る人たち。
相談を受ける側の人たち。
揺らがない大人として、子どもたちを教える人たち。
測り続けている人。伝え続けている人。
処理している人。きれいにしている人。
警察の人。消防署の人。
ふつうに誠実に働く人。
お母さん。お父さん。そして、子どもたち。



ぼくは、あれから何度も訪れるようになった福島を
とても広くてきれいな場所だと思っていて、
いろんな話を総合すると、
多くの場所で放射線量は下がってきていて、
お米はすべての袋を検査して
問題がなかったことだって知っている。
けれども、そこで出会う笑顔が
すべてくったくがなく、
なんの混じりけもないかというと、
きっと違うと思う。
笑顔の底にある、
わずかな疲れやひとすじの曇りも、
なんらかの形ですくいとられるべきだと思う。
それもぜんぶ含めたうえで、
いっしょに未来へ向かうべきだと思う。
子どもじみた表現でいえば、
がんばろう、と15回言う合間に1回くらい、
たいへんだよね、と言ってあげたい。
できれば、なるだけ、明るい調子で。
ちょっと友だちをからかうみたいな感じで。
いやぁ、たいへんだよねぇ、と。
それが厳しい現実に
物理的な作用をまったく及ぼさないことは百も承知で。
胸を張って小さな愚痴を聞いてあげたい。
言うまでもなく、福島に限らない。
あれから4年、誰の心にも、疲れが溜まってきている。
ことに、真剣に考え、真摯に向き合って人たちには。
三浦院長は言う。
「疲弊している人たちを助けるために、
簡単で、効果があるのは、話をすること。
ご飯を食べたりして、話を聞いて、
溜まっているものを引き出してあげること。
じつは、『院長』という役割は、
そういうときに役立ったりするんですよ。
つまり、私が聞き役になると、
『院長に言った』っていうことが、
その人の心に、効果があったりするんです。」
そしてここに、吉村先生の名前が出てくる。
吉村順子先生は、鶴見大学文学部の教授であり、
臨床心理士でもあって、
この取材のきっかけとなるメールをくださった方である。
疲労の淵にいた三浦院長の話を、
最初に引き出したのが吉村先生だった。
「震災のあとは、とにかくいまやらなくちゃ、
ということの連続だったので、
むしろ、しのげていたんですけど、
ちょっと落ち着いたころに、
体を壊したり、痩せたりすると、
心が弱るというか、大丈夫かなって思うんですね。
自分の将来に、少し恐怖を感じるようになってしまう。
ちょうどそういうときに
吉村先生と会って話をして、
ああ、こういう心の開き方があるんだ、
というふうに感じて、ずいぶん助かったんです。
ふつうに食事しながら話すだけでも、
いつの間にかカウンセリングみたいになるんですね。
あの時間がなかったら、
心が前を向かなかったかもしれない。」
たいへんな判断を何度もくだし、
多くのひとたちの不安を取り除いてきた三浦院長でも、
疲れをたっぷり抱えている。
ほぐしながら進めればいいなと思う。
いろんな人のいろんな疲れを、
できれば気軽に、引き出して、ほぐして。
三浦院長は言う。

「ズバッと、なにかが解決できるようなことは、
やっぱりなくて、一歩一歩重ねていくしかない。
正直、投げ出したいときもありますよ。
でも、日々、進めてきた一歩が重なっていくんです。
ものごとは、100件あるとすると、
99件は、厳しい、たいへんなことです。
でも、ひとつくらい、ああよかった、
しあわせだった、みたいなものがある。
その1個を心のポケットの中に入れて、
なるだけ自分の心のポケットを
からにしないで、絶えず、進んで行く。
難しくて、たいへんですけど、
それしかないんじゃないですかね。」
つまり、とぼくは思う。
福島の記事は、じつは、
こうしてまとめるまでに、すごく時間がかかる。
いつも、すいすいとは書き進められない。
かならず、滞る。
そのかわりに、書きながら、ずいぶん自分がわかる。
いつもは、この部分に覆いをかけているのだな、と思う。
2011年3月11日の大震災から4年が過ぎて、
一歩一歩進んでいくしかないのだと、
みんな、もうわかっている。
スーパーヒーローがすべてを
元どおりにしてくれたりはしない。
だから、先を見れば、途方に暮れそうになる。
まだまだこれが続くのか、と思う。
それでも、日々、できることを続けていくしかない。
現場で起こった突発的な困難を
当事者が瞬間の判断や勇気で乗り越えることについては、
離れた地にいるぼくらは、力になることが難しい。
けれども、当事者たちが、当事者として、
続く平坦な日々に感じる徒労に対しては、
たぶん、なにかできることがある。
たとえば、その毎日の風景が、
いつもとほんのちょっと違うというだけで、
歩くときの気分が変わるのではないかと思う。
しょうもない具体例かもしれないが、
一歩一歩、誠実に、確実に、
進まなくてはいけない毎日の現場に、
ある日、「ほぼ日刊イトイ新聞」という
ちょっと変わったメディアが取材に来るだけでも、
行く道に、少し、変化が生じるのではないか。
写真を撮って「へー!」と話をおもしろがるだけで、
その一日がちょっとしたアクセントになるのではないか。
そして、それを、当事者でない誰かに伝えることも、
離れた場所で震災後の仄暗い平坦の連続に
うっすらと疲れる第三者の意識に
なにかしらの波紋を起こすことができるのではないか。
それにはもちろんぼくらに
ある種の強さがなくてはならない。
しっかりと考え、向き合い、身の丈を知って、
ときにおもしろく、うんざりさせないように、
かといって誇張に逃げないように、
心の真ん中にはしっかりと
自分の「たのしみ」を持って、
取り組んでいかなくてはならない。
早野龍五も、友森玲子も、糸井重里も、
そうしていると思う。
ぼくはそれを精一杯、まねしたい。
それだけをやり続けるというのは、
さすがにちょっと無理だけれど、
ときどきは、「よし!」と小さく決意して、
両手をパンと叩いて、出かけたい。
書くことが滞っても、まとめるのがたいへんでも、
行動できる自分でいたいと思う。
さて、三浦院長は、須賀川市の出身ではない。
医大で遺伝子の研究が全盛だったとき、
理論や知識ばかりで
手術の技術がない外科医は自分の理想ではないと感じ、
福島の真ん中にあって交通の便がいいからという理由で、
19年前、それまで一度も訪れたことのない、
須賀川市の公立岩瀬病院に赴任してきた。
臨床の現場で自分の技術を磨き、
外科医としてレベルを上げたあとは、
いつか大学へ戻るイメージも持っていたという。
鼻っ柱の強い自信家の後輩に対して、
医大の先輩たちは
『どうせすぐに帰ってくるよ』と笑ったという。
須賀川の駅に降りたとき、
目の前に広がるありふれた田舎の夕方の風景と
すすぼけた公立岩瀬病院の建物を見て、
「選択を間違ったか‥‥」と
三浦院長の心は折れそうになったそうだ。
しかし、三浦院長は休まず働き、
救急車が来たら、絶対に断らず、
何年も地道に活動して、
地元の方からの信頼を勝ち取った。
いまや、三浦院長と公立岩瀬病院は
須賀川市にとってなくてはならない存在で、
震災を乗り越えた新しい病棟では
若い職員たちが生き生きと働いている。
「このまちは無駄には人を死なせない。」
このまち、というのは、須賀川市のことである。
三浦院長にとって須賀川市は、
いつしか自然と「このまち」になった。
長く時間をいただいた取材の最後に、
「いま、はじめて須賀川の駅を降りた
19年前の自分に、
なにかひとこと声をかけるとしたら
どんなことを言いますか?」と訊くと、
三浦院長はにっこり笑って即答した。
「『よくぞ、ここを選んだ!』と。」
2015年3月 永田泰大

2015-03-27-FRI