『中国の職人』
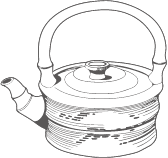 3の巻 周桂珍(紫砂壺・急須)
3の巻 周桂珍(紫砂壺・急須)
録音日 2011年9月20日・21日
録音場所 北京郊外 工房にて
周桂珍師は、1958年に新中国になって出来た宜興の紫砂工廠に入って王寅春と顧景舟両師匠について茶壺作りをおそわった。先に紹介した徐兄弟とは違って全く新しい時代に育った作家である。話を聞いていくとわかるが、顧景舟、徐秀棠、漢棠師とも同じ時期に宜興にいた。それぞれ違った立場から当時を振り返っている。
周師は第5期2006年に中国工芸美術大師に選定されている。定年退職後、茶壺作家である息子夫婦と北京郊外に工房を作って創作に励んでいる。
息子の高振宇さんも顧景舟師に学んだ茶壺作家。高さんの妻の徐徐さんは徐秀棠師の娘。徐、高の一族は中国を代表する茶壺作家である。
工房は北京郊外の住宅街の一郭にある。厳重な門構えで、庭があり、住宅も同じ敷地にある。高さんや徐徐さんとは別に、周師は自分だけの作業室を持っている。
窓の大きな現代的な作業室はシンプルで、作業台と小さな卓上の轆轤、幾つものヘラ類、机の上にBOSEのCDプレイヤーが置いてある。作業台の側には大きな甕があり、仕掛かりの茶壺は甕の中で乾燥しないように保護されている。
クラシックが流れる中で、急須作りをしながら、2日にわたりインタビューに答えてくれた。
国の工芸美術大師達の作品は日本円にして数百万円で取引されるそうだ。時にはオークションで1000万円を超えることもあるとか。業者が値を競ってつり上げるらしい。値を上げることで利益を上げようとする業者も多い。偽物も出て来るほどのブームである。
周師の話を聞こう。

『親は茶館屋』
生まれたのは1943年の旧暦の8月24日。今は新暦だけど、昔の人はみんな旧暦で言ったの。自分の年代の人達は、みんなそうですよ。
旧暦は今でもありますよ。田舎の人は今でも、農作業はみんな旧暦で計算してます。
新暦に換算するのは、毎年違いますけど、私の8月24日は、9月で、仲秋の後でしたね。たまたま、明日、9月21日が今年の私の誕生日です。旧暦の8月24日。68歳になるんです。
生まれた場所は、江蘇省宜興の丁蜀鎮。丁蜀鎮は、昔は数万人しかいなくて、その多くは陶工だったね。陶磁を作ってたんですよ。
私の父の名は周洪根。母は呉根娣。
私は4人兄弟の長女で、下は弟3人です。
父は、お茶屋さんをやってました。お客さんが来て、お茶飲んで行くところ。そこではお芝居をやったり、琵琶を弾きながら謡ったりもするんですよ。みなさんが溜まる場所だったんです。茶館に来るのは、陶工が多かったですね。
茶館の主人っていっても、生活水準は普通。そんなにお金持ちではないです。1949年の新生中国が出来てからは、うちは小商人の扱いだったね。
お祖父ちゃんは、父が11歳の時に亡くなってるんですが、仕事はコックさんだったんです。どっかの弟子に行ったんでしょうね。よくは知りません。
お祖父ちゃんが早く亡くなったから、父はちっちゃい茶館を始めたんです。あの近辺は、お茶がとれて、水も良かったし、陶工たちが休むところがなかったからね。だんだん人が集まって来るようになったので、歌なんかのショーをやるようになったらまた人が集まって来たんです。陶工たちだけでなく、近くの農村から町へ出て来た人達も寄っていくようになりました。うちでちょっと休んで一服してから帰るとか、そこで商談をするとかそういう場になったんですね。
茶館は解放前にやり始めたんですけど、解放後もずっと続いていて、1杯のお茶は紅茶でも緑茶でも0.1元だったんですよ。今で言うと、1角です。饅頭を食べてもらったりしたね。肉まんなんですよ。南の人は、みんな肉まんたくさん食べるからね。肉まんが1個、0.03元。1角の3分の1。紙幣も幾つもあってね、解放して50年代になってから全部新貨幣になって、統一されたんです。
陶工たちは、朝早く来る人もいれば、一仕事してからの人もいるし、窯開けで夕方に来る人もいました。
自分の家で飲まないのは、まず、魔法瓶がないんです。しかも湯を沸かすのも調理もみんな竈ですから、ご飯作る時しか火を起こさないんです。だから、わざわざお湯を沸かすのがもったいないから、ちょっと茶館にお湯を汲みに行くとか、そういう習慣だったんです。
朝、自分の急須を持って出て、途中で朝ご飯を買って来て、お茶飲みながら朝ご飯食べるとか。仕事が終わって帰る時にも、家族のために自分の急須にお湯をいっぱい入れて持って帰るとか、そういう生活の習慣だったんです。
このときの急須は大きいのよ。そう、土瓶ですね。
当時、物価が安くて豆腐も1丁は1分なんですよ。0.01元。豆腐1丁が丁度お茶1杯。土瓶に満杯の湯の値段。
飲茶というのは、広東、広州の習慣だから、このあたりではピーナツとかカボチャの種とかおつまみは出さないね。お茶だけ。朝ご飯買ってきて「おーい、お湯」みたいな感じですよ。
近所は商店街だったんです。この家は豆腐売って、この家は生活用品と小物、あの家はうどんを売ってと、貧しい、小さなお店が並んでたんです
うちのお店には3、40人ぐらい入るんですよ。一つのテーブルに4人座りましたが、8人も来たら、みんなかたまって一緒に飲むんです。
お客さんが入って来たら、ボウルにお湯を入れて、きれいなタオルを持って行くと、顔を洗って、手を拭いて、お茶を飲むんです。それが気持ちいいからみんな来るんです。
その当時は、お湯で顔を洗ったり、お湯を沸かしてもらうということは、一つの贅沢だったの。
テーブルの上に載ってるのは、一人分は急須1個にお茶碗1個。この時の急須は、大きめの急須で、1杯分が1角。
大体、宜興では紅茶飲むんです。宜興の紅茶は、急須で入れると3回飲めるの。4回目となるともう味がなくなっちゃう。ですから、3回飲んで1角なんですよ。そこからはお湯入れてもお金取らないの。
『急須に関心が』
私が紫砂の急須に興味を持つようになったのは、父の茶館でたくさんの急須を見てきたからなんです。普通の工員とかあんまりお金持ってない人達は、お店の急須を使ってお茶飲むんですけど、ちょっと贅沢な人、少しお金持ってる人達は自分の急須持ってうちに来るんですよ。そこで「私の急須は、良く養われてる」とか、磨き上げた艶や輝きを自慢気に見せるんですよ。それで、おまえの急須はこうだ、私のはこうだと、みんな自慢したり評価したりするんですよ。
そういうのをやってたから、紫砂の急須は素敵なものなんだと覚えたんです。
丁度その時期は、自分の師匠になった顧景舟さんも、同じ町で急須作りをしてたんです。でも、顧さんは、茶館に行ってお茶飲んだりはしないの。彼は、とても潔癖性だから、自分の家でお茶を飲む。
お店の中のテーブルは10個ぐらいあって。椅子は長椅子。2人掛けだけど3人座れる。
私のここの作業場(10坪ほど)の倍ぐらい。お店の名前は、「雲記茶館」。父は字も算盤も上手で、商店街で人気者だったんです。志が高い人だったから、自分の名前を「周雲鵬」って変えたんですよ。何でその名前にしたか理由は言わなかったけど、ある日突然、この名前になってしまって。茶館もこの雲という文字を取って「雲記茶館」にしたんです。「記」は、お店の名前によく使われる字です。例えば、「昇竜記食堂」というふうに付けるの。
父は身体が丈夫ではなかったけど、同年代の人達の中では、知識持ってたんですよ。ただ、出世出来なかったから、志を名前に託したんじゃないかと思っています。
私の母は、陶工の家の出なんです。母方のお祖父ちゃんは、大きい甕を作る陶工だったんですよ。母も小ちゃめの瓶を作ったりしていました。
あの時代は、男性は外で働いて、女性は家で働くものでした。家事もやったし、家族全員の着る物とか靴とか作ったもんです。ですから、お店は父が切り盛りしてたの。お手伝いが二人いました。一人雇って、もう一人は父方のお祖母ちゃん。暇だったからお店番をしたりお手伝いをしていたんです。
琵琶法師が謡ったりする場所は、特別に舞台とかないんですよ。入り口に向かって奥の空いてるところで、弾いたり謡ったりしていたんです。
1954年ぐらいからすごい自然災害があって、食料とか全部配給になって、みんなお腹いっぱい食べられなくて、茶館に来るお客さんもすごく減ったんですよ。
それで58年に大躍進運動始まったでしょ。その時は、みんなまた状況良くなって、で、また来てくれるようになりました。
茶館は、58年から60年ぐらいまでは、繁盛してすごく状況良かったんですけど、60年にはまた大自然災害あったんです。食料が全然収穫できなくて、みんなお腹いっぱい食べられないから、もう誰も茶館に来なくなったんです。それで、茶館は60年に閉めたんです。
でも、お湯だけは沸かしてたんですよ。みんなお茶飲みに来なくてもやっぱりお湯とか飲まなくちゃならないから、お湯を1分、0.01元で買いに来てたんです。
まわりは竹で出来てる魔法瓶を持って来るんです。あの頃そういうのができたんですね。
私の記憶では、魔法瓶の値段が1個0.6元だったわ。その時、うちはお金の余裕が全然なかったけど、節約して節約してやっと魔法瓶1個買ったんです。自分の服とかも勿論全然買うお金はないのに、それは買いました。
家の中では、私は名前で呼ばれてました。周桂珍ですから「桂珍」と。父は名前で呼ばれるんですけど、母は、「桂珍のお母さん」とか「桂珍のママ」とか、そういう呼び方なんです。お母さんたちの名前は公表しないの。だから、外では名前のない、誰々のお母さんという呼び方でした。
普通は、子供はみんな名前で呼びます。ただ、ちょっと地位のある人とか、ちょっとお金持ちの人の家の娘に対してはやっぱり「お嬢さん」というような呼び方をするんですけどね。

『きれいな川がありました』
私もお店は、手伝いましたよ。
父は、30代から肺結核だったんです。それでも茶館は経営していました。私達はすごく気をつけてたから感染しなかったんです。
ご飯を食べる器とか別にしてましたし、洋服洗う時も全部別々にしてました。手伝うのは、学校終わってから店じまいの9時まで。
何を手伝ったかというと、店が終わったらテーブルをきれいに拭いて、椅子は、全部テーブルの上に4つ載せて、床を拭いて、お客さんが顔洗うタオルとか洗面器とかも全部川で石けん付けて洗って、干す。そういう仕事をしてました。だから、小さい時からずっと働いてたんですよ。たくさん家のこともしました。
友達は家で親達と楽しそうにご飯食べていたのに、私たちは家に帰ると父が病気で具合悪いときは寝ていたし、今日も熱が出たとかいうことがしばしばありましたから、ちょっと寂しかったですね。
弟が3人いるから、その面倒見るのも私の仕事でした。学校に行く前に釜でご飯を炊くのも私の役目でした。8人家族のご飯の支度もしました。途中からお母さんも働きに出掛けて、お祖母ちゃんもお店で手伝うようになったから家事とか全部私がやってたんですよ。小さい時からよく働いて家のことを全部やったんです。
60年代まで、食料が配給制だったんですが、うちは、病人がいたり小さい子供や老人もいたので、まともに8人分が配給されないんですよ。
病人と子供と老人は、食べる量が少ないから、健康な8人の家族より量は少ないというわけなんです。今日はご飯、明日はお粥。次の日はちょっと軟らかいご飯、重湯。更にうどんか汁物みたいなものにしないと、食料足りないんです。
まあ、少しは現金収入あったから、夜中に、餅や肉まんを売ってたところがあるので、そこで買っていました。それは、配給の中に入らない食料です。
夜中の12時頃に弟を連れて買いに行くんです。そんな日は、先に寝ておいて12時になったら、時計はないから勘で起きて、4歳の一番下の弟も起こして、3人連れて行くんです。それで先に開いた店で餅を8個買って、今度、肉まんの店が開いたらそれを買って家に帰るんです。親たちが朝の3時とか4時ぐらいから茶館開けなくちゃならないから、私がその役目をやってたんです。ご飯もお腹いっぱい食べられなくて、栄養も足りないし、父もその間に亡くなったんです。1960年か61年、40歳になる前でした。
茶館で使う水は、 川の水です。山から流れてきた水なんですよ。とてもきれいなんです。飲むのもそうだし、洗濯でも何でもそこなんですよ。8月になると、その川に小魚がいっぱいいてすごくきれいに見えるんですよ。
その川には思い出があります。
昔は、朝、町中、甕を転がしていくコロンコロンという音がしました。焼き上がった大きな甕を登り窯から出した時、まずコンコンと叩くんですよ。割れてないか確かめるんです。その音もきれいだし、その後にコロコロ転がして行く音もとてもきれいでしたね。転がして川辺に行くんですよ。船に乗せてでっかい市場へ運ぶの。そこまでちょっと離れてるから全部船で運ぶんですよ。
その当時ほとんどが手で漕ぐ船でしたけど、唯一、あそこだけは機械のエンジンのある船が動いていました。そのエンジンは、日本製。日本の船なんです。大きい木の船でね、たくさん甕を載せられるんです。その船が通ると、スクリューで底を掻き混ぜるから、その後は汚れるんです。ほんとうはすごくきれいなんですよ。
この川の名前、正式な名前はわかんないけど、リー川と聞いたことがあります。でもみんな、ただ「川」って言ってましたね。
『戦争中』
日本との戦争のときは、私が小さい頃です。あの町には日本軍が駐留してたんです。セイリュウ山という山があるんですよ。日本兵は、その山の上に見張所作ったんですよ。そこから上海に行く道路が見下ろせるので、陣地をふたつ作ってました。
そこの日本兵たちが、町に来て買い物したり、床屋に行ったりしてたんですよ。で、ある日、私が、まだ2歳ぐらいの赤ちゃんの時に竹籠に入れられて庭に置かれてたら、日本兵に連れられて行ってしまったんですよ。そこの山に。多分、可愛いと思われたんでしょうね。それで、親たちがすごく心配して、町の偉い人に「連れて帰って来て下さい」とお願いして、その人が行って連れ戻して来たそうです。
私はお風呂へ入れられてきれいな洋服を着せられて帰って来たんですって。そんな話を母に聞かされたんですよ。
その時は、日本軍は、そんなに人を殺したりはしない時代だったんですよ。その更に前は、ちょっと酷いこともあったんですけどね。
私が12、3歳の頃、母が作った壺とか甕とお米や大豆を交換してたんです。町の中では物が売れないんで、物々交換だったんですよ。
お祖母ちゃんが、母に遠い所に行って売って来なさいといったんですって。それで母は、甕を担いで川渡って宜興の市内まで行ったんです。15キロぐらい歩くんですよ。川渡る時に転んで壊したとき、そこにいた日本兵の奥さんが買ってくれたそうです。現金もらって帰って来たって聞かされたことあるんですよ。町に行くとお金になったそうです。
『女性の教育』
1949年に中華人民共和国が出来るでしょう。その前は、蒋介石の中華民国の時代だった。蒋介石の軍隊が南京から宜興を通って広州の方に撤退していくんですよ。それで、我々は、みんな家に入って隠れていたんです。
それで、撤退していったあとに外へ出たら、道端に、いろんな道具とか釜とか鍋とか、生活道具いっぱい捨てられてました。そんなことを覚えてます。
解放した頃、母の世代はみんな字が読めないし、書けなかったんです。女性は、学校行けないから、字が読めなかったんです。それで、政府が女性たちに昼間の仕事終わってから、掃盲班というのがあってそこに行かされて、文字を学ばされたんです。
そこでは、「紫砂の急須」とか「羊肉」とか「どこどこの家の豆腐」とか生活の中によく使われる文字を、まず先に覚えるんですよ。更にそれぞれの家に、適齢の子供がいたら、政府が極力学校へ行けと指示したんです。
学費は2元でしたが、もし払えなかったら減らしてもらえて、1元でも1.5元でも払える範囲でいいからと。極力、学校へ行かせるようにしたんです。
今の中国の西域の政策に似てます。
解放後は、女性も家から出て社会参加始めたんです。それまではみんな家庭の仕事や旦那の仕事を手伝うぐらいしか出来なかったんです。物を売りに行くのも男性の仕事だった。女性はずっと家に籠もってました。
それで55年、公私合併して工場もいくつか出来たんです。合作工場ですね。それで女性も男性と同じように工場に入って働いて、同工同酬になったんです。同じく働いて、同じ報酬もらう。そうなったから、町中、すごく活気が出てきたわけですよ。
女性もどんどん勉強しに行ったり工場に働きに行ったり、子供も学校に行くようになって、あの頃は非常に向上的な雰囲気でしたね。

『学校へ』
中国の当時の小学校は、6歳から入ってもいいし、7歳から入ってもいいし、8歳から入ってもいいんです。小学校は6年まででした。
その当時は、中学校はすごく入りにくいから、ほとんどの人が小学校で終わりなんだけど、でも、私は、お父さんが早く亡くなったから、自分はもうちょっと勉強して家族の面倒を見たいと思って、更に2年間、半工半読というのがあって、そこに行きました。
半日勉強して半日働くんです。働くと言っても、学校に紫砂の先生が来て、紫砂を教えるんです。でも、その時、私はまだ子供だったから、そんなに真面目に紫砂を作ったりもしなかったけど、2年間行ったんですよ。
私が学校に入ったのは、数え年で9歳。遅かったんです。
数え年の数え方は、生まれた時が1歳で次のお正月で2歳。だから、満で数えるのにプラス1歳なんですよ。私は8月に生まれて1歳でしょ。次のお正月で2歳。そうやって数えました。学校卒業した時は数えの17歳でした。
私が行った半工半読のところは紫砂中学校と言うんです。その紫砂中学校に入って卒業して、そのまま紫砂の工場に入ったんです。
紫砂中学校に入ったのは、1958年か59年ですよ。入ってからお父さん亡くなったから。
◎『掃盲運動』
新中国は国力をつけるために、まずは工業化を目指した。文字を読み書きできる国民が必要とされる。そのために中国は建国直後に識字運動に力を入れた。ある数字によると、当時識字率は男性は50パーセント以上、女性は5パーセントほど。全国平均でも25パーセントではなかったかといわれている。女性の身分が低かった封建制の名残が強かったことや、長い戦乱や革命のために学ぶ機会が少なかったなどの理由が考えられる。昔から識字運動はあったのだが、中国は広く、方言が多く、表意文字としての漢字の難しさもあった。
そのために、1950年、中国政府は識字率を高めるために、漢字を簡体にした「簡体字」作りを開始し、同時に発音をローマ字で示す「ピンイン」を普及させていった。
1958年の2月27日に中国共産主義青年団は、「掃盲先進単位」の表彰式を行った。掃盲とは字の読み書きできない人をなくそうという運動のことで、それを熱心にやっているグループを表彰して運動をより広げようとしたのだった。中国ではこうした模範を表彰して運動をすすめるという手段がよくとられる。新中国は女性の地位を上げることや文化の空白、政治的な空白を埋めようと新しい方式を採用し、国民はそのことを受け入れ、「新しい国」づくりのために、多くがそれをよろこんで受け入れていた様子がわかる。周師の話を続けよう。
『紫砂工場で』
昔ね、女性たちは川辺に行って洗濯をする間にちょっと話をしたりするだけだったけど、解放後には夜間学校があって、そこに勉強しに行くようになりました。そこでお互いに文字を教え合ったり、友達が出来ました。
解放後すぐ、何軒かで住民会みたいな組織が出来たんです。
それで、隣同士喧嘩したという時には仲裁したり、町全体が、新気象というんですけど、新しい風が吹き抜けていくような、がんばろうという雰囲気でした。戸籍制度もその時に始まったの。その前には戸籍なんかなかったんですよ。
1958年に公私合併して工場出来たでしょ、その工場が創った学校が半工半読の中学なんですよ。工場が学校に経費あげて、学校で2年間勉強した子たちが工場で働くように。後は、必ずしも工場に行かなくてもいいんですよ。そこでは学費は払わなくていいんですよ。
我々は、紫砂工場の半工半読の第1期生なんです。工場が出来て、学校を作って最初の生徒です。私たちの時は、2クラスあったんですよ。1クラスは、30人ぐらいで、だから、全部で60人ほどでした。
その次の年の学級は、3クラスになったんです。
今、宜興に住んでいて、国の工芸美術大師に選ばれた何人かは、同級生です。
私は紫砂中学校に行って初めて紫砂に触れました。
私達の合作社の名前は「宜興紫砂工芸工場」。
55年に合作社を作った時に、町の中には徐秀棠さん(第1章に登場)のお祖父ちゃんが経営してるような個人の会社があったんです。そういういくつかの会社が自分たちの物を持ち寄って合併したんです。それが合作社です。
それで、その時に徐さんのお父さんとかお兄さんとか、あと自分の師匠の顧景舟先生たちは、あの当時ももう名人だったけど、彼らは、合作社の第1期生として入ったわけです。名人にも、国が「是非、入ってきてください」って呼びかけたから、みんな入ったんです。
1956年ぐらいに小学校とか中学校卒業してから入った人達もいるんですよ。私は、第3期。紫砂の工場の学校で2年間勉強してからそこに入ったんです。だから、3期の入社です。
学校では、2年間勉強しながら実技も習ったんです。
60人の同級生のうち、農村から来た人達の何人かは、村に帰ったり、急須作りに興味ない人は途中で辞めていきました。
本来ならば全員工場に入る筈ですが、結局、工場に入ったのは半分以下だったんじゃないかな。
あの時は、田舎から都会にいっぱい出て来たんですけど、国の政策で田舎から出て来た人達は、みんな田舎に帰れっていう指示があったんです。だから、いっぱい帰ったんですよ。
『紫砂工場で修業』
紫砂の工場に勤めた時の最初の給料は、第1期生は、男女一緒で11.6元。
まあ、12元ですよ。寮に入っている人はそのうちの8元は食事代、残りの4元は、石けんを買ったり歯ブラシを買ったり。
2年目は13元。3年目は15元。15元が1、2年続いて1963年ぐらいから、出来高制になったんです。作った数で支払われるようになったんです。
工場に泊まっている人も多かったけど、私は家から1.5キロほど歩いて通ったんです。自転車を買うお金もないし、まだ売ってるところもなかったから、ずっと歩きでした。
12元もらったら、私は家から通っていたから6元の食事代払って、残りの6元のうち1元はお小遣いとして残して。あとの5元は、家に入れてました。
工場に食堂があって朝と昼と晩、3食全部そこで食べたんです。朝、50グラムのお粥。お昼は200グラムのご飯。夜も200グラムぐらい。
200グラムのご飯は0.6元。おかずは、0.04元か0.06元。スープは0.02元。
おかずは、冬は大根か青菜炒め。おかずは一つしかないの。脂もないから主食のご飯をたくさん食べるの。あの時代は、全国的に貧しかったし、お金あっても物はないし。スープといっても、漬け物とか大根とか青菜とかが少し入っていて、ちょっと醤油を入れたり、塩を入れただけのものでしたね。
今言った状況は、大災害があった時の1960年、62年から63年までの3年災害の様子なんですよ。あの頃は貧しかったからね。
その前とその後は、ちょっと高いけどお肉ありました。
作業は、三つの班に分かれてました。
製品が出来るまでの工程を話しますね。
山から紫砂の石を採石します。それを砕く「砕石」をします。それに水を加えて「泥」状にして、それを漉して土にして、「叩き」「成形」「絵や彫刻」「乾燥」「薬」「検品」「包装」「運搬」。こうなってました。
材料は、大きさや形はさまざまでしたが、10×30×40センチぐらいのレンガ状の形で来ます。三つの班の仕事は、「材料作成」「成形工場」「窯務」です。成形の中に、形を作る私達の仕事と、絵や文字を彫り込む作業がありました。
私がいた成形組では、師匠は急須でしたが、私達徒工は湯飲みから始めたんです。私は初めて2個作って、とても上手だと褒められました。
2ヶ月間同じ湯飲みを作り続けました。毎回高い評価を得ました。それは、私に悟性があったからだと思います。センスですね。器用だったと思うし、努力しました。作ることが面白くて好きでした。やっていくとわかってきて、褒められるとうれしくて、楽しくなったんです。なによりいい先生に出会えたことが一番だったと思いますね。顧景舟先生もそうですし、後で夫になる高海庚もいい指導をしてくれました。
何度も何度も同じ物を作りました。
私は完璧主義者で、それは今も変わりません。それがうまくなった秘訣の一つだと思います。
その後に急須を作るようになりますが、これも訓練は一緒です。まず一つの形をずっと訓練しました。それができたら、次の形を学ぶんです。そうやって訓練してきました。
紫砂工場には学習班がありました。学習班というのは、仕事以外の時間を利用して、夜の7時から北京の美術大学の先生とか学生たちが来て、古い急須を再現する時にどういうふうに測るとか、教えてくれたんです。私たちそういうことは勉強したことないんですよ。それで教えに来てくれたんです。
この当時は、作る物は、図面で来る場合もあれば、作ってある急須を見本として持ってくることもありました。
私の3人の弟のうち一番上の弟は、実家が茶館だったから、公私合併の時にサービス業に入ったんです。服務公司に所属して、レストランとか食堂みたいなところで働いてたんです。で、下の2人の弟は、田舎に下放されたんです。農家に。後に、宜興に戻って来たんですけど、弟たちは誰も急須作りにはならなかったですね。3人とも身体が大きいから急須職人には向かないんです。弟たちは3、4年ぐらい下放して、またみんな戻って来て、1人は青磁工場に、もう1人は壺のような大きい物を扱う工場で働きました。
3人とも物作りのセンスはあったと思うけど、素晴らしい先生に巡り会わなかったし、そういうチャンスには恵まれなかったんです。
◎『婚姻法』
徐秀棠師の話にも恋愛の話があった。結婚した相手は自分の弟子だったと。周師の話にも結婚のことが出てくる。この後登場する景徳鎮の絵付け職人・丁蜀鎮師も結婚の話をしている。私達現代日本人にしてみれば、なんでもない当たり前の職場結婚であり、恋愛結婚であるが、新中国建国まではこうしたことは自由ではなかった。中国の長い封建制のもとでは、女性は奴隷的服従を強いられていた。子供も同じで親の命令には絶対服従であった。徐兄弟が、親が決めた師匠に付いたのもそういう背景があってのことである。
1950年、新中国は「中華人民共和国婚姻法」を公布した。大きな目的は、女性に対する差別や抑圧を除くため。新中国は男女平等と女性解放、子供の利益、人権の保護を唱えており、それをすぐに実行に移したのだ。
そこでは男女の婚姻は自由で、一夫一妻、男女平等を謳っている。それまでは当たり前であった親の強制による結婚は否定され、売買婚、請負婚などの金銭による結婚も悪しき習慣として排除された。いずれ大きくなったら息子の嫁にするために養女を金銭で買う習慣や「納妾」と呼ばれる制度も廃止された。さらにこの法律では、それまでは否定されていた寡婦の再婚も認められた。因みに、この時の結婚しても良い年齢は、男が20歳、女が18歳である。この制限が1980年の改正婚姻法では、男が22歳、女が20歳になる。人口過剰による計画出産の義務に伴う規定であった。いわゆる「一人っ子政策」のためである。
1950年の婚姻法は当時の若者達にとっては素晴らしい解放であった。新中国が目指す平等が自分たちのものになったのを実感したであろう。国はこの法律を全国に行き渡らせるために大きく宣伝、貫徹するように大きな大衆運動を展開した。
その結果が徐秀棠師や周師の結婚の話につながっているのである。
中国の姓は基本的に夫婦別姓。結婚しても以前のまま。自主的に協議の上、夫や妻の姓に変えることや新たな姓を名乗ることも認められているそうだが、子供は父の姓を名乗ることが多い。

『文革の頃』
文化大革命が始まった1966年の時、私は妊娠中でした。娘がお腹にいたんです。
結婚したのは1963年、私が22歳で、夫が24歳でした。
夫は、研究所にいたんですよ。研究所には、顧先生と徐さんのお兄さんの徐漢棠と夫と3人だけだったんですよ。その人達がデザインをしました。それを、私達が作ったり、他の人に作らせたり、そういう仕事をしてました。
その時は、劉少奇っていう国家主席がいたんですが、「打倒劉少奇」っていう運動があって、みんな町に出てデモやったりしましたね。でも、工場の生産は停止しなかった。ずっとやり続けてたんです。そんな騒ぎの中でも、品質管理もしっかりしてましたから文革中に作った紫砂も、品質はしっかりしてるんですよ。
仕事始まる前にみんな『毛沢東語録』を持ってて、それをいくつかを読んで、それから仕事が始まるんです。
私達は文革中も大量生産品は作ってなかったんですね。今まで通り1個1個生産をしてたんです。
ただ、文革が始まってちょっと後に、紫砂は、資本主義者の生活のスタイルだから良くないというので、急須の生産が止まりました。
私達は、お茶を大きいコップにたっぷりの湯を注いで飲んでたでしょ。それを、急須でゆっくりと楽しむとかいうのはブルジョアだと。急須でお茶を飲むのは、文人趣味の資本家や金持ちのやることで、急須を作るのは資本主義者のための仕事だと。それは止めようということになって、急須の生産量が減ったんです。だけど、工員達が生活しなくちゃなんないでしょ。工場としては、給料出さなくちゃなんないから、紫砂で作る汽鍋とか土鍋とか、そういうものも作ったんです。ご飯を炊いたり、調理用の鍋ですよ。
工場の中でも、セクトに分かれたんです。「私は、この派」「私は、この派」って。それで派同士で批判したりしたんです。
私は「経済主義反対派」に参加しました。徐さんと同じ派閥です。それで2班ぐらいに分かれたんですね。
日曜日とか残業すると、前は、残業代出してくれとか工場に対して要求してたんですが、私達は、そんなの止めようと。私たち、革命のために働いているんで、お金のために働くんじゃない。だから、国にそんな要求するのは良くないとか、そういう主張していました。それが経済主義反対派。
もう一つの派は、経済主義派です。今はみんな経済主義ですよ。
当時、私は、そんなのよくわからなかったんです。
それまで1000個とか2000個とか来てた急須の注文は、日本に輸出したり全国各地に送っていました。その中には、海外の首脳や要人に差し上げるお土産とかも入ってるんですよ。
文革が1976年で終わるけど、78年に広州で中国輸出入商品交易会が開かれて外国に向かってたくさん売るようになるまでは、そういう注文に応えるしかなかったんです。
文革の間は、男女の差別とかそういうことは、全然なかったね。紫砂の工場には、女性が多かったんです。女性は細かいものをじっくりと作って、男性の方が大きい物を作るのが得意でした。急須とかは忍耐力のある女性がじっくり作る。だから差別とかは全くなかったですね。
小さい時には、女の人達は、名前がなかったりするぐらい卑しめられてたのに新政中国になったら、すごく女の人達の立場が上がりましたよ。
古い時代には私達はまだ小さかったから、新しい時代になってもそんなに戸惑ったりはしないんですね。寧ろ、もう自分も家庭が出来たし、夫婦共働きで自分が自由に使えるお金も出来たわけだから、気持ち的にも自由で喜びの方が大きいんですよ。
その時代は、私の家では父はもう亡くなってましたけど、母もまだ働いてたんですよ。働かないと食べていけないから。
私が子供を産んだときには、産休は56日間でした。その後は、工場に託児所があったので、そこに預けて働いて、おっぱいあげに行くとか、お昼時間に子供の顔見に行くとか、そういう生活でした。子供達2人ともそういうふうに育ててたの。
文革の最中に顧景舟先生とか、王主任とか、工場長だった夫の高海庚は、虐められたり、自己批判させられたりは全然なかったです。なぜならば、国は高い技術と芸術性を持った職人達、顧先生や私の師匠の王さんを保護してました。だから全然そういうのは、なかったんです。寧ろ、死ぬまで面倒見てくれて死ぬまで給料もくれたんです。大事にされていましたね。
文革時代は出来高だったんですよ。だから、時間ないからいろんな運動には参加出来なかったの。経済主義反対というのは、出来高払いに反対なのではなくて、それ以上の物を政府に要求するのには反対だったんです。自分の所属じゃなかったり、自分が要求すべきじゃないのに更に別の物を要求するとか、そういうことに反対したんです。
私の趣味は急須を作る以外は、洋服作りでした。
1年以上貯金してミシンを買ったんです。当時毎月10元ぐらい貯金してたんですよ。1年半ぐらいでミシンを買えました。それで、洋服作りました。
私は裁断は出来ないから、主人が上海で裁縫の本を買って来て勉強して、裁断出来るようになったんです。休みの時に生地を買って来て、主人がそれを裁断して、私がミシンかけて、子供たちの服は、中学校卒業するまでは、全部私が作ってたんです。自分の洋服も自分で作って。
急須と同じようにうまく出来たから、いつもみんなに褒められましたね。
『日々の暮らし』
あの当時、私は、すごく忙しかった。毎朝、石炭を熾さなくちゃなんないからね。ご飯作るのも全部石炭。それを熾して、朝ご飯作って子供たちを学校へ行かせて、それで市場に野菜とか買いに行って、家に置いて、洗濯して、干して、慌てて工場に行くんです。この頃は自転車です。自転車は、結婚してから2人で貯金して、買ったんです。150元ぐらいだから、1年間ぐらい貯金したら買えましたね。
自転車で、工場に行ったら、午前の仕事は10時半に終わって、慌てて自転車で家に帰って、お昼ご飯作って、子供たちが帰って来たら、それに食べさせ、また仕事に行くんです。
勤務時間は、夏は6時半から始まって10時半まで。休憩があって、午後は12時半から5時半まで。冬は30分遅れて7時からでした。2時間から4時間の残業をしましたね。
家でも急須作りをやりましたよ。
時間がある時には、夫が土の塊を持って来て、いじったり、図面を描いたりしてましたから、それを見て「あ、これ面白そうだから作ってみようか」とか、そういうこともありましたし、自分も修業のために名人の急須を真似して作ってたんです。陳寿珍さんていう人のをよく作ってたんですよ。
だけど、作っても作ってもその人の魂まではたどり着けないんですよ。
技術は達してるはずなのにどっか違う。夫にその話をしたら、夫は「やっぱり陳寿珍は陳寿珍、周桂珍は周桂珍だ」と言ってました。そういう冗談言ったりしましたね。
彼がデザインした物は、勿論、私が一番うまく出来ますよ。他の人に作らせてもうまく出来ない。私が一番彼の意図を理解してますから一番うまく出来ます。家の中でもずっとそういう話をしてましたからね。
『文革後』
それまでの一連の騒ぎの後に、林彪事件とかがあったから、文革が終わったと感じました。1976年、四人組が駄目になって、77年あたりから夫は、抜擢されて陶磁公司の方に入りました。
工場長も辞めてその上に昇進したんです。もっと紫砂をアピールするために上海と北京で展示会をやったんですよ。紫砂展をやった時、私も初めて北京に行きました。その展示会には名人作の物がいっぱい展示されたんです。すぐ香港人が買いに殺到しました。そこからみんな有名人になってたくさん売れて、業者が製品を家まで買いに来ましたね。
私は、毛沢東のために作ったことはないけど、贈答品として作っていたのは確かです。鄧小平は失脚したり、また出て来てまた失脚したりを3回ぐらい繰り返しましたが、78年に日本を訪問した時に、持って行くお土産を探しに来ました。
その時に蘇州の刺繍、揚州の漆か玉だと思うんですけど、それと宜興の急須が選ばれたんです。
それは夫がデザインし、私が作った集玉壺という急須でした。それをなぜ知ったかというと、4、5年前に杭州で茶文化検討会が開かれた時に、私が呼ばれて行ったら、当時、そのお土産を選んだ人がいたんですよ。その方が、私が紹介された時に寄って来て「あなたが周桂珍さんですか」「当時、私は、あなたの急須を見ました。素晴らしいから日本への贈答品に選んだんだよ」という話を聞かされたんです。
1978年の交易会では、急須よりは盆栽鉢が多かった。それも日本からの注文がたくさん来たんですよ。紫砂は通気性が良いでしょう。それで、盆栽に使われるんです。植物の活生率が高いから、日本からヨーロッパに輸出したりするのもやってたんです。だから結構鉢を大量に作ってました。
81年に、顧先生と夫と、徐秀棠さんの3人で香港に行きました。急須はどんなふうに売られてるか見たいと。海外に行くと、その人達は、帰ったらテレビを1台買えるんですよ。そういう決まりがあったの。
1回海外に訪問に行くと、1台。その人達が出掛ける時に国から補助が出るんです。例えば、洋服代とか食事代とか。でも、香港にいたら彼らは、賓客の扱いです。名人ですからね。だからみんなかかった費用を向こうが出してくれるでしょ。するとそのお金が余るわけですよ。それでテレビ買えたの。
顧先生が14インチのカラーテレビを買って、うちは17インチの白黒を買って来た。村の中では、テレビはうちの1台しかなかったから、みんな見に来るの。窓が大きかったから、みんな窓越しに並んで見るわけ。
85年、私が初めて香港に行ったんですが、自分の急須が香港ドルで5000元で売られてるのをびっくりしました。
5000元ていうのは当時、人民元に換算すると3000元ぐらいなんですよ。私たちの給料がまだ100元にも達してないのにねえ。驚きましたね。
工場では、急須は1等品、2等、3等と分けられたんですよ。勿論、顧先生は1等で7元。他の人は6元。でも、そういうふうに区別するのはつまらないからって、みんなで一律6元にしましょうと。つまり、1個作ると6元もらえたんです。それなのに、そんな値段が付けられてたんですよ。
主人も香港に行って、そういうことがわかった。先方も工場での価格を知っていたので可哀想だからって、香港人は、工場から500元で買って行ってたんです。そして帰ったら、10倍で売ってたんです。
主人は、会社に申請して、もっと職人にお金を払いましょうと主張しました。売値の10パーセントまでいかないけど5パーセントぐらい払いましょうと。それで500元で買われた時には、私たちは25元もらえたんですよ。
ですから、私、一番高くもらった給料は100元超えるわけですよ。それは、もう非常に高い給料でした。
改革開放が始まった1979年以降も、家で自由に作ることはまだ出来なかったですね。
工場で作ってるのを、香港に輸出すると、だんだん、商人が個人のところに買いに来るようになったんですよ。でも、夫が生きている頃はきちんと管理してたから出来なかったの。外国商人の利益を守るために急須は外に流しちゃいけないと。だから、全部注文受けて工場で作って、そのまま渡したんですけど、他の商人も増えてきて、それで乱れてしまったんです。香港の商人は家に買いに来て、工場と同じ値段で回収して行くんですよ。
工場より高いお金を置いていく人も出てきたんです。それで乱れてしまったんです。
工場に納める個数は、ノルマで決まってました。それをまず保証してから自分の分をこっそり作ってました。私は、最初そういう意識も全くなくて、香港人が私に色んなお土産を持ってきた時に、お礼で1個余分にあげたりはしていたんです。でも、私の急須がよく売れるから声を掛けられるんですよ。
それで子供たちも大学に行くようになって、お金も必要だし、少しずつは売るようになったんですよ。それは主人が亡くなってからです。生きてる間には、そんなことは出来なかった。主人が亡くなったのは85年でした。工場長をしてましたが、心臓が悪かったんです。まだ47歳でした。
うちではテレビを買った後、暫くして、洗濯機も買いましたね。
夫の父、お祖父ちゃん、お祖母ちゃんは無錫に住んでいて、無錫の洗濯機工場で働いてたんですよ。親戚だから1台は買えたんです。一つの洗濯槽しなかくて、脱水は出来ないものでした。それを1台買ったんですね。それで、86年に初めての冷蔵庫を買ったんです。
子供たちは大学に行ってたから、私は一人暮らしでした。作った料理も食べきれないから、冷蔵庫に入れておいたら何回も食べられるでしょ。そのために買ったんですよ。
改革開放が始まったんですが、もうそのころから資本主義的な意識も芽生えてきました。商人が工場に買いに行くと工場の方にお金入っちゃうけど、家に来ると自分のところに入るじゃない。だから、みんなそういうことしてたんですね。
香港、台湾の商人だって、直接私達にお金をくれた方がいいからね。
私が、工場で指導的立場になったのは1979年あたりからです。80年になる前です。その時は、新しく出来た班に派遣されました。
そこには若者が多かったんですよ。私は30代で、その人達は20代。それは、文革が終わった後です。部下は20人ほどでしたね。
『国級の工芸美術大師(人間国宝)に』
定年の年齢は女の人と男の人では違うんです。一般の工員は50歳。肩書きのついてる人、例えば、工芸師とか技術員とか、そういう場合は女が55歳で、男性は60歳。私は55歳で退職しました。
私は、2004年に国の陶磁工芸大師になったんですね。その2年後の2006年に中国工芸美術大師になったんです。63歳の時です。
紫砂の急須を作る人で国の工芸美術大師になった人は、全部で10人なんですけど、顧先生ともう1人、女性の名人は亡くなったんです。顧景舟先生は1988年第2期に選ばれています。今、健在なのは紫砂の分野で8人です。
主人も生きていれば、勿論、私より早くもらえましたよ。残念だったですね。
顧先生と主人に会ったことが、私にとって、すごく大きかったんです。この2人のまわりに、文化人の友達とかいっぱい集まったんです。その人達からいろんなことを聞いたり、学ばさせてもらいました。私にとっては、そういう影響も非常に大きかったと思います。良い物を見たり、良い話を聞いたり。
おかげで私の人生があるんです。
今は息子も、息子の奥さんも急須を作ってます。息子の奥さんは、工芸美術大師の徐秀棠先生の娘です。ですから私のまわりには急須作りがいっぱいいるんです。今も毎日工房で、こうして音楽を聴きながら作ってますよ。

