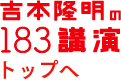子どもの哲学
1 昔はなかった子どもという概念
僕の今日のテーマは「子どもの哲学」となっています。題はどういうふうにつけてもいいわけですが、子どもというのをまずどう区分するのか、どこにその区分の特徴があるのかというところからお話をして、何がいったい子どもにとって問題なのか、あるいは子どもについて問題なのか、あるいは問題はないのかということをお話しできたらと思います。それで児童心理学とか児童哲学、児童精神医学などの国際的な権威といわれている人たちの子どもの区分の仕方というのを表にしてみました。
まず、こういうところで子どものことが一連のテーマとして扱われるということは、子どもに何か問題があるからだと思われます。問題があるから子どもに関心を持たざるをえないということがあるのかと思います。しかし、子どもという概念、考え方ができあがったのはそんなに古い昔ではありません。つまり、昔は子どもという概念はあまりなかったわけです。
結局は何が子どもという言葉、概念を生み出したかというと、教育だと思います。私塾、あるいは自分の家で親が子どもに勉強を教え、規律を教えというふうにしていたときには、子どもという概念は必要でなかったんですが、学校が制度としてできあがったということから、どうしても子どもという概念が必要になりますし、子どもとはこういうのだと決めておいて、学校に何歳になって入るべきものだと決めないといけないということから、子どもという考え方が出てきたということです。
子どもは昔からあったというわけではないので、ある時期から子どもという概念が必要になって、その必要に関係がいちばんあるのは学校、教育というものが制度としてできあがった。それから以降、子どもという概念が必要になってきた、そして生み出されたということではないか。ほかの理由もあるかもしれませんが、いちばん大きな理由はそれじゃないかと思います。
2 子どもという概念の区分
共通しているのは初めの0~1歳を乳児といいます。0~1歳を乳児ということはどの児童心理学者も子どもについての哲学者も一致しています。一致しているのはそこだけです。乳児とは何か、これはどんな人が考えても、どんな人が編み出しても同じではないかと思いますし、みなさんも同意するんじゃないかと思われるのは0~1歳です。つまり、母親からおっぱいを飲まなければ栄養が取れなくて死んでしまう、授乳、お乳なしには生きていけない、また排便の世話とか着物の世話なしには生きていけない。自分で歩いて、自分で着替えてということはできませんから、そういう時代を乳児ということだけはどんな人が考えても一致しているところです。
しかし、それから以降はすこぶる怪しいことになってきます。ここに4、5人の学者、研究者の考え方を取ってきていますが、幼児期を2歳から5歳に取る人もいますし、6歳に取る人もいます。ピアジェというフランスの児童心理学者、発達心理学者は七歳まで幼児と取っています。たいていは2歳から5~6歳までを幼児期といっていますが、6~7歳までを幼児期という心理学者もいて、決して一致しないと言えます。
その後になってくると、ほとんど全部いい加減というか、意味がない分け方をしています。たとえばバーカーという人の、あまりいい本ではありませんが、標準的な本の中では、児童期といっています。そして児童期を5~6歳から10歳と区分しています。児童期とはいったい何なんだということになるわけですが、児童期というのは人間にはないわけです。ただ、学校があるから何となく学校へ通い始める子どもという意味合いで児童期という言葉が成り立つわけで、児童期というものが人間の中に本当にあるのかどうかとなると、すこぶる疑わしいことになってきます。勢い、何歳から何歳まで児童期というんだというその区分も人によって違ってきて怪しいことになってきます。
それからその後、これは個人差も著しいし、人によって区分の仕方も著しいわけですが、思春期という区分もしています。思春期というのは何歳からということについては人によって多少の違いがありましょうし、個人差を問題にすればたくさん違いがありましょうが、共通の表象というのはありえます。つまり、性徴というか、性的な兆候、しるしというものが前面に出てくる。引っ込んでいる、前面に出てこないという意味だったらゼロ歳からあるわけですが、とにかく男性の性徴とか女性の性徴、性的なしるし、特徴が身体、肉体の前面に出てくるということで言えばだいたい共通して、11歳の人もいますし、10歳の人もいるけれども、それからの数年間を思春期といっています。これはかなりはっきりした言い方で、誰でも区分のつけやすい時期だし、共通の兆候、しるしを知りたいと思うのであれば知ることができる、それを目印にすることができるということになりますから、思春期というのは割合にわかりやすい。
3 子どもにとって重要なふたつの時期
そうすると、乳児期と思春期というのはだいたいどんな人が考えても意見が一致しやすいところです。そしてそれは非常に重要なことですが、誰でも共通で意見が一致しやすいというそこが、人間の生涯と言ってもいいんですが、子どもにとっていちばん重要なときです。つまり、そのふたつの時期に間違わなかったら、たいてい間違うわけですが、人間というのは生涯大丈夫なんだ。何が大丈夫だというのはあれなんですが、とにかく大丈夫だ。あいつは大丈夫な男だとか大丈夫な女だと言えるためには、0~1歳、乳児のときと、思春期、あるいは思春期を前後してですが、その時期が大丈夫だったらば大丈夫なんです。その時期がだめだったら、人間というのは、誰でもそうですが、みなさんも思い当たるでしょうが、ものすごくきついことになります。
思春期というのは自分でもよくわかっているところがあります。子ども自身でもわかっていて何かやっているとか、わかっていてこうならざるをえなかったということがあるわけですが、何しろ0~1歳、乳児のときというのはご当人にはまったくわからない。これははたから聞く以外にない。はたから聞くといっても、本当によく知っているのは母親ですが、母親にどうだったと聞いても、たいてい本当のことは言ってくれませんから、非常にわかりにくい。自分でわからないで、しかもものすごく重要だという時期です。
もっと極端に第一義的に言えば、0~1歳、乳児のとき大丈夫だったら、人間というのは大丈夫なんです。どんなことがあっても大丈夫だ、どんな目に遭っても大丈夫だ、心配なんか何も要らないということになります。
極端なことを言いますと、児童期という曖昧な時期、時期になっていない時期というのがあるわけですが、そこでいろんなことが出てくるでしょう。現在だったら、たとえば登校拒否、いじめ、学校内暴力、家庭内暴力、いろいろあるでしょう。その手のことは0~1歳のとき大丈夫だったら絶対大丈夫です。絶対起こらないし、起こっても何でもない、直ってしまいますから放っておけばいいというくらいに、0~1歳というのは重要なときです。
その重要なときに子どもには何の責任もないわけです。つまり、知らないし、何もできないわけですから。おふくろさんがおっぱいを飲ませてくれなければ栄養失調で死んでしまいますし、排便、排泄でも母親ないしそれに近い人が世話してくれなかったら、自分ではできないわけで、これもどうにかなってしまう。場所の移動もできない。1歳近くになれば這っていけますが、自分では積極的にここからここへ行きたいとか表へ行きたいといっても行けないわけで、全部、母親ないし世話してくれる人がしてくれる以外にないわけで、自分には何の責任もありません。
しかし、自分には何の責任もないにもかかわらず、この時期が人間にとっていちばん重要です。だから乳児期というのを別の言葉で定義すれば、自分に責任がないにもかかわらず生涯自分にいちばん関係のある時期、それが乳児期なんだという定義もできるくらいの時期です。そこが非常に重要です。
それから思春期というのがとても重要です。重要なるゆえんは後で申し上げることにいたしましょう。
4 乳児期に植え付けられる基本的信頼と不信
せっかくこういうふうに区別したわけで、重要なとき、およびいい加減に区別されているときに、どういうことが特徴になっているかを申し上げます。0~1歳のときは、子どもには責任がないにもかかわらず、子どもの生涯にとって最も重要な時期、あるいは最も影響の重大な時期というふうに、僕なら乳児期というのを定義します。しかし、それぞれの学者さんはそれぞれ定義をして、そのとき何があったか、何が特徴なのかをちゃんと出しています。
たとえばバーカーは、6カ月ごろから笑うとか、8カ月ごろには人見知りが始まるとか、いろいろ書いています。1年ぐらいまでに母親に対して一種の親しみと安心感を持ち、ほかの人に対しては母親と違う感じを抱く。それから授乳、おっぱいをやるとか睡眠の型がだんだんできあがってくる時期なんだ。1歳近くになれば、どこの家でもいまのお母さんはそうでしょうが、排便とか排尿を教え込みますし、離乳食をやって離乳するみたいな時期が始まると思います。このバーカーという人が言っている乳児期の特徴というのはもちろんみなさんのほうで重々ご承知で、本人としては経験していないでしょうが、お母さんとしてだったら誰でもよく知っていることで、特徴を挙げても別に意味はそんなにないことになります。
次に書いてあるエリクソンという人は優れた発達心理学者ですが、この人は乳児期の特徴をどう言っているかというと、「基本的信頼対不信」、そういうものが著しく子どもの中で現れてくる時期だという言い方をしています。
どういうことかというと、乳児のときに母親に対して特別な信頼感を抱くことになる。成長して幼児期、児童期、思春期になって、あるいはもっとみなさんみたいな大人になってから、人を信じられるか信じられないかということの基本は、乳児のときに母親から植えつけられた基本的な信頼感がうんと安定していれば、その人は生涯のどの時期を取ってきても、人に信頼感を抱いて接するという接し方ができるような人間になるという意味合いで、基本的信頼感が乳児のときに植えつけられる。
それに対して不信感、つまりそのときに何らかの意味で母親に対して信頼感を持てないという体験をしているとすれば、あるいは母親が乳児に対して信頼感を持たせないような育て方のパターンを取ったとすれば、それは生涯にわたってその子どもの負担になっていきます。人を疑うか疑わないか、人を信頼できるかということで、生涯にわたって大変苦しまなければいけない。
僕らは大なり小なりそういうことで苦しんでいるわけですが、それはどうしてかというと、子どものときに母親から100%基本的な信頼感を植えられるような育て方をされている人というのは非常に少ない。みなさんだってそうだと思います。またみなさんだって母親として、俺は自分の子どもに対して100%基本的信頼感を与えるような育て方をしたと言える人はまずまずいないわけです。たいていどこかで手を抜きます。それはやむをえないことがある。経済的な理由とか病気、あるいは夫婦間の仲が悪くてとか、いろんなことがあって手を抜かざるをえないというのがだいたいどんな母親でも現状です。
だから大なり小なり手を抜いているけれども、基本的には俺はよくやったほうだよという母親はいるでしょう。たとえば70%までは子どもをうまく育てたつもりだよと心の中で言える人がいると思います。人には何とでも言えますが、そうではなくて、本当に心の底から、俺は自分の子どもに対して70%ぐらいまではやったなというふうに育てられたらたいしたものだと僕には思えます。そこまでやれたらたいしたもので、まして100%なんてまずいない。大なり小なりだめだよ、手を抜いたり、手を抜くつもりはなかったんだけど抜かざるをえなかったという目に誰でも遭っています。
そうすると、70%の信頼感を無意識のうちに植えつけられている。だから長じてのち人とのつき合いの中で、70%ぐらいは人に対して心を開いて信頼感を持てるんだけど、あとの30%はどこかで疑いを持ってしか人に接しられないというのは皆そうだと思いますが、大なり小なりそういうふうになっているのが人間の現状です。これはごまかすことができません。乳児を過ぎたときにはすでに遅いので、どうしようもないわけです。
5 人間は決定論ではない
そうしたらば人間はどうするかということになるわけで、お前だめかということになるけど、それはそうでないというのは後で申し上げますが、人間というのは絶えず現状を超えていくものだと言ったらいいんでしょうか、自分の資質とか性格を超えようとする、あるいは弱点があれば弱点を超えようとする、そういう存在が人間です。だから超えよう、超えようとして、全面的に超えられることがある。しかし、それは意識して、つまり努力して超えるわけです。努力をやめたらすぐに元に戻ります。乳児のときの基本的信頼感が70%だったら70%に戻りますし、40%だったら40%に戻ってしまいます。そのくらい基本的な要素は乳児のときに決まってしまいます。これはものすごくよく考えたほうがいいことです。
また、これはある意味で宿命論になってしまいます。それだったら0~1歳で人間というのは決まってしまうじゃないか。たしかにそうなんです。一面ではたしかに決まってしまいます。これはいかんともしがたいことです。なぜならば、自分はそのとき責任がない。知らない、意識していないわけですから。母親からの十全な信頼感を身に受けたかどうかは母親の問題であって、自分の問題でなかったわけで、仮に自分が資質的に40%しか人間を信じられないという人間になってしまっても、それは自分の責任ではないですよ。
しかし、それは宿命でもないんです。なぜならば、努力すれば、あるいは意識すれば、意図すれば、それを超えて、信頼感を持つこともできますし、獲得することもできます。ただ、その努力をやめれば、人を信頼するとか人に心を開くということを意識的にやめてしまえば、乳児のときの元に戻ってしまいます。それは誰でもそうです。いつでも人間というのはそういう格闘をしているわけです。乳児のときに植えつけられた基本的な人間に対する信頼感と、これではいかんということで努力してそれを超えようとして人に対して接するということを絶えず心の中で繰り返しているというのが現状です。みなさん自身がそうだし、僕ももちろんそうです。そういうふうにして人間というのは他との関係を結んでいる。それほど乳児の時期というのは重要です。
だからエリクソンという人は、基本的信頼感および不信感というものがこの時期に形成されるから、そこで乳児期というのをつかめばいいと言っているわけです。
ピアジェという人は心理学者ですから、もっぱら身体反応みたいなことを主体に乳児というのを考えていて、これは反射の段階だと言っています。反射の段階というのはどういうことかというと、たとえば何かにぶつかって痛かったらワーッとすぐ反射的に泣いてしまうとか、何かが落っこちてきたら反射的に目をつぶってしまうというふうに、目に見えたものとか聞こえたものとか、感覚を基にして、感覚に対して反射的に行動する、それが乳児の時期の特徴だと定義しています。つまり、言葉を覚えた以降、こうしなさいと言われて、しようかしまいかと考えて、そのうえでしたとかしないとか、ものを考えて行動するということがまだない段階で、何か危ないものが落っこちてきたら目をつぶるというふうに、反射的に行動する段階だという区別の仕方をしています。
こういう区別の仕方はもちろんとても大切ですが、ただ区別してみただけ、乳児の身体の動かし方とか反射、反応の仕方を特徴として取り上げてみただけということになると思います。
6 乳児期後期――吸うことと噛むこと
その乳児期の後、1歳に入ったころから少しずつ言葉も覚え込むようになります。言葉を覚え込むようになると、反射的な行動だけではなくて、思考する、考えるというほどではないんですが、言葉を解して、愉快な感情とか不愉快な感情を表情に表したり、楽しいときには笑ったりすることができるようになり、また何でも自分本位で、自分がいちばん大切で、自分を中心にして言葉を言うとか振る舞う、そういう態度を取る時期だということになります。
エリクソンはもっと乳児を分けていて、乳児期の後期、1~2歳を「自立性対恥、疑惑」と言っています。これは先ほどの「基本的信頼対不信」と同じことで、信頼、不信という感じ方が無意識ではなくて、少し自分でわかるような感じで信頼と不信を表明できるようになる。それから信頼したものに対しては喜びを表すことができるし、不信のものとか事柄に対してはそれらしい表情とか態度を取れるようになるということだと思います。
この中でエリクソンはいちばんみごとな言い方をしていると思いますが、すべての特徴というのは母親の乳房を吸うというようなことが基本であって、感情が荒立っているときには噛んだり、吸うとか噛むというかたちで周囲のもの、特に母親に対して感情の快、不快を表現する。だから吸うとか噛むというのがいわば外界に接触する、外界を確かめる第一のやり方になってくる。ものがそばにあっても、つかんで、それを口に持っていって吸うとか噛むというかたちで、すべて外界にあるものに対して働きかけるときには吸うとか噛むということが中心になる。
それから疑惑みたいなものはお尻から来るんだという言い方もしています。つまり、疑惑とか疑い、不信、恐れ、脅威というのは何となく背後からやってくるという感じ方をこの時期に初めて覚えるんだ。疑惑、疑いというのはお尻から、背後からということが乳児期の特徴だ。そして人間が恐れの感情とか不意打ちの感情、おっかないものは後ろから襲ってくるという感じ方をまず基本的に覚えるのは乳児期の後半、1~2歳である。この言い方はとても興味深くて、また鋭い言い方だと思われます。
7 母親の態度のさまざまなニュアンス
いま言った特徴でもって乳児期というのを心理学者、哲学者という人たちは定義づけています。それで乳児期の問題というのは終わってくるわけです。いろんなことがありますが、たとえば基本的不信を母親からどういうかたちで植えつけられるかとなると、これは非常に難しいことです。また誰でもが免れがたいことでもあります。
自分の気分がゆったりして赤ちゃんを抱きしめて、お乳をちゃんと与えられるみたいな育て方を100%していたら何も文句はないわけですが、人間というのはそういうわけにいかなくて、一時的なことであれ、何かの原因があって、忙しく立ち働かなければならない。たとえばちょうどいま鍋が噴きこぼれているところだというときに、赤ちゃんが泣いて、あっちが心配でしょうがないのに、急いでそわそわしながら、早くやめればいいと思いながらおっぱいをやったりしているということは誰にでもあるし、どんな人でも免れない。そういうこと自体は一時的なことだからたいしたことではないけれども、それでも信頼感を損なう一時的な現象ではありうるわけです。そういう態度で何回か母親としておっぱいをやらざるをえない状態があったとしたら、それは乳児に対して不信感を与えることになるのは確実です。
その手のことは生活している限り避けがたいことです。どんな母親でもそういうことをやっています。早くやめないかなと思いながらおっぱいをやっているとか、泣いているから嫌で嫌でしょうがないんだけど、黙らせたほうがいいやということでおっぱいを吸わせるということは、どんな母親でもある時期、あるいはあるときやっている。それは免れがたいことですが、それでも不信感を覚えることは確実だと言えます。
しかし本当の意味の基本的不信感というのはそういうのではなくて、たとえば自分と夫とは仲が決定的に悪くなっていて、いつ別れようかと思っている。あの人の子だと思うと、おっぱいをやる気も本当はしないんだけど、やらなければ泣きやまないし、栄養失調になってしまうし、仕方がないから私はやっているんだということが1年とか2年とか続いたとしたらば、これは相当決定的な不信感ということになります。
そこでもって母親というのはいろんな態度ができます。つまり、そこが非常に複雑な問題になってくるわけですが、心の奥底では、こんな子はくたばったほうがいい、要らないんだと思いながら、仕方がないからおっぱいやってるというときにでも、知識、教養のあるお母さんは、そんな態度を見せたら子どもに悪いから、表面はニコニコと笑って、よしよしと言いながら、優しくするということも人によってはできる。また母親というのはそうでなければいけないものだという倫理観、道徳観を持っているとすれば、そのお母さんは心の中でどう思おうと、それは表さないで、言葉とか態度では優しくしてやらなければいけないと思いながら、しかし心の中ではまったく逆だということもありえます。それから最も簡単に、まだおっぱいを吸っているのに、ワーワー泣いても途中でぶん投げてしまうという母親もいます。それらの母親の態度というのはさまざまな段階で、さまざまなニュアンスとやり方がありうるわけです。
そうすると確実なことは何かというと、子どもに露骨にお前なんか嫌いだとか嫌だと見せつけたらよくないからといって、どんなに表面を優しくしようと、心の中で本当はぶん投げてやりたいと思っていたら、それは確実に子どもにはわかるし、生涯植えつけられています。乳児は何もしゃべらないし、積極的に学びもしませんが、受け入れということだけは100%心の底の底まで受け入れますから、ごまかしは利きません。表面をどういうふうに優しくしていたかということと、本当はそうじゃなかったということのさまざまな食い違いというのは全部、子どもが受け継ぐことになります。乳児は確実にわかりますから、ごまかすことはまったくできません。
長じてのち、私はあなたを育てるために、こんなに自分を犠牲にして苦心したんだよといくら言ったって、それはだめなんです。そうかなと表面は受け入れますが、心の底からそれを納得するということは本当にしていない限りはありえない。お母さんが子どもが大きくなってから、お前を育てるためにどれだけ苦心したかしれないといくら言ったって言わなくたって同じですから、ごまかしは全然利きません。それくらい乳児期というのはすごいことだとお考えになったほうがよろしいように僕には思えます。
8 幼児期と言葉の役割
そういうふうにして乳児期が過ぎて、幼児期に入ると、それぞれの学者さんはそれぞれの言い方をしていますが、言葉を覚えている、あるいは覚えたということが基本になります。言葉を覚えると何ができるかというと、さまざまな人がさまざまな言い方をしていますが、2つあります。ひとつは反射的に行動するのではなくて、何か言われたとかこういうことがあったとしたら、それはこうなのかな、ああなのかなと判断したりするという意味合いで、考えることができるようになります。
もうひとつは目の前に何かがなくても、それが目の前から横へ行ったらどうなるかとか、いま目の前にあるけど次にはどう行くだろうか、次にはこういうものはあっちへ行く、あるいは向こうから何か飛んできた、それは自分の近くに飛んできたけど、やがてこっちに来て当たるかもしれないと判断したりするということが幼児期にはできるようになりますが、それはなぜかというと、言葉を覚えたということが基本になるわけです。
つまり言葉を覚えたということは、物事を考えることを覚えた、あるいは目で見たもの、耳で聞いたもの、鼻でかいだものを自分の中で、あれは何の臭いかなとか考えることができるようになるということを意味します。ですから幼児期と乳児期と何が違うかというと、言葉を覚えたことを基本にして広がっていく世界が違ってくるということがわかります。
そうすると目の前にないものでも思い浮かべて、あれはこうなるに違いないということができるようになりますから、勢いそれを極端に広げると、いろんなことを空想することができるようになってきます。幼児期になると、夜中に目を覚まして、お化けが出てくるんじゃないかとか、風の音のガタガタというのを聞いて非常に怖くなってしまったりということもありますが、それはなぜかというと、目の前にあるものに反応するだけではなくて、目の前にないものでも、こういうふうにあるんじゃないかと空想したり想像したりすることができるようになったということから出てくる世界の広がりです。言葉を覚えたということが基本になって、それが展開されていくわけです。
9 遊ぶということ
もうひとつ心理学者が大切だと考えていることは何かというと、遊ぶ、遊びを始められるということです。これも基本的には言葉を覚えたということから来ると言っていいと思います。
遊びにはいくつもの種類があります。ひとつはお人形でままごとの遊びをするとか、実際に母親や父親がやっていて自分も入っている生活を、自分が母親になったり父親になったりということで、小規模でやってみせる。ままごと遊びとか、お医者さんごっことか、実際にある生活を小さな規模で再現してみせる遊び方というのがあります。
もうひとつそれと対照的なのは集団の遊びです。昔で言えば、近所の子でもっておにごっこをしたり、ベーゴマをやったり、集団で何かする遊びができるようになります。
この遊びの種類というのは、いまの子だったらパソコンやコンピューターゲームで遊ぶ、つまり映像で遊ぶという遊び方があります。この映像で遊ぶという遊び方は、ままごと遊びとかお人形遊びというのともちょっと違います。ままごと遊びは現実にある生活を小さな規模で自分たちが道具を使ってやってみせるという遊びですし、人形を子どもに仕立てて、自分が母親になって遊ぶというような遊び方です。映像の遊びというのはそういう意味合いでは何も手応えがあるわけではありません。テレビとか映画の映像があるだけであって、手応えといえば、ただボタンを押すとか操作するということだけです。つまり、現実の生活とか現実の何かがあるとすると、それを手応えのない映像に直して、そこで遊ぶという遊び方がいまだったらあります。
これからさまざまな科学技術が発達してくると、遊び方も発達してきて、もっと違う遊びもできてくるかもしれません。遊びの種類というのは増えていくかもしれませんが、基本的に言えば、現実の生活の中で起こる事柄を集団または個人でどういうかたちで小規模にしてやってみせるかということになります。
つまり、遊び方の基本というのは子どもにとっては生活の仕方それ自体であって、子どもにとって生活自体が遊びであり、遊び自体が生活であるということになります。やがて大人になれば、職業というものにどうやって対処したらいいのか、あるいは集団の場合には、社会的な生活の中でどう振る舞えばいいのか、そういう基本的な問題を遊びの中で展開するわけです。この幼児期に、そういう意味合いで遊びの展開をほぼ終わります。幼児にとって遊びは生活そのものであり、生活そのものが遊びであるというかたちになっています。種類はいかように増えていくかもしれませんが、基本はそういうところであまり変わらないんじゃないかと思えます。
ワロンという心理学者もだいたい同じことを言っています。日本の村瀬さんという人でもって4番目の赤いところを補ってありますが、村瀬さんはもっと細かい分け方をしていて、幼児期でも1.5~2.5歳と2.5~4.5歳とはちょっと違いますよと言っています。
1歳半~2歳半のところで、自分の心の中で考える、想像する、その中に自分というものがいつでも入ってくる、そういう入り方の自分というのを発見するときだ。つまり、現実に対して自己を発見するというのではなくて、自分の心の中で空想したりしているときに自分というものがその中にある、そういう意味の自分を発見する時期だと言っています。
2歳半~4歳半のときには、自分が空想したり何かを考えたり思い浮かべたりすることの中に、人間の共通性というものがあるんだ。本当の意味の自覚は青春期でなければ起こりませんが、そういうことが漠然とわかるという感じ方ができるようになってくるという分け方をしています。
それから4歳半~6歳半の幼児期の段階で、友達同士との争いとか勝負事、こうすると悪いんだとか、こうしたら人からとがめられるんだということを漠然と知るようになってくるという言い方をしています。
ここのところでそれぞれの学者さんで多少の言い方の違いがありますが、幼児期というのが、言葉を覚え、言葉の種類を増やしということの中で起こってくる世界の広がりなんだという意味合いで、乳児期と違うという認識では、どの学者さんも同じだと言うことができると思います。
10 児童期という根本的な矛盾――性的欲求の発現とその抑圧
本当を言いますと、ここらへんで性の兆しに基づくさまざまな兆候が兆すわけですが、この兆しが顕在化するのは次の児童期と専門家が言っている時期です。この児童期という区分は、もしも学校という制度がなかったとしたら成り立たないと思います。学校という制度があるから児童期という区分をせざるをえないし、しているんだと僕には思われます。こんなものは本当の意味合いでは人間にあるかどうか疑わしいといえば疑わしいんだということになってしまう。
そこが根本的な矛盾であり、根本的な問題ですが、もし児童期というものを僕が定義するとすれば非常に簡単です。本来的に言えば、人間の性にまつわる意識が発動すべき、つまり第一義的に前面に現れ出てくるべき時期であるにもかかわらず、学校制度があるために、あるいは教育の必然とか必要というのが人間にあるために、それを抑圧する。この時期はまず性的には禁欲を強いられて、その代わり知識の学習とかいろんな学習をとにかく第一義にさせられて、性的な意識というのは弾圧、抑圧されてしまう、後ろのほうに引っ込められてしまう時期だと定義すれば、児童期というのはいちばんわかりやすい。
児童期に起こる問題というのは、登校拒否から家庭内暴力、学校内暴力、その手のいまときどき問題になるようなあらゆることがあるでしょう。そんなものが全部起こるのがこの時期です。しかし、なぜ起こるかというのは非常に簡単なことで、本当ならば性的な表現行為がいちばん前面に顕在化していくまさにその時期に、それを弾圧、抑圧して、それは悪なんだ。きわめて禁欲的に勉学に次ぐ勉学、勉強しろ、学業に努めろ、知識を学習し、体育を学習し、道徳を学習しろ、それが第一義だ、これに違反したやつは劣等生である、これをよくやったやつは優等生であるというふうに、まるで逆のことをやる時期というのが児童期です。
この逆のことをやる時期が人間にとって必要なのかどうかは本格的に論議しなければ、簡単に決めつけることはできません。だから僕は簡単には決めつけませんが、基本的に児童期を定義しろ、児童期とは何だと言えと言われたら、僕だったらそう言います。つまり、性的な発現が初めて起こる時期に、それをいちばん下のほうに引っ込めて、抑圧し、抑制することが善であって、その代わり性的なこととはまったく関係のない、関係なくはないんでしょうが、知識、体育、道徳を勉強しろ。しかも制度として、勉強しなければだめなんだ、大人になれない、義務教育を通らなければ全然だめだというふうになっていて、とにかく強制的に何年間かやらせられ、やる。これにうまく適合して学べなかったら劣等生だ、学べたやつは優等生だと決定される時期です。
これはたしかに性的な発現力の抑圧であり、それを禁欲的に抑えたうえで、知識、体育、技術、道徳を学びなさいというふうに学ばされる。こういうことは人間にとって必要なんだよということになるのかもしれません。しかし、従来僕が知っている発達心理学者は誰一人としてそのことを本格的に論議した人はいません。本格的に論議できていない。これらの人も全部だめ、いい加減です。
また、いい加減に開放的なことを言う人もいます。こんなときに義務教育と称してぎゅうぎゅう学業を押しつけ、道徳、技術を押しつけて勉強し、義務教育を通らなければ先へ行けない、お前は世の中に出たってだめだと烙印を押される、こんなのはけしからんのだと簡単に言う教育研究者がいるんですが、これも僕は怪しいと思っています。本当にそうかというのはなかなか難しいことで、本格的に論議しきらなければならない重大な問題だと僕は考えています。
だから簡単に結論することはできません。人間というのは解放すべきものを抑圧して、強制的に学ばせなければ学べない、生涯学ぶことはない、そういうことを学ぶ時期が必要であるかどうかは非常に重要な問題であるし、わからない問題です。いまのところ結論することができない問題ですから、簡単に結論は言えませんが、もし基本的にこの時期を定義しろと言うなら、僕だったらいま申し上げたような定義をすると思います。この時期のあらゆる問題は全部その問題です。
11 理想の教師の姿
たとえば登校拒否でも、学校内暴力、いじめでもいいけれども、どうして起こるんだと考えるとするでしょう。そうすると、個々具体的な例を取ってくれば百通りの登校拒否、学校内暴力、いじめがあるとすれば、百通りの原因、百通りのきっかけがあります。しかし、そんなことは百通り、千通りやったって意味がないことであって、ただひとつの意味は非常にはっきりしています。
つまり、性の発現に伴って起こってくる遊びの欲求、ふざけたい欲求、暴れたい欲求を、そんなことは不可能でしょうが、教師がよくわかっていて、教室内のどこかで穴を開けておく。性的発現に伴う凶暴な要求、暴力の要求、騒ぎたい要求、ふざけたい要求に対して、まじめな教室のどこかに開放感の穴が開けられるような授業をもしやれる教師がいたら、と僕は理想的に申し上げますが、学校内暴力、登校拒否、そういうのは全部なくなってしまいます。基本的に言えばそうですよ。簡単なことです。
この時期は性的な発現の時期にもかかわらず、それを抑圧しておいて、まじめな知識とか道徳、技術の蓄積を教え込むという最も嫌な、言ってみれば相反することを教え込む時期ですから、その矛盾をどこかで穴を開けて解放するということができるような授業をやれる教育者がいたら、この問題は基本的には全部解けてしまいます。もしこの中に教育者の方がおられて、お前が言うほど簡単かと言われると、僕は一言もないんだけど、これは哲学として言っているわけで、基本的にはそうです。そういう授業ができたら、これは全部終わりだ、基本的に解決してしまいます。
それはどうやったらできるのかというのは専門家の問題であって、何か言うことはできないのですが、基本的には簡単なことです。この間に起こるあらゆる事柄は全部その問題だと思います。何を抑圧し、どんな知識を学ばせようとしているのかをよくよくわかっている教育者がいて、もしもその両方を、つまり解放しながら、しかも知識を植え込み、技術、道徳を植え込みということが同時にできる教育が、教室内なら教室内でも可能ならば、あるいは学校なら学校というものの中に可能だったら、あらゆるそういう問題は解けてなくなってしまうというのが結論だと僕には思われます。そこの問題に帰着すると思います。
もちろん心理学者たちはさまざまなことを述べています。しかし、基本はまったくそうです。性的な発現力に伴う人間の行動の仕方、暴れたくてしょうがない、騒ぎたくてしょうがない、悪ふざけしたくてしょうがない、遊びたくてしょうがない、笑いたくてしょうがない、そういうこともどこかで解放できるような教育のやり方ができるならば、少なくとも登校拒否から学校内暴力、いじめにわたる問題の大半はなくなってしまいます。
もうひとつ、これは逆に消極的な理由ですが、そういうふうに抑圧しておいて、知識を学べ、技術を学べ、道徳、規律を学べということを学校の中でやらせているのはまだいいとして、これに適合できない子、脱落する子、知識も途中まではわかったんだけど、それ以上蓄積するのはついていけないという子どもがいるわけです。そういう子どもがいたって解放すればいいんだけど、それは劣等生だ、これについてきたのが優等生だという等級の決め方をしたら、僕が劣等生だって、暴れるよりほかやることがないですよ。
つまり、性的な発現力に伴うあらゆることは抑圧されている。そうしておいて、知識とか技術を学べと押しつけられる。ついていけなかったらお前は劣等生だという等級をつけられる。そうしたらば暴れたり、いじめたり、学校の窓でもぶち壊したりする以外にやることがないわけです。だってしょうがないでしょう。抑圧されている、引っ込められている、学業にはついていけない、ついていけなければ劣等生だ、お前は先へ行けないと言われたら、人間にはやることがない、それならいくらでも暴れてやろうということになりますから、暴れるのは当然です。この種の問題は個々の原因を持ってくれば大変難しいわけですが、基本的には大変やさしいことで、大変やさしいことを解決するのが難しいというだけのことです。
それでは、どんな子どもが脱落しやすいかといったら、それは乳児のときにだいたい決まっています。母親が決めてしまっています。ここのところでうまくなかったら脱落しやすくなっているんです。どこからどう見たってしょうがないじゃないですかということになってしまいます。この状態が現在の状態だと思います。もしかするとこれはますます展開、発展していって、もっと拡張していくかもしれませんし、引っ込むかもしれませんし、波があるかもしれません。しかし、問題の基本点というのはすこぶる簡単だ。難しいけれども、単純だ。それは知らないよりも知っておいたほうがいいし、押さえないより押さえていたほうがいいと僕には思われます。
12 思春期前期の重要さ
さて、児童期を過ぎたら、あとは言うことなしということになってしまいます。あとひとつだけ人間の生涯を決する重要な時期というのは、児童期の末期か、思春期の前期か、児童期というのは性的発現力が徹底的に弾圧されて、禁欲的な学業成績優秀というのが優等生となるような制度になっていますから、そういう時期の終わりから思春期の初めにかけて、たとえば年上に決まっていますが、自分のおばさんとか、自分の家に家政婦さんがいたら家政婦さんでもいいんですが、そういう人から性的な手ほどきを受けたとか性的ないたずらをされたというチャンス、機会があったりすると、それは相当決定的な意味を持ちます。
言ってみれば人間の生涯の中で決定的な意味を持っているのは、乳児期とその時期しかないのです。その時期に、女性だったらレイプみたいな無理やり性的に犯されたという体験に該当するんでしょうが、男性だったら年上の女性から、接する機会がなければ近親とか家政婦さんといった人から性的に徹底的ないたずらをされた、手ほどきを受けたということが、たった一回ということではなくて、ある程度の期間重ねられたみたいなことがあったら、それはかなり決定的な影響を与えます。乳児のときほどではありませんが、というのはすでに分別がついていますから、自分なりの欲求もただ抑圧されているだけでありますし、ある程度の判断力もありますが、ものすごい衝撃を受けるわけで、その衝撃の体験はその人の生涯にわたって、特に家庭生活、結婚生活に対して決定的な影響を与えると思います。
しかし初めに申し上げたとおり、人間というのは決定論ではないのであって、弱点、欠陥、つらいことがあるとすれば、いつでもそれを超えようとするのがすなわち人間ですから、それを超えることはできます。ただ、大変な努力、大変なエネルギーを使わないと超えられないというくらい、非常に決定的に大切なことを意味していると思います。
13 ルソーの乳児期
それでは例をいくつか申し上げましょう。まずジャン=ジャック・ルソー、つまり世界の近代思想の曙を開いた巨人の一人ですが、そのルソーに『告白』というのがあります。岩波文庫で3冊本でありますし、やさしく書かれていて、いい本ですから、お読みになるといいと思います。ルソーが『告白』の中で書いていることがあります。僕は2つの時期が重要だというのは違うところから知識を獲得したり考えたりしているわけですが、どういうわけかその問題はどの偉大な人も偉大でない人も皆一致しています。ルソーみたいに偉大な人もその2つの時期をとても問題にしています。
乳児、ゼロ歳のときですが、ルソーは、自分は弱々しく、とうてい育ちそうもない、生きていけそうもないと言われた赤ん坊として生まれたんだと言っています。それはもちろん自分ではわからないわけで、近親の人か父親に聞いたんだと思います。尿が詰まって出ないということが症状としてあったそうで、とても育ちそうもない、ひ弱な子どもとして生まれた。そして生まれるとすぐに母親は、産後の肥立ちが悪いというんでしょうか、死んでしまった。自分は、父親の独身の妹が同居していて、そのおばに育てられることになった。
これだけ聞くと何でもないように思えますが、もし持とうとするならば決定的な意味を持ちます。母親の乳房はたぶん一度も吸ったことがない。それだからどうと言ってしまうと決定論になってしまうんですが、そういう意味ではなくて、しかし非常に重要なことのひとつだと思います。
それから日本でもこのごろは多くなりましたが、ヨーロッパでは義務みたいに結婚するというのはないから、同居している独身のおばさんとか姉さんとかがよくいるんです。そういう人が代わりに育てるということで、母親代わりに育ててくれた。独身でしたから、母乳ではなく育てられたということがあります。
これだけのことはみなさんだってそうだという人はたくさんいると思いますから、何でもないといえば何でもないんですが、逆に何かになったときにはものすごく重要な原因になるわけです。おわかりになりますか。つまり、このこと自体は、人によってはそんなの言っていられない、母親が弱かったら死んでしまうわけで、誰でもいるよ、そんなことをいちいち気にしたってしょうがないじゃないかということになるわけですが、逆にその人が何かになったら、大泥棒になったとか、性格破綻者、精神病になったとしたらば、それがものすごく重要な原因になります。そういう意味合いを持ちます。
14 偉大になることは救いではない
そしてもうひとつ、これは幼児として重要なことなんですが、親父さんがあるときから家を出て、別居になってしまう。それから寄宿舎に行くわけですが、その寄宿舎に行く8歳のときまで、自分が往来でよその子と駆け回って遊んだことはなかった、つまり遊ぶことを許してくれなかったと書いています。これはものすごく重要なことです。おばさんが、あんなガキと教育上よろしくないから遊ぶなと言って、家で遊ばせたんだと思います。でなければルソー自体が体が弱くて外で暴れて遊ぶということがなかったのか、どちらか、あるいは両方の原因だと思いますが、とにかく幼児期を過ぎて8歳まで外で近所の子どもと遊んだことは一度もなかったというんですが、これは冗談じゃないというほど重大なことです。
どんな心理学者でも挙げていることですが、集団的な遊びも覚えていく、シンボルとしての遊び、映像としての遊びも覚えていく、知識、空想も増えていくという時期に、外で遊んじゃいけないと言われた、そういう育ち方は決定的な意味を持つと思います。乳児期についても決定的なことであって、こんな人がまともに育つはずがないと言ってもいいんだけど、人間というのはそれを超えていくもので、もちろん超えたからルソーは普通の人より偉大になったわけです。
しかし、ルソーは『告白』の中で偉大になったということを書いていますが、偉大になったということはその人個人にとっては救いではないんです。あの人は偉大だと言ってくれた、そんなことは本人が本当に幸福か不幸かということにとってはどうってことはないんですよ。せいぜい褒められたとき、ちょっといい気持ちがしたというそれだけのことなんです。ルソーは、自分はものすごく不幸だったとも言っていますが、それは本当にそうなんです。本当に幸福かどうかというのは、ルソーは偉大な人だと言われたら、多少はいい気持ちがしたかもしれないし、お金も少しは入ったかもしれないけど、そういうのはあんまりたいしたことがない。それよりもルソーが内心で苦しんで、それを超えようとした、その苦しさのほうがはるかにつらいことで、はるかに不幸なことです。
だからルソーは、自分は一生涯不幸だったと言っています。あんな偉大な人がと誰でも言いたいところだけど、そんなことは全然問題にならないんです。それほど重大なことだと思います。こういう幼児期の育ち方をした。ましてや自分で書いているくらいですから。告白録ですから生涯のいろんなことを書いているはずですが、だらだら毎日あったことを書いているわけではなくて、自分の印象に深いこととか転機になったことを書いている。自分で書いているくらいだから、自分でも重大だと思っていることを書いているのは間違いないことで、それはとても重大だと思います。
それから家の中で育ったんだから当たり前なんですが、5、6歳のとき、死んだ母親が遺していった小説その他の本のたぐいはことごとく読み尽くしたと書いています。これは知識的には非常に早熟に育ったということを意味しましょう。まして外で遊ぶことはできないから、そういうことをする以外にないわけで、それはしただろうと思います。これはルソーを偉大な知識人にした助けにはなったでしょうが、かたわにした助けにもなったと僕は思います。
15 せっかんとマゾヒズム
さて、8歳のときに父親が事件を起こして家を出て、自分はおじさんに預けられ、おじさんの子ども、いとこと一緒に、ランベルシエという牧師さんの寄宿舎に預けられます。そこでルソーの生涯を決する事件があります。ヨーロッパには、適齢期だから結婚しろとあまり言わないから、オールドミスの独身の女の人が割合たくさんいるんです。そういう牧師さんの妹に、あるとき悪さをして、折檻される。この折檻というのもよくわからないんですが、ばかに偏執的なしつこい折檻をされるんです。鞭か何かでぶたれたりした。
そのときルソーは快感を感ずるんです。つまり、マゾヒックです。サドマゾの遊びというのがあるそうですが、マゾヒックな快感を感ずる。それを感じてからは、わざと悪いことをして折檻されるということを何度か繰り返すうちに、折檻されたくていたずらしているんだというのが牧師さんの妹にわかられてしまう。それまでは一緒の部屋で寝ていたんだけど、別の部屋へ行けと追い出されてしまうという事件があります。
原因は乳児のときにあって、母親が亡くなり、おばさんに育てられたということで、すでに第一義的に大変な傷、無意識のショックを受けているわけですが、これはある程度意識したときの第一の性的なショックです。ルソーにとって生涯の傷になります。それ以降は、きれいな女の人を見ると皆、牧師さんの妹と同じように、マゾヒックに自分を折檻してくれる人に見えた。ルソーは一生そうです。そういう傷をここで負うわけです。
なぜルソーはそんな傷を負ったか。おふくろさんに折檻されてぶん殴られたという体験をした人はたくさんいるけど、別にマゾヒックにならない人もたくさんいます。しかし、そういうふうに言うと乳児のときが問題になって、それはここの問題だということになる。ましてその延長線で、幼児のときに外でほかの男の子と遊ばせてくれなかったというのも決定的じゃないかとなるわけです。そういう意味合いで逆にさかのぼっていく。女の人に折檻されたら皆マゾヒックになるかというと、そんなことはない。それは違う。誰でもなるわけではないんだけど、そうなったとしたらばどうなんだということになってくると、あそこなんだというふうに逆になっていきます。
16 クルミの木の事件
もうひとつ牧師さんの事件があります。牧師さんの庭に、クルミの木があった。これもよくわからないんですが、牧師さんに教育上、お前はあのクルミの木に水をやれと言われた。そして、クルミの木以外のところに行ってはだめだと言われた。ただ水をくんできて、クルミの木に水をやってということをある時間やれ、今日もやり、明日もやれと言われたというんですが、そこが児童期ということに関連して非常にわかりにくいところです。つまり、ある年齢のときに、この種の厳格さに意味があるかどうか。
言ってみればクルミの木に水をやればいいんだろということでしょう。そうだったら、やるだけはやるから、ほかのことをしたっていいだろ、遊んだっていいだろということになる。ある量の水をやるということだったらちゃんとやるから、その代わり終わったら、あるいは途中で少し休んで、ほかの遊びをしたっていいだろということになりそうな気がするんだけど、そうでないですね。絶対いけない、とにかく一定量の水をクルミの木に何時間かやれ、今日もやれ、明日もやれ。教育というのはこういうふうになっています。
これはヨーロッパのある時期に特有なものなのか、それとも一般的に学童期、児童期における教育にはそういうことが本当に必要なのか、あるいは西欧社会でのみ必要であって、東洋的な社会の親子関係などの中では必要でないのか、そういうことは大変わかりにくいところです。こういう告白録などでどうも俺にはわからんなと思えるのはそういうところで、折檻というのもよくわからない。何もそんな怒らなくたっていいじゃないか。怒ったっていいけど、叩かなくたっていいじゃないか、お尻を引っぱたかなくたっていいじゃないかと思うんだけど、結局そうするでしょう。そういうのはよくわからないところです。
ここの場合でもそうです。クルミの木に水をやれと言われる。ところが、いたずら心を出すんです。それは当然だと思うんだけど、クルミの木のそばにヤナギの木があって、あそこにも水をやってやろうと思う。しかし少なくとも表面上はやりに行くことはできない。つまり、クルミの木に水をやれということだけしかやらせてくれなかった。そばにあるヤナギの木にやりたくてしょうがないんだけど、やらせてくれない。そこで、牧師がいないときに、クルミの木の根元からヤナギの木の根元に溝を掘って暗渠みたいにして、葉っぱをかぶせて、土をかぶせて、知らんぷりして、クルミの木に水をやると、幾分かはちゃんと流れていってヤナギの木に水が行くようにした。それが見つかったら、こんな子どもはいない、おじさんに言いつけると言われて、さんざん怒られたと言っています。
その2つの事件を契機にして、自分はランベルシエという牧師さんとその妹という先生であった2人に対して不信を抱くようになった。それは向こうにも反映して、おじさんが呼ばれて、引き取ってくれと言われて、家に帰されたと言っています。これは人間的な基本的信頼ということに関連するんでしょうが、それに対して初めてルソーが傷を受けたという体験だと思います。
17 思春期以降に持ち越されたマゾヒズム
ただ、ルソーが回顧しているところでは、このときの田園の生活、いとこと心の中を打ち明け合うような親密さを持つようになったことは自分にとって収穫だったと書いています。
ジュネーブの家に帰って2、3年は、今度は自発的に、いとこと2人で家をあまり出ないで、細工物に熱中した。弓をつくってみたり、笛をつくってみたり、凧をつくってみたり、紙鉄砲をつくってみたり、とにかくあらゆる細工物をやった。外にあまり出ないで、そういうことばかり2、3年熱中してやっていたと書いています。その種の体験は言ってみればルソーの児童期の体験に属するわけです。
それが思春期以降に持ち越されたのは何かというと、父親は退役軍人か何かと街で決闘の真似事みたいなけんかをして、剣を抜いたと訴えられて、裁判で有罪になって、おもしろくないので家を出てしまうんですが、その父親にルソーは会いに行った。そのとき自分は11歳だった。父親の家の近所に、ウィルソンと書いてありますが、父親の親しくしている奥さんがいた。その奥さんに娘さんが一人いた。その娘さんと自分は仲よくなった。娘さんは23歳だったと書いています。そのときその娘さんと自分とは、一面から見ると姉さんのように親しみ、一面から言うと恋人のように人並みに嫉妬したりしてという関係を結んだ。その結び方、姉さんのようにというところはルソーのマゾヒックなところと関係があると思います。
そういう恋愛と兄弟愛の中間みたいな、二重みたいな関係をその娘さんと結びながら、一方では近所に男勝りの娘がいて、その娘とはマゾヒックな関係を結んでいた。その娘に威張られて、怒られて、謝ったり服従して言いつけを聞いたりするというのが快感で、そういう関係を結んだ。その2つの関係をある時期まで持続して結び続けたということをルソーは告白しています。
この女性に対するマゾヒックな感じ方というのは生涯変わらないで持続したところだと、ルソーは自分でも書いています。そういう自分を顧みれば、大変不幸な生涯だったと思っていると言っています。いまもし心理学者が言ってみるとすると、ルソーは地で行っていると言うことができると思います。それくらい人間の幸不幸ということに対して非常に重要な意味を持つと言えます。
その下に太宰治の場合を書いてありますが、太宰治のことは僕が弘前か何かでやった本が出ていますから、そこで見てください。
18 三島由紀夫の乳児期
三島由紀夫さんの場合を言いますと、『仮面の告白』という作品の中で、乳児期のことをどういうふうに言っているかというと、ひとつは生まれたときの光景、産湯を使われたたらいのところに日光が差してきて、それがキラキラと見えたのを覚えていると言い張って、そんなばかなと笑われた。だいたいお前が生まれたのは午後9時ごろだ、日光が出ているわけがないと言われたと言っています。しかし僕は、生まれたときの光景を覚えていると言っていることは、何が重要かということはここではいいとして、とても重要な気がします。
三島さんという人もものすごく不幸な人です。生まれてから49日目に、母親は2階に、下におばあさんが寝ているわけですが、おばあさんがかわいくてしょうがなくて、2階で赤ん坊を育てるのは危ないと言って、母親から赤ん坊である自分、0歳の乳児である自分を切り離して自分の部屋に連れてきた。おばあさんが年とって病気がちで自分の寝室で寝ている、そこに自分を連れてきてしまった。そしておばあさんに育てられたと書いています。
おばあさんは病気であるし、脳神経症で、神経が病的に鋭くなっていて、厳格であり、偏執的であり、あらゆる病的な要素を備えていた。そのおばあさんが自分を放そうとしないし、母親のところへやろうとしない。自分の部屋に寝かせきりで育てられたと言っています。1歳未満のときに階段の3段目ぐらいから落っこちたことがあるとも言っています。こんなことは別にたいしたことがないような気もします。おばあさんの脳神経症というのは、おじいさんの病気のせいだということを誰が知っていただろうと書いてあるから、それは梅毒だと言っているんだと思います。
そういう幼児期、つまりおふくろさんがいるのに、49日たったらおふくろさんからおばあさんのところにもぎ取られて、おばあさんの病的な神経と病気で寝がちのところでおばあさんに育てられているというのはちょっとむちゃくちゃじゃないか、こんな育てられ方は不幸のどん底を約束されたようだということになると思います。そういう育てられ方を乳児のときにしています。
19 幼児期を象徴する体験と遊び
そして自分の幼児期を象徴する事件だと書いていることがあります。それはおばあさんが近所の若い衆と親しくしていて、夏祭りのときに家の中に神輿を呼び入れた。その呼び入れた男衆たちの、半分恍惚となったような、また高揚した、わっしょいわっしょいという掛け声とか振る舞いが自分に圧倒的な意味を持ったと言っています。もうひとつはそのとき家の庭に招き入れた町内の神輿がそこで暴れて、庭木を折ったりした。そういうことは子どものとき覚えがありますが、普段しゃくにさわっている家に行くと、わざとよくやりますから、(笑)きっとそういう意味合いで多少、あんちくしょう、あの家はすかしてやがると思われていたんじゃないでしょうか。だからちょっと暴れた。それも相当ショックで、幼年期の自分を象徴する体験だと言っています。
それから三島由紀夫さんも同じで、幼年期の遊び相手は、自分の病弱のために、近所の女の子3人と決められた。近所の女の子3人が家の中に招き入れられて、ままごと遊びみたいなのをして遊んだと言っています。これもものすごく決定的なことのように思います。
もうひとつ体験として言っているのは、5歳ごろに赤いコーヒー状のものを吐いた。2時間ばかり心臓が止まって死んだような状態になって、やっと2時間後に蘇生した。それは自家中毒だと診断された。自家中毒というのは、みなさんのほうがご存じだし、体験もおありだと思いますが、いまのお医者さんだったらきっと、どんどん食わせろと言うと思います。食わせないとは言わないと思います。それからお母さんが気持ちをゆったりしたほうがいいですよと言われると思います。もっと突っ込んで言えば、夫婦仲でも少しよくしたほうがいいですよということです。それで治ってしまうわけです。つまり自家中毒というのは、乳児、幼児にとっての欲求不満、抑圧です。その抑圧の原因は母親との関係とか母親と父親の関係とかいろいろあるでしょうが、いずれにせよそういうものだ。それ以降、自家中毒が持病になったと言っています。
20 マゾヒズムと同性愛
そしてもうひとつ重大なことは、ルソーの場合はマゾヒックですが、三島さんの場合はマゾヒックでもあるし、もしかすると、たぶんそうだと思いますが、同性愛者と言っていいようになります。
児童期に入ったころ、あるいは幼児期の末期ですが、ルソーと同じように、こういう遊び方をしていますから、本を読むよりほかないですから、読み書きは普通の子どもよりも達者になります。ところが何になりたいかと言った場合、たとえば俺は博士になりたいとか大将になりたいとか、昔の子ども、つまり僕らぐらいの年代の子どもはよく言うわけですが、そういうふうに言うのと同じ意味で、自分は汚穢屋さんとか花電車の運転手、地下鉄の切符切りになりたいと言ったと書いています。
このことはマゾヒックと同性愛的ということのひとつの象徴として言っていいくらいで、三島さんの決定的な不幸というのは生まれたとき、乳児のときに決定しているし、まして幼児期の育てられ方というのはルソーと瓜ふたつとまでは言いませんが、非常に近似しています。これでもって一生生きていけというのは無理だよと言っていいくらい、大変不幸な育てられ方を乳幼児期を通してされています。ここで三島さんがマゾヒックな性向を持ち、同性愛的になっていったというのはまことに当然であるし、それ以外には生きていくすべもないくらい大変だったろうなと思われます。
ルソーも意志の強い人だったんでしょうが、三島さんも意志の大変強い人でしたから、みなさんもちろんご存じでしょうが、長ずるに及んで、ボディービルをやって、ひ弱な虚弱児童だったという自分の面影がまったくないみたいな、筋骨隆々たる体にしてしまいます。剣道、空手は有段者になるし、駆け足はやるしということで、体を自分で人工的に意志的に鍛えてしまいます。
三島さんの刻苦勉励の生涯の努力というのはことごとくそうです。全部、意志的な努力です。乳幼児期にすでに植えつけられてしまった、決定されてしまった自分の資質を超えよう、超えようとする努力に次ぐ努力、あるいは奮励努力、刻苦勉励に次ぐ勉励、その連続です。
徹底的に自分を人工的にしてしまいます。肉体すら人工的に鍛えてしまいます。普通の人よりももっと頑健な筋肉隆々たる体にしてしまいます。スポーツ、武道の達人、有段者に自分を鍛えてしまいます。もちろん僕らの時代で言えば世界的な数少ない日本の作家、小説家に自分をしていってしまいます。結局最後には人工的なものの均衡がぶっつりと切れて死んでしまう、割腹自殺してしまうということになりますが、三島さんの刻苦勉励の生涯と、肉体さえも意志的に鍛えてつくってしまうというやり方、生き方、それを全部決定しているのは乳幼児期だと思います。
三島さんは、僕らの同時代では偉大な小説家、世界的と言える非常にまれな作家ですが、そのこと自体はルソーの場合と同じで、人間は自分の置かれた資質、宿命というものをいかに超えるか、いかに超えられる存在かということの意味で、2人ともたぐいまれなお手本、模範であると言えます。これ以上の模範はないというくらい、模範的な生涯を送った人です。しかし、いったん違う面からいくと、こんなに不幸な育ち方と不幸な生涯を送った人はいないと言っていいくらい、不幸な人であると言えます。
つまり、われわれも大なり小なり不幸も背負っているわけですが、われわれの背負っている不幸はこれらの人に比べればはるかに楽なものだ。これらの人たちは乳児あるいは幼児のときに、お前は生きてはいけないんだよと言われたと同じくらい、ひどい育てられ方をしています。これは物質的な問題でも何でもありません。たぶん個々の人を取ってきたら、ルソーのおばさんも、三島由紀夫のおばあさんもお母さんも普通の優しい人であったんでしょうが、いったん子どもと母親という問題の関係の中に置かれたときの幸不幸の決定の仕方から言えば、普通の人よりはるかに不幸で、言ってみればお前は生きてはいけないんだよと言われているのと同じような生かされ方、育てられ方をしながら、それを超えよう、超えようとした生涯だと言うことができます。
21 子どもとは何か
子どもとは何なのかということになりますが、子どもというものは子ども単独では意味がまったくない存在、また定義することができない存在です。少なくとも母親、もっと言えば父親も交えて、親というものと込みでしか定義することもできないし、決めることもできない。だからいったん児童期、思春期になって、非行化したとか学校内暴力、家庭内暴力、おかしくなってしまったと言ったときには、半分はもう遅いんです。
しかし半分は、そんなことは簡単なことよ、それは母親、父親との問題よということが、解明できるというのはおかしいけど、父親、母親の側からも子どもの側からも、そのとき自分はこう考えたんだけど、本当はこう考えてやるべきだったというようなことが十分なかたちでわかって、育てられ方がわかり、育て方をちゃんと話し合っていくことができて、全部わかった、こうだったんだ、それでこういうことになっているんだということが解けたら、そんなものはいつだって解けてしまう。それ以外の解かれ方はありえない。本当を言えば、それでも半分は遅いんだから、半分は初めのときの問題だから、初めにしたほうがいいですよとなるわけです。だから初めに決定論的なものが半分あって、いったん表れた思春期とかに、まだ半分は余地があるよ、さかのぼる余地もあるよということになると思います。
子どもというのはあくまでも父親、母親、つまり親というものと2世代の込みで考えなければ成り立たない考え方ですし、込みで考えるべきだと僕には思われます。そうすると、いろんな問題がおのずから解けていくことがあると思います。僕らがこういうことをよくよくわかることができたら、またこういうことに対して割合にフランクに話すことができたり話し合えることができたりということがあったとしたら非常にいいことだし、子どもにとっても親にとっても幸いなことだと思われます。
しかし、僕らは大なり小なりそんなことはできなくて、たくさんの隠しごととか抑圧、子どもに対してうまいことを言ったり、親からうまいことを言われているんだけど本当は違っていたとか、そんなことをたくさん持っているわけです。そういうふうにして生きているのが僕らの現状であって、まずまず大過ないのはなぜかといったら、50%、あるいは55%ぐらいはまあまあで育ったから、まあまあやっている。(笑)40%となったら、相当きついわけですよ。まともにやっていくにはきついし、まともな振りをするのもきついし、それを超えようとするのも大変きついという場面になっている。これはみなさんも外見がどうであるにもかかわらず、心の中をよくよくあれしてご覧になれば、全部思い当たることが、僕も思い当たることしか言っていないわけで、おありになると思います。
つまりこういう問題が、たとえば子どもについて考えられる基本的な問題だと僕には思われます。まだここに分裂病者の女の子の場合とか、太宰治の場合とかありますが、それはみなさんがいまのことを基にしてお考えくだされば、いかようにでも考え方を切り開いていくことができるんじゃないかと思われます。時間もまいりましたので、これで終わります。(笑)