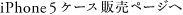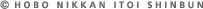紳士が立っていた。
六十歳前後といったところだろう。しかし背筋はすっと伸び、衰えは感じさせない。上品な銀縁のメガネをかけていて、にこにこと笑っている。
しかし、お客さんじゃない、と今村が感じたのは、メガネの紳士が上下一体となった作業着、いわゆる「つなぎ」を着ていたからである。夏の目前に控える蒸し暑い日に袖もまくらず、つなぎの中にはアイロンの効いたシャツを着込んでいる。
「いらっしゃいませ」と、一応、今村は言ったが、意味合いとしては「何のご用ですか?」といった感じだった。そういう対応に紳士は慣れているようで、席に座るでもなく、店内を見回すでもなく、カウンターの中の今村に向かって微笑みながらこう言った。
「営業中に申し訳ございません。店長様でいらっしゃいますか?」
「はい、そうですが」
何かの営業かな、と今村は思った。
この古ぼけた喫茶店に飛び込みの営業が入ってくるのは珍しいことではなかった。なにしろ、辺り一帯に店らしい店といえば、この喫茶デュラムセモリナくらいしかない。あてもなく歩き回るうちにここらへたどり着いた営業担当者が、ダメ元兼休憩の意味でドアベルを鳴らすのはよくあることだった。
つなぎの紳士は店長の怪訝な視線を予期していたようで、何か質問を受ける前にポケットから名刺を出しながらにこやかに言った。
「カスガ電機の鳥飼と申します」
「はぁ」
カウンター越しに名刺を受け取る。鳥飼は微笑みを崩すことなく言った。
「いつも弊社の製品をご愛用いただきまして、まことにありがとうございます」
今村には、覚えがなかった。カスガ電機……? 鳥飼はにっこりと笑ったまま、天井を指刺した。
「こちらでございます。弊社のエアーコンディショナー。おそらく、ECSS-5600かと」
見上げる天井には、埋め込み式のエアコンがある。型番もメーカーも気にしたことがなかった。ばたばたと居抜きで入ったときからそこにある。今村は正直に言った。
「そうなんですか。いや、よくわかってないんですが」
「ECSS-5600です。間違いありません。といいますのも──」
鳥飼はぐいと乗り出した。
「このECSS-5600は室外機に特徴があります。いえ、機能的には普通の室外機です。ECSS-5600の室外機は、内面ではなく外見的に特別なのです」
「はぁ」という今村の相づちを気にせず鳥飼は続けた。
「特徴はその曲線にあります。ほぼ直線で構成された室外機にあって、ファンを覆う部分に施された独特の曲線。これが、ひどく美しい。や、これは個人的な評価になりますな。ですが、そう感じるのは断じて私だけではないでしょう」
鳥飼は指先でクイッとメガネのフレームを持ち上げた。
「人はとりたてて室外機の外見なぞに興味を持ちませんから、その美しさに気づきません。けれども、もしも何かのめぐり合わせで複数のエアコン室外機を見比べる機会に恵まれたら、きっと気づくはずです。ECSS-5600の室外機は特異だと。美麗だと。ソフィストケイトの極みだと」
今村はその姿を思い浮かべようとしたが、店の室外機がどこにあるのかさえ思い出せなかった。今村の目が窓の当たりをさまよったのを見て、鳥飼は言った。
「この店の室外機はあちらの西側の壁の外にあります。私は店の前の通りのずっと向こう側から気づきました。ひと目見て気づきました。あそこにECSS-5600の室外機があると。つまり、あの喫茶店にはECSS-5600が備え付けられていると」
喫茶デュラムセモリナは、もともとは古い商店街の一角にあった。しかし、周囲の店舗と土地を所有する地主が見切りをつけたようで、2年ほどまえからあちこちの建物が一斉に取り壊されてしまった。とはいえ再開発の具体的な計画もまだないようで、周囲はいったん駐車場と自販機だらけになっている。いってみれば、広い場所にぽつんと一軒、古い喫茶店があるような状態だから、おそらく室外機も見つけやすかっただろう。
「それで、エアコンがどうかしましたか」
今村は訊いた。鳥飼はうなずいた。
「営業中に恐縮ですが、ちょっと検査させてもらってよろしいでしょうか?」
いま? 今村は当然気が進まない。
「あの、とくに問題なく動いてますが」
すると鳥飼の顔が急に曇った。あれほど生き生きと語っていたのに、ひどく悲しげな表情だった。
「いまのところは、大丈夫のようですね」
「いまのところは?」
続きをうながすと、鳥飼の顔はさらに悲しげに歪んだ。その深い悲しみには若干の悔しさと憂いが含まれているようだった。鳥飼は噛みしめるように今村に告げた。
「残念ながら、ECSS-5600はリコール対象商品なのです」
「えっ」
「申し訳ございません」
鳥飼は深々と頭を下げた。そして古びたバッグから手慣れた動作でファイルを取り出すと、開いて書類を見せた。リコール対象商品リストのなかに、たしかにその型番がある。
「そうなんですか。じゃ、使い続けてると?」
「はい。困ったことになります」
鳥飼は寂しげに首を振った。
「ですから、内部部品の交換、修繕を前提に、ちょっと検査させていただければと」
「そうですか……そういうことであれば」
「ありがとうございます」
鳥飼はまた頭を下げた。きれいなお辞儀だ。
「あの、このエアコンを使い続けているとどうなるんでしょうか?」
今村が訊くと、鳥飼は一瞬言葉に詰まった。そして言った。
「中爆発する可能性があります」
「ちゅ? ちゅうばくはつ?」
「はい。最悪の場合、中爆発する可能性があります」
「……中爆発? ですか?」
「中爆発です」
「中爆発って、なんですか?」
「中爆発は、中くらいの爆発です」
「中くらいの、爆発?」
「そうです。中爆発は、大爆発と小爆発の中間くらいの爆発です。中爆発は大爆発よりも小さく、小爆発よりも大きい。いや、こんなことは説明するまでもありませんね」
そう言って鳥飼はアハハハハと笑った。笑い声だけ妙に甲高かった。
「さて、それでは失礼して──」
鳥飼はそう言って荷物を置くと、エアコンの下へガラガラと店のテーブルのひとつを移動させ、ひょいと靴を脱いでそこへ上がった。ある意味、非常識な行為だったが、身のこなしが軽やかだったので不自然さを感じなかった。鳥飼は真下からエアコンの噴出口をじろじろと眺め、両手を上げてあちこちをコンコンと軽く叩いた。
そして、その古風な機械の働きぶりを確かめるべく、鳥飼は天井へ向けてじっと耳をすませた。しばし、そのまま動かない。その静止は、周囲の者にも同調をうながす緊張感をともなっていた。今村も思わず息を止めて耳をすませた。
それは、先客の二人も同様である。
ドアベルが鳴って以降、男と店長の独特のやり取りを由希子も謙一も無視することができなかった。二人は室外機の美しさについての話を聞き、中爆発に興味をそそられ、そしていま、天井のエアコンの音につい耳をすませていた。
「なぁ」と、こらえきれず謙一が小さくささやいた。
「場所、変えようか?」
謙一はできるだけ優しくそう言った。それは結論を曖昧にするためだけの煙幕のような優しさではなく、本心からのものだった。さきほどから謙一は由希子に言いようのないシンパシーを感じていたのだが、由希子はもちろん、謙一自身もその意味がよくわかってなかった。
ただ、謙一は、ここでの曖昧な別れ話をいったんスタートラインまで戻したいと強く感じていた。
「こんなところで話すのもなんだし、さ」
謙一は努めて親密な感じで言った。由希子はその親密さが気に入らなかった。
「いや、いい、続けましょ」
由希子はそう言って、さり気なく水の入ったコップを手元へわずかに引き寄せた。察知して、謙一の左肘あたりがピクリと動いた。
「……ほほぅ」と天井付近で鳥飼が言った。
対面する男女の視線も自然、そちらへ移る。
「大丈夫そうですか?」と喫茶店の店主が下から問いかける。
「……いや……これはなかなか……」
鳥飼は目を閉じて、聞き入っている。そのまましばらく変化がない。こらえきれず今村は尋ねた。
「音で、わかるんですか?」
鳥飼はゆっくりと目を開け、穏やかに答えた。
「わかります。音で、すべてがわかります」
今村はもう一度耳をすませてみた。しかしやはりなにもわからない。首をかしげる今村に向かって鳥飼は言った。
「機械の調子はだいたい音でわかります。なにか問題を抱えていると、どこかにほんの少し、不自然な音が混じるものです。人だってそうじゃないですか? 体調が悪いとき、機嫌がよくないとき、その人の声を聞くだけでわかったりしませんか?」
そうかもしれない、と由希子は思った。
「人だけじゃなくてね──」そう言うと鳥飼はつなぎのポケットからiPhoneを取り出した。ロックを解除すると画面を操作し、身をかがめてそれを今村に見せた。
かわいいチワワの写真だった。
「マツジロウといいます」
「かわいいですね」
「マツジロウの鳴き声を聞くと私は彼の考えていることがだいたいわかります」
「長く飼ってらっしゃるんですか」
「もう11年になります」
「11年。長いですね」
「それだけ長くいっしょにいると、鳴き声だけでなく、駆け寄ってくるときの足音とか、お腹に耳をあてたときのグルグルいう音とか、ちょっとした音を聞くだけでいろんなことがわかるようになってきます」
今村は手にしたiPhoneを鳥飼に返した。iPhoneのケースには顔の黒い犬の写真がプリントされていた。マツジロウではなく別の犬だ。
「耳が、いいんですね」
iPhoneを返しながら今村は言った。鳥飼は少し照れくさそうに笑った。
「否定しません。私は子どものころからずっと吹奏楽をやっていました」
「楽器はなにを?」
「ホルンです。グレザリアン式の」
「グレザ……なんです?」
「グレザリアン式ホルン」
今村も由希子も謙一も、そんな楽器は知らなかった。
それについて今村が質問しようとしたとき、エアコンの音を聞いていた鳥飼が眉をしかめた。
「む、まずいな……」
鳥飼はそうつぶやくと、少し立ち位置を変えて、違う場所の音を聞いた。
「なにか?」と今村が訊いた。
「ちょっと……まずいですね……このままだと」
「え? 爆発ですか?」
「中爆発する可能性がないとはいえません」
ガタン、と音を立てて起ち上がったのは謙一だった。額にじっとりと汗をかいている。それを見て、鳥飼が慌てて言った。
「あ、いえ、大丈夫です、可能性の問題ですから。あの、申し訳ありませんが──」
鳥飼は今村に向き直るとこう言った。
「エアコンを切ってもらえますか。いますぐに」
今村は慌てて壁のスイッチを押してエアコンを止めた。
すぉぉぉぉぅぅぅむ…………と、ファンが止まる。訪れた静寂によって、それまで鳴っていた音は逆説的に存在感を際立たせた。
「なあ、やっぱり、場所変えない?」と落ち着かない様子で謙一が言った。「いや」と由希子は反射的に答えた。相手がこの流れを嫌っているということは、自分にとってチャンスだ。由希子はコップをさらに自分の近くへ引き寄せた。思ったとおり、謙一はそれに気づいていない。謙一は、止まったエアコンを調べる鳥飼をちらちら見ながら、鼻の頭をしきりに親指で掻いている。いらいらしているときの彼のクセだ。
そういえば、と由希子は思った。謙一は大きな物音に弱い男だった。雷とか、背後からの突然のクラクション。ことに破裂音には弱く、以前、二人で懐かしい折紙を披露し合ってたとき、由希子が紙鉄砲を折って「パン」と振って鳴らすと、本気で嫌がっていた。電車の中で誰かが大きなくしゃみをしたとき、「わっ」と声を上げて驚いたこともある。
エアコンがよくないことになっている? 中爆発? 謙一はしきりに鼻の頭を掻いていた。
いまなら行ける、と由希子は確信した。が、同時に、いまはダメだとも悟った。いまの謙一にコップの水をぶっかけても意味がない。なぜなら、コップの水は別れ話の最中に相手にぶっかけてこそ、意味がある。エアコンの調子に怯えながら、検査するつなぎの男を見つめていらいらしている謙一に水をぶっかけたところで、ただのイタズラにしかならない。
由希子は水の入ったコップから指を離した。
つまり、彼にコップの水をぶっかけるためには、彼を別れ話に引き戻さなければならない。果たして自分は何を望んでいるんだろう、と由希子は思った。
そして再びドアベルが鳴る。
その人が勢いよくドアを開けたため、ドアベルはジャガジュワワァンとけたたましく鳴った。おかげで謙一は椅子から飛び上がるほど驚いた。
(続く)
|