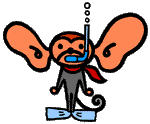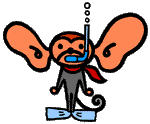|
第14回 黒船(9)
退船命令
前回は、遭難した黒船ハーマン号が、
逃げ場のない岩礁地帯を、さながら幽霊船のように、
ユラユラと漂い始めたところまで、お話をしました。
乗客たちが、起き上がってきました。
生きた心地がしないとは、
このようなことをいうのでしょうか。
屈強の乗組員たちは、荒海にほんろうされながらも、
歯をくいしばって、その抜き差しならない状況に
堪えています。
船長は、人々が船から離れないのが、
一番安全であると判断していました。
その晩は凍てつくような寒さでした。
2月の厳冬のさなかですから、
船中の多くの人たちにとって、
その寒さはとても堪え難いものでした。
近くの浜辺の住民たちが、松明を灯し、
口々になにか言い合って、大騒ぎをし始めたころです。
その船から数個の遭難信号灯が、
夜空に打ち上げられました。
その打ち上げは、まるで花火を見ているかのようでした。
船の左右両舷に備えつけられていた、数隻の救命ボートは、
滝のように船に打ち込んでくる大波に流されたり、
あるいは浜辺にたどり着く前に、水舟になったりで、
ほとんど役には立ちませんでした。
ハーマン号の喫水が、さらに深さを増してくると、
人々は甲板にゾロゾロと上がってきました。
波浪がやがて、最上階の甲板にまで、
ジワジワと押し寄せてくると、船長たちは、
すぐに人々を操舵室に集めました。
次から次へと押し寄せてくる高波に
さらわれる人もいました。
負傷して流されたり、
難破船の破片につかまって波間に浮いていた人たちは、
打ち寄せる波で岸まで運ばれてゆきました。
遭難者たちにとって、
とてつもなく長い一夜が明けようとしていました。
意外なことに、難破船は、
岸から距離にしてわずか3/4マイルほどの、
小さな湾口付近にあることがわかりました。
船中には、およそ100人くらいの乗客たちが
とり残されていました。
あれほど凄まじかった風と波が、
まるでウソのように急速におさまってきたようです。
その凪ぎを待っていたかのように、
救命ボートの一隻と、数隻の小型の伝馬船が
岸から近づいてきました。
うまい具合に、難破船の横腹にピタリと船を着けると、
船内に残されている人たちを自分たちの船へと誘導し、
助けてくれました。
日本人の行動は、とても勇敢でした。
船が暗礁に接触した後、すぐにその状況を理解し、
すばらしい自制心と冷静沈着さで、
静かにリーダーの命令を待っていました。
船長はやがて、腰帯に刀を結び、裸のまま海に飛び込んで
岸まで泳ぐよう、彼らに伝えたのです。
さて、つづきは、次回をお楽しみに。
井上たかひこ

「水中考古学への招待」
井上たかひこ著 成山堂書店
2000円(税別)
ISBN4-425-91101-6
|