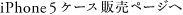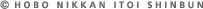銃口ははっきりと鳥飼に向けられている。おまけに、トリガーに指をかけている貴史は侮辱されたと感じている。喫茶デュラムセモリナはいまや密室で、全体がある種の興奮状態にある。
何が起きてもおかしくない状況だ。
「試してみるか」
そのセリフは二度目だったが、真剣味が明らかに違った。貴史の右腕の筋肉の一部が衝撃にそなえてぐっと盛り上がる。
銃を向けられたつなぎの老紳士は答えた。
「かまいません」
由希子と謙一は緊張で身動きひとつできなかった。マリはさっきから貧血みたいになっていて、意識が遠のきそうだった。今村だけが、ほんのわずかに残る店長としての機能から、どうすればいいのだろうかと考えていた。
ふぅ、と低く息を吐き出したのは貴史のほうである。重圧は撃つほうにある。撃たれるほうの鳥飼は、どこか醒めているようだった。
銃を向ける貴史を諭すように、鳥飼は言った。
「どうぞ。それは空砲です」
貴史は奥歯を噛みしめる。腹立たしい。鳥飼の眉間を見つめながら、弾丸がそこにめり込むことを想像する。飛び散るだろうか。近すぎるだろうか。ああ、もう、なんだか、いろいろと面倒だ。
「じゃあ、いいな」
貴史は言った。最終通告。鳥飼は目を閉じた。ほんのわずかな沈黙。
やがて、鳥飼は言った。
「……ちょっと、考えさせてください」
え、とマリは思った。鳥飼の態度があまりに盤石だったから、そのひと言がひどく意外だったのだ。それは由希子も謙一も今村も同じだった。そして、貴史にとっても。また、鳥飼に揺らぎが生まれることで、事態はより深刻さを増したようでもあった。夢の中みたいだった場面に現実の色彩が配され、実際的な恐怖が重く場に流れ出る。どっと重力を感じる。
戸惑ったのは、貴史も同じである。銃口をそらすことも、トリガーをひくこともできない。こんな状態で保留になるとは思わなかった。
「で?」
いら立ちながら貴史は言った。
「どうすんだ?」
貴史の唇の一端が不自然につり上がる。鳥飼は目を開けて、穏やかに言った。
「やっぱり、やめます」
え、とマリは口に出してしまった。
「辞退します」
鳥飼はそう言って、両手を軽く上げた。貴史は混乱した。そして、相手にイニシアチブを取られていることに腹を立てた。
「なんだよそれ」
あやうく貴史は撃つところだった。いろいろ面倒だった。
「空砲なんだろ?」
「空砲です」
「じゃ、試せよ」
「……いいえ」
「命が惜しいか」
「はい」
え、と貴史は思った。怒りがこみ上げる。
「お前、言ってること、めちゃくちゃだろ」
「すみません」
なぜか鳥飼が謝る。貴史は言葉がない。鳥飼が続ける。
「困るんです、万が一、私が家に帰れないと」
鳥飼は不安そうに首を振る。とても不安そうに。
「私は、私の実感として、それは空砲だと思ってます。自信もあります。けど、それとは別の次元で、まったく別の話として、私が家に帰れないかもしれないというのは、絶対に避けたい」
貴史は何がなんだかわからない。鳥飼は、貴史の目を見つめて、やさしく言った。
「家に、チワワがいましてね」
鳥飼はその姿を思い浮かべていた。
「もう老犬です。11歳になります。食欲は落ちましたし、寝て過ごすことも多いんですが、大好きな毎朝の散歩は絶対に欠かせません」
貴史はまたしても鳥飼の話を聞いていた。
「マツジロウといいます。毎朝、マツジロウの足音で目を覚まします。起きて、散歩に行くのです。毎朝です。それが……それができなくなるのは、困る」
鳥飼は申し訳なさそうに言った。少し涙ぐんでいる。
「本当に困るんです」
そして例のものすごく自然な動作で、テーブルの上に集められているiPhoneのなかから自分のひとつを手に取った。スリープを解除すると、待ち受け画面は犬の写真である。それを貴史に見せながら、鳥飼は言う。
「マツジロウです」
鳥飼の頬を涙が一筋、伝う。そして鳥飼はiPhoneを元の位置に戻し、ごく自然に背中を向けると、壁際の席まで歩いていって座った。
彼は辞退したのだ。
それで、貴史はむしろ冷静になった。不条理な辞退だったが、最初の不条理を持ち込んだのは自分だった。だったら続きも不条理でいい。辞退した男を怒鳴りつけてもしかたがない。
「じゃ、お前でいいや」
貴史は銃口を座っている由希子のこめかみに向けた。無造作な挙動に、新品の金属みたいな冷ややかさがあった。
由希子は反応できない。すぐに撃ちそうな気配がある。なぜなら、この男は、いろんなことが面倒くさくなっている。由希子は目を見開き、向かいに座る謙一を見た。
謙一は反応しようとした。が、大混乱していた。謙一は別の財布を持っていた。そこに10万円持っているかもしれなかった。しかし、正確にいくら入っているのかわからなかったし、それをいま確かめさせてくださいというわけにもいかなかった。いや、そういう問題ではなくて、いまは彼女に向けられた銃口をなんとかしなくてはいけなかった。飛びかかって、いや、その前に立ち上がって、いや、とにかく何か言うべきだろうか? ああ、あっちの財布にはいくら入ってるんだ。
貴史は、もう撃ちそうだった。唐突で深刻な恐怖が由希子を貫いた。
「待ってください」
別の場所から声が響いた。声にはしっかりとした意志があったので、貴史はその無造作な行為を中断してそちらを見ずにはいられなかった。
今村はもう一度、くり返した。
「待ってください。試すなら、私をお願いします」
彼は、喫茶デュラムセモリナの店長だった。
(つづく)
|