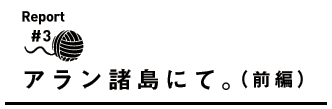2012年6月。
三國さん、和枝さん、たまちゃんの3人は、
ヨーロッパの西の端、アラン諸島を目指しました。
今回から前後編にわけて、
島々をめぐる3人の様子をレポートします。
成田空港を出てから、
飛行機を乗り継ぎ、列車に揺られ、
最後の乗り物は、船。
およそ40分、波のあいだを進むと‥‥
岩だらけの島の姿が浮かんできました。
ここまでが約20時間。
それはなかなか、ヘビーな道のり。
アラン諸島はどこにあるのか、
再度、地図で確認してみましょう。
イギリスの西に位置するアイルランドの、そのまた西。
世界の果てのような場所に、その島々はあります。
Googleマップを拡大すれば、
アラン諸島は、3つの島から成ることがわかります。
東から順に、
「イニュシィア島」
「イニシュマーン島」
「イニュシュモア島」という名前‥‥
覚えにくいですよね、現地にいても混乱しました。
面積は、いちばん大きなイニュシュモア島でさえ、
東西約12キロ、南北4キロというサイズ。
人口は3島あわせて約1400人。
石灰質の岩盤が隆起してできたこの島々。
おとずれた旅人の目にまず飛び込んでくるのは、
島中に広がる、この石垣の壁でしょう。
よろしければ上のGoogleマップをどんどん拡大して、
さらに表示を「写真」に切り替えてみてください。
3つの島々にびっしりと、
まるで編みものの目のように広がる石垣が
はっきりと見て取れます。(Googleマップは、すごい)
この石垣は、「トレリス」と呼ばれています。
▲トレリスはどこまでも、どこにいっても。
岩盤に覆われ、「土」がないこの島では、
かつて、ハンマーで岩を砕き、海草をまぜることで
ジャガイモなどを育てる土壌をつくったといいます。
トレリスは、
そうしてつくられた貴重な「土」が
強風で飛ばされないように張り巡らされているのです。
▲冬には、トレリスが冷たい強風をさえぎって‥‥
▲牛や馬、羊たちを凍えから守る役割も。
強風が渡る、そのアランの海を、
斉藤和枝さんは、気がつけば見つめていました。
▲船に乗るたび、海の中を見つめる和枝さん。
▲港では、海の生命感を探すように。
▲しゃがみこみ、痩せた地面をみつめることも。
帰国後しばらくして和枝さんにお会いしたとき、
しみじみ話してくださったことがとても印象的でした。
「アラン島に行って、気仙沼の豊かさを知りました。
あんなに厳しい場所で、
漁業や農業をやっている人たちがいる‥‥。
気仙沼は恵まれています。
津波はあったけど、それでもこんなに豊かな海がある。
アラン島から帰ってきて、
子どもたちの前で話をする機会があったんです。
『みんなが住んでる場所はね、
世界中でもとっても恵まれた場所なんだよ』
そういうことを自信をもって話せました」
そんな厳しい土地で、
大西洋の強風から身を守るために、
島の人々がトレリスのように身につけていたのが、
独特な網目模様の「アランセーター」でした。
ここから続くモノクロの画像は、
1960年代のはじめにアラン諸島で撮られたものです。
しばしこころを、50数年前に‥‥。
▲イギリスやスコットランドの漁村の
フィッシャーマンズセーターがこの島々に伝わり、
アランセーターがうまれました。
▲当時、島の女性はみな、
競い合うように編みものをしていたそうです。
1950年代、アランセーターはアメリカを中心に
世界中に輸出され人気を博します。
日本では、1969年〜1971年にかけて大流行しました。
その背景に、ひとりの人物の存在がありました。
パトレイグ・オショコン氏。
編みものをアラン諸島の産業として成立させた人物です。
▲もともとは弁護士。
40代でアイルランドの言葉や古い風俗の研究をはじめ、
そこで知った美しいセーターを世界中に広めるように。
オショコン氏は編みもののコンテストを開き、
島の優秀な編み手を集めました。
彼女たちには、当時の平均的な手編み内職賃金の
3倍を支払っていたそうです。
▲最盛期、島には100人以上の編み手がいたとか。
時間を現在に戻しましょう。
半世紀が過ぎ、流行も落ち着いたいま、
アランセーターはどんな存在になっているのでしょう?
三國さん、和枝さん、たまちゃんの3人は、
3つの島をめぐり、アランニットに出会っていきます。
まずは、この場所からご紹介。
土産物屋さんが軒をつらねる一画の、
「アランセーターマーケット」というお店です。
足を踏み入れれば、ぎっしりとセーター。
そのほとんどは機械編みのものでした。
一部、ハンドニット(手編み)のセーターもありましたが、
編み手そのものがすくなくなったため、
ハンドニットをたくさん扱うことが難しくなったとか。
このお店に手編みのセーターをおろす編み手は
現在6人しかいなくて、
しかもそのほとんどは島の人ではないそうです。
なるほど、なるほど‥‥。
こんな工場もたずねました。
『イニシマン・ニッティング社』。
アラン諸島の編みもの産業として、
いまも成功を続けている会社です。
▲工場に隣接するショップには、
アランの伝統を受け継いだ新しいニットが。
ニューヨークや東京の有名店に商品を送り出す
人気のニッティングメーカーで、
基本的には機械編みで様々なアイテムをつくっています。
▲店内にはアランの伝統を伝える写真をディスプレイ。
創業者のターラック・デ・ブラカン氏は、
雇用を増やすことも目的として会社をたちあげていました。
▲アラン諸島、伝統のボート、
「カラハ」をかつぐ3人の男がロゴマーク。
すてきなショップでした。
実際ここで、たくさんお買いものもしました。
でも、「気仙沼ニッティング」は
「手編みニット」を産業にするプロジェクトです。
ハンドニットに、会いにいきましょう。
ふつうの住宅のように見えるたてものの壁に、
「ARAN KNITWEAR」の文字。
ここには、
ひとりの女性が30年かけて編みあげた
ニットの数々がありました。
作者の名は、メアリー・オフラハティさん。
2年前に病気で亡くなられた女性です。
残されたハンドニットを
夫のシェイマスさんがここで管理・販売していました。
▲シェイマスさんは現役時代、灯台守の仕事をしていました。
▲メアリーさんの思いがこめられたセーターたち。
▲複数の柄をたっぷりと編み込む‥‥
それがメアリーさんの作風でした。
編みものを仕事にしていなくても、
趣味で続けたり、家族や親戚のために編んでいる人は、
ふつうにいらっしゃいました。
この女性は、お世話になった宿の奥さま。
宿で編みものの話をしていたら、
ご自分が編んだものを見せてくださり、
アランセーターについてのお話を聞かせてくれたのでした。
それはたとえば、セーターの柄について。
様々なモチーフがあり、
それぞれに豊漁や安全などの意味が込められているけれど、
「家紋」というわけではないのだそうです。
ただし、自分が編んだセーターは一目でわかるので、
不幸にして海難事故が起きた場合は、
それを着ているのが誰かを判別できるのだとか。
なるほどー。
こうしていくつかの
手編みのアランセーターに出会っていくなかで、
この旅に出かけた3名が、
ひとめ惚れをするセーターがあらわれます。
それが、こちら。
三國万里子さんはこのセーターを見て、
「自分のデザインでないことが悔しいです」
と笑いながらおっしゃいました。
たくさんのすてきなセーターを見てきて、
それぞれにいいなぁと思ってきた、3人ですが、
これはとくべつだったようです。
なぜとくべつなのか‥‥言葉ではうまく言えない様子。
はたして、たまちゃんが試着をさせてもらったら‥‥。
どうでしょう、サイズ感もぴったり。
似合う。
なによりも、本人がこんなにうれしそう。
このセーターを編んだモレッド・イ・フラハータさんと、
いっしょに写真を撮ってもらうことになりました。
モレッドさんは、お母さんも編みものの名人で、
最盛期には島のまとめ役をしていたそうです。
ご自身も娘さんとお孫さんに編みものを教えながら、
息子さんが経営するカフェで、
手編みの作品を販売されているのだとか。
記念写真をお願いしたら、
こころよく‥‥というか、とてもうれしそうに、
ほんとうにうれしそうに、
応えてくださいました。
なんでしょう‥‥この感覚は‥‥?
うれしくて、よろこばれて、またうれしくて‥‥。
私たちが今回の旅で見つけるべきものは、
どうやらこの感覚の近くにあるものかもしれない。
そんなことを3人は思いはじめました。
そして‥‥
そのことをはっきりとわからせてくれる、
ひとりの編み手に、このあと3人は出会うのです。
(つづきます)
※今回、本文中に登場した
1960年代初めのアラン諸島の貴重な画像は、
静岡市の洋服屋さん、
『セヴィルロウ倶樂部』のご協力で掲載されました。
店主の野沢弥市朗さんは、
1980年代にパトレイグ・オショコン氏と知り合い
日本でのエージェントを務めていたかたです。
『セヴィルロウ倶樂部』では現在も、
アラン諸島・アイルランドで編まれた
ハンドニットのアランセーターを取り扱っています。
くわしくはHPをご覧ください。
|