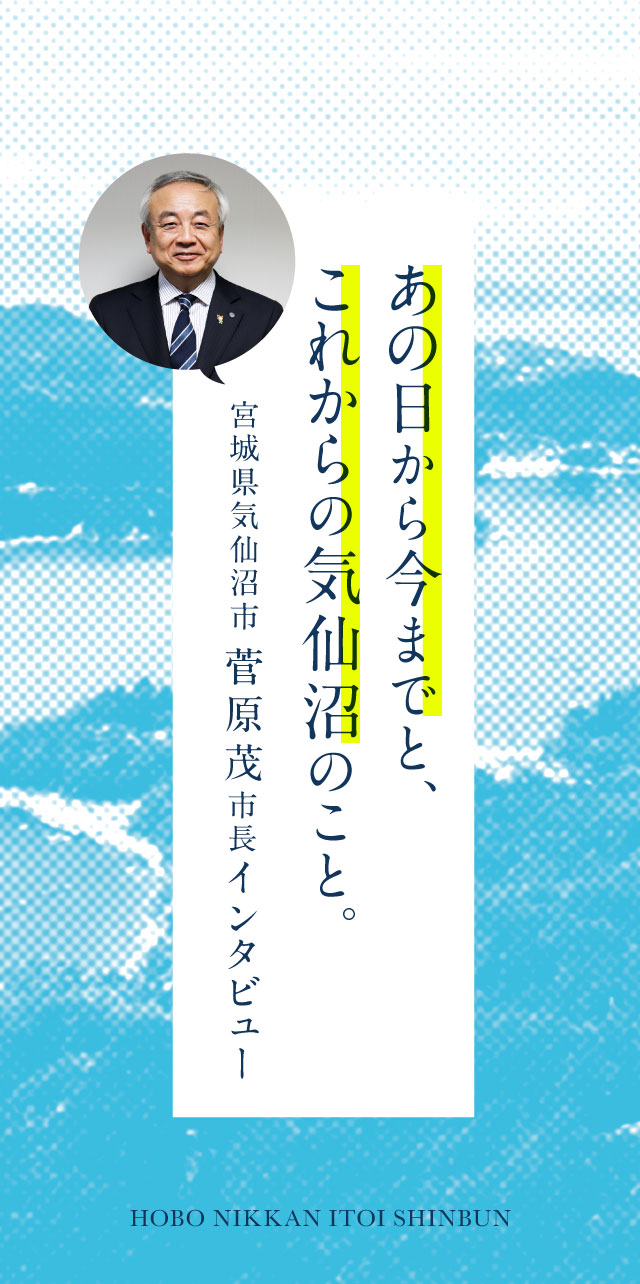
ほぼ日が気仙沼とご縁ができ、
何度も行き来するなかで、菅原市長と
お会いする機会がたびたびありました。
落語会「気仙沼さんま寄席」の
はじまりも、市長と糸井の話がきっかけでした。
市長が現職に就かれたのは震災の前年、
そして震災後11年経った今も、
市長として気仙沼市を導いておられます。
甚大な被害を受けた気仙沼が、
どのようにして現在の姿になったのか、
復興をずっと見続けてこられた市長だからこそ
語れる言葉がありました。
このときの続きのようなインタビュー、
担当はほぼ日の藤田です。
※インタビューは2月末にZOOMで行いました。
写真は、3月に現地で撮影したものです。
- ――
- よろしくお願いいたします。
8年前に市長にインタビューを
させていただきました。
その節はありがとうございました。
- 菅原
- よく覚えていますよ。
当時は大震災のことを聞くということが、
話す側以上に、聞く皆さんも
いろんな神経を使われた時期なのではと思っています。
- ――
- 当時、お話を伺うなかで、
市長がおっしゃった、震災翌日に見た海には
色彩がなかった、という言葉が心に残っています。
- 菅原
- ええ。色がないというか、
本当にセピア色だったんです。
50年前の写真を見たような、
SFなんかでよくある、人類がいなくなって
自分だけが残されてしまったようなシーンを
連想させる色でした。
その後、実際に大島にも渡りましたけど、
コーヒー牛乳の上に油が浮いて、
その上を船が走ってるような感じでね。
- ――
- ああ‥‥。
市長は、もともと気仙沼のお生まれで、
海の近くでお育ちになったんですよね。
- 菅原
- そうです。私の生まれたところは、
道路一本挟んですぐ海だったんです。
春夏秋冬、さまざまな海と船と、そこに行きかう人を
日常的に見てきました。
でも、我々が小さいころのほうが
海は汚かったんですよ。
- ――
- えっ、そうなんですか。
- 菅原
- 出入港には船がいっぱいで、生活物資が
海にバーッと流されて、
湾の角にはゴミがたまっていました。
そのなかに電球の白熱灯なんかが混じってるので、
学校帰りに石を拾って、
それを割るというのが僕らの遊びだったんです。
他にもタモでクラゲをとったり、
小さいころ、よく岸壁から海に落っこちる夢を見たり。
まあ、そんなふうな海との密接な関わりのなかで
生きてきましたね。

- ――
- そんなふうに身近だった海が、
ある日突然襲いかかって来るなんてことは、
想像もできないようなことだったのでしょうか。
- 菅原
- 私は昭和33年の1月生まれなんですが、
以前は、気仙沼市民の記憶の中の津波と言えば、
昭和35年5月のチリ地震津波で、
チリからやってきた遠地津波のことだったんです。
当時私は2歳だったので、その記憶はありません。
で、そのあとも津波注意報や警報には遭遇しているんですが、
このまま私は津波そのものは見ないで
一生を過ごすかもしれない、という思いがありました。
- ――
- 人生に何度も起こるようなことではない、と。
- 菅原
- はい。そう思っていたところ、
東日本大震災の1年前、平成22年2月28日、
やはりまたチリから津波が来て、
一部の岸壁を津波が超えたり、
養殖施設がぐちゃぐちゃになったりしたところを見ました。
津波というのは私の中ではずっと想像の世界だったけれど、
大人になって初めて体験して、それが自分にとっては
最後の津波の体験かもしれないという思いがありました。
ところがその翌年、我々の想像をはるかに
超えるような大津波が押し寄せてきたんです。
- ――
- しかもそのとき市長は確か
就任されて1年も経たないときだった‥‥。
- 菅原
- そうですね。いま申し上げたのは
個人としての思いで、
市長としては、就任後は、
宮城県沖地震は来るということが前提で、
その覚悟もしてましたし、
気仙沼市の防災体制もそのように動いていました。
宮城県沖地震というものが、
99%の確率でやってくるという予測があったんです。
ただ、実際来た津波は、想定されていたものとは、
全く違うスケールのものでした。

- ――
- 3月11日、市長はそのとき市役所にいて、
人命救助を最優先にしつつも、
全ての方が極限状態のなか、
四方八方からいろんなことが押し寄せてきて、
指示するといっても、めちゃくちゃな状況だった、と
おっしゃっていましたね。
- 菅原
- そうなんです。でも、当時は、
特に悩むとか迷うなんて暇もなく、
ただできることを一つ一つ対応するしかないという感じでした。
そのなかで、現場の人達には
ベストを尽くしていただいたと思っています。
この津波と、他の災害と違うところは、
たとえば川のどこかが決壊した、
などのポイントが掴めないことなんです。
海岸地帯の全てがポイントで、
同時多発的に災害状態になっているので、
我々が直後にできることは非常に限られていました。
- ――
- 当時、水の被害だけでなく、
津波で燃料タンクが倒されて
火災がおき、気仙沼湾が火の海にもなった、と。
- 菅原
- はい。陸上の火事と海の火事と両方ありまして、
海の火事はもう手の付けようがないという状態でした。
陸上の方についても市内の消防には限度がありましたが、
翌12日の夕方に東京消防庁を中心とした
緊急消防援助隊が気仙沼に到着したんです。
私は市内の視察をしている途中だったんですが、
東京消防庁の車と交差点でちょうど遭遇しまして、
それからどんどんどんどん消防車が連なって
気仙沼に入ってきたんです。
車両でいうと50台以上の消防車の隊列を見て、
心の底から「助かった!」と思いました。
- ――
- 「助かった」と‥‥。
- 菅原
- その人達は12日の朝から数時間かけて
気仙沼に向かって来てくれた人達なんです。
装備も優れた消防車が何台も何台も来ましたので、
心強くてね。
到着してお疲れになってるはずなんですが、
そのまま消火にあたってくださいました。
これなしには何ともできなかった。
それから人を交代しながら、長く気仙沼の火災に
対応していただきました。
気仙沼の火災が鎮火したのは、それから2週間後なんです。
平成23年の3月25日がいわゆる「鎮火宣言」なので。
- ――
- 2週間‥‥。
そんなに長い期間燃え続けるというのは、
想像を絶します。
- 菅原
- そうですね。気仙沼の消防も警察も自衛隊も、
東京消防庁等の緊急消防援助隊の皆さんがたも
合わせて行方不明者の捜索をして。
結果的には、亡くなった人を
見つけていく形なんですけども、
残ってる建物に入って、人がいないかを確認して、
印をつけていく。
家に「CR」の文字をスプレーで書いてましたね。
クリアーのCRです。
- ――
- この場所は見た、という印に。
市長は、当時一番辛い仕事だったのは、
遺体安置所の担当になった職員だったと思うと
おっしゃっていましたね。
あれから11年が経ちますけど、
行方不明の方が今も200名以上いらっしゃると‥‥。
- 菅原
- 多くの行方不明者は、津波の引き波で、
海から戻って来れなかったんだと思っています。
特に気仙沼湾の外側、外洋に面しているところに
行方不明者が多いと思います。
ご家族の方一人一人が心の整理をしては思い出し、
心の整理をしては思い出し、
ということの繰り返しなのではないかと想像しています。
そのことが頭から離れる時間は、
年月とともに少しずつ長くなっていくのでしょうが、
考える時間が減ることそのものに
罪悪感のようなものを感じる方もいるでしょうし、
人によっても差があるものだと思っています。
- ――
- その、町まるごとの悲しみを乗り越えながら、
皆さんが復興に向かって進んでこられたと思うのですが、
11年を振り返って、市長の心に残っていることは、
どんなことがありますか。
- 菅原
- それは、やはり追悼式ですね。
震災の半年後、平成23年の9月11日に
最初の追悼式を行いました。
翌年の3月11日にも行い、それから毎年
追悼式を行っています。
震災から半年後に初めて追悼式をした日、
私は出口に立って、献花してお帰りになる
ご遺族をお見送りしたわけですが、
そのとき自分がものすごく‥‥この言い方が
適切かどうかわかりませんが、
ものすごく、疲れてしまったんです。
それはずっと立っているからということではなく、
顔を合わせてお辞儀をするとき、
ご遺族の方々の表情に、非常に重さがあった。
それを私が多少なりとも受ける形になったことで、
体にきたんでしょうね。
それが回を重ねるごとに少しずつ、
私も耐えられるようになってきた。
というのも、ご遺族の皆さん方の顔から
重さが少しとれて、少しずつ柔らかな表情に
戻ってきているように思うんです。
追悼式の開催に感謝の言葉をいただくこともあり、
ご遺族の方々が、少しずつ元気を
取り戻していっているのを、自分の体ごと感じています。
- ――
- 相当の覚悟をもって、
ご遺族のお気持ちに寄り添いながら、
復興を進めてこられたのではと思うのですが、
個人として考えた場合、その重みに耐えられない、
投げ出してしまいたい、というような状況や
気持ちになられたことはなかったのでしょうか。
- 菅原
- それはないですね。
投げ出したいと思ったことは一度もないです。
市長としての職責に対しては
常にフルスロットルで続けてきています。
投げ出したいと思うことは、考えのどこにもない。
市長という仕事は、平時も含めて
そういうことだろうなと思っています。
大震災の直後はやらなくちゃならないことだけが多くて、
やった方がいいこと、やりたいことは後回しです。
でも、その比率が少しずつ変わっていき、
だんだんやらなくちゃいけないことだけではなくて、
やったほうがいいこと、やりたいことが
少しずつ増えてきました。
それが復興だというふうに思います。
- ――
- 復興、ということについて、
やりたいことというのは、
たとえばどのようなことでしょう。
- 菅原
- 復興事業の中でいうと、
たとえば造船所を移転して統合して大きくするだとか、
津波に耐えられる石油タンク基地を作る、
ということがあります。
そういうことは復旧ではなくて復興であり、
もっといえば、創造的復興を増やしていく、ということですね。
それから、まちづくりにおいて
これはやっていこうと力を入れてきたのは「人材育成」です。
気仙沼市が他と際立って違っているのは、
そこにものすごく力を入れてきたことなんです。
- ――
- 人材育成に。
- 菅原
- 震災後に、被災地にはほぼ日さんも含めて、
外部の方達がいろいろお世話をしてくださって
素晴らしい知恵を授けてくださったり、
いろんな機会、チャンスをくれたわけですけど、
それに対応できる人を増やさなくてはいけない。
気仙沼で人材の育成をすることによって、
自分ごととしてまちづくりを担う人達が動き始める。
併せて、市外からの支援に対して、
レスポンスのいい、反応のいい市民の数を
増やすことも目標でした。
というのも、
気仙沼が「すぐ反応をしてくれる」という場所になると、
支援をする側にとっても、非常にやりやすいでしょう。
- ――
- たしかに、そうですね。
- 菅原
- この11年、私達は、
そして市民は大きく変わったと思います。
最初は、NPO、NGOなど支援をしてくださる方との
付き合い方に戸惑ったと思います。
そんなにしていただいていいの? というような。
言葉を選ばなきゃいけませんが、
この方達は何者なんだろう、
というような思いもあったと思うんです。
じきに、この方達は私達のことを考えてくれて、
いろんな能力をお持ちの方なんだ、
ということがわかってきまして、
本当にさまざまな支援をいただいてきました。
震災で、かけがえのない命も含めて、
失ったものはとっても大きいですが、
それでも震災後に私達が得たものも、
ものすごく大きいんです。
それは人と人との繋がり。一言で言えば縁です。
震災直後は、みんなで助け合って
この難局を乗り切るんだ、避難所を運営するんだ、
という絆が生まれ、「絆」が大切な言葉になりました。
その後、私達が復興過程で感じた、
一番大事な言葉は、「縁」だと思います。

- ――
- 縁。
- 菅原
- はい。この縁が、気仙沼市や、
気仙沼市民にとって、宝なんです。
震災がなければ
お会いすることができなかった皆さんから
いろんな機会をいただいて、元気にさせてもらって。
交流の幅が広まっただけではなくて、
人によっては、仕事の面でも、個人の活動においても、
大きな飛躍に繋がった方もいらっしゃいます。
私達はただ、
この縁に支えられてここまできたなあと思っています。
(つづきます)
2022-03-11-FRI

