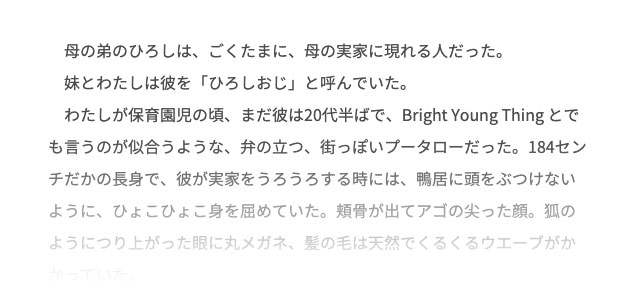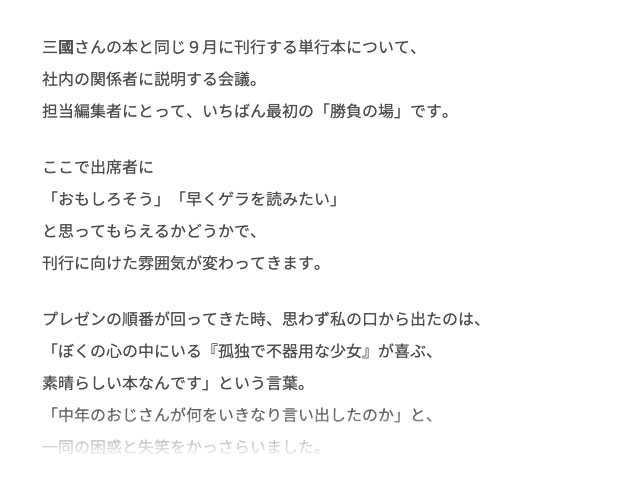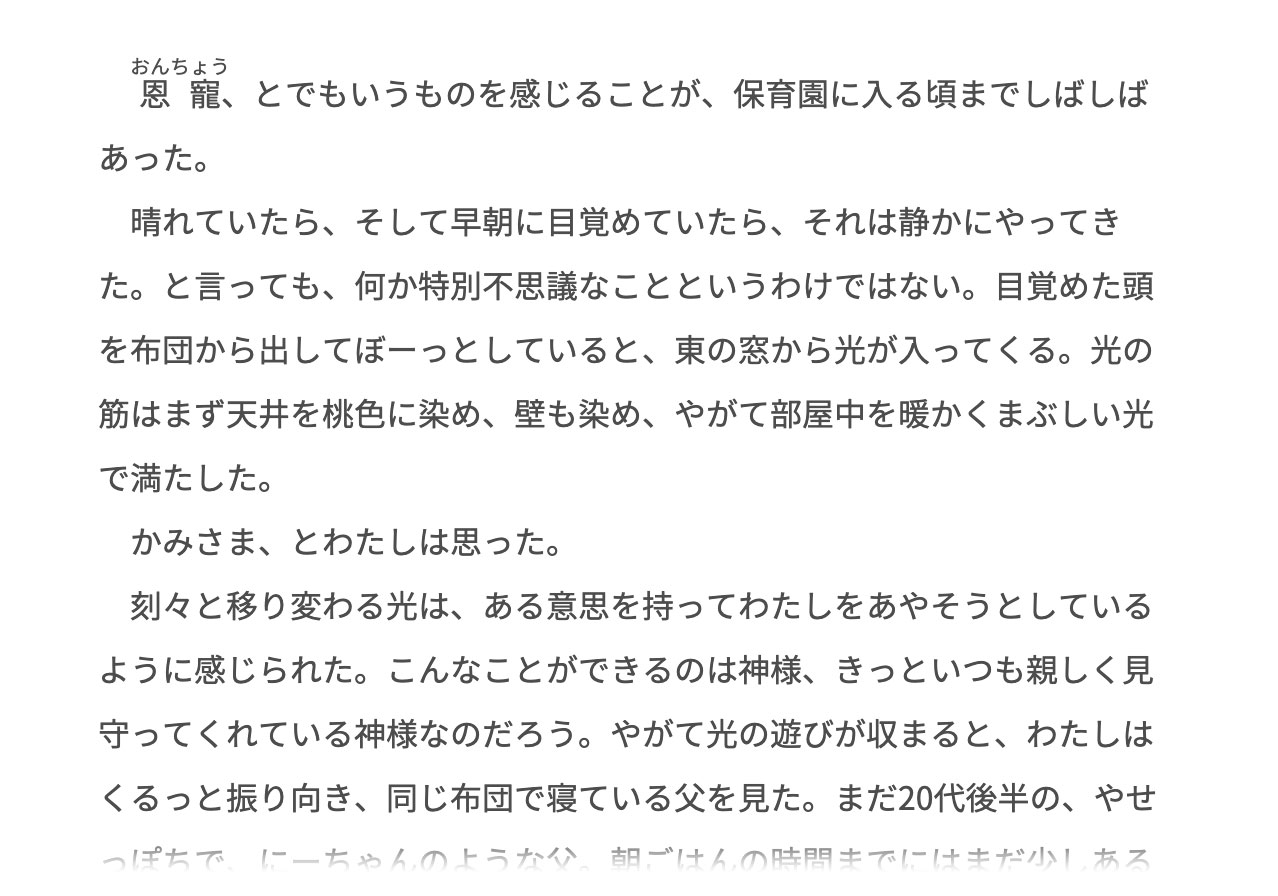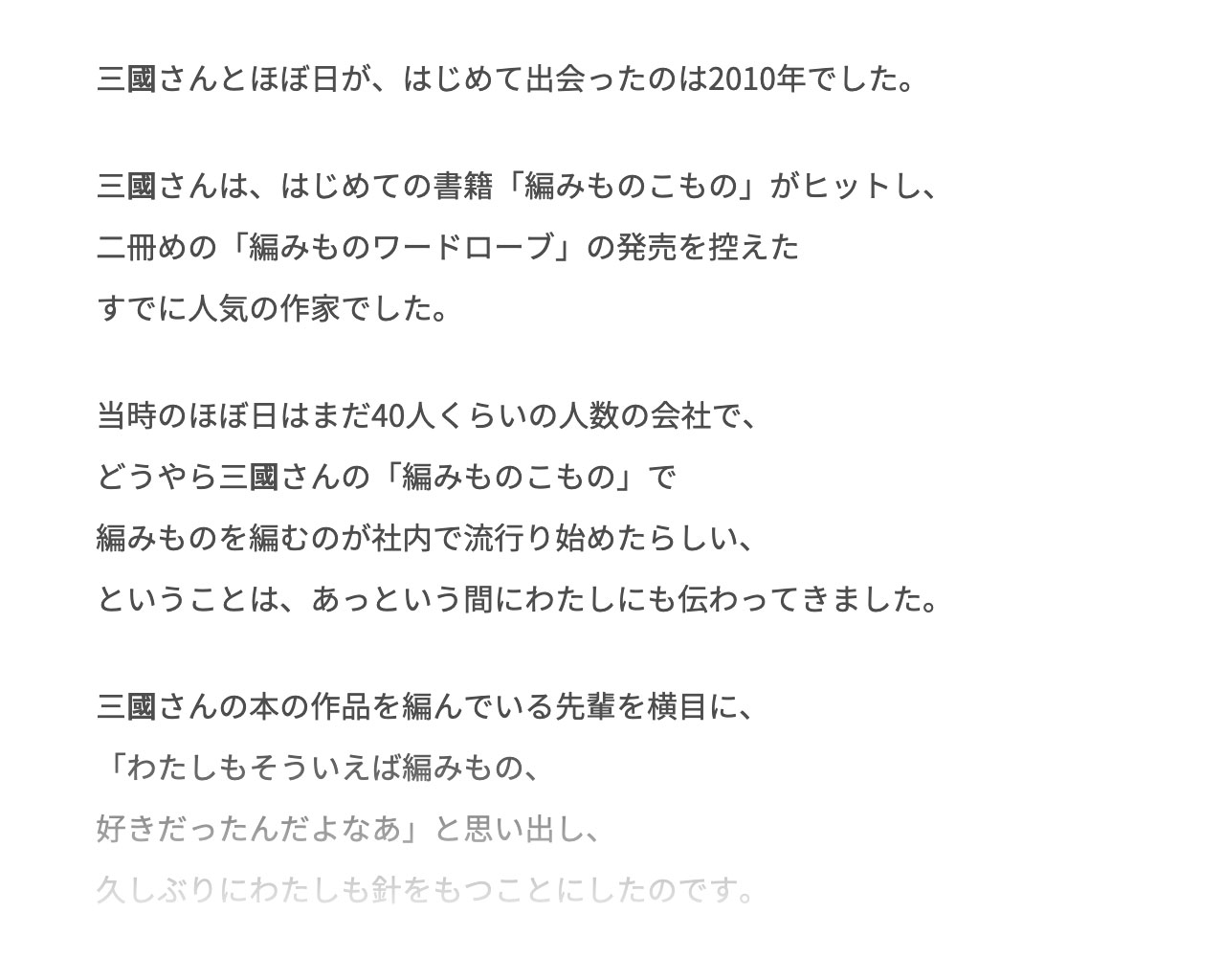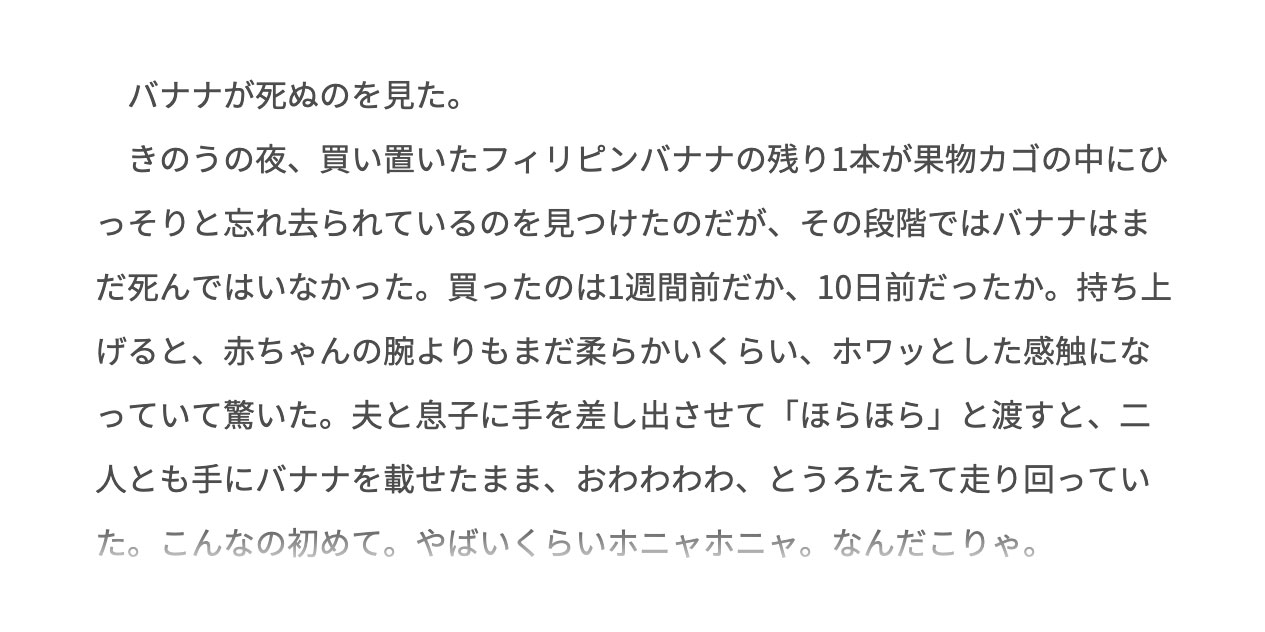ニットデザイナーの三國万里子さんが、
新潮社さんから初のエッセイ集を
出すことになりました。タイトルは、
『編めば編むほどわたしはわたしになっていった』。
この素敵なデビューをほぼ日は応援します!
新潮社さんと相談し、本のなかから3編を特別に
試し読みできるようにしていただきましたので、
ぜひ(ぜひ!)お読みください。
本の担当編集者である松本太郎さんと、
ほぼ日の乗組員2名による推薦文も一緒にどうぞ。
写真・有賀傑 モデル・松浦りょう メイク・草場妙子
三國万里子さんの文章に出会ってください

- 毎年、すてきな作品を発表し、
多くのファンが新作を待ち望んでいる
ニットデザイナーの三國万里子さんが、
このたび、新潮社さんから、はじめてのエッセイ集、
『編めば編むほどわたしはわたしになっていった』を
リリースすることになりました! - この素敵なニュースを聞いて、
「いつかそうなると思っていたよ!」と
誇らしく思うファンの方も多いと思います。
なぜなら、三國さんがときどき書かれる文章は、
短いものも、長いものも、すごくいいから! - 新しい作家・三國万里子さんの晴れのデビューを、
私たちほぼ日はもちろん応援します!
まだ三國さんの文章に触れたことのない方は
ぜひこの本で三國さんの文章に出会ってほしい。
本に収められた29編のエッセイのなかから、
とびきりの3編を掲載させていただき、
試し読みできるようにしました。 - また、本の担当者である新潮社の松本太郎さんと、
この本の誕生の現場にたまたま居合わせた
ほぼ日の永田とみちこが、この本についての、
それぞれに熱い、推薦文を書きました。
(試し読みの3編もこの3人で選びました) - いままで三國さんのファンだった方も、
編み物とは無縁で知らなかった方も、
きっとこの本を通じて三國万里子さんの
新しい一面に魅了されると思います。
まずは、とにかく、お読みください!

この本の担当編集者
松本太郎さん(新潮社)

松本太郎さんが試し読み用に選んだエッセイ
※クリックして読むことができます
ひろしおじ
母の弟のひろしは、ごくたまに、母の実家に現れる人だった。
妹とわたしは彼を「ひろしおじ」と呼んでいた。
わたしが保育園児の頃、まだ彼は20代半ばで、Bright Young Thing とでも言うのが似合うような、弁の立つ、街っぽいプータローだった。184センチだかの長身で、彼が実家をうろうろする時には、鴨居に頭をぶつけないように、ひょこひょこ身を屈めていた。頬骨が出てアゴの尖った顔。狐のようにつり上がった眼に丸メガネ、髪の毛は天然でくるくるウエーブがかかっていた。
母によれば、ひろしは東京で大学生活を送った後、富山の立山の山奥でアルバイトをしながら、スキーを滑って暮らしていた。そうかと思えばこんどはフランスのどこかの山に行って、おんなじことをしていた。フランスには随分と長く、確か10年ほどもいたのではないかと思う。
年に1、2回帰ってくると、1週間くらいは実家に滞在するのだが、ひろしが来ていることは、ショッキングピンクや鮮やかな青の、男物のビキニパンツが洗濯物干しにかかっているのでわかった。
おじは若くて、ちびな姪たちにそれほど関心を持っていなかったと思う。
おう、まりちゃんしーちゃん、土産だぞと渡してくれるのが、大抵いつもロッテのクールミントガムの1ダース入りのパックで、妹とわたしはげんなりした。あれは4、5歳の子供にはヒリヒリするし甘くないし、もらっても困る。だからそのたびに、それ、からいやつでしょ、いらない、と返した。わたしたちのために買って来てくれたわけじゃなくて、いつも買い置きを持ってるからくれたのだというのも見え見えだった。
ガムがない時には、フランスから買って来たというヌードのカレンダーを渡されたこともある。70年代らしくソフトフォーカスの、金髪やブリュネットのヌード写真が12ヶ月分綴られているやつだ。わたしと妹がぽかんとしていると、美しいものを見る眼を養うためだ、でもまだ君たちには猫に小判だなとかなんとか言って、結局自分の部屋に持って行って吊るした。末っ子のひろしおじは親たちに可愛がられて、家を出た後もまだ子供部屋がそのまま残されていたのだ。
ひろしは当時わたしより妹のことがお気に入りで、一緒にご飯を食べる時にはいつも妹の隣に座った。ある時妹が「おじちゃん、なんでわたしの隣に座るの?」とすげないことを言ったら、それ以降、妹の隣に座ることはなくなったらしい。
ひろしは実は、意外とそういうことを気にする人だった。
「らいらく」を装って、繊細な人だったとも思う。
始終何かを思って、揺れているような人でもあったかもしれない。女の人のすることはおもしろい、と言っては帽子を編んだり(縄編みの入った結構手の込んだ帽子だった)、高校の写真部時代に買った良いカメラで何か撮影しては、風呂場で現像していた。
ある日ひろしは、わたしの母を庭の草花の中に立たせて、フィルム1本分写真を撮った。彼の写した母は例のヌードカレンダーのようにソフトフォーカスで、わたしたちが見慣れた牛乳配達をする母とは違っていた。モノクロの印画紙に写っていたのは、しんとした、若く綺麗な女性の横顔だった。
母のことをひろしは「やすこさん」と呼んでいたが、その呼び方にはいつも、ほんのりと敬意と愛情が感じられた。そういえば彼は、母にはちゃんとしたお土産を買って来ていた。たいていは向こうのスキーセーターで、機械編みのトナカイ柄のもあれば、極太糸で手編みした幾何学柄のヨークセーターもあった。わたしは母がパンタロンに合わせてこれらのセーターを着ている姿が好きだった。母はそれを知っていたのか、わたしの身長が彼女のを追い越す頃、着るのならまりちゃんにあげる、と言って、その中の3枚ほどを譲ってくれた。
本場物のスキーセーターは、どこかもっさりしていたが、そこも含めてわたしは気に入って、よく着ていた。わたしが大学に入った冬、小田急線の電車の中で「まりちゃん」と呼ばれて顔を上げると、ひろしが立っていたことがあった。
その時わたしはそのお土産セーターのうちの1枚を着込み、リュックを背負って本を読んでいた。読んでいたのは少し前にひろしが薦めてくれたガルシア・マルケスの『百年の孤独』で、「おじちゃん、これすっごいおもしろいね」と感想を言うと、ひろしは丸メガネ越しにわたしを見て、「そうでしょ。でもさまりちゃん、まだそんな格好してるの、全然垢抜けないね」と笑った。
そういえばわたしが行くことになる大学を薦めてくれたのも、ひろしだった。
中学生の頃のある日、母がひろしに向かって「まりこは友達がいなくて」とぼやくと、「まりちゃんは喩えていえば瓢湖(という湖が近くにあった)の白鳥の群れに迷い込んだ鶴だよ。ここで仲間が見つからなくても、他の鶴がいるところに行けばいいさ。ワセダとかどう、きっとまりちゃんに合う仲間がいるよ」
と言ってくれた。
わたしは年頃で、「友達がいない」なんてことを母が誰かに相談するのを聞くのは恥ずかしかったし、今になってみれば、まあ、あの大学は人がいっぱいいるからね、くらいのことでしかないけれど、でも、その言葉を一筋の光明のように信じたからこそ、続く高校時代にわたしは自己流で受験勉強をしたのだ。
高校3年の2月、わたしはひろしのマンションに泊めてもらいながら受験会場に通った。その頃にはもう、ひろしは東京で職とお嫁さんを得て、小田急線の登戸で暮らしていた。受験当日の朝になると、出かけようとするわたしに向かってひろしは、
「おし、まりちゃん行ってこい」
と声をかけ、深紫色の液体が半分ほど入ったグラスを差し出した。フランス産の、どすっとくるやつだ。わたしは飲み干すと礼を言い、一瞬熱くなったお腹を感じながら、乾いた東京の冬の中に出て行った。
次のひろしの思い出も東京で冬だった。
大学を出た年、アルバイトを変えながら暮らしていたわたしは、長年付き合ったボーイフレンドと別れたこともあり、どこか違う環境に行きたいと思うようになっていた。
あの時、なぜひろしに連絡したのだろう?
考えるまでもなく、それは、ひろしがいつもわたしにとって「外の世界を開いてくれる」人だったからだ。
電話をしてから数日後、ホテルニューオータニのロビーで待ち合わせて、上階のバーに行った。カウンターに座って飲み物を頼むと、ひろしは若いバーテンダーに向かって言った。
「お兄さん、この子どう? もらってくれない? 彼氏と別れてぼんやりしてるの」
急にそんなことを言われて、はいでもいいえでもなくにっこりするバーテンダーを見て微笑み返すと、ひろしはわたしの方へ向き直り、言った。
「まりちゃん、秋田の山奥に日本一の温泉旅館があるよ。そこの社長のこと少し知ってるから、まりちゃんのこと頼んでやるよ」
それを聞いて、わたしはこころからうれしかった。
スキー場でアルバイトしていた頃の、ゆらゆらしながらもいつも何か探していたひろしと、自分を重ねたのだと思う。それから少ししてわたしの「秋田行き」は決まった。その温泉宿は冬は比較的客が減り、人手が必要なわけではなかったのに、宿の社長がひろしの顔を立ててくれたのだろう、雇ってくれることになったのだ。両親や祖父母たちは、わたしが温泉宿の仲居をすると言うと、呆れ、猛反対をした。その仕事をわたしに薦めたひろしの立場も、親戚内で悪くなったはずだった。でもひろしは言い訳をせず、ただ母に向かって「まりちゃんは東京に飽きたんだよ」とだけ言ったらしい。
こんなに世話になったひろしは、もういない。
自分の人生をひとに代わって生きてもらうことはできないよね、と、いつだか一緒に飲みながら話したのを覚えているが、それを言ったのは、ひろしだったか、わたしだったか。ちゃんとお礼も言えていないのに、という心残りを、わたしはたぶんずっと持ち続けていくしかない。

松本太郎さんによる推薦文
※クリックして読むことができます
心の中にいる
「孤独で不器用な少女」が喜ぶ、
素晴らしい本
三國さんの本と同じ9月に刊行する単行本について、
社内の関係者に説明する会議。
担当編集者にとって、いちばん最初の「勝負の場」です。
ここで出席者に
「おもしろそう」「早くゲラを読みたい」
と思ってもらえるかどうかで、
刊行に向けた雰囲気が変わってきます。
プレゼンの順番が回ってきた時、思わず私の口から出たのは、
「ぼくの心の中にいる『孤独で不器用な少女』が喜ぶ、
素晴らしい本なんです」という言葉。
「中年のおじさんが何をいきなり言い出したのか」と、
一同の困惑と失笑をかっさらいました。
けれど、それからしばらくして、
ゲラを読んでくれた若手の男性社員から
「読んでいる間、めちゃめちゃ幸せでした!」
という感想が届き、ある先輩編集者からは
「素晴らしい原稿を読ませてくれてありがとう」
とメールが送られてきました。
いつもはクールな若手女性社員からも
「会議では『なに言ってるの?』と思ってましたけど、
私の中にも『孤独で不器用な少女』がいました!」
という感想が。
ある部長はゲラを渡した数時間後、
私の席まで駆けつけて来て、
「一気に読んじゃった!
自分の過去が次々と思い出されて、
いい意味で生皮をはがされるような思いで読んだよ」。
ゲラを読んでくださった書店員さんからも、
続々と熱い感想が寄せられています。
三國さんの文章は、なぜそんなにも読む人の心を掴むのか。
それは、「文字として書かれている以上の何か」を
感じられるからではないかと思います。
三國さんの心の深いところから取り出された言葉には、
その背後に豊かさが広がっている。
読んだ人が、必ずと言っていいほど
自分自身の思い出とともに感想を語ってくれるのは、
言葉の背後にある三國さんの思いが胸の奥に響くから、
つい自分を重ね合わせて読んでしまうのだと思うのです。
今回、試し読みに選んだ「ひろしおじ」もそんな一編です。
三國さんが人生を切り拓くきっかけをくれた
叔父さんの話なのですが、
読み終えた後、たくさんの感情とともに、
これまで自分を助けてくれた人の顔が思い浮かびました。
(そして、今回の本の刊行を、最も喜んでくれる一人が
「ひろしおじ」ではないかと思っています。)
読む人を虜にする三國さんの文章。一人でも多くの方に、
その魅力を感じていただけたら嬉しいです。
松本太郎(新潮社)
本ができる現場に居合わせた乗組員
やまかわみちこ(ほぼ日)

みちこが試し読み用に選んだエッセイ
※クリックして読むことができます
父
恩寵、とでもいうものを感じることが、保育園に入る頃までしばしばあった。
晴れていたら、そして早朝に目覚めていたら、それは静かにやってきた。と言っても、何か特別不思議なことというわけではない。目覚めた頭を布団から出してぼーっとしていると、東の窓から光が入ってくる。光の筋はまず天井を桃色に染め、壁も染め、やがて部屋中を暖かくまぶしい光で満たした。
かみさま、とわたしは思った。
刻々と移り変わる光は、ある意思を持ってわたしをあやそうとしているように感じられた。こんなことができるのは神様、きっといつも親しく見守ってくれている神様なのだろう。やがて光の遊びが収まると、わたしはくるっと振り向き、同じ布団で寝ている父を見た。まだ20代後半の、やせっぽちで、にーちゃんのような父。朝ごはんの時間までにはまだ少しあるのを知っているらしく、父は目を開けない。わたしは布団に潜り、ごそごそと父の脇の下に滑り込んだ。父はわたしの手を握った。起きてるよ、というように。
その頃、わたしは時々父に観察されていたと思う。
一人で遊んでいると、通りかかった父が立ち止まり、じーっと見ていることがよくあった。ある時父は、そうやってわたしを眺めた後で、
「まりこは大器晩成型だな」
と、ぼそっと呟いた。
「たいきばんせいって何?」
「うんと後になってからさ、大物になるってことだよ」
聞きなれない言葉のせいで記憶に残っているシーンだが、残念ながら50歳に近くなっても、まりこに大物になる兆しはない。
「まりこはスローモーだな」と言って笑うこともよくあった。「スローモー」がなんのことかはわかっていた。でもスローな人間には、自分がそうであるということは、わからない。わたしにはわたしの時間が流れていた。わかるのはそれだけ。
父は特別子煩悩な人ではなかったが、優しかった。わたしが小学生の頃は、早く会社から帰ると、おう、まりこ、バドミントンやるか、と声をかけてくれた。わたしは絵を描いたり、ちまちま裁縫する手を止めて、父と連れ立って裏の畑に行った。
バドミントンだから、一応カウントは取るのだが、それにさして意味はなかった。わたしが下手なせいで、ラリーがあまり続かなかったからだ。それでも父は呆れもせず、気長に遊んでくれた。わたし達は何度でも落ちた羽根を拾い上げては、今度こそ、と、ラケットを振った。
ペシッ。ぽとん。
わはははは。
ペシッ。ペシッ。ペシッ。ペシッ。ペシッ。ペシッ。ペシッ。ぽとん。
おお〜〜〜〜〜〜。
こんな感じだった。声を出して体を動かすと、せいせいして、気分がよかった。暗くなって畑にコウモリが飛び始めても止めず、日が沈んで羽根が見えなくなって、ようやく家に戻った。
中学生になると、周りのいろんなことが変わった。わたしもそれに合わせて変わろうとしたが、うまくいかずに、つまずいた。クラスに馴染めなかったのだ。
何か「ステージ」が変わったことはわかるのだが、その新しい場所での振る舞い方がわからない。おたまじゃくしがカエルになるべき時が来たのに、わたしだけ手足が生えてこない、陸に上がったのに、呼吸も一人だけエラでしているような感じだった。
実際、苦しかった。
息の仕方、ちょうど良い「吸って、吐いて」がわからなくなり、クラクラして、教室にいるのがしんどくなった。休み時間には誰もいない場所を探して隠れるようになり、2年生の半ばになると、早退を繰り返すようになった。そのことが担任から母に伝わり、母は父に話した。
夜、両親の部屋に呼ばれた。
父はわたしに「周りの人とうまくやっていくことの大切さ」を説いた。
「そんなことでは社会に出てから困ることになる」ということを、いろんな言葉で繰り返した。そんなことは、わかりすぎるくらいわかっていた。だってもう十分に困っていたから。
「じゃあどうすればいいの」
と聞くと、
「自分から話しかけてみればいい、なんでもいいから」
という。
「なんでもいい」ということが、わたしには全くわからない。何を話せばいいんだろう。彼らが興味を持つような話題を自分が提供できるとは思えなかったし、休み時間に何事かを話している彼らの輪の中に入っていくことなんて、場違いすぎて、もう今さら、無理だった。その「場違い」な感じを父にわかってもらうのも、果てしなく不可能なことに思われた。
父は「社会」の側にいる人間として、そこになんとかわたしを引き入れようと頑張ってくれたのだと思う。しかし「社会」を主人公にして物語を組み立てようとする時、正しいのはそこに適応する者で、適応できないのは努力が足りないから、という話の筋道になってしまうことがある。
その時も「そんな簡単なことがなぜできないんだ」と、本当にわからない、という顔で言われ、たしか、わたしは泣き出したと思う。まるで、泳ぎかたがわからずに溺れそうになっている時に、「泳ごうともしない」と言われているようで、途方にくれた。
畳み掛けるように、「人の上に立つ人間になろうと思うなら」と父が言いかけた時、「人の上に立とうなんて全然思っていない」と、わたしは言葉を遮った。
それは本当だった。
でも、そこに続けて、「お父さんのことも尊敬してないから」と、言ってしまったのだ。父は返す言葉を持たなかった。隣で聞いていた母も顔色を変えた。そしておそらく、わたしをたしなめたと思うのだが、その夜のことはそれ以上、思い出せない。
社会、という、父の論拠の立つ土台を崩そうとして、稚拙なわたしは「社会で働くお父さん」を丸ごと、なぎ倒すように否定してしまった。本当のことを言えば、父のことは「尊敬」も「軽蔑」もしていなかった。そんなこと、考えたこともなかった。
昔から、ただ大事な父だったのだ。
ずっと、わたしと一緒にいてくれる人だった。
それから、父とわたしはお互いに対して少し距離を置くようになった。
仲が悪くなったわけではない。
父はがっかりしながらも、わたしを許してくれたのだろう、ということを感じたし、わたしも父が理解してくれなかったことを、もうあまり恨まなかった。わたしが親とは違う考えをする一人の人間である、という声明を出すためにあそこまでやる必要はなかった。ただ、ありがたいことには、わたし達は家族でい続けられた。お互い歳を重ねながら、少しずつ変化していくものだ、ということを多少ぎこちなくも、受け入れていった。
わたしはやがて高校に入り、大学へ進み、卒業し、就職につまずいた。
フリーターになり、いくつかの職を渡り歩いた。そしてその間、一番応援をし続けてくれたのはおそらく父だったのではないか、という気がする。ある時、母からの電話の後で父に代わったことがあった。
どんな話の流れだったのだろう、それはもう思い出せないが、
「わーーー、って叫びたくなる気持ちは、おれにもわかる」
と父が言ったのだ。
曲がりなりにも社会に出たのに、大した葛藤もなく戦いもせずにへたれてばかりいたわたしは、ひどくもったいない言葉として、それを聞いた。
今、父は70歳だ。
高卒で入社した化学工場を定年退職の後、嘱託として1年勤め、さらに「プータロー」するのも退屈だと翌年には再就職した。市民ホールの守衛だ。マークⅡからプリウスに乗り換えて、母の手作りの弁当持参で週に3日通っている。時々、電話で話す。
「お仕事お疲れさま」と水を向けると、ちょっとうれしそうに仕事の話をしてくれるが、それもほんのわずかで、すぐに「孫に代われ」と言う。
まりこに話すことは大してない、とでもいうように。
わたしもそれなりに歳をとり、これでなかなかいい話し相手になった、ということを父もそろそろ知っていい頃だと思う。

みちこによる推薦文
※クリックして読むことができます
三國さんという人は、
どんどん変化して進化している
三國さんとほぼ日が、はじめて出会ったのは2010年でした。
三國さんは、はじめての書籍「編みものこもの」がヒットし、
二冊めの「編みものワードローブ」の発売を控えた
すでに人気の作家でした。
当時のほぼ日はまだ40人くらいの人数の会社で、
どうやら三國さんの「編みものこもの」で
編みものを編むのが社内で流行り始めたらしい、
ということは、あっという間にわたしにも伝わってきました。
三國さんの本の作品を編んでいる先輩を横目に、
「わたしもそういえば編みもの、
好きだったんだよなあ」と思い出し、
久しぶりにわたしも針をもつことにしたのです。
はじめて三國さんのレシピで編んだのは
「編みものこもの」のミトン。
それまでも編みものが好きだったとはいえ、
ちゃんと編み図を見て編むということを
ほとんどしてこなかったので、
それなりに苦労し、時間もかかりましたが、
なんとかはじめてのミトンを編みました。
ミトンを編みあげたことで、
三國さんの企画を考えていた乗組員から
「いっしょに三國さんのコンテンツやろうよ」と
声をかけられたのでした。
わたしもなにか手伝えるかなあ、
くらいの軽い気持ちでしたが、
先輩たちはいつもの企画となにか違うムード。
「せっかくならただの書籍の紹介や、
展示の紹介に終わりたくないよね」
「なにかいっしょに楽しいことができないかなあ」
みんなで何回も集まり、うんうん頭を捻りました。
今思えばそのころから三國さんは特別な作家でした。
何度か社内で打ち合わせたあと、
ついに三國さんをお呼びしての打ち合わせとなりました。
はじめてお会いする三國さんは、
わたしたちの「なにかいっしょにやりましょう!」という
漠然とした期待をいったんうけとってくださって、
ゆっくりと、ひとつひとつ、
「できそうなこと」「できないこと」を話してくれました。
2冊めの本を出すにあたっての個展の取材は、
「ぜひどうぞ」。
アトリエの見学は、
「ほんとに家のただの台所なので、できない」。
本や自分についてのインタビューは、
「編集者にインタビューしてほしい」。
ただミトンを編む、という動画中継は、
「できるとおもう。ただし、合間に
ヨガをする時間と昼寝の時間を設けてください」。
たった一度打ち合わせをしただけで、
ほぼ日のみんなも、わたしも三國さんのことを面白がり、
三國さんを紹介するコンテンツは
トントン拍子に楽しく進みました。
三國さんがミトンを編む中継をしてから、
三國さんの存在感は高まり、
「手帳のカバーのデザインをしてほしい」
「ホワイトボードカレンダーの数字の柄をつくってほしい」
「気仙沼ニッティングのデザイナーになってほしい」と
三國さんにほぼ日からの仕事がどんどん増えていきました。
三國さんは毎度わたしたちの勢いと
しめきりの短さに(すみません‥‥)驚きながらも
「ぜひやります」と引き受けてくださり、
「できましたよ」と
締め切りより早く仕事を提出してくださるのですが、
提出の前には平気で2~3案、
「一回編んだけど、ほどきました」と
自分の中でボツにしたりしていて、
三國さんの仕事への気高さに、憧れの念が強まりました。
そんなふうにして、わたしが三國さんと
いつの間にか12年つきあってきて驚くことは、
三國さんという人は、
どんどん変化して進化していることです。
一番最初に会ったときの三國さんは、
携帯電話は持っていなくて、
「だいたいは家にいるので」ということで、
緊急に連絡をとるときはお家に電話をしていました。
ほどなくして、気仙沼への出張のため、と
iPhoneを購入されました。
みんなでアラン島へ出張することになったとき、
三國さんは一度も海外へ渡航したことがなかったので
パスポートを初めてとることになりました。
三國さんは海外の本を原書のまま読まれることも
よくあったそうなので、
英語のコミュニケーションも難なく、
現地では海外がはじめてとは思えないくらい
のびのびと過ごされているように感じました。
その後は現在の感染症が蔓延するまで、
年に一度はヨーロッパへ旅をされるようになりました。
三國さんの書く文章がとても素敵だな、ということは、
ほぼ日とのお付き合いがはじまった
当初のメールのやりとりから
みんな感じていたことだと思います。
その当時の三國さんは、子育て真っ最中で、
夜は21時ごろには寝てしまい、
夜明けとともに起き出し、
制作の時間にあてられていました。
わたしは夜、会社から帰宅する前に、
明日の朝にはご覧になるかしら、と思って
メールをお送りしておくと、
翌朝コケコッコーと、鶏が鳴くような早朝に
しっかりとよく眠って英気を養い、
おいしいコーヒーを飲みながら
さて、今日一日どんな作品を作ろうかと
腕まくりしているに違いない三國さんから
キラキラと輝くような文面のメールをいただいていました。
文末はいつも
「みっちゃん、今日もよい一日を。」と
締めくくられており、
わたしは出社しつつ三國さんのメールを開封するのを
いつもたのしみにしておりました。
Twitterのアカウントを開設されてから、
三國さんの表現には文章と写真が加わり、
たくさんの方の目にふれるようになり、
どんどんと磨かれていきました。
ほぼ日の「生活のたのしみ展」の企画のために、
「スール」というムック本を三國さんと
実妹のなかしましほさんと制作したのですが、
その中に、いまの三國さんを予感するような
エッセイが掲載されています。
三國さんはもっと文章を書いたらいいんじゃないか、
読んでみたい、きっとすてきなことになるに違いないと
おもわせる何かがありました。
三國さんご自身も文章を書いて
表現されることに自然のなりゆきを感じられたのか、
わたしたちの「もっと読んでみたい」という希望を伝えると、
三國さんからエッセイが
たびたびメールで届けられるようになりました。
三國さんからのエッセイは、
ほぼ日の編集の永田とわたしに届けられ、
わたしはただ毎回感嘆するばかりでしたが、
永田は、
「上手な人に散髪をしてもらうみたい」と
三國さんがおっしゃるように、
編集者としての提案を毎度丁寧に、
そしてたのしそうに返していました。
毎回ただこれを読ませてもらっていていいのだろうかと
身震いするほど、おもしろかったし、勉強になりました。
そして、今回、この文章を書くにあたって、
そのときにやりとりしていたメールを読み返したのですが、
おどろいたことに、今回の本に載る原稿は、
最初の頃にメールでいただいていたものから
さらにさらに遠くまで羽ばたくような
素敵さをまとっていると気がつきました。
三國さん、いつのまに
こんな文章を書くようになったんだろう、と
ずっと見守ってきたはずなのに三國さんすごいよ! と
わたしはいま静かに興奮しています。
三國さんのエッセイにふれると、
自分の人生にファイトが湧いてくるように感じます。
どうかたくさんの人に読まれて、
たくさんの人に愛されますように。
そしてまた、あらたな三國さんに
出会えるのをたのしみにしています。
やまかわみちこ(ほぼ日)
本ができる現場に居合わせた乗組員
永田泰大(ほぼ日)

永田が試し読み用に選んだエッセイ
※クリックして読むことができます
昼寝
バナナが死ぬのを見た。
きのうの夜、買い置いたフィリピンバナナの残り1本が果物カゴの中にひっそりと忘れ去られているのを見つけたのだが、その段階ではバナナはまだ死んではいなかった。買ったのは1週間前だか、10日前だったか。持ち上げると、赤ちゃんの腕よりもまだ柔らかいくらい、ホワッとした感触になっていて驚いた。夫と息子に手を差し出させて「ほらほら」と渡すと、二人とも手にバナナを載せたまま、おわわわわ、とうろたえて走り回っていた。こんなの初めて。やばいくらいホニャホニャ。なんだこりゃ。
これはムリでしょ、食べられないよね、と言いながら、すぐさま捨てるのも躊躇われて、暫定的に食器棚の上にぽつんと置いたのだった。が。
その翌朝、つまり今朝だ、バナナが死んでいるのを見つけたのは。朝食の用意をしようとして食器棚を開けながら、ふときのう置いたバナナはどうなったかなと目をやると、なんとしたことか、バナナの周りには水たまりができていた。それも「湿っている」というレベルではなく、もともとのバナナの体躯から考えられるより、ずっとたっぷりした水の中に少し小さくなったバナナが浸かっていた。
思わず後退った。
ねえ、来て来て、バナナが、ほら!
呼ぶと、起きたばかりの息子がやって来た。わたしの横に立ち、おわ、なにこれ、と言ったきり絶句している。二人で5秒間、死んだバナナを見つめた。
「なんか、ごめんね、おれが食べなかったから」
と息子は言った。半分はバナナ、半分はわたしに向かって。
「仕方ないよ。でもさ、バナナってこんなことになっちゃうんだね。水が出るなんて、わたしも初めて見た」
液体化に止めようもなく向かっているらしいバナナを、わたしはそっとつまみあげてスーパーの袋に入れ、袋の口を結わき、食器棚の上の水たまりを台ふきんで拭った。バナナは昨晩、闇の中で、もう、バナナであることをやめたのだ。
という記憶を反芻しているわたしは、昼食後の午睡から覚めたところで、わたし自身バナナのように体を曲げてフローリングに横たわっている。床がひんやりして気持ちがいい。
全開にしたサッシの向こう、近くの保護樹林でたくさんセミが鳴いている。わたしは片手で座布団を抱きしめて、もう片手は後ろ頭の根元に当てている。眠るときはいつもこの体勢だ。
なぜこんな格好で寝るのかには理由がある。
わたしは眠くなるとだいたいいつも呼吸が浅く、胸から上が固まってしまっているように感じる。後ろ頭がずーんと重い。それが、横になり、頭の根元に手を当てて目を瞑ると、その重さの「もと」が手から吸われて、体の回路に戻っていく感じがするのだ。
手は頭蓋骨の中にたまりすぎた、熱というか、電気というか、そういうエネルギーを吸い取ってくれるようで、眠り終えると頭が軽く、すっきりしている。呼吸が深くなっている。指先がチリチリしている。何か名付けようのないものが、わたしの体の先端まで巡っている。重力を感じる。とても親しい、なつかしい重さだ。
意識がわたしの体をかき集めて垂直にする以前の、地球の泥の一部としてのわたしに戻った感じ。ずっと昔、生まれた家の、庭を囲む長い廊下で昼寝をしていた自分を思い出す。バスタオルに仰向けに寝かされたわたしはまだ2、3歳だ。目が覚めると母が洗濯物をたたんでいた。縁側の向こうには、午後3時ごろのレモン色を帯びた明るい空に、白く薄い月が浮かんでいる。
昼寝から目覚めるたびに、地球というとても巨きな生き物が持つリズムに、呼吸に、自分が調律されるのを感じる。潮の満ち干に同調するのか、わたしの中にも安らかに潮が巡るようだ。それが「生かされている」という状態なんだと思う。わたしの中の水はより大きな流れと一緒に巡り、まだあのバナナのように生命体としてのフレームの外に溶け出したりはしない。
初湯殿 卒寿のふぐり 伸ばしけり
いつか読んだ句がふと口に上ってくる。
阿波野青畝という人が90歳の正月に詠んだ句だ。めでたいってこういうことかな。90歳の青畝さんも、46歳のわたしも。生きるということにはそれ自体に快感があるらしい。熱い湯船でしわくちゃの「ふぐり」を伸ばす、昼寝をして深い息に戻ってゆく、目を開けて昼の月を眺める。そんなこと全てに。
そろそろ起きだして午後の仕事をしよう。
この体を持ち越して行くのだ、いつか自分であることをやめる日は、あのバナナのようにきっと、全てを手放して、安らかだろうが。

永田による推薦文
※クリックして読むことができます
冬の夜中のようなこのことばに。
三國万里子さんの文章が好きで、
いずれこの人は書くことも
表現の軸にしていくのだろうと思っていた。
いつからそう思っていたのだろうと、
記憶と記録をさかのぼっていった。
自分の少々エキセントリックな趣味を告白すると、
ぼくは、そのように、漠然としたおおまかなものを
どんどん細かく砕いていくのが好きだ。
いつの間にか色を転じたグラデーションを
1ミリずつ進んだり戻ったりしながら確かめて、
どうやらこのへんかなと
変質の境界線を見定めるのが好きだ。
経験上、どれほどふわふわした印象でも、
誠実に微分していけば具体的な事実が切り出せる。
ぱっと電気が走るような直感的な感動でも、
スローモーションで見返していけば
これがなければそうはならなかっただろうという
繊細なスイッチを発見することができる。
もちろん、あらゆるものが解体できて、
かならずそこから核心を取り出せるわけではない。
なんだか最後までもやもやしてわからなかった、
ということだってしょっちゅうある。
それでも、これ以上は近づけないな、
というぎりぎりのところまではそばに行ける。
自分の対物レンズの倍率の限界までは
焦点を合わせたくなる性質をぼくは持っている。
三國万里子さんの文章は特別だと感じたのは、
いったいどこからだったのだろう。
ふだんから自分の感情を動かしたトリガーや
物事の印象の分水嶺を探ることが好きな自分にしては、
そのポイントが曖昧なのがまず不思議だった。
たとえば三國さんが何冊も出している
編み物の本のなかに添えた文章が根拠なら、
ぼくはそれをくっきり覚えているはずだ。
「三國さんは書くべきだと思います」と、
三國さんご本人に告げたことを覚えている。
この人がなにも書かないなんてもったいない、と、
強く感じていたことも覚えている。
なにか自分なりの根拠がなければ、
書くことを人に勧めるなんて大それたことはできない。
ぼくはどこでその確信を得たのだろう?
しばらくあれこれとあたって、
ああ、これだ、と自分を納得させたものは、
三國さんとやりとりしていたメールのなかにあった。
メールにしてはちょっと長めの、
ひとかたまりの文章だ。
とはいえ、タイトルもついてないし、
作品として区切られてさえいないものだったから、
ぼくはそれを切り出せていなかったのだ。
それは、三國万里子さんと、
料理家である妹のなかしましほさん、
つまり「長津姉妹」と一緒に、
何かおもしろいことができないだろうかと、
あれこれ話し合いをしていたころのメールのなかにあった。
そのメールのなかで、三國さんは昔の話を書いていた。
ある具体的な場面の描写だ。
渋谷にある喫茶店で、
三國さんは妹のなかしまさんと話している。
それはまだ三國さんがニットデザイナーとして
デビューする前のことで、子育てを一段落させ、
「そろそろ働かなければ」と思っているけれども、
いったいどんな仕事をすればいいのかわからなくて
ちょっと途方に暮れている。
そんなシーンが思い出話として書かれている。
なかしまさんに向かって、三國さんは弱音を吐く。
いまの不安な自分と、
そのいまとつながっている自分の未来に対して、
ある種の諦観とともに、
目の前に座るなかしまさんに向かって
三國さんはこんなふうに言ったのだという。
ことばをそのまま引用する。
息子が大きくなって、親や夫が死んだら、
きっともうすることもないし、
実家の畑に冬の夜中に出て行って、
そこで眠れば死ねるでしょう。
さて、ぼくは、ぼくの個人的な好みである、
自分の心を動かしたふわふわしたものを
細かく砕いていく作業に入る。
対物レンズをきりきりと切り替え、
ダイヤルを回してできるだけそこに接近する。
どうしてぼくはこの文章に感動したのか。
なにによってぼくの心は動かされたのか。
文章のなかでもっとも際立っているのは、
死の方向を見渡す書き手の独特の覚悟と凄みだ。
けれども、どうやらぼくの興味は
その本質を包む器のほうにある。
ぼくに特別な印象をもたらしたのは、
ことばのリズムと情景の美しさだ。
とりわけ、最後の2行。
実家の畑に冬の夜中に出て行って、
そこで眠れば死ねるでしょう。
こうして書き写してじっと眺めるだけで、
大げさでなくこころが動く。
美しいなと思う。
美しいものはなんだろう。
死は印象深いが、美しいのは、死ではない。
死は、この文章に欠かせない重要なものだが、
それはいわば自然の一部として背景のようにある。
だから、強いけれども、死は主役ではないのだと、
ぼくは接眼レンズを覗き込みながら思う。
わざわざことわることもバカバカしいが、
さっきからぼくが口の端に泡を飛ばして語っているのは
徹頭徹尾ぼくの主観に過ぎない。
その意味でいえば書き手自身の意見さえ気にしない。
死を見渡すこの美しい文章のなかで、
ぼくは死よりも大切なものを自分の感動の根拠にする。
具体的にいえば、この美しい4行の文章を、
とうとう1行に絞るなら、こうする。
実家の畑に冬の夜中に出て行って
これ以上はもう砕けない。
この1行をぼくはしみじみと眺め味わい反芻する。
語彙、語順、リズム、助詞。
それらぜんぶの結びつき。
「実家の畑」「に」「冬の夜中」「に」「出て行って」
そしてその1行によって立ちのぼってくるのは、
ずっと前から自分のなかにあったような、冬の情景。
そこに実家があるということ。
実家から歩けるところに畑があるということ。
畑に対する深い信頼があるということ。
冬の夜中が苦悶の生じないくらい寒いだろうということ。
──ちなみにその冬は新潟の冬である。
出て行く、というある種の気軽さ。
冬の夜中、という揺るぎのない静寂。
実家、というにぎやかで暖かそうな場所。
彼女は、夜中まで、どう過ごしていたのだろう。
そのときが来た、と感じたのだろうか。
靴は、履いたのだろうか?
扉は、そっと閉めたのだろうか?
実家の畑に冬の夜中に出て行って
ああ、なんて美しくて、優しい1行だろう。
どの品詞もありふれた平易なものなのに、
ぜんぶの結びつきによって、
かけがえのない世界をつくりだしている。
つまり、この1行がこの1行でなければ、
ぼくは三國さんに「書くべきです」なんて、
おせっかいなことを言わなかったかもしれない。
(別の1行にいずれ出会っただろうとは思うけど)
ことばというのは、
いや、ことばに限らずある特別な表現というのは、
たしかに心に、言い換えれば運命に影響を及ぼす。
その表現をした人の運命に、
あるいはその表現を受け取った人の運命に。
すばらしい作家は、そのようにして、
自分の表現で運命を切り開いていく。
ぼくはそう思う。
三國万里子さんは、あるとき編んだミトンで
ニットデザイナーとしての運命を切り開き、
そしていま自分の書いた文章で
文章の人としての運命を切り開いたのだとぼくは思う。
書くことをおすすめしたことがきっかけとなって、
三國万里子さんは、ぼくと、
ほぼ日の編み物担当のみっちゃんに向けて、
ぽつぽつと自由にエッセイを書いて送ってくださった。
そのすばらしい文章が溜まれば溜まるほど、
簡単にコンテンツにして掲載してはいけない気がして、
新潮社さんから出版していただくことになった。
本のタイトルは、
『編めば編むほどわたしはわたしになっていった』。
こうなるべくしてこうなった、と思う。
ぼくが上で激しく噛み締めたようなことばが、
おそろしいことに本のなかには、
1冊分、まるごと詰まっている。
読んでいただければきっとわかる。
文学としての強さを保証する。
だから、どうぞ読んでいただけますようにと、
ぼくは思いのずいぶん深い部分から祈るのだ。
読む人の、冬の夜中の畑が、きっと現れる。
永田泰大

2022-09-21-WED