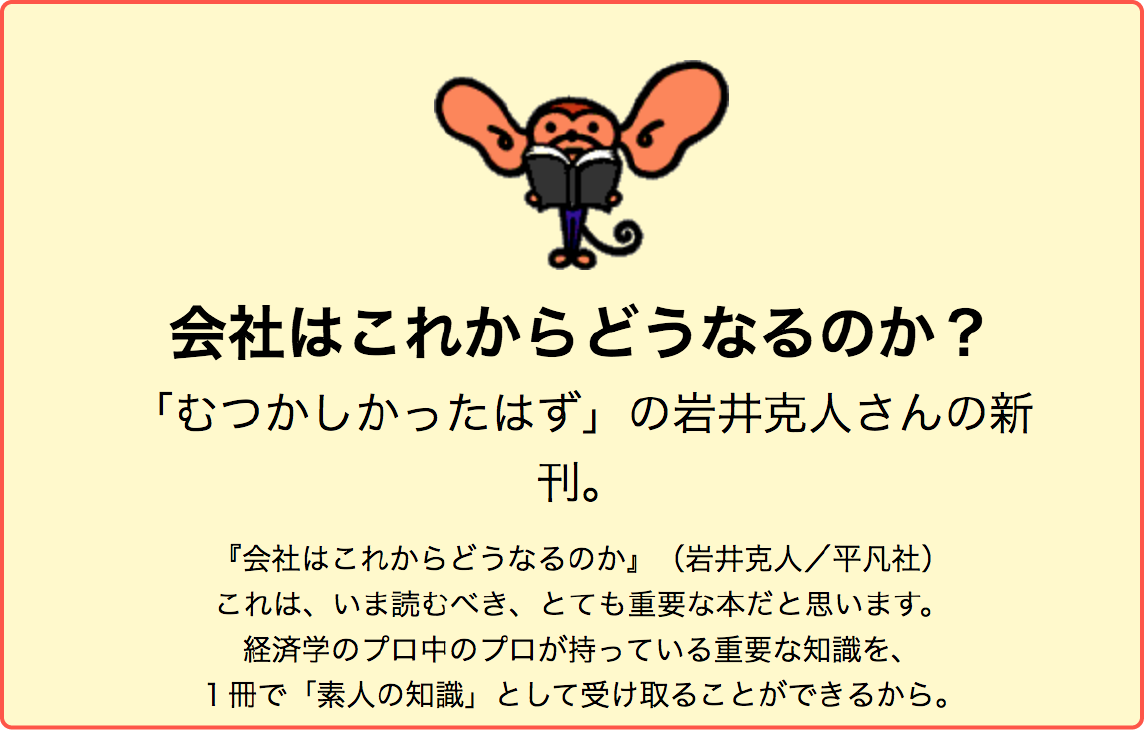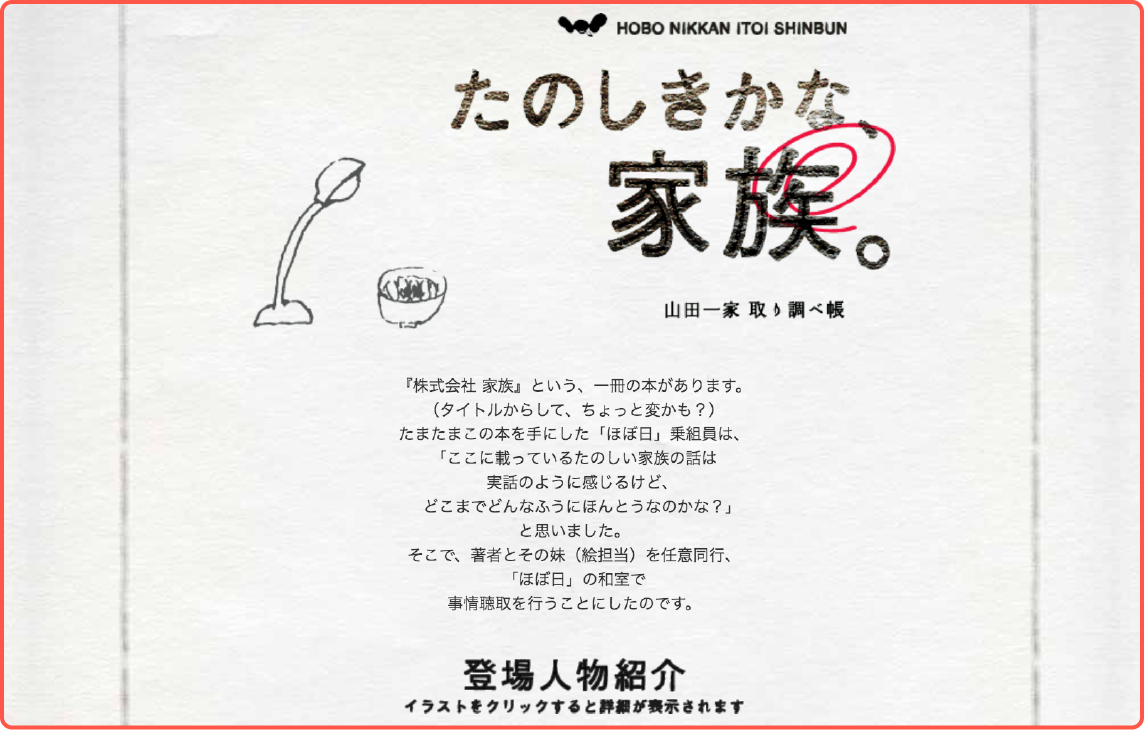なにせ創刊から22年ですから、
ほぼ日刊イトイ新聞の
アーカイブはほんとうに膨大です。
年末年始の休みに読み直す、といっても、
いったい何から読んでいいのやら?
そこで、ほぼ日刊イトイ新聞を
むかしから読んでいる人たちに、
おすすめの読みものを
音楽のプレイリストをつくるみたいに
ユニークな切り口から
ピックアップしていただきました。
(ありがとうございます!)
ピンと来たらぜひ読んでみてください。
印刷したいコンテンツ。
山邊 恵介(やまべ けいすけ)
靴磨き職人の仕事をしていた山邊くん。
その後、筑波大に進学、現在大学院生。23歳。
(編集部記)
ほぼ日を一番集中して読んでいたのは、
おそらく中高7年間(2009-2015)だったと思います。
実家の動きのおそいパソコンで貪るように読んでいて
特にいいと思ったものは縮小印刷しホッチキスで留め、
学校や職場でも読めるように持ち歩いていました。
実家を離れスマホを持つようになった今でも
コンテンツを読んでいて
「あ、印刷したいな」と思うことがあります。
印刷して、何度も読みたい。
何回も読み返して、自分にその言葉を一つずつ
染み込ませたりぶつけたりしたい。
そうやって少しでも自分の血や肉にしたいと思った
インタビューと対談を10、選びました。
私の印刷したいコンテンツ
(実際に印刷していたものも含めて)、どうぞ。
毎日拍手が来るかわかんなくて、
毎日拍手がうれしいからいいんじゃない? ──矢沢永吉
2007年に展開された「ほぼ日の就職論」特集の
フィナーレを飾った対談。
「ほぼ日の就職論」はほぼ日が「はたらく」ことを、
正面きって考えた初期の企画であり、
以来書籍や展覧会にもなる「はたらきたい」にも
繋がっていきます。
いま見るとすこしびっくりするほどの密度と
厚さで作られたコンテンツで、
それは特集のはじめとおわりに
糸井さんが書いている文章からも感じられます。
読み手にじかに持ち重りのする何かを
手渡してくれようとする、そんな文章です。
対談で、一度も就職したことがないと
当たり前のことをいう矢沢永吉に
盟友・糸井重里はしっかりと尋ねます。
「事業者としての基準ってある?」
「いつからそういう人になったんですか」
「義務感もあるの?」
確かに矢沢さんは
どこかの職場に就いたことはないわけですが、
しかし、「オレはいいけど、YAZAWAはどうかな?」
といった語で知られるように
矢沢永吉はE.YAZAWAを経営し、
働いてきたことが浮かび上がってきます。
不良のような永ちゃんが誰にも教わらず、
自分で決めつけず、クソがつくほど真面目に
何度も確認しながら就職先としての自分のこれからを
考えて、決めてきたこと。
「息止めて走ってきた」YAZAWAに対して本人が
「がんばりすぎちゃったかな」とさえ言います。
明らかにヤザワは二人以上いるのです。
結局「わたし」という自分しかいないんですよ、
ということでもあります。
特に第7回「矢沢の就職論」では、
お前がお前を引き受けないで一体どうしようか、と
ごくはっきり、矢沢永吉は言葉にします。
これは是非読んでほしい。
私は靴磨き屋をはじめる前にも、
靴磨き屋が赤字でどうしようもない時にも、
靴磨きの仕事をやめて大学へ行こうかどうしようか
考えている時も、
この対談をくり返し読みました。
読んだからといってまっすぐ答えが見つかるようなものでは
全くないし、
矢沢さん本人も「わからないんだよ」と言ってるし、
どちらかというと弱っている時に読むと
結構負担がかかるコンテンツかも知れません。
一方で、YAZAWAだって不安だし迷ってきて、
そしてそこから歩いてきたんだ、
この事実には励まされる部分もあれば、
おののくような気持ちにもなります。
自分を勇気づけて、よっしゃ、行こうと言ってやれるのは
「もうひとりの俺」であって
それをさらに超えて、
思いがけずに迎えてくれるかも知れない存在が、
お客さんであり、他人なのだと
この対談を読むたびに思います。
ちなみに、「10年前はさあ」と
同窓会のようにお二人は話しはじめるのですが、
このコンテンツからさらに10年を超えての対談
「スティル、現役」と合わせて読むと、
答え合わせではないですが、
なにかビリビリっとくるものがあります。
2
Johny Weir!!!
オフィスにジョニーがやってきた。
ぼくが代表できるのは
「ジョニー・ウィアー」だけ。
I don’t represent any community
because I represent Johnny Weir.
──ジョニー・ウィアー
このコンテンツの副題は
「オフィスにジョニーがやってきた。」
やってくるだけでコンテンツになったのは
高田純次さんくらいではないでしょうか。
フィギュア・スケーターのジョニー・ウィアーが、
ほぼ日のオフィスにやってきて
あちこちに話をしながら、記念写真をとって帰っていく。
たとえば「沈黙」について、
あるいはアスリートとアーティストの両側面を持つ
スケートについて、
好きなものについて、プリンやロシア、ラビオリ。
エビは嫌いじゃない、とか。
他愛もないような話を聞いて、話して、それを読む。
私は一体なにをしているのでしょうか。
それは非常にわずかではあったとしてもその人の人となり、
らしさのようなものを、
感じ取る時間を過ごしているのだろうと思います。
この時期のほぼ日の対談には、
特にそういう時間をふんだんに流していこうとする
無意識のたくらみがそこここにあったように思います。
インタビューイ、ビューア双方の「らしさ」のようなもの、
これをつくるのが、ジョニー・ウィアーの言葉では
「心(ハート)」だと語られます。
また、アスリートでありアーティストである氷の上では
「魂(ソウル)」が身体の主人になるのだ、とも。
「氷の上にいるときは魂。氷から離れたら心。
そのふたつがあるのはいいことだと思います。
もしも、どんな場所でも同じ自分だったら、
飽きちゃうんじゃないかと思う。
For me, on the ice ,it’s “soul”.
Off, the ice, it’s “heart”.
It’s good to have both.
If I were the same everywhere
I would probably be bored.」
この魂と心の両方を持ち、独特にして唯一の
「ジョニー・ウィアー」の表現を
作り上げてきた当時26歳のスケーターは、
周囲との関係において「誰とも戦っていな」いし、
「誰かに受け入れてほしいとも思わない」。
それは、彼が自分だけを代表/representしていることと
繋がっている。
誰かの主義や主張、権益とも関わらずに、
実は当たり前に唯一な自分の
表現/presentを育てていくことは、
媚びとも戦いとも遠い仕事だと言えます。
僕がこのコンテンツを印刷したい理由の一つには、
日英併記の対談であることが挙げられます。
もちろん素晴らしい翻訳ではありますが、
「らしさ」を掴みとるには
やはりジョニー・ウィアーは実のところ、
なんと言ったのかを知りたい。
そのために出力して、辞書を引きながら読みました。
それはつまり、彼のそのものの表現を知りたい
ということでもありました。
自分は、つねに、
自分のことを気に入ってないんです。
でも、それを「百も承知」なんです。 ──本木雅弘
不定期更新の「俳優の言葉」シリーズは
それぞれ連載が開始されると、
その日から11時を心待ちにするようになります。
中でも第一回の本木雅弘さんは、正直さを基準にした場合、
一種格別なものがあります。
期待されたことがらを期待された通りに話すことは、
おそらくインタビューを何度も受けてきた人には
難しくないことなのだろうと思いますが、
このコンテンツにそのような互いの読み合いは
ほとんどありません。
むしろ、「こういうことが期待されるんだけど、
でも違うの」みたいな
無言の読み合いを暴露してしまう瞬間さえあります。
それは、自分自身を「ニセモノ」だと思うような
「自己卑下の意識」を堅くもち、
「自虐で結婚しよう」とさえした人の魅力がなす
正直さという現象です。
正直さが、個人に備わった能力や性格ではなく、
他のものと自分との関係の上に色々と条件がそろった結果、
現れるものだとしたら、
このインタビューでそれはゆらゆらと立ち上がっています。
しかし、なんともつかみ所がありません。
肯定的に言い切るのではなく、
「いや‥‥」とにぶい否定が続いていくこと。
これがもしかしたら、ひとつの正直さのしっぽなのかな、と
このコンテンツを読んで以後考えるようになりました。
その証拠というか傍証として、インタビューの終わり方も
「正直」なものとなっています。
つまり、非常にキレが悪い。
尾をひく読後感に、ゆっくり立ち上がって拍手したい。
このインタビューが行われたすぐ後くらいに、
原稿をまとめている最中のほぼ日の奥野さんと
話す機会がありました。
もうずっと、このコンテンツのことを話すんです、
奥野さん。
全然違う話をしていても、
「あ、それについても本木さんがですね」と言って、
インタビューの内容をすごくたくさん教えてくれました。
一緒に聞いていた方が少し呆れているように見えるぐらい、
「本木さんが」とおっしゃっていました。
寡黙な奥野さんがものすごく興奮して話していた
という事実が、
私に少しひいき目でこのコンテンツを
読ませているのかもしれませんが、
そうだとしても、やっぱりいいんです。
4
建物や家具になるために
息づきながら待っている
石や木との対話
素材はあるものを使うしかないから、
人のほうがいつでも最大限、
やるしかないんやで。 ──朝比奈秀雄
読んでいるこちらが、ピリッとするくらい
インタビューの現場の緊張が伝わってくることがあります。
たとえば、聞き手が尋ねようとすることがらを
話し手がにべもなく手放してしまう場合。
日本建築を手がけてきた朝比奈秀雄さんの
インタビューの初回は、
聞き手の期待に対して
「そんなもん、なんも、あらへんよ」と
朝比奈さんがさっぱりと答えるところから始まります。
それでも、と食い下がってと言いますか、質問を変えながら
聞き手は尋ねつづけます。
そのおかげで、私はこれを読むことができる。
東大寺の柱石から、琵琶湖を進んでいた船の底板、
果てはウィンザー城の敷石までが
静かにならぶ工場を歩きながら
インタビューはより具体的に進んでいきます。
カーブした木をどう使おうかとか
古い灯籠を庭に置くのはどうしてかとか、
実物を前にしながら語られる一つひとつの話から
ひしと感じるのは、
これはとんでもないことをなんでもないかのように、
何十年もやってきた人の話であるということです。
「なんもあらへんよ」に広がっている、
おどろくばかりにカラフルな厚い時間と経験。
聞き手と話し手が互いに面と向かい合うのではなく
一緒に肩を並べて歩いて、「ほら、あれ」と
同じ対象を見ながら話したのでなければ、
あり得なかったインタビューだと私は思います。
長崎で靴磨き屋をしていた時、
70代80代の職人さん達と話すのは
大きな喜びでもあり、同時に試されるような
ヒリヒリした時間でした。
その人の中にある知恵や経験を聞き出そうとすると、
全然話してくれなかったりするんです。
それが、目の前に壊れかけた靴であるとか、
製作中の革靴を間において
「おやじさん、ここは?」と尋ねると、
本当にたくさん教えてくれました。
それは職人たちの知恵や考えというのは
個人の中に大事にしまわれているのではなく、
物との間に橋をかけるようにして存在している
ということだと思います。
朝比奈さんのインタビューを読むたびに、
職人たちの橋がかかった時の
嬉しそうに話す身振りを思い出します。
ええ‥‥。
最期、最期ね‥‥談志は‥‥ ──立川志の輔
今は亡い人の話を、
その人とごく親しかった人がはじめるとき、
いつも以上に耳をそばだてて聞いてしまいます。
生前には話されることがなかったこぼれ話を聞き逃すまい、
というよりは、思い出を語る人の声に惹かれるのです。
この対談では、立川志の輔さんの師である
立川流家元・立川談志さんの逸話が随所に登場しますが
それは一般に思い出と呼ばれるものが連想させる
穏やかで暖かなものではなく、聞くものに冷や汗をかかせ、
語るものに問いかける種類の記憶のようです。
「落語のはなしをしましょうか」と題された
コンテンツではありますが、
当代随一の落語家である立川志の輔と話すということは、
なにを話していても
「落語のはなし」になってしまう人の話を
聞いているのであり、
志の輔さんが「落語のはなし」をするときに
「師匠談志」を語らずに済むはずもない。
そして、師匠の話をしていけば、
自ずと立川志の輔の落語の原点に触れることになり‥‥と、
らせんを描くように対談は広がります。
特に志の輔さんが師匠談志から教わった
「芸能」と「芸術」の違いは、
ほとんど全ての働く人が自分ごととして考えられるような
「問い」だと思います。
型破りでありつつ独自の原理に基づいて動いた落語の人、
立川談志さんを志の輔さんはこの対談中
「談志」「師匠談志」と呼びますが、
ただ一度だけ「師匠は」と呼んでいます。
そのことに気がつきながら読むと、
師弟ってやはり憧れを土台にした関係なんだなと
思わずにはいられません。
そしてその関係は、師匠が亡くなった後も
弟子の中に生き続けて、弟子に迫りつづけ、
弟子はこだまする師匠の声を聞きつづける。
このことから言えることは、
死んでしまった人の声を
聞きつづけようとする人がいる限り、
いつだってその声から
新しい教えを受けられるということです。
棺に蓋をするのではなく、死者をうしろから踊らせよう。
あの人の基本が
「味噌、醤油」なんですよ。
それはもう、そうです。 ──宮本信子
糸井さんの第一回伊丹十三賞受賞をきっかけにはじまった
「伊丹十三特集」。
この特集は、多彩にして
さまざまな分野で才人だったが故に、
なんともややこしい存在である
伊丹十三さん「について」ではなく、
伊丹十三さんという個性を
存分に楽しまんとするコンテンツの集積です。
私が伊丹十三さんにぐっとはまりこんでいく
最初のきっかけは、この特集でした。
当時、中学生だった私は
伊丹さんの映画もエッセイも知らないままに
ほぼ日の「伊丹十三特集」そのものを、
何かの伝説を聞くように嬉々と読んでいました。
「ねえねえ、これすごい面白いよ」と
パソコンの画面を母親にみせると
「え、なに伊丹十三好きなの?」という感じで、
母親は自分の本棚から
『ヨーロッパ退屈日記』『女たちよ!』
『再び女たちよ!』『日本世間話体系』などなど
手垢のついた文春文庫をごそっと出してきてくれました。
母親は若かりし頃、伊丹十三フリークだったのです。
それから瞬く間に私の中で巻き起こった
伊丹十三フィーバー。
九州の半端な田舎で、
どこかにもっと面白いことがあるはずだと
俯きながら学校と家を往復していた私を、
その「どこか」に連れて行ってくれる人、
それが伊丹十三さんでした。
その後、伊丹十三を教えてくれたほぼ日を読む姿勢も
ますます前のめりなものになっていき現在に至っています。
そんな「伊丹十三特集」の最後、糸井さんと対談したのが
伊丹十三さんの伴侶であり仕事仲間であった
宮本信子さんその人です。
この対談は先ほどの
「落語のはなしをしましょうか」と同様に
今は亡き人を回想しつつ
彼の人を生き長らえさせるはたらきをしていて、
宮本信子さんの中で伊丹さんが
「元気でいらっしゃる」様子が伺えます。
その元気な伊丹さんが宮本さんを通して語る、
表現と制作に対する思考が
川底の砂金のように光っている対談です。
この砂金を読み手は持ち帰ることができます。
特に宮本さんと糸井さんが語る
「伊丹十三」の「黒字主義」「食っていかねば」の姿勢は、
靴磨きをするようになってからも
大学院で勉強している今も、
自分が物事を考えるときに
しつこく思い出すようにしています。
この砂金がこれからも
私を食わせてくれるだろうと思うのです。
7
会社はこれからどうなるのか?
「むつかしかったはず」の
岩井克人さんの新刊。
もちろん、それは
いろんなヒントを与えただけであって、
ほんとの意味での「解答」を
与えているわけではないんですね。 ──岩井克人
私がほぼ日のコンテンツの中でとりわけ楽しみなのは
いわゆる先生や学者と呼ばれる方々が登場するものです。
普段は教壇に立って講義をしていたり
専門書を書いている先生方が
興味のある素人代表団であるほぼ日と出会う時、
思わぬ魅力が見えてきます。
その知の膨大な広がりや明快な理論というよりは、
学問を仕事として生きていこうする
働く人の姿が現れるのです。
世界的な経済学者である岩井克人先生が2003年に
一般読者へ向けて書かれた
『会社はこれからどうなるのか?』を入り口に
進められるこのインタビューでは、
岩井克人という一人の働く人が
いかにその道をならしながら歩いてきたのかを
読むことができます。
注目したいのは、世間からの期待と
自分の世間への違和感とをうっちゃってしまわずに、
そこに自分の仕事をさがしだす胆力の
ようなものを岩井先生が持ちながら進んできた事実です。
しかも期待のされ方が半端じゃない。
日常生活ではあんまり
「わたしは当時、世界で一番期待された若手といっていい」
とさらっと話す方とお知り合いにはなりません。
世界で一番期待されるんですよ。
しかも誰かに勝つとか、
ものすごく高いビルを建てるとかじゃなく、
「今のこの世界をよりよく考えられるように
してくれるんじゃないか」という期待です。
それのトップ・オブ・ザ・ワールドですよ。
余談ですが、私が大学ではじめて
「研究者」と呼ばれる人たちと接してわかったのは、
先生たちはあまり謙遜をしない、ということです。
不必要に「とんでもございません」とは言わないし、
「大したことはありませんから」とも仰らない。
自分のいついつの仕事にはこういう良い所があった。
それはこういう面で貢献をしたんだ。
別の部分では欠点もあったがね、と、
どんなに声が小さかったり、無口な先生でも
わりとはっきり自分で自分の仕事の評価をしていました。
自信家ばかりが研究職に就いている、ということではなく
基本的に独りで、自分の名前で仕事をする研究者の場合、
過去の自分の仕事との誠実な対話が
最良のヒントになるんだろうなあと思います。
その振り向く態度はおそらく
色んな人が使えるのではないでしょうか。
あの、これで原稿は大丈夫なんでしょうか? ──森重文
引き続いて、学問界からの
インタビューイーのコンテンツです。
しかし、先ほどの岩井先生のコンテンツとは
まるきり正反対の仕上がりになっているコンテンツです。
岩井先生のコンテンツでは中盤以降に展開される会社論、
価値論は鮮やかに明快に説明され目から鱗なんですが、
このインタビューに登場する
数学者・森重文先生の話していることは
もう、ほんとうに気持ちよく、わかりません。
ほぼ日のサイエンスフェローである早野龍五さんが
聞き手になり、
さらに興味ある素人代表団の「ほぼ日」二名が
「茶々」入れ役として同席し、
万全の体制で行われたインタビューなのに、です。
わからないのドライブがかかってくるのは
第5回くらいからで、
それまでは、数学者として生きてきた森先生の
道ゆきがなぞられます。
ここまではわかります。
いや、わかりますといっても、
京都大学の大学院入試で
「ひとつだけまちがっていた」と言われて、
「そんなはずはない」と調べ、
試験の「採点方法が悪かった」ことを
明らかにしたなどという大学生は
そんなにたくさんいるわけではありませんから、
わかったといっても、「はあ」と頷くていどな訳ですが。
それでも、第6回の「コーン」の出現以降に比べれば、
まだわかります。
もう、コーンが‥‥。本当に、なんなの、コーン‥‥?
森重文先生の専門である代数幾何学の話が膨らむにつれて、
素人代表団も物理学者である早野フェローも
むろん読者であるこちら側も完全に置いてきぼりなんです。
ふつう、インタビュー記事では
あってはならないことでしょう。
読者はおろかインタビューアーまでも混乱するなんて。
あげく、森先生自身もコンテンツの行く末を案じています。
しかし、です。
わたしがこれを印刷したいとまで思うのは、
このコンテンツが「わからない」体験の面白さを
決壊せんばかりに満々とたたえているからなのです。
インタビュー後半は話も流れもわからなさすぎて
笑いが止まらなくなってきますが、それは決して
屈折したものではありません。
森先生が図まで描いて説明してくれているにも関わらず
こちらは先生が言っていることが皆目わかりません。
むしろ図が事態を悪化させているようにさえ思えます。
言っていることは、わからないんです。
でも、自分にはわからないことを
じっくり考えて解く人がいるという
現実そのものの面白さに読み手は引き込まれて、
それでも言ってることはわからなくて、
そしておかしくなって笑うのです。
わかりやすくすることで
広く面白がってもらえるものもあれば、
わからないけど面白いというコンテンツもある。
たくさんあります。
よくわかんないものを価値のないものだと
捨ててしまうことが決してないように、
わたしはこのコンテンツを印刷しておきたいのです。
最高純度の「わからなさ」を
ぜひ体験してほしいと思います。
9
ライフライン。
あのときの水道、電気、ガスを
復旧した人たち。
なにしろ、
やれることからしか手がつけられなくて。 ──荒嘉久
ほぼ日の永田さんが継続的に作っていらした
「福島についてのコンテンツ」のひとつ。
水道、電気、ガスといった「ライフライン」が災害によって
不通に陥ったとき、少しずつ確実に
「通して」いった人たちへのインタビューであり、
福島県だけでなく、茨城県や
阪神淡路大震災の際の「現場」にいた方々も登場します。
どこから手をつけていいのか見当がつかないような状況を
前にしながら、考えられる原理原則を手がかりにして、
異常を日常に戻していく仕事をした人たちです。
本当に、こうした仕事をした人たちが話してくれて
永田さんが聞いてくれてほぼ日がそれを載っけてくれて
よかったなと、思います。
水道も電気もガスも、普段から生活者の目線上には
ないもので、見上げたり想像したりしなければ、
存在自体にも気が付きません。
ましてや絶えず点検と保全をしている人がいると、
蛇口をひねりながら思うことはごくまれです。
だから、ここで、このコンテンツでその人たちの言葉で、
家族の話とか風呂の話とかなんでもないような話を
読むことができてよかったと思います。
超人でもなく天才でもなく、
ノウハウと決意を持った一個人がグループをつくって、
なんでもない生活の大きな土台を
どうやって繋ぎなおしたのか。
これを知ることは、忘れないことと思い出すことを
わたしに要求します。
目線を上にあげて電線を見て、
蛇口をひねりながら思い出して、
風呂を沸かして考えるのです。
これは誰の仕事なんだろうか、と。
これは誰の仕事だったんだろうか、と考えるのです。
毎日は難しいかもしれませんし、
そんなこと考えて何になるのかと
思われるかもしれませんが、
こたつが暖かいことが、水が飲めることが、
お湯を沸かせることが
全部、会ったこともない誰かの仕事なんだと思い出して、
忘れないでいるのは、世界の中での自分の位置を
正しく測る上でものすごく大切だと思うのです。
他者を受け入れましょう、
感謝しましょうと口にするその前に、
私の生活っていったいどうやって可能になってるのかを
考えてみる。そのきっかけとして、最良のコンテンツです。
忙しくなる前に、ぜひ読んでみてください。
さあ、いよいよ最後のコンテンツです!
そして、このコンテンツは説明しようがないし、
説明すると個性死んじゃうタイプのコンテンツです。
近くにいても離れていても、それなりに面倒だったり
厄介だったり心配だったりする家族ですが、
話すネタには事欠きません。
その詰め合わせみたいなコンテンツです。
この年末年始は帰省できなかった人や
おかえりを言えなかったご家庭も
多かったのではないでしょうか。
これを読んで、帰省した気になりましょう。
これを読んで、誰かが帰ってきたと思いましょう。
初笑いがまだでしたら、ここでしてってください。
そうでなくても、このコンテンツの最終回だけでも
読んでください。
ページを開くとまず最終回ですから、
読んでくれるだけでいいんです。
そこに出てくる、「山田姉妹」のお父さんが
年始に必ず言うひとことを、
大きな声で無責任に言いましょう。
それだけで今年はもう十分です。
いやはや、長くなりました。
最後まで読んでくださりありがとうございました。
今年もプリンターの電源を入れて、
私はほぼ日を読もうと思います。
まったく私ごとですが、実はわたし、年男なんです。
ありがとうございます。
みなさまにとって良い一年になりますように!!
2021-01-05-TUE
-
イラスト&タイトル:あーちん
あーちん
2002年生まれ。9歳のとき、お母さんのすすめで
「ほぼ日マンガ大賞2012」にエントリーし、
約1000通の応募のなかから見事入選。
小学生漫画家として、『くまお』の連載をスタート。
初の単行本『くまお はじまりの本』を出版。
2年半の連載の後、小学校卒業をきっかけに、
『くまお』は246回で終了。
続く、中学時代は、好きなたべものを描く
『たべびと』を連載。
終了までに144品のたべものを描きあげた。
現在、春からはじまる大学生活、準備中の18歳。