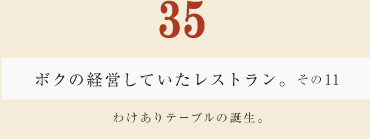共同経営者の友人が、
台湾からワザワザ買って
大切なお客様にだけおすすめしていた
とびきりのお茶の名前を彼は言う。
ええ、ございます。
そういうボクに、彼はこう続けます。
「あのお茶をもう一度、飲みたくって
今日はワザワザきたようなモノ。
今日は本当にラッキーですな」と。
ひときわ大きな声で言う、
彼の言葉に隣の彼らが反応します。
「そんなにおいしいお茶なのですか?」と。
好々爺氏はニマリとしながら、
「よろしければ、お試しになってみますかな?」
はい、よろしくと話はまとまり、
お茶のポットを全部で3つ。
ひとつは彼に。
ふたつは彼らに。
そして茶碗を人数分。
それまでそこの一角に、漂っていた酒の匂いが、
麝香にも似た甘くて濃密なお茶の香りにとってかわられ、
サービスしているボクまで気持ちが明るくなってく。
中国茶はね、まずは香りをたのしんで、
口の中で転がしながら
ワインをたのしむように飲めばいいんですよ、
と彼は彼らにひとくさり。
なるほど、確かにと、彼らはお茶を味わって、
それにつれてお酒のペースが落ちていく。
不思議なほどに彼と彼らは和気藹々と、
互いにお茶を注ぎつ、つがれつ。
彼らのテーブルからにじみだしてた
不穏な気配と緊張感が、すっかりなくなり、
店全体の空気までもがやさしくなった。
テキパキ料理を片付けている好々爺氏。
彼らが食事を終える前には、全てを食べ終え、
おいしかったとお勘定。
気づいて彼らが彼にいいます。
「ゴチソウになったお茶のお代は、
ボクらに払わせていただけませんか?」と。
「お騒がせしたお詫びもかねて」
そう付け加える彼らに言います。
「ひとりよりも大勢でたのしむ食事は、
お金で買えぬ贅沢ですから。
私がおすすめしたものは、
私が払うというコトで‥‥」
お見送りするボクに彼は一言。
今日はとってもたのしかった‥‥。
厄介なテーブルであればあるほど、
そこでたのしんでやろうって闘士がわくってもんだ。
と、いってニッコリ。
またくるネ、と後ろ姿もさっそうと、帰っていかれた。
|