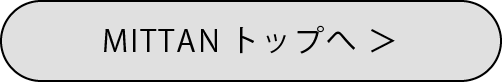「ほぼ日」がMITTAN(ミッタン)の服と出会ったのは
2016年、H.P.E.の谷由起子さんのご紹介がご縁でした。
TOBICHIで催された
「H.P.E.谷由起子 ラオスの布 × MITTAN展」で
谷由紀子さんがプロデュースする
ラオスのレンテンの織物を使った
洋服のオーダー会があり、
そこで服の製作を担当していたのが
MITTANだったのです。

ラオスの少数民族のひとびとが
家ごとに綿花から育て、糸をつむぎ、
同じように育てた藍で染め、
まいにちすこしずつ織った、
ひとつひとつ表情のことなる反物。
お客さまはそこから「これ!」というものをえらび、
MITTANがからだにぴったり合う
シャツに仕立てましょう、
というイベントでした。
たいそうこまやかに、お客さまととことん話して、
納得のいくものづくりをするすがたに、
「もっとこのチームと仕事をしてみたいなあ」と、
担当した私たちは思ったものでした。

当時のことは、この記事にまとめてありますので、
ぜひお読みいただければと思います。
それから彼らにお目にかかるたび、
「ほぼ日ストア」で、つまりネットショップで
販売をしたいとお願いしてきたのですけれど、
じつは、なかなか「OK」が出ませんでした。
というのも、MITTANの服は、
彼らの服づくりを理解する人の手によって、
直接、販売をしたいという方針があったから。
卸し先には、「この服には
こういうストーリーがあるので、
こういうことを伝えてください」と、
きちんとやりとりをするのだといいます。
そのためMITTANが手に入るのは、当時、
彼らの信頼する各地のセレクトショップのみ。
それぞれのお店で、
きちんと試着をしていただいたうえで
販売するというスタイルが基本だったのです。
パソコンやスマートフォンの画面から
「カート」に入れて買い物をするのでは、
どうしても「人の気配」が薄い。
それに、写真での表現に自分たちの感覚が反映されない。
そのことがどうしても気になるということが、
彼らがネット通販をよしとしない理由でした。

自前のショップを(もちろん通販サイトも)
持たないMITTANですが、
それも「自分たちはあくまでも作り手である」ということ、
そして「伝えることはとても難しい」と考えているから。
けれどもときどき、セレクトショップの一隅を借りて、
自前のポップアップショップを展開することがあり、
そのとき、MITTANのみなさんが直接お客様にふれ、
お見立てして、納得のゆくまで試着をするさまは、
しょうじき、胸打たれるものがありました。
そこで私たちがお誘いしたのが「生活のたのしみ展」。
2回のイベントでいっしょに販売をしました。
そこから彼らの服が、
ほんとうにたくさんのかたがたのもとへ
旅立っていきました。
(このコンテンツをお読みのかたのなかにも、
「MITTANの服、持ってますよ! というかたが、
きっと、いらっしゃることと思います。)
そうしてすこしは距離が縮まったからでしょうか、
今回、MITTANとしてははじめて、
「ほぼ日」でネット通販をしてみましょう、
ということになったのでした。
生活のたのしみ展をとおして、
こういうみなさまのところに届くんだな、
ということが想像できるようになったことが、
MITTANのなかでの、変化だったようです。

はじめての「通販」。
さてここまで「MITTAN」というブランドを
一人称のように書いてきましたが、
主宰しているのは三谷武さんという男性です。
でも三谷さんはあまり表に出ることを好みません。
最初は個人事業としてはじめたのですけれど、
「最初から、自分がつくっているという
気持ちはうすかったんです」
とまで言います。
ましてや会社として立ち上げた現在は、
チームでの仕事がほとんど。アトリエ内だけでなく、
MITTANを理解する各地の工場のかたがたと
協力しながら服をつくっています。
だから「個人デザイナーの世界」でもなければ、
「作家としてのものづくり」ではない、という考えです。
MITTANの服づくりは、
装飾的なディテールや
ジェンダー的な「洋服」の要素を、
できるだけ入れないようにしているそう。
逆に、民族服の要素の入った服が多く、
みずからも「あたらしい民族服」という言い方をしてます。
生地にはそれがつくられた背景や歴史があり、
それを服として纏(まと)うことが
たいせつだと考えています。
‥‥と、そんなふうに書くとちょっと理屈っぽいですよね。
だいじょうぶ、
MITTANの服のよさは、着てみるとわかります。
デザインに、理屈を吹き飛ばすようなちからがありますし、
カジュアルウェアと組み合わせることもでき、
ハイファッション、ハイブランドとあわせても
ひけをとらないかっこよさがある。
それでいて肩の凝らない着やすさがあります。
洗濯をくりかえすほどになじんでいく「育つ」ところ、
そしてきちんと「その人らしい」スタイルに見えるところ。
‥‥だんだん、ネット通販に向いていないという
三谷さんのことばを思い返してしまうのですけれど、
いいえ、きっとネットでもこの魅力は届くはず!
そう信じて、販売をしたいと思います。

MITTANを立ち上げた三谷さん。
表に出ることを好まない三谷さんですが、
彼のことをちょっとだけお話しします。
三谷さんは、1981年生まれ。
文化服装学院のアパレルデザイン科出身です。
高専時代はコンピュータプログラム系の勉強をしていた、
という理系のひと。
とうぜん「SEになる」という夢を持って
勉強をしていたのですが、
ファッション雑誌で見たモードの世界に魅かれて進路変更。
当初はマルタン・マルジェラやバレンシアガに夢中、
というファッション青年だったのだそうです。
そこからどうして「現代の民族服」の方向へ‥‥?
それは、ファッションで巨額の資金が動く生産の背景に、
まずしい国のひとびとが、それも子供たちまでもが
不当な労働を強いられている、というかなしい現実を
知ることになったからだといいます。
「そうじゃないものづくりがしたい。
そういう気持ちが芽生えたんです。
物づくりをして傷つく人が少ないといいな、
ということを、考えるようになりました」
そう三谷さんは語ります。

「きちんとした背景で作られた服が、
人の大事な記憶の傍らにある。
そんな風になればよいなと考えていました」
多くの服、そして、それにまつわる感性って、
「今」に価値がおかれているのが、現代の服の在り方。
過去はどんどん価値がなくなっていってしまう。
「そんなファッションのサイクルから
抜け出したものを作りたい。そう思っていました。
長く服を着られるように、お直しもし続けたいし、
定番的に同じものを作り続けたい。
いっしょに服をつくる工房や布の工場に、
常に仕事を供給し続けることだって大事です。
たぶん、ぼくには、既存のサイクルへの
強い反抗心があるんだと思います。
それは、ブランドを設立・運営していく上での
モチベーションになっています」
(いま「お直し」という言葉が出ましたが、
MITTANの服は、ほつれたり破けたり、
もし不具合が出たときには、お直しが可能です。
今回、「ほぼ日」で購入された服が、
将来、お直しが必要となったときは、
「いつでも、直接、ご連絡ください」とのことでした。)

服ってなんだろう。生地ってなんだろう。
縫うってなんだろう。
着るってどういうことなんだろう。
そんなことを考えていくうち、気がついたら、
アジアを中心に、世界中のいろいろな「布」を
買い集めていたのだそうです。
卒業後は、生地から扱う中規模のアパレルに入社。
さらに自分が思うようなものづくりをしている
小さな規模のアパレルに転職。
「そろそろ独立しよう」というタイミングを待ち、
退職して1年半ほどは、
ニットの勉強をしたり、
パターンを作ったり、
実際にサンプルをつくったりしながら
ブランド立ち上げの準備をしたそうです。
すばらしい「手」との連携。
最初に書いたラオスの布もそうですが、
糸からつくり、家で織るような布は、
「目がそろっている」ことがなく、
さらに一反一反、個性があります。
そういうものは「最新技術」との相性がわるい。
高性能のミシンで、化繊のじょうぶな糸で
テンションをかけて縫ったりしたら、
やぶけてしまうこともある。
そうですよね、現地では、布の目をひろうようにして、
繊維を切らないように手で針を刺して縫うような布です。
それをつかって、
現代の日本で私たちが着る「服」をつくるのは、
じつは、とてもむずかしいことなのでした。
ですからとくべつな布を使うことの多いMITTANでは、
縫製をお願いする工場の確かな技術も必要。
布探しとおなじくらい、
工場探しということも、
MITTANの大きな仕事のひとつなのですね。
「いまでは、この布なら、この工房に。
この布だったら、あの工場に、と、
そんなネットワークができあがってきています」
小さな工房なら、たとえば基本1人でやっている、
というところもあるのだそうです。

こちらの写真は、MITTANと同じ京都にある、
縫製のアトリエ「ミンクスキョート」代表の村雲由里さん。
三谷さんとは前職からのおつきあいで、
MITTANもこの5年、ずっと縫っているのだそうです。
「手が、きれいなんです」
と三谷さん。
その意味は、彼女が縫う布は、
仕上がりがとてもうつくしい、ということ。
でもMITTANの使う布って、
縫うのがとても難しいんじゃ‥‥?
「そうなんですよ。伸びたり、穴があきやすかったり、
基本的に、手織りの生地は、
地の目がとれませんから(笑)」(村雲さん)
「地の目が取れない布をなにも考えずに縫うと、
おかしな服ができあがっちゃうんです。
それを村雲さんは、調整して裁断し、縫ってくださる。
つまり、パターンと布を納品して、
裁断からすべてやっていただきます」(三谷さん)
それはさぞたいへんなのでは‥‥と思いきや。
「MITTANさんの生地に触っていると、
とても落ち着くんですよ。
なにより、手が荒れない。
化繊のプリントものをつくっていると、
どうしても荒れていく手が、
MITTANを扱うと、荒れない。
そんな布を扱うことができるのは、
私にとって、とてもしあわせなことなんですよ」(村雲さん)
でも、うんと硬い生地を縫ってもらうこともあるのだそうで、
そういうときは「申し訳ない」と三谷さん。
「ウチの硬いバリバリした生地のジャケットを、
100枚かな、やっていただいたばかりなんです。
それ、着物がベースになってるので、
内側が全部、ぐるっと手まつりで、裾も手まつり。
針が生地を通りにくいですから‥‥」(三谷さん)
「『きぬえりしめ』っていう細い長い
着物用の針を使って縫いましたね。
こんなこと、ふつうのアパレルではありえない!(笑)」
(村雲さん)

今回「ほぼ日」で扱う服は
ミンクスさんの手によるものではありませんが、
同様に、三谷さんたちが信頼する工場で、
1点、1点、ていねいに縫っています。
取材を終えて、私たちは思いました。
「人の営み」として健康である。
そんな活動をし、ものづくりをすることを、
きっとMITTANとそのまわりの人たちは
愛しているのだろうな、と。
効率性とか生産性、コストを考えることも
ものづくりにはとても大事ですけれど、
それだけじゃなく、人が人らしい暮らしをしながら、
つくれるものをつくる、そんなものづくりの原点に
立ち返る気がしたのでした。

2018-11-20-TUE