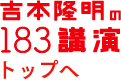日本人の死生観
1 司会
2 宗教以前の死生観
いまご紹介にあずかりました吉本です。わかりやすい内容でしゃべると言われましたが、それはうそで、実はわかりやすくないことを言うという評判がある人間なので、できるだけ気をつけてわかりやすくお話ししたいと思います。よろしくお願いします。
今日のテーマは「日本人の死生観」、死と生についての考え方ということですが、このテーマは二つやりようがあると思います。一つは現在の日本人が一般的に死について、そして生についてどういうふうに考えているかということをお話しすることだと思います。もう一つのやり方は、そうではなくて日本人が、遠い、遠い昔に、宗教も何も入ってきていないで、そういう影響を受けなかった、あるとしても自然に対して持っている宗教的な気持ちだけだったという時代の日本人は生と死についてどういう考え方をしていたか、そういうことについてお話しする、その二つのやり方があると思います。僕は、今日は前のほうの日本人が宗教的な影響を受けなかった時代にどういう生と死の考え方をしたかということをお話ししてみたいと思います。
もしそれで時間があったら、話の筋道から行くようでしたら、いま生と死について日本人がどういう考え方をしているだろうか、あるいはどういう考え方だと考えたほうがいいかというお話に入っていきたいと思います。
大昔、日本には古代になると少し宗教が入ってくるわけですが、古代以前の未開とか原始というところで日本人が人間は死んだあとにどういうふうになっていくと考えていたのだろうかということを申し上げたいと思います。
まず第一に、死んだあと人間の魂はあまり遠くへは行かないのだと考えていたように思われます。それからもう一ついえるとすれば、魂が肉体から離れて、どこかあまり遠くないところに漂っていて、繰り返し、繰り返しまた帰ってくるという考え方をしていたように思います。
もう一つ、あえて言いますと、死んだときに魂がいる世の中と、自分のいる現在の世の中との間には、そんなに断絶、分け隔てがないのだ、いつでも呼ぼうとすればやってくるし、またいつでも自分のほうからも行くことができると考えていたという痕跡があります。たとえば沖縄では、あの世、死んだあと魂が行く世界は、本土の言葉でいえば後生(ごしょう)ですが、向こうのなまりでいえば、「ぐしょう」だと思いますが、後生というのはいつでもお目にかかれるところだと考えていたように思われます。
柳田國男という民俗学者は、自分が若いときに国文学と和歌の先生から、君と僕の間のこの空間だって、これはあの世なんだよとか、あの世とは隠れ世ですが、隠れ世なんだよという話をしたことがあると書いていますが、そのように目に見えないのだけれども、ごくそばのところで、死んだあとに魂が行くところがあったと考えていたように思われます。
それではあの世というのはどのように思い描いていくかということを考えていくと、日本人が考えていたあの世は三つあると思います。一つは、もちろん村里のそばの山ですが、山の頂というところにあの世があって、そして死んだ魂は山の頂にとどまっている。またいつでも迎えに行けば帰ってくると考えますので、一つは山だと考えるべきだと思います。
もう一つは海、海のかなただと考えていたと思います。海のかなたにあの世があって、船に乗っていけばそこへいつかは行けるものだ、またそこからは何らかのかたちでやってきて、いつでもこの世には生きているものがあると考えていたと思います。
そしてもう一つ考えられるのは、地下です。海岸の洞穴みたいなものを通して、その洞穴の向こう側の地下のところにあの世があって、いつでもそこへ行けるし、また洞穴のところに行くと、いつでもあの世と行き来する、交換することができると考えていたと思います。
日本人のあの世の考え方、死んだあと人間はどこに行くのだという考え方は大きく言ってしまうとその三つがあると思います。この三つはいろいろな意味合いがあると思うのですが、もし時間があれば、それについて自分の考え方も申し上げてみたいと思いますが、一応その三つが考えられると思います。
3 山の頂に霊が集まるという考え方
たとえば四国に有名な剣山という山がありますが、そこに旧暦の四月八日に山登りをする風習があります。その風習は全国いたるところにあるわけですが、それはなぜかというと、神様に会いに行く、死んだあとの魂、祖先の霊に会いに行くのだということで、山登りが非常に大きなお祭りの要になっています。
山登りをどういうふうに考えていたかというと、たとえば死んで一年たつと、山の中腹のところに魂がいる。だから中腹のところまでお参りに行く。また二年たったら、もう少し上のところに魂がいる。またその次の四月八日にはさらにもう少し高いところまで登っていく。そうすると一種の兆しみたいなものを感じて、登った人が、ああ、ここで死んだ人に会ったというある感じを受けて、そうすると安心してまた山を下りてくる。
しまいにその山の頂まで登る。そこで死んだ人に会ったという感じを受け取ったときに、その死んだ人はもう神様になっている。自分たちも死んだ魂は神様になって世界にいるのだから、それ以降はたとえば三十三年目に山登りということではなくて、一般的にその人に会いに行くということになって、一般的なお祭りに代えてしまう。だから三十三回忌までは山登りみたいな行事をするということがいたるところにあるわけです。
それから亡くなることには逆のことがあります。というのは、ある人がお産をする場合、それがどういうしるしでわかるかというと、たとえばきこりさんとか、猟師さんとか、山の仕事をしている人は、山の中の大きな木の下で休んでいるとふと馬のひづめの音が聞こえた。そうすると、ああ、これは村のだれかの家でお産があって、人が生まれるのだと感じる。山を下りてくると、確かにどこそこの家で赤ちゃんが生まれている。そういう話ももちろんあります。
また難産になってしまって、どうしようかというときに、厩から馬を連れてきて山に登っていく。そうするとどこかで馬が突然何か目に見えないものに出会ったように驚いて立ち上がったりする。そういう兆候があると、ああ、山の神様に出会ったのだから、これで難産は解消すると考えて、また馬を引いて家に帰ってくる。そうするとちゃんと子どもが生まれている。そういう話もあります。
具体的な例でいいますと、たとえば山形県に飛島という島がありますが、そこでこういう伝説、言い伝えがあります。飛島で磯辺の荒岩のところが、仏教でいえば賽の河原で、そこには霊が集まってくる。その向かい側に険しい無人島があって、その島の頂に霊がひとたびとどまって、それからはるか向こうの鳥海山に死んだ人の霊はやっていって、鳥海山の頂に宿るという考え方が伝承されています。
村の人は荒岩の賽の河原といわれているようなところのそばの道にいると、目には見えなくてだれもいないのだけれど、何となくいい歌声が聞こえてくる。それは賽の河原のほうに消えていく。そうすると、ああ、今日はだれかが死んだのだとすぐにわかったという伝承があります。村里に行ってみると、やはり昨日、だれかが亡くなっていた。だから賽の河原に行く道で歌声が聞こえると、だれかが死んだことがわかるし、死んだ人の魂はまず賽の河原のところにやってくるのだということがわかった。そういう言い伝えがあります。
その種の言い伝えはたくさんありますし、賽の河原といわれているものがどこに行ってもある。たとえば佐渡の外海府というところにやはり賽の河原があって僕もお目にかかったことがあります。いたるところにそういうところがあって、それはそういうところに霊が集まっているという考え方の表れだと思います。それは賽の河原と呼ばれていますが、別に仏教が入ってきたからそうなったというよりも、もっと以前からそれはあったと思います。つまり宗教なんか入ってこないときからそういう考え方があったと思います。
柳田國男の『遠野物語』の語り部であった佐々木健が話していましたが、自分の娘が死んだときに夢を見た。そのときに自分の娘は山の中腹のところで道を探して迷っていてうろうろしているのに出会った。死んでから三十日ぐらいたったあとに、やはり同じように娘の夢を見た。そのときに娘は、あなたは山の上のほうの天空を飛ぶようにして走っていった。四十日ぐらいたってまた同じような夢を見た。そのときには橋の上で娘に出会った。お前はいまどこに住んでいるのだと言ったら、娘は、自分はいま?ハヤシネの頂に住んでいますと答えて立ち去って行った。そういう話をしているのがあります。
それは夢ですが、夢うつつにそう考えていたとしても、同じことだと思います。それはどういうことかというと、死んだ人は山の上に行くものだという考え方は一般的に無意識の中にもあったということを意味している一つの例だと思います。
この山の頂に霊があるという考え方は何を意味しているのだろうかということをよく考えてみると、それはたぶん昔は里に住んでいて、田畑を耕して農業をやっていた人たちと、山に住んでいてきこりや猟師をしていた人たちと、その間をつなぐものとして伝承が生まれてきたのだと思います。神様は山のほうに行くし、人間は死んだあとに山の上のほうに行く。それには通路をつけてやればいい。その通路をつけてやれば、その通路を通って山の上のほうに行く。もちろん山の上のほうの神様は、迎えに行けばいつでも里のほうに帰ってくるし、霊もまた帰ってくると考えられていたと思います。
だからこれは平野に住んでいる里人と山に住んでいる人たちとの間に、何か宗教的なつながりもあるし、死んだあとの世界についても考え方のつながりもあります。また実際の行き来もあった。そういうところから生まれた伝承であり、考え方だと思います。
4 海の彼方に霊が集まるという考え方
もう一つ、先ほど言いましたようにこれとはまったく違うようでもありますが、人間は死んだあとに海のどこか、かなたに行くものだ、また海のかなたのどこかから死んだ人の魂は帰ってくるものだという考え方があって、これは山の系統とはまた別の系統に伝承があると思います。
その伝承によれば、それでは何が海のかなたの死んだ人が行くところと現世とをつなぐものと考えられていたかというと、それは折口さんという人が現実に、詳細に申していましたが、それは空を飛ぶ鳥だ。特に雁が飛んでくると、その雁は海の向こうの魂が集まるところから人の魂がやってくる使いであるし、また死んだ人の魂をこちらから海のかなたの世界へ連れていく使いだと考えられていたといえると思います。
一般的に空を飛ぶ鳥が、この世と人が死んだあとに行く世界とをつなぐものだと考えていたのが、海のかなたに死んだ人は集まるのだという考え方をしていた人たちの考え方だと思います。そうすると空飛ぶ鳥があの世とこの世とをつなぐ使いだという考え方と、山の頂と里との間が神様と死んだ人に行き着くつなぎなのだという考え方との間には、大変な違いがあると思います。
たぶん海のかなたに死んだ人が行くところがあるのだと考えた人たちは、もちろん海辺に住んでいた人たちでしょうけれども、海辺に住んでいたと大ざっぱに言ってしまうと、日本は島ですから大きくとらえれば、たいていだれもが山のふもとにいたといえますし、だれも海のほとりにいたといえるようなところに日本人は住んでいましたから、そういうふうに大ざっぱに言うこともできます。
たぶん海のかなたに人間が死んだあと魂のあり場所があると考えた人たちは、稲作を持って日本に渡ってきた人たちではないかと思います。つまり海のかなたから渡ってきて、そして稲作を持って平地、里に入ってきて、そこで農耕に従事したという人たちの伝承が、たぶん海のかなたにあの世があって、そこから魂はいつでも帰ってこられるという考え方を取ったと考えることができそうに思います。
これに対して山の上のほうに死んだ人が集まるところがあるという里人の考え方は、たぶん稲作など農耕が始まる以前から、この日本の列島に住んでいて、そしてだんだん里住まいをするようになった人たちが主に伝えている伝承のように僕は思います。それはあながち断定したりすることはできませんが、そういう気がします。
5 洞窟の向こうに死者の世界があるという考え方
ところでもう一つ、人間が死んだあとにどこに行くかということについて、大昔の日本人がものすごく考えていたことがあると思います。それは先ほど言いましたように海岸の洞窟を通して、その向こうに世界があると考えていたと思われます。この考え方は、たとえばアイヌの人たちはそういうふうに考えていた。洞窟のところを通ってあの世があって、あの世というのは自分たちのこの世界とまったく同じような世界があって、同じように生活している。ただ、現実の生身の体はないから、体に苦になるようなことは少しもないのだ、一種の浄土に似た楽土なのだと考えていて、どうやったらそこに行くのかというと、死んだあとに洞窟を通ってその世界に行くのだと考えられていたと伝えられています。
南の沖縄のほうでも、洞窟に死んだ人を葬った跡がいっぱいあって、そこでお祭りをやるという風習が現在でもあります。もう一つ挙げてみると、和歌山県の熊野にやはり洞窟信仰みたいなものがあります。たとえば日本の神話の中でいうと、伊弉冉尊、伊弉許尊が日本の伝承上の日本人の始祖であるという神話上の人になっているわけですが、その伊弉冉尊が死んだあとに伊弉許尊がまた生き返らせようとして追いかけていく。そして神話は二つの伝承になっていますが、一つの伝承は、追いかけていってちょうど出雲の国と伯耆の国のちょうど……
【テープ反転】
……たとえば日本語と朝鮮語とか、日本語と中国語とか、あるいは南方語とかどこでもいいのですが、そういう言葉は厳密に類型をつけようと、つまり類似関係とか祖先が同じだという関係をつけようとしてもつけられないのが現在の状態だと思います。それはいまわずかに類縁がつけられるのは、本土語と沖縄語とか、最近でいえば少しずつそういうことをしていると思いますが、アイヌ語と日本の本土語です。もしかしたら類縁がつけられるというか、これは祖先が同じだったということが何となくいえそうだというのはそのくらいだ。日本語と朝鮮語、日本語と中国も、日本語と南方語で、これが同じ祖先の言葉だとはどうしてもいえないぐらい日本語というのはある意味で奇妙な言葉で、特別なところがある言葉だということがいえます。
これはどういうことを意味しているかというと、さまざまな言葉が混和しながら長い年月をかけて徐々にでき上がった言葉だからだと解釈するのが一番いいような気がします。ですから僕の考え方ではさまざまな日本人の死生観と申しましても、本当に微妙なニュアンスまでたどっていくと、千差万別の死についての考え方、生についての考え方があって、とてもとても統一的に取り上げることは難しいということになるのですが、いろいろな先人たちの研究の成果として、だいたいいま申し上げた三つの類型に大ざっぱに分けられる生と死についての考え方を持っていたのではないかといえると思います。
まだ日本人が宗教も何も持たなかった時代、あえて宗教というのならば自然宗教しかなかった時代、自然に持っている習慣とか風俗として持っている信仰心しかなかった時代に考えられる死についての考え方、あるいは死んだあとに人間が行くのはどこだろうかということについての考え方は、大ざっぱにその三つの類型に分けられます。たぶんその三つの類型は、三つの時代的な、あるいは時間的な類型をも意味していたりしますし、またある意味では日本人を構成しているたくさんあった種族のうちで、大ざっぱに三つの種族の考え方を象徴しているみたいなこともいえるのではないかと思われます。
このように考えていくと、日本人の生と死の考え方は大ざっぱにいうと南のほうの島、つまりパプアニューギニアのほうからフィリピンとかジャワ、スマトラなども経て、日本の西南太平洋の島々から、またアジア大陸のインドとか東南アジア、中国とかシベリアとか、そういうところの海岸へりに一般に分布している考え方のある類型の中に入ってしまうことは確かだと思います。
たとえばパプアニューギニアの人たちも同じような考え方をしているという報告があります。それは死んだ人は沖にある島にみんな集まって、そこで生活している。村でだれかが子どもを生むと、その島からだれかの霊がその子どもに入り込んだからその子どもは生まれたのだという考え方が流布されていることがいわれています。それは何が仲立ちをするのかというと、女の人が沐浴をしたときに海の水に流れていった小さな微生物を通じて、女の人の体の中にその霊が入り込んで、そして赤ん坊を産んだのだと、そういう言い伝えがあります。それはアジア、オセアニア地帯の海辺に一般的に流布されている考え方です。
そのようにいつでも割合と近くの島とか近くの山とか近くの洞窟とか、そういうところを通していつでも霊が行き来しているという考え方は、一般論でいえば、そういうところに入ってしまうと思います。つまり一般的に海辺のアジアと、海辺のオセアニアの島々の中に日本人の死と生についての考え方も入ってしまうように思います。だから日本人には特殊なところもたくさんありますが、このように特殊なものとはいえないところもたくさんあると思います。
6 魂の性質
たとえば魂はどういう性質を持っているかということは、海の信仰の人、山の信仰の人、洞窟信仰の人、日本人も全部同じなわけですが、それは魂というのがいつでも行き来することができると考えられて、いつでもこちらに入り込んだり、向こうへ行ったりすることができるのだと考えられていたと一般的にいえます。
日本人が考える場合も、死者はいつでも魂として行き来することができるという言い伝えがたくさんあります。たとえばこういう言い伝えがあります。赤ん坊を死なせてしまった両親とか、おじいさん、おばあさんはものすごく悲しくてしょうがないので、子どもがきっとどこかに必ず生まれ変わってくるのだということを確かめたくて、死んだ子どもの手のひらに墨で印をつけて葬ると、それがたとえば村のだれかの家で子どもが生まれると、その子どもの手のひらに死んだときにつけた印がついていたという話があります。
もっと極端な話では、そういうふうにして死んだ子どもの手のひらに何か印を墨でつけて葬った。大名の家で生まれた子どもの手のひらを見たら、そこにその印がついていた。一般的な言い伝えによればその印を消すには、子どもを葬った墓の土を持ってきて、その土でそれをこすらなければそれは消えないという伝承があった。大名のところからひそかに使者が、お前の子どもを葬ったお墓の土くれをくれないかと言いに来て、その土くれを持って大名の家に帰っていって、それでこすったら手のひらの印が消えた。そういう話は伝承として伝わっています。
それはたぶん相当広範囲に伝わっている話だと思います。そういう話は、もちろん生まれ変わりができるということを表す言い伝えですが、同時に魂はいつでもどこへでも行けるのだ、またそういう気持ちがあるのならばいつでも呼べるのだ、そういうところにいるのだという考え方のしるしだと思います。
またこういう話もあります。徳川時代の話の中にあるのですが、非常に霊能力みたいなものがある子どもがいて、その子どもが自分はだれかの生まれ変わりだというのをかすかに覚えていた。前に自分がいたところは、こういう村で、こういう場所で、こういうところにこういうものがあってと、姉さんにそれをいちいち話すので、姉さんが不思議がって、じゃあそこに行ってみようと、二、三里離れた村里に行ってみたら、その子が言ったとおりの景色がちゃんとそこにあった。そしてその子が言ったとおりの道を探すと、そこに一人の子どもがいて、それはその子が言ったとおりの顔かたちをしていた。そういう話があって、それが本当だとか、うそだとか大騒ぎになったというのが徳川時代のお話の中にあります。
これはあまり笑ってはいけないというのは、最近出ているアメリカの宗教社会学者の書いた本が翻訳されています。皆さん、専門に近いわけですからお読みになった方もおられると思いますが、そういう言い伝えが本当かどうか、インドに行って非常にまじめに調査したことが書いてあります。調査した結果、自分はだれそれの生まれ変わりだと言う人がいて、その人の言うことを全部聞いて、あやふやな、あいまいな要素は全部取り払ってその場所に行ってみたら、ちゃんとそういう人がいて、その人に聞いてみると、自分はそうだと言ったという調査記録を出しています。非常にまじめにそういうことをやって、まじめにそういう結論を出しています。あの世から人間はいつでもよみがえって帰ってくることができるということは確実なのだと言い方をして、その宗教社会学者はその本でそう信ずる以外にないという結論を出しています。
僕は、そうは思いません。それはやっぱりうそであるとは思いますけれども、しかし根拠のないうそでない。つまりそのことはインドとか東南アジアとか日本なども含めて、アジアの海辺の地域で非常に普遍的に、どこにでもあった一種の未開、あるいは原始時代の信仰の非常に強固な形態であって、まさにそのころの人はそのように感じて、そのように思ったことは現実であると考えても、現実でなくて夢であると考えても、それはまったく同じことを意味していた。それくらいに宗教ではない宗教として、あるいは習慣では習慣として、あるいは風俗ではない風俗として確信していたと考えると、決して根拠のないうそではないと思います。
日本のそういう言い伝えの中にも、うそではないうそだと言いましょうか、あるいはうそであるけれども本当なのだと言ったらいいでしょうか、そういうものが含まれていることは確かだと思います。問題なのは、そういう死についての考え方、生についての考え方はどのような時代に、どのような地域にそれが分布していて、どのような役割を持って、どのような意味を持っていたかということがとても大切であるという気がします。
だからこのような考え方を宗教社会学者が非常に真剣に、怪しい要素、言い伝えの要素を全部排除したうえで調査をして、それである結論を出すということは、たとえその結論について異論があるとしても、それはとても重要なことであるような気がします。そこのところで考えていくと、先ほど言った山に亡き人の霊が集まる、海のかなたに集まる、海岸の洞穴に集まって、それからあの世界に行くという考え方も決して根拠のない言い伝えでもないし、根拠のない信仰でもないし、根拠の無いうそではないのだということがいえると思います。
7 仏教の考え方
いま申し上げた一般的な日本人の死についての考え方、生についての考え方を根こそぎ変えてしまった、あるいは根こそぎ発展させてしまったのは、仏教が日本に入ってきたときです。それは発展であるとともに、ある意味合いでいえば激しいことでもあるということができると思います。つまり死んだときに生まれ変わったりするということをどこで断ち切ったらいいだろうかということの労苦の果てにできあがったのが仏教です。
仏教は輪廻転生、生まれ変わりとか魂が動くという信仰を一面では継承しながら、生まれ変わって現世にやってきたときに、あまり苦労が多いとか、心の苦しみ、あるいは物質的な苦しみが多いとか、つまり貧困な生活をもう一度やらなければいけないということがある時代から大変人々の心を苦しめるようになった。こういう苦しい世の中からどうしたら逃れられるのかということを人々が考え始めたときに仏教が生まれたわけです。
仏教は、あるやり方をすれば輪廻を断ち切ることができる。仏教は浄土といいますが、死んだあと浄土に行ったならば、そこは非常に楽しいところであるからそこからもう帰ってこなくていい、そこに行ったきりでいいと、つまり輪廻を受け継ぎながら、輪廻を断ち切るというのが仏教の考え方です。
また場所的に言っても、これは宗派によってさまざま違いますが、いずれにせよ十万億土のかなたにあの世の世界があって、そこは浄土、楽土であって、楽しいことばかりがある世界だ。死んだあと人間はそこに行ってもう帰ってこなくてもいいのだという考え方だと思います。場所としても山の上にあるとか、海のほとりにあるとか、あるいは海の岩礁の向こう側にあるという言い方を全部やめて、西のほうに十万億土があって、そこに行くのだ。そこは楽しいだけでもう帰ってこなくていいのだという死生観は仏教が入ってきてから日本人の中に入ってきたと思います。
ですから村里の人たちが目を上げて周辺にある山を見ると、その山の頂に自分の死んだ子どもがいるんだという考え方の親しさとか懐かしさというものからすると、仏教は基本的にはそれを断ち切ってしまいましたから、割合に寂しい考え方といえば寂しい考え方だと思います。山に迎えに行ったら死んだ人の魂がまた帰ってくるということはなくて、十万億土のかなたから帰ってくるのはお盆のたった三日間だということに変えてしまいました。だからある意味合いではとても寂しいことになったと思います。
でも皆さんがご承知のように仏教や、現在も行われている習慣の中には大昔の海の向こうに死んだ人が集まるあの世があるのだという考え方とか、山の上にあったのだという考え方、また海の洞窟にあったのだという考え方は、仏教自体がある意味ではそれを吸収して、受け入れていまも伝えているということでは、一種の日本人の大昔の死生観を受け継いでそれを発展させたともいえるわけです。
そういう意味では仏教はインドから始まったのですが、日本に入ってきて、日本人に受け入れられたときには、日本の大昔からのそういう死生についての考え方を受け入れて吸収したうえで成り立っているともいえるわけです。別の意味でいえば、そういう考え方を断ち切ろうとして、もっと遠くのほうに死んだ人の集まる場所を持っていってしまったといえると思います。
こういう仏教の考え方が一般の人たちの中に入っていったのは、日本でいえば中世だと思います。つまり鎌倉時代に入ってそういう仏教の考え方が一般の人たちの間に浸透してきたと思います。その中に大昔から日本人が持っていた考え方が全部混合しながら、ある部分は捨てられ、ある部分は習慣として残って、それが仏教の習慣のように言い伝えられてきていると思います。
たとえば四月八日という日は、お釈迦様の誕生日とか、花祭りとか、一見すると仏教に関係があるように思われますが、柳田さんはそうではなくて、大昔の日本人は新年が四月八日だと考えていたというのが自分の考え方だといっています。ですから必ずしも仏教とは関係ないのだけれども、仏教的な習慣がそれをまた受け継いで、日本人の死生観を変えていったといえると思います。
8 親鸞の浄土という意味
鎌倉時代の仏教もそうですが、日本浄土教が法然、親鸞から始まったわけですが、浄土教が始まる前までの日本の仏教の修練の仕方は、たくさんの修行を積んで、そのうえである精神状態をつくりあげると、あの世の世界に行くことができる。あの世をぐるっと回って帰ってくることができる。あの世の世界は、地獄の世界はこうなっている、極楽の世界はこういう光景があって、こういうものがあって、こういうふうにきれいだったと、そういうことができるようになるというのが仏教の修行の眼目であったということができます。
特に密教と呼ばれているものはそうです。密教の曼荼羅の世界はある修練の仕方をすると、その修行の果てにあるイメージが思い浮かんできて、その世界が曼荼羅の世界で、そこで死後の世界を歩いてきて、また帰ってくると、それが密教の修行だということができます。
そして浄土教が出てきて、それは違うのではないか、そういう世界は違うのではないかということで、もう一段日本人の死生観を中世以降に変えたと思います。つまり自分たちの浄土教の考え方はそうではない。修練に修練を積んで、自分の肉体をいじめて、精神もいじめて、断食もやるし、荒行をしたあとにある精神状態になって、あの世の世界を思い浮かべて、そこを自由に出入りすることができるというのが仏教の修行だというのはおかしいと、初めて日本の浄土教の開祖、つまり法然とか親鸞が初めて言い出した。だいたいそういうことは難しくて特別な人にしかできないし、またそんなことにそんなに意味があるとは思えないのだということを言って、浄土はそういうところにはないと言い始めたわけです。
そして浄土教は、浄土を象徴するある言葉を唱えさえすれば浄土は出現するし、そこにいつでも入れるのだという考え方をして、特に親鸞はそうですが、あの世の世界をほとんど信じていなかったと思います。親鸞は二つの言い方をしています。たとえば信者の人たちに向かって手紙を出していますが、その手紙の中ではいずれ浄土でお目にかかりましょうみたいなことを書いたりしていますから、そういう書き方でいわれている浄土は、確かに十万億土とか、そこに霊が集まるところと考えていたことを意味しています。
だけどもう一つ親鸞が本気になって自分の宗教の眼目をいうときには、そういう言い方はしていなくて、非常に厳密な言い方をしている。その厳密な言い方というのは何かというと、浄土を象徴するある言葉を唱えたときに、自分たちはすぐに浄土に行ける、そういう場所を得ることができるのだという言い方をしています。そのすぐに浄土に行けるある場所を占めることができるのだという言い方でいわれているものが、仏教語でいえば正定聚というのですが、そういうものに自分はなれるのだ。そうなったときには自分はいつでも浄土に行けることを意味しているのだという言い方をしています。
そういう言われ方の中では、浄土というのは決してどこかにそういう世界があって、霊魂がそこに集まると考えていないことを意味しています。もっと極端にいうと、親鸞はそういう意味合いでの浄土、つまりどこかにそういう霊魂が集まる世界があるということを本当は信じていなかったと僕は思っています。だからそういうふうに日本の浄土教は仏教の信仰も、また一段変えてしまったといえます。これは人間の死生観を考える場合に、ある意味で非常に画期的なことなので、日本の浄土教、つまり法然、親鸞の浄土教は世界仏教史の中でとても特別な意味を秘めていると考えます。特に死生観についていえば、とても特別な意味を秘めていると考えることができます。
少なくともいま申し上げたようなところが、日本人が大昔、宗教などを持たなかった大昔に持っていた死についての考え方、そして死んだあとに魂がどこに行くのかということについての考え方、それから仏教が入ってきたときにそれがどういうふうに変わったかということ、そして仏教が入ってきたところで、また少しどういうように死についての考え方を変えていったかということについての大ざっぱな見取り図を描いてみると、いま申し上げたようなところに帰着するのだと考えます。
この考え方の延長線に加えることがあるとすれば、主に明治以降になってキリスト教が入ってきて、キリスト教の信仰がまた別に加わったことだと思います。キリスト教の信仰の中にも、宗派はいろいろありますから、一概には何もいえないのですが、それはほとんど無神論に近いところから、日本の固有の宗教と同じように山の向こうに、あるいは洞窟や海のかなたにあの世、あるいは天国があってという考え方から、天国の否定に等しいような、プロテスタント的な宗教もキリスト教の中にはあるわけですが、それは全部さまざまなかたちで、明治以降の日本にキリスト教として入ってきました。
だから明治以降の日本人の死生観について考える場合には、新たにキリスト教的な信仰が人間の死と生をどういうふうに考えたか、死んだあとに天国に行くと考えたか、あるいは天国は本当はないのだと考えているのかということはありますが、そういうことを含めてキリスト教的な要素が入ってきたということが、新たに日本人の死生観に対して加わったと考えることはできると思います。
9 類型自体が危うい時代
さて大ざっぱな見取り図でいえば、ここから現代の日本人はどういう死生観を持っていたかということに入っていかなくてはいけないわけです。ところで現代の日本人はどういう死生観を持っていたかということを考えるうえで、どういうふうに考えていったら一番考えやすいかということは、残念ですがわかっていません。またそういうことを厳密にやられたことがないわけです。ですからむしろそれは皆さんのほうがよく知っているのではないかと思われます。
つまり日常、ご老人、病人、死者というものにある意味ではどうしても付き合わざるをえない皆さんのほうが、本当は日本人がどういうふうに死を考えているか、死のあとにどういう世界があるか、あるいは世界がないかということについてどう考えているかということはよく知っているのではないかと考えますし、皆さんのほうが現代の日本人がどう考えているかということを……
(テープ交換)
……いえることは、そういう大昔からの考え方をとっている日本人はいまでもいますし、またそれを捨ててしまった人もいるわけです。またまだ仏教の信仰があって、本当は自分の気分、実感としてはあまりあの世の世界があるとは信じていないのだけれども、しかしお盆になるとやはり郷里に帰ってこいというから帰っていくと、ちゃんとそこで霊まつりをして迎え火や送り火を焚いて、死者を迎えてまた送り出すという行事があるから、何となくそこに加わっている。そうすると加わっている間だけは何となく祖先の死者と出会ったような感じがしないでもない。しかしまた都会に帰ってきたら、そんな感じは全然ない。だから死後の世界があるなんてちっとも思っていないという方もおられます。
また強固なキリスト教ないし仏教の信仰を持っていて、もちろんあの世、浄土もあるし、天国ももちろんある。死んだら自分は必ずそこに行くし、人々も必ずそこに行っているのだと信じている方もおられます。もちろん唯物論もちゃんと入ってきていますから、死んだら死にきりであるし、焼き場で焼いてしまったらもう煙で元素に帰ってしまう、それだけのことで、死んだあとの世界なんてありはしないと思っている人もいます。
だからそう考えると、現代の日本人の死生観を統一的にこうだと言うことはとてもできない。そうならば具体的に言う以外にない。ところが具体的に、まず手始めに先ほど僕が申しましたように、山だという信仰もあるし、海だという信仰もある。また洞穴だという考え方もある。
そのように類型に分けられればいいのですが、この類型に分ける考え方をすれば、大ざっぱに仏教的な風俗習慣があり、キリスト教的な風俗習慣があり、それから唯物論的な習慣があるという分け方もできるのでしょうけれども、僕が考える現代は、たぶんそのように大ざっぱに分けられて、キリスト教的類型、あるいは仏教的な類型、あるいは全然無神論だという類型、そういう分け方自体もだんだん危なくなってきているのではないかということができます。つまりそういう考え方すらだんだん危なくなってきているような時代、あるいは段階、あるいは社会に入りつつあるのではないかというのが現代の状態だと僕は思っています。
ですから皆さんの段階では、たぶん郷里でお盆だからお正月だから帰ってきなさいといえば、帰っていかれて、そこで迎え火を焚いたり、送り火を焚いたりというお盆の行事があって、お坊さんを呼んでお経を読んでもらうということもありましょうし、またところによっては山の中腹にお参りに行くこともあると思いますが、それらはその人が信じているからそうあるというのではなくて、習慣としてあるということのほうが大きい。だからもう少し時代が進んでいくことを考えると、そういうものすらなくなってしまう。送り火とか迎え火を焚くという行事自体もだんだんなくなっていきつつあるような気がしますし、そういう時代に入っていくような気がします。
それに対しては、二つの考え方があるでしょう。そうなっていくのは、いかにもわびしいことであるから、そういう風俗習慣、信仰は非常に大切に守っていかなければならいあという考え方があると思います。守っていかなければならないという考え方が一方にあるにもかかわらず、しかしそれがまただんだんなくなっていくというのも避けがたい運命だ、避けがたい時代の進展だということもまたできそうに思われます。ですから現代は、それを守っていかなければならないような大事なものとか、捨ててしまうには惜しい、大昔からの習慣にある一種の懐かしさみたいなものでしょうか、親しさみたいなものでしょうか、そして守ろう、守ろうと考えてもなおかつだんだんなくなっていくことは避けられないのではないかと考えたほうがいいのではないかとも思われます。
そうすると日本人の死生観について、いま絶対こうなのだ、こういうふうになっているのだと言うことはなかなかできなくなっているといえるのではないかと思われます。ですから、どうやって日本人の死生観を確かめていったらいいのかといえば、極端にいえば個々の人がどう考えているのかということを、死の場面で、あるいは病気の場面で、あるいは老いの場面と、個々具体的な場面でもって調べていくとか、具体的に当たっていって、その考え方を一つひとつ確かめていかなければいけないみたいなところに入りつつあるのではないかと僕には思われます。
つまりそこまでも徹底してというか、そこまで退いてというか、そのうえで日本人はどういう死についての考え方、どういう生についての考え方をしているか、本当に確かめていくことがとても大切なような気がします。それ以外にやりようがないし、またそれ以外に実りのある方法はとても使えない。それ以前の宗教的な考え方を適用したり、あるいは大昔の日本人の考え方はこうだったからこうなのだと適用しようとすると、全部調子が狂ってしまうというか、あてが外れてしまうというか、狂ってしまうような気がします。
だからそういうことではなくて、一つひとつ、言ってみれば一例、一例に当たって、老いについての考え方、死についての考え方、あるいは死後に世界があるのか、ないのかということについての考え方を具体的に確かめていくというやり方が本当は一番実りのいいやり方であって、またそういう意味で申しますと、皆さんが一番実りの多いことができる場所におられるのだと僕には考えられます。
10 福祉問題ではない老人問題
僕らが唯一いえることは、つまらないことといえばつまらないことですが、たとえば六十歳以上のご老人たちにアンケートを取ったデータがあります。たとえば僕が大切だと思ったのは、年をとってから子どもたちの世話になるつもりか、ならないつもりかというアンケートを取ると、六〇%ぐらいの人は、自分はできるならば子どもたちの世話にならないようにしたいという考え方の人が出てきています。
僕の理解の仕方では、半分以上のご老人たちが年をとっても子どもたちの世話にならないでやっていきたいと思っている、実際できるかどうかは別ですが、そういうご老人が半分以上、六〇%、七〇%となったということは、だいたいご老人たちが死の世界を克服したという言い方はおかしいのですが、死の問題を解決したことを意味していると思っています。
これは実際的にも解決したら、なおよろしいわけです。つまり死に対して、自分が経済的にも精神的にも自分が処理していきます、自分の一番親しい子どもたちにも、本当ならばお世話にならないようにして、自分で自分の死について考えていきます、経済的にも考えていきますし、精神的にも考えていきたいと思いますというご老人が、たとえば五〇%を超したということは、たぶん死の問題が物質的な、生活的なという意味合いで解かれたということを意味し始めたと僕は思います。
老人問題とか死者の問題、あるいはもっと広範囲にいうと身障者という問題になるわけですが、その問題は本当をいえば福祉事業の問題でもなければ、国家の福祉予算の問題でもないし、地方自治体の福祉問題でもなくて、それらは全部過渡的な、その場の間に合わせに過ぎないので、老人問題の本当の解決、身障者の問題の解決、死者、あるいは死の問題の解決は、その人自身の力で、それが全部解決されてしまう基盤がつくられるということが最後の理想の目的なので、そこに至ったならば福祉の問題や行政の問題はもう二の次、三の次に問題になってしまうべき性質のもので、その問題は決して福祉の問題ではない。
11 死の問題を最後まで追いつめつつある現在
生死の問題については、非常にはかないところに突入している、つまり現在、突入しつつあって、わびしくなってしまっているわけです。しかし逆の面からいきますと、だんだんと自分で経済的にも精神的にも死の問題、あるいは老いの問題を解決したいのだ、あるいは子どもの世話にはなりたくないのだというふうに思い始めたご老人が出ていることは、死の問題を日本人がとうとう最後の問題、つまりいまはやりの言葉でいえば究極の問題のところにだんだん持っていっていることを意味していると僕は理解しています。
ご老人たちは意識しているにしろ、無意識にしろ、だんだんと死の問題を最後の問題のところに、つまりそれは自分自身が解決すべき問題であり、自分自身が経済的にもちゃんと解かなければならない。そのうえでなお子どもたち、近親の人たち、周囲の人たち、あるいは国家がやってくれるのならば、それはありがたいからそれに越したことはないけれども、自分はそれに全然頼らないで、自分自身でそれを解きたい、解決したいと思っている。
物質的にも解決したいし、精神的にも解決したいと思っているご老人が現れてきているということは、言ってみれば死の問題を最後の問題のところにご老人たちが意識するにしろ、しないにしろ、追い詰めているというか、最後の問題のところで考えようとしている。そういうところに、やっと日本の社会も到達しつつあるのだということを意味していると僕は思います。
ですから、たとえば大昔から日本人の懐かしい信仰、つまり山に霊が集まる、あるいは海に霊が集まる、あるいは洞窟を通してかなたに人間の霊が集まって、またいつでも帰ってこられるのだということはとても懐かしい信仰でありますし、仏教の信仰も懐かしい信仰ですが、その懐かしい信仰は、たぶん否応なしにだんだんなくなっていくことが、時代の進展、社会の進展としてどうしても避けがたいように僕は思います。
しかしそれで終わりかというと、決してそうではない。統計でみると、昔のご老人たちは年老いて姥捨て山に捨てられるという伝承もあるくらいだし、全部他動的です。年をとると否応なしに子どもの世話になることも非常に他動的というか、自覚的でなくてそうなっていってしまうということがそこの代々のしきたりで、そこで悲劇が起こったりしてきたわけです。
現在のご老人は、自分たちは子どもたちには世話になるまいと思って頑張りたいと思う人たちが出てきたということは、つまり死の問題が最後の問題のところにまでとうとう追い詰めた。日本人が死の問題をちゃんと解決する基盤、筋道を獲得してきたということを意味していると僕は考えます。ですから大昔からある懐かしさ、美しさというものがどんどん衰えていくということは、ある一面ではとても嘆かわしいことでしょうけれども、ある一面からいうと、そうではなくて人間はとても強いものなのだ、自分で自分のことは解けるのだ、あるいはどこまでもやっていけば必ずそれは解けるのだというところにご老人たちがちゃんと入りつつある。
統計によれば、そういう考え方のご老人が増えてきているということを見ると、実際にそれはできるかどうかは具体的な条件によるわけですが、いわば死の問題、死の問題は同時に生の問題ですが、それをとうとう最後のところまで追い詰めてきたなということを意味していると僕は思います。
その面から見たならば、やはり人間というものは、日本人という中に人間は全部含まれるわけですし、またそうでなければいけないわけですけれども、日本人が考えることは人間が考えることなのだというふうになるべきなのでしょうけれども、日本人の死についての考え方、生についての考え方もとうとう来るところまで来つつあるな、つまり最後のところまで追いつけてきたなという感じがする。それはとてもいいことなのではないか。そこのところはある意味で希望なのではないかと僕には思われます。僕はそういう理解の仕方を取ります。
ですから必ずしも懐かしい、古く美しいものが消えていくことは残念ですが、しかし残念だというばかりではなくて、一方ではご老人たちはもっとたくましく、自分の問題は自分の問題であるという考え方の人たちがどんどん増えていくということで、言ってみれば死の問題を最後のところに追い詰めつつあるという兆候も、統計によれば確かに見えるわけで、それは大変いいことなのだ、言い換えれば希望なのだと言うことができると思います。
12 死生観の絶望と希望
この問題はたぶん皆さんが一番近いところで、実際に調査したり、実際にぶつかったりできる立場におられるわけです。その問題を本当によく確かめて、調べる以外に方法はありませんから、いまどのくらいの考え方をどういうふうにしているなということをつかまえることができるようになったらば、どういうふうに考えていったらいいのだろうか、あるいはどういうふうに対応したらいいのだろうか、老人問題に対してはどう対応したらいいのだろうか、死者の問題に対してはどういう対応をしたらいいのかというようなことを、自ずとそこから獲得していくというのが一番いいやり方ではないか。また本当を言えば、それ以外のやり方はないのではないかと僕には思われます。
それ以外のやり方をすると、いま医学関係、精神医学の関係、臨床医学の関係でアメリカやヨーロッパで大きく行われている死者に対する対応の仕方についての書物が、日本でもぼつぼつ出ていますが、それらの書物は、僕の理解の仕方では大なり小なりキリスト教的な、宗教的な救済感がどこかにあるわけです。そのことは日本の問題に置き直してみると、それに該当するのは仏教ですから、仏教的な救済観がどこかにあって、調査とか考え方が打ち出されています。
僕の理解の仕方では、それはキリスト教的な信仰、あるいは仏教的な信仰の厚い人たちに対しては、それは効を奏するというか、有効で、それはいいやり方だ、いいことなのだということがいえるけれども、一般論として現代、あるいはこれからのち、そういう宗教的な信仰が習慣としてもどんどん衰えていき、これからのち、それが有効であるかどうかはすこぶる保ちがたい、保証しがたいことのように思われます。
だからそこではそうではなくて、死はやはり自分の問題であり、自分が解決すべき問題だというところが希望として表れつつあるというところです。信仰のある人には信仰がある人のように、信仰のない人にはない人のように、死の問題、老いの問題を自分が解決してきたし、これからも解決すると考えている人には、その人のように、そういう対応の仕方は個々具体的に、もう少し緻密に、信仰一般のところで解消したり解釈したりするのではなく、もう少し緻密なところで、もう少しこれからあと起こるだろう事態に含められたところで、この問題を具体的に解いていかれることが一番よろしいのではないかと思われますし、僕らもそれ以外の何らの考え方は思い浮かばないわけです。
ただ、僕らの頭の中には、何か大ざっぱに、大昔から日本人の死についての考え方、生についての考え方、現在のそういう考え方の混乱とか行く末とかも含めて、漠然とした見取り図、イメージみたいなものはあるものですから、それをお話しすることはできるのですが、それ以上の、本当に個々具体的に当たっていかなければ救済にも解決にもならない。具体的に個々に当たりながら、非常に緻密な対応の仕方を考え出していき、日本人の伝統にも、それから現代の繊細さにも、現代の高度に発達した社会にも相適合するという考え方とかやり方をつくり出していく以外に、僕には本当の意味の救済とか解決はないのではないかと思われます。だから現代の日本人の死生観は、大変混乱していますし、絶望的なところと希望が持てるところと両方がないまぜになってあるのだと僕自身は考えています。
僕がお話しできそうなところはこういうところに尽きるのですが、僕は自分なりにそういうことについてこれからも考えたり、何か表明したりしてみたいと思いますが、そんなことよりも皆さんのほうがきっとそれにふさわしい場所におられるわけですから、本当に個々具体的に、緻密にその問題を調べていかれたり、当たっていかれたり、あるいは経験していかれたりして、そこから出てくるものは、とても貴重なものになっていくのではないかと僕は考えます。お粗末でしたが、一応ここで終わらせていただきます。(拍手)
13 司会
14 質疑応答1
(質問者)
信じているものがあるか、あるとすればどういうものを信じているか。
(吉本さん)
後のほうからお答えしますと、ぼくは宗教を信じていないですから、ただ、家の宗教というのは僕のところは浄土真宗という親鸞系統の家の宗教です。ぼくが死んだら、べつに僕は、注文はないですけど、浄土真宗の坊さんが来てやるんじゃないでしょうか。ぼくはそれを否定しません。つまり、そういう人はいますけど、おれは宗教なんかないし、お葬式なんか嫌だから、そういうのはしないでくれという人はいますけど。ぼくはそういうのは全然ないわけです。
あとで、家の宗教がそうだったからそういうふうにするというのはそれでいいわけで、全然ぼく自身は信じていないけど、宗教として信じてませんけど、習慣としては信じているといいますか、しきたりとしての宗教というのはおかしいのですけど、救済としての宗教じゃなくて、しきたりとしての宗教というのはわりあい信じておりますから、信じているというのはおかしいですけど、それを否定しませんから、考え方として否定しませんから、そういう意味合いでは僕はきっと僕の葬式はそうなんじゃないかなというふうな予想することはできますけど、僕自身は宗教を信じているわけではありません。そういう意味合いでは死んだ後に天国があるとも思っていませんし、浄土があるとも思っていないわけです。
僕自身が死についてどういうふうに考えているかというのを申し上げますと、それはいまお話しましたけども、ある意味で延長になるわけですけど。ぼくは50%以上のご老人たちが自分のことは自分でやっていくし、自分でぜんぶ処理していきたいとか、物質的にも精神的にも自分でやっていきたいというふうに考えたときに、死の問題というのは解かれたことを意味するんじゃないかということを申し上げましたけど、ぼくもご老人一般として言えば、そういうふうな心構えをできるかどうかは別なんですけど、できるならば、そうしたいというふうに考えていますから、ご老人一般としては僕はそういう考え方と同じなわけです。
ところで、いくらかものを書いたにせよ、人前で表現してきたりした者としての何かをちょっとだけ付け加えいたしますと、それだけが究極的な解決ではないんじゃないかという考え方が僕の中にはあります。それは、死について、こういうことが獲得したいわけです。それはなにかといいますと、死っていうものが何であるかということは別なんですけど、とにかく死というものがあって、死というものが向こう側、つまり、未来であると考えるか、あるいは、上のほうにあると考えるか、そういう時間とか、空間とかいう意味合いで比喩をしてしまうと言いようがないのですけど。ただ、上のほうにあると考えようと、未来にあると考えようと、どちらでもいいわけなんですけど、ぼくにとってはいいわけなんですけど、死というものから逆に現在の自分を照らし出す視線といいましょうか、それを経なければ得ることができなかったら…(テープ切れ)、過去の経験の蓄積によって決定されるわけです。
つまり、今日、誰かと会って、おれはこう言おうというふうにおもう思い方とか、あいつとあったらこう喧嘩をしてやろうと思っている思い方というのはどこから出てくるかというと、その人の過去に蓄積した人間関係と様々な蓄積した体験の結果として自分の考え方というのはあるわけなので、それでもってこれから誰かと会った時に喧嘩してやろうというふうに思ったりする考え方がでてくるわけです。
そうすると、人間の考え方はいつでも過去から出てくるわけです。あるいは、過去の経験から出てくるわけです。それから、人間の社会のあり方というのも過去の歴史からでてきているわけです。誰も未来の経験から現在を照らし出して自分の行為を、行動の仕方とか考え方を決定するという考え方を誰もしたことはないわけです。
ところで、ぼくの考え方では未来を経験することはできませんけど、ただ、経験の蓄積はあるわけです。それは、ただひとつあるわけです。それは、死というやつです。これは、多くの人間の死というのはぜんぶ蓄積されていますから、それはある意味で経験といえるわけで、この経験は目に見えない経験ですし、誰も手でつかむことのできない経験のように見えますけど、これをよくよくつかむことができて、この経験から逆に現在というのを照らし出したら、じぶんの行動の仕方といいますか、行為の仕方とか、態度に対する対し方とか、あるいは、社会に対する考え方とか、人間に対する考え方というのは違ってくるに違いないというか、違う要素が出てくるに違いないというふうに僕は思っているわけなんです。
ですから、逆に死のほうから、死がなにか実体のあるものだとは思いませんけど、死のほうから逆にいまの自分のあれを照らし出して、それで自分の行為を決定するくらい照らし出すことができたら、それでもってたぶん死の問題は、ぼくにとっては解決されるに違いないというふうに、僕自身は思っているわけです。
なぜならば、人間というのはそれを考えない限りは、人間は過去からしか現在を考えることができない。あるいは、過去からしか自分の行動を、行為を決めることはできないので、過去の体験とか経験の蓄積とか、過去の人の判断とか、それによって自分の現在の行い方を決めているわけですけど。そうじゃなくて、未来かなにかわかりませんけど、とにかく死というもののほうから照らし出してみたら、こういうふうに見えるはずだとか、見えるぜ、だから、これはこの場合こうすべきだとか、こういうふうに考えるべきだとか、こうすべきだとかというような、そういうことが決められるということがあると僕自身は思っているわけです。
それが僕にとっての死の問題ですし、死をどういうふうに考えるかという問題でもありますし、それをどうやって自分の現在の生き方のなにか参考にできるかという問題でもあるというふうに、僕自身はそう考えているから、それは必ずしも信仰じゃないのですけど、死の問題というのは自分なりの解き方で解いてみたい。少なくとも、逆方向から現在の自分を照らし出す経験といいましょうか、それが得られるそういう視線というのが、自分でどこかでつかまえてやりたいというような、そういう考え方を僕自身はとっているわけです。
それが僕の死についての考え方なので、これは必ずしも宗教ではないのですけど、宗教ではないのにもかかわらず、死の問題というのは重要だというふうに僕自身は考えている最後の理由はそういうところに帰するような気がいたします。それが僕の現在の考え方です。
15 司会
テキスト化協力:ぱんつさま(チャプター14)