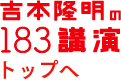続・日本人の死生観
1 死に至る5つの段階――E.K.ロス『死ぬ瞬間』
……さればといって、与太話もできないし、一番やりにくい員数のような気がするのですが、コバヤシさんがおっしゃったとおり、日本人の死生観、死と生についての考え方とういことでお話ししたのですが、その続編みたいなところから入っていってみます。
夕べも一杯飲みながらそんな話が出たのですが、人間の死は、一般に人間は必ず死ぬものであるという言い方と、それから私は必ず死ぬという言い方とは、同じように見えて違う。一般的に人間は死ぬものだということは、何となく大ざっぱな言い方ではいえそうに思えるけれども、私が死ぬということは、私にはよくわからないはずだという話になってきたわけです。
そこの問題をもう少し厳密に追い詰めた仕事、調査がいくつか翻訳されて出ています。その中で初めでもあるし、おもしろいというか、一番興味深いのは、ロスという精神医学者の『死ぬ瞬間』という書物です。それは何がおもしろく興味深いかというと、人間は死ぬものだという、その死ぬ瞬間をもう少し緻密に追っていくと、まずだれでもたどる経路があるということをそこで結論づけています。
その経路とは何かというと、重病で、もう回復不能だという宣告を受けた場合に、病者はどういう反応をするかというと、その第一段階では、まず否認という言い方をしています。つまりそんなはずはないと認めないという反応が起こるといっています。それはほとんど例外なしにそうだ。そしてその次には、なぜ俺だけがこういう病気で、こういう目に遭わなければならないのだという憤りが現れてくるのが第二段階です。
では第三段階ではどういう表れ方をするかというと、延命とか取引という言葉を使っています。それは神様や目に見えないものとの取引で、自分にはまだし残したことがたくさんあるし、家族のことも不安だから自分にもう少し命を授けてくれれば、その代わりに何でもいたしますというかたちで延命ということがだいたい起こってくる。
第四段階では、それが過ぎてしまって、一種の憂鬱状態、鬱状態みたいなものが起こってくる。その鬱状態が過ぎてしまって最後の段階では、受け入れというのでしょうか、諦めというのでしょうか、そういうことが起こってくる。その最後の諦めの段階が起こってきたときには、患者さんはたいてい二十四時間以内ぐらいに亡くなるという結論を出しています。
それは一見するととても残酷な調査で、残酷な結果を出しているわけですが、しかし別の面からいうと、ただ人間は必ず死ぬものだという言い方とか、私は私の死を確認できないという言い方でいわれるあいまいさを、もう少し厳密に追い詰めて考えて、真正面からぶち当たっていったという意味では、初めてのものだと僕には思えました。だからその本を読んだときは、とても感銘を受けたし、ショックを受けました。
僕は、そういうことに関連して、文学の話をしたことがあります。それは大ざっぱにいいますと、文学作品の中に展開される物語は、ロス女史が言っている五つの段階と同じような段階をだいたい踏むものである。つまり物語の構造は、死ぬ瞬間の構造と同じようなものなのだということを、僕は以前に話したり書いたりしたことがあります。
2 死に瀕したときからはじまる文学
ところで、今日は僕が文学のことについて何をしているのだということでお話ししてみたいと思います。第五段階、最後の受け入れの段階で、死に瀕したときから始まる文学を僕はいまやっておりますので、それを非常に大ざっぱなところで、こういうことを自分はしていますという意味合いでお話ししてみたいと思います。
それには僕が根拠としたことが二つあります。第五段階で死に瀕した人が、そのまま亡くなってしまえばそれがわからないわけですが、病気ということではなくて、たとえば交通事故みたいな場合に、死に瀕した人が快復して治ったという人の体験を集めたいくつかのデータがあります。日本の人のデータについては、『潮』という雑誌がありますが、そこの編集者と協力して、例を割合たくさん集めたことがあるのです。
死に瀕して、そのまま亡くなったというのではなくて、そのままうまく治って生き返った人の体験ですが、まず第一段階として、自分が死に瀕していて、お医者さんが人工呼吸をしてみたり、看護婦さんが慌しくそこを出入りしたり、近親の人が驚いて、悲しそうに叫んでいるとか、自分が寝ているベッドの周辺でそういう動きをしているのが、何か部屋の二メートルぐらいの高さのところから自分で見えた。それが第一段階です。
そのあとの体験は人によってさまざま違いますが、一様にいえることは、そのうちに何か自分が暗闇のようなところをスーッと通っていくような気がして、そこを通り過ぎたら、今度は明るい風景が開けてきた。その風景は、橋があって、そこへ行くと、たとえば死んだ親が、お前はここに来るな、帰れと言われたから帰ってきたら、生き返った。さまざまですが、まず空中に浮き上がったところから、自分のベッドの周辺をいろいろな人が慌しくしているという風景を自分で見たという体験が、まず第一段階に必ずあるわけです。そのように言っていない場合にも、そういう段階を経て、自分はどこかへ飛んで行ったという体験がほとんど例外なしにあるわけです。
その体験を記述した人の非常に多くが、たとえば十人のうち七人とか八人は、だからやっぱり死んだ、死んだというけれど、死んだあとの世界はあると思うと言っています。あと三人ぐらいはそういうことを言っていないわけですが、だいたいその種のことは宗教や宗教観と結びついて体験が語られていることが多いのですが、それはいったい何なのだろうかということが一つあるわけです。
3 つくば万博・富士通館の高次映像
もう一つ、今度は宗教に近くなくて、まったく科学技術的なことですが、僕はつくばの科学万博へ二回かそこら見に行ったのですが、富士通というハイテクの会社の富士通館というのがあって、非常にびっくりするような高次の映像をそこで見せてくれました。その高次の映像とはどういう映像かというと、まずコンピューターグラフィックスの映像のように時々刻々移り変わってくる映像を、ドーム型の天井から周辺全部、部屋中がスクリーンになっていて、見る席がずっと上のほうに上がっているわけです。
そのスクリーンにコンピューターグラフィックスの映像が映し出されるわけですが、それを立体視の偏光めがねではないのですが、色差式の、こっちに赤い色、こっちにブルーの色のめがねをかけて見ると、ドーム型の部屋のスクリーンから映し出されている映像が立体的に浮かび上がってくる。それは浮かび上がってくるだけではなくて、衝突しそうになったり、自分の周りを飛び交ってくるわけです。
もしこちらがスクリーンの外を見たら、普通の空間だとたちまちのうちにその裂け目のところでばれてしまうわけですが、座席が割に上のほうにあって、前後左右、天井も全部がスクリーンになっているのでどこを見ても、一応意識的に見ない限りは立体的な映像が飛んでくるわけです。ですから自分がその中にいながら、そういう立体像がぶち当たるように飛び交ってくるのを見ているという映像になるわけです。その映像はまずかつて見たことのない高次の映像であって、びっくりしたわけです。
その手の試みはつくばの万博では、ほかの二、三のところでもやっているのですが、たいていは向こうにスクリーンがあって、赤とブルーのめがねをかけてそのスクリーンだけを見ている限りは映像が飛び出してくるのですが、いったんスクリーンの外に目をやったら、たちまち現実の空間になってしまうので、ああ、何だ、これはうそかと思えてしまう。ところが富士通館だけはそれを完璧なかたちで、どこを見てもこれがただの映像かとは思わせないように、全部が映像空間の中に自分も入っていて、それを見る。そして立体像が飛び交ってくる。この体験はかつて見たことがない高次な映像の体験でした。
4 上からの視線と平行の視線
僕はそれもとても衝撃を受けたわけですが、自分の中にそういうものもあったわけですが、何とかしてこの高次の映像はいったい何なのか、自分で理屈づけてみたいという考え方を持ちました。その考え方が前に申しました死に瀕した人が帰ってきたときの体験の中に必ずある、自分がまず初めて意識を失ってしまったら、自分が空中に浮き上がって、死に瀕して横たわっている自分が見えて、なおかつ周りでお医者さんたちがうろうろしていたり、あわてたりしているのが見えたという、その体験が、僕の中では見えた体験としては同じものだという考え方があります。これも併せて一つ自分なりに理屈づけてみようと思いました。
これは言ってみれば、この高次の映像と、死に瀕したときに必ず現れるとされている映像、つまり死に瀕している自分が見えたという映像とを同じように理屈づけてみると、僕の理解の仕方では、それは二つに分解したらいいのではないかと思えたわけです。その二つとは何かというと、一つは自分の目の高さで地面と平行に見える立体像、つまり普通僕たちが他人や周囲の風景を見ているときに見える立体映像と、もう一つ、真上から下を見ているときの映像が、その二つの映像をもし同時に見ているという体験がもし可能だとしたら、それは僕がつくばの万博で見た高次映像と同じものが見られることを意味するはずだと僕は考えました。
それから死に瀕した人が、空中から自分が死に瀕して横たわっているのと、周囲をお医者さんや看護婦さんが駆け回っている映像が見えたというその体験も、やはり死に瀕している自分の姿を自分が見ているという体験ですから、これも一種の高次映像です。これもまた分解すれば、やはり上のほうから見ている視線と、立体的に自分が目の高さで平行に見ている立体像と、その二つを同時に見ることができた。つまり同時に合わせて見るときにできる映像を考えれば、いま言いました死に瀕したときの体験とつくば万博のような科学技術的につくられた高次映像、その二つはつくれることになると僕には思われました。だからその二つに分解すればいいのだと僕自身は考えました。
5 宗教体験と高次映像
もう一つの体験は、昔からいわれていますが、宗教体験です。たとえば密教の修行者がその修練によって曼荼羅の世界に入っていくという場合に、まず最初に自分が空中に浮き上がるという体験を経て、そのあとで曼荼羅の世界を歩く。その世界の体験が豊富であればあるほど、宗教家として修練を積んだ人だとなるわけです。昔から東洋の宗教がいっている宗教体験ですが、その体験もやはり同じで、修練によってそういう体験を自分でつくれるように修行していくということになるわけです。
宗教を侮ってはいけないのですが、たとえば密教のそういう体験も、死に瀕した人のそういう映像体験も、言ってみればどういうときにできるかと、僕は例を集めて分析して、一生懸命考えました。結局、僕が得た結論ははなはだ貧弱な結論で、それは要するに死に瀕して意識が減衰状態になったときに、たぶんその映像が出現するということです。つまりロスがいう第五段階の最後の瞬間の直前のところに意識状態がなったときに、たぶんその映像体験が出現するというのが、僕の非常に貧弱な結論でした。
だからそういう見方をしてしまえば、密教の体験もはなはだ貧弱な体験になってしまうので、それは意識の幻睡状態、つまりニア・デス、死に近い意識状態を修行によって人工的につくっていくことができれば、それが密教の体験に該当するというのが僕の結論でした。それははなはだ貧弱な結論で、宗教のほうからいえば大目玉で怒られてしまうと思います。
僕自身もそういうふうに思えるところがあって、というのは僕は神秘的ではないのですが、宗教の意味は、それは科学的に解釈すると大したことはないのだというところにはないので、科学的に大したことがあろうがなかろうが、その宗教体験自体がその人の精神状態を救済するかどうか、それが豊富な体験であるか貧弱な体験であるかは別問題であると思います。
たとえば交通事故を起こして死に瀕した人の体験は、言ってみればピンからキリまである。貧弱な体験というのは、ただ自分が死に瀕したら、部屋に飛び上がったところで死に瀕している自分の姿が自分で見えた。それから暗いところをスーッと走っていくように見えて、それからその向こうに明るい先が見えた。明るい先の向こうには知っている人がいて、お前はこっちに来ないで帰れ、帰れと言われたから帰ってきた。そうしたら自分は生き返った。言ってみればそういう体験です。
曼荼羅の世界みたいに、修行をした人の高位高僧の仏教の体験は、大変華やかな体験です。浄土の華やかな楽土のイメージが自在にちゃんと体験できたり、また地獄で人が苦しんでいるのがまざまざと見えたという体験とか、その体験自体のイメージが豊富であればあるほど、たぶんそれは宗教としても豊富であるし、またそういう豊富なイメージの体験をしたことが、人間の心を非常に豊かにするもとになりますから、その宗教の意味は、別のところにあってそれを科学的に解釈すると他愛ないことであるかどうかは、また別問題のように思います。
少なくとも僕はどんなふうに神秘的に解釈しようとしても、僕自身がはなはだ貧弱な合理主義者のところがありますから、僕にはそう思われました。つまり密教の宗教家みたいな人は人工的な修練によって、ものすごく自分を無生物に近い状態、死に瀕したところに近い意識状態に自分を持っていけるということが修行の眼目であって、それができたらばたぶん豊富なイメージ、まず自分の体が空中に浮かんだような気がして、それからあとずっと華やかな曼荼羅の世界を巡ることができるようになるのだと思います。
死に瀕した体験の中に現れる映像は、それよりも貧弱ですが、しかし同じようにたぶん、死に瀕する直前の意識状態、意識が崩壊直前になったところで出てくるイメージが、そのイメージではないかと僕には思われました。だから実際にそういうふうに意味づけるとどうということはないのですが、ただ、自分が横たわっている姿が自分で見えたという体験は、映像体験としていえば非常に高次な体験であって、たとえばつくば万博の富士通館が科学技術的に初めて実現した映像は、それは大げさな言葉遣いをすると人類が初めてつくりだした映像体験だと僕には思えます。
現在までのところ、これ以上高次な映像は考える必要がないのであって、また実現することはまずできないので、これが一番高次な映像だと考えます。たぶん僕の理解の仕方では、ごく普通の立体的に見える目の高さでもって見える映像、立体像に対して、同時に真上から見た映像を組み合わせることができたらば、そういう映像状態をもし自分がつくれたならば、それはたぶん同じ体験がつくれたことを意味するのではないか。だから分解するとすれば、そういうふうになるのではないかというのが僕の原則的な理解の仕方でした。
6 言葉の概念とイメージ
それで今度は文学作品についても考えてみたわけですが、どんな文学作品でも要素的に分解してしまうと、まず考えられる限り三つの要素的な流れがあるように思われます。一つは、言葉の概念が持っている意味、それが物語を次々に展開させていく、運んでいく、進行させていくということが、どんな文学作品の中にもある大きな流れだと思います。それは概念の意味が物語を展開させていく。言葉の意味の流れに従って、物語の流れが展開されていくというのが、大きな文学作品の根本になっている一つの要素的な流れだと思われます。
もう一つ考えられるのは、言葉の概念が意味ではなくてイメージをつくりあげる、そういうものが文学作品の中には必ずあるといえると思います。ある文学作品を見ると、クライマックスに近いようなところでは、たとえば彼はこのとき何々と語ったというような言葉の意味だけではなくて、その描写自体がイメージをつくりあげている箇所が必ずあります。
それは一般に僕らがある文学作品、あるいは小説を読んだときに、この小説はどうだったといわれて、ああ、この小説はおもしろかったよ、あるいはよかったよと言う場合に、そのよかったと言っている人がどういうふうに思いながら言っているかというと、たいてい一番鮮やかであった箇所、あるいは鮮やかであったいくつかの箇所をつなぎ合わせて、そしてあの作品はよかったよと言っているのだと思います。そのときに鮮やかなイメージをつくりあげるいくつかの箇所があって、そのときには言葉は意味でもって流れている……
【テープ反転】
……というような箇所を必ず作家はつくりあげています。それは一つの場合もありますし、たくさんの場合もあります。それから非常に少ない場合もあります。それは言葉の意味と、言葉がつくりあげるイメージと、その二つがあいまって、文学作品の流れをつくりあげているということがわかります。
もう一つ考えられるような気がします。そのもう一つとは何かというと、言葉、イメージには違いないのですが、言葉の概念全部がイメージ、あるいは映像に転化してしまっている。本来ならば言葉の機能ではないはずのものを言葉がつくりあげてしまっているという箇所がある場合があります。その箇所というのは、言葉の概念が何を描写しているかという意味を全部消してしまって、全部がイメージになってしまっている。そういう箇所を作品が持っている場合があります。
つまり言葉の概念が全部イメージ、あるいは映像に変わってしまったという文学作品の箇所を考えてみると、僕の理解の仕方では、先ほどから言っている高次の映像、あるいは死に瀕した人たちの体験する映像と同じように、普通の立体的な目の高さで地面に平行に見える立体像のイメージと、もう一つ上のほうから見ている映像とが組み合わさった映像が、そこで実現しているという箇所が、ちょうど文学作品の中で言葉の概念が全部イメージに転化してしまった場所に該当すると考えられます。そこでは言葉で描写してあるにもかかわらず、読む人は全部イメージとして感じているという箇所がよくよく注意すると必ずあるといえそうな気がします。
7 宮沢賢治『銀河鉄道の夜』のイメージ
これは例を挙げないと何となく口だけみたいなことになってしまいますが、例はたぶんいくつも挙げることができると思います。僕が好きな人の好きな作品で例を挙げると、宮沢賢治の『銀河鉄道の夜』という代表的な童話作品があります。
主人公のジョバンニという少年は夢の中で銀河鉄道に乗っている。友だちのカンパネルラは、溺れそうになった友だちを助けようとして飛び込んで、友達は助かったけれど自分は溺れて死んでしまって、いわば死後の世界を歩いているという意味合いで銀河鉄道に乗り合わせている。
主人公は夢の中で、カンパネルラと一緒に銀河鉄道に乗って、どんどん進行していくわけですが、二人を乗せた銀河鉄道は白鳥の停車場で停まります。向こうに銀河が煙るように流れているのが見えていて、あそこの河原まで行ってみようと、二人が列車を降りて河原に下りていくところがあります。そこには河の流れといっても水なんかは流れていないから何も目に見えないのですが、しかし何かが流れていると感じられる。その流れのところでジョバンニとカンパネルラが手を浸してみようとするところがあります。
そうすると水も何も流れていないのに、流れの表面のところにだけキラキラと光が輝くという描写があります。やっぱり銀河は流れているのだとジョバンニとカンパネルラが考えるところがあります。そこの描写を見ると、たとえばジョバンニが銀河の水のところに手を浸したと描写されていて、浸すと流れの表面のところにキラキラと輝く渦みたいなものがあって、やはり流れているのがわかったと描写されています。
それはつまりジョバンニが銀河の流れに手を浸してみたら、手の周りを光が渦巻いた。だから水が流れているのだとジョバンニは思うのだと描写されていると同時に、ちょうど銀河鉄道の列車の向こうのほうからそういうふうに流れに手を浸して、光の渦が手の周りを取り巻いて、ああ、水が流れているのだなとジョバンニが思っている。つまりジョバンニから見られた手の周りの光の渦のイメージと一緒に、そういうふうにして手を浸しているジョバンニとカンパネルラの二人の姿を、もう一つ違うところから見ている視線、そういうイメージが同時に浮かび上がってくるといえます。
それはとても珍しいイメージですが、本来的にいえばジョバンニは銀河のほとりまでやってきて、流れに手を浸してみた。そうしたらそこで手首のところに光の渦が取り巻いているのが見えて、ああ、やっぱり銀河というのは流れているんだなと考えたといえば、ジョバンニが自分の手首のところの光を見ているというイメージだけが出てくるはずですが、そうではなくてその全体、つまりそれに手を浸しているジョバンニの姿とカンパネルラの姿を別のところから見ているもう一つのイメージが、そこに同時に重なっているということがいえそうに思えます。
だからそういう箇所は珍しいのですが、そのときに実現されているのは、そのように描写されているのですが、言葉の意味はどうでもよくなってしまって、概念の意味が全部イメージに転化されてしまったときには、単に描写だけではなくて、その描写自体をもう一つ違うところから見ているイメージが同時に喚起される。このイメージはとても高次なイメージであるといえそうに思えます。
8 高次なイメージから文学を読む
この種のイメージが喚起される文学作品は、まれではありますが、たまにはあります。
僕は一番典型的に『銀河鉄道の夜』という作品の中で茫漠として銀河を旅しているイメージがあるわけですが、茫漠として旅をしている二人のイメージと同時に、二人が何かをしているのをどこかでもう一つ見ている視線のイメージがある。不思議なイメージを喚起する作品で、この作品の由来がどこにあるのか、よくよく分析してみると、僕はいま申し上げた高次映像と同じように、一般的に言葉が喚起してくるイメージを、またもう一つイメージとして見ている視線がそこに加わっているときに、言葉の意味よりも言葉全部がイメージに転化されてしまっている。そういう高次なイメージを実現しているように僕には思われます。
だからそういう箇所がある文学作品、そういうものを喚起する描写の場所を持っている作品は、必ずいい作品だといえそうに思いますが、それではすべてのいい作品は必ずそういう描写を持っているかというと、一概にはそうとはいえないと思います。そういう箇所を持っている作品はいい作品だといえそうだけれど、いい作品がすべてそういう箇所を持っているかというと、僕はそうとは思えない。
なぜかというと、文学作品というのは、言葉でつくられていますし、言葉の本来的な機能は意味ですから、意味によって物語をつくりあげることが、少なくとも第一の機能です。イメージをつくるのならば、それこそフィルムでつくったり、絵画でつくったりしたほうがつくりやすいので、文学作品は必ずしもイメージをつくるためにはいいつくり方ではない。文学作品は言葉の意味で物語を進行させることが第一義で、そういう高次なイメージを喚起する作品だけがいい文学作品だとはいえないと思います。しかしそういう場所を持っている作品がいい作品だといえると思います。だからそういう箇所があって、それが文学作品のもう一つの要素をつくっているように僕は思います。だからこういう箇所をもしある一つの文学作品が持っているとすれば、その文学作品はとてもいい作品ではないかと僕には思います。
そうすると文学作品はいま申し上げた意味の流れによって物語を進行させるという要素と、それから意味の流れを保ちながら、同時にイメージをつくりあげている箇所を必ず持っている、そういう流れを必ず持っている。それからもう一つ、高次な映像で、意味の流れは全部イメージに変えられてしまっているような箇所を持っている。その三つの要素をもし文学作品の中からより分けることができれば、たぶんある文学作品をとても高次なイメージの箇所から読んだことを意味するように僕には思われます。
9 島尾敏雄『夢屑』における高次映像
こういう作品は、探せばいくつもあると思うのですが、僕はたまたま自分の知り合いの作家で、こちらに来る直前に亡くなった島尾敏雄という作家がいます。島尾さんの作品の中でときどきそういうイメージを喚起するところがあって、例を挙げてみると、『夢屑』、夢の断片という意味ですが、そういう作品があります。それは、短い断片ですが、とてもおもしろいというか、見事なイメージを喚起する作品です。
一例を挙げてみると、作品の中で私ですが、自分と細君と子ども二人と四人が即身仏をつくる、つまり即身仏になる儀式に参加することになったというところから夢が始まるわけです。そしてそういうのが何だかおっかないような、不安なような気がしたのだけれど、即身仏になる坊さんが一人、一緒に先導者を務めてくれるというので、何となく信頼できるような気がして、親子、夫婦四人が並んだ。自分が初めに並んで、その右側に奥さんが並んで、子どもが二人並んで、最後にお坊さんが並んで座った。
いよいよこれから即身仏になる儀式が始まる。そうするとなぜだか知らないけれど、お坊さんがやってきた。それがものすごく巧まざるユーモラスでもあるわけですが、お坊さんが自分のところにやってきて、これから入定の儀式があるのだけれど、費用はいくらかかるから承知してくれと耳打ちした。だけど何でこれから入定をするのに、なぜかかった費用のことまで考えなくてはならないのかわからないとか、お坊さんも変なことを言うものだという気がしたのだけれども、それも一つだと思って納得した。
どこからどう始まるのかと思っていたら、儀式をするお坊さんは、自分の後ろのほうにいた。後ろに回って自分の肩と首を押さえた。納得はしていたのだけれど、少しいやになってきたというか、命が少し惜しくなってきた。だけど儀式は始まってしまっていて、儀式をやるお坊さんが後ろから自分の首を押さえつけて前のほうに折り曲げていた。もうこれはやるよりしょうがないと思ったけれど、押さえつけられて土のところに自分の額がついてしまった。下へぎゅうぎゅう押しつけられて、これから首を切られてものすごく痛い瞬間がやってくるに違いない、でも一瞬だから我慢しようと思っていると、ぎゅうぎゅう押さえつけられているうちに、額が土の中にどんどんめり込んでいった。
そうしたら首がどんどん向こうへ行ってしまって、ちっとも痛いという瞬間がなかったけれど、それは自分だけがそのときにもう向こうの世界に行っていた。だけどこちらの人から見ると、どうも自分は死んだということになっているらしい。自分は痛くも何ともなくて、ただ土の中にめり込んで、向こうに顔が突き抜けたと思ったらば、自分は向こうの世界にいた。それはこちらの世界の人からいうと死んだということになるらしいというのが、その作品です。
僕の描写はまずいですが、土に額が押しつけられて、きっと首切り役人みたいなもののイメージからその夢を見たわけでしょうけれど、その次にはその首切り役人が自分の首をぶった切るという瞬間が必ず来るだろう、いまにも痛いのが来るだろうと思っているうちに、ずるずると土の中に首がめり込んでいって、向こうに行ったら、それはどうも向こうの世界にちゃんと出ていた。それはこちらの人からすれば死んだとなっているらしい。そこのところで一種の高次の映像のイメージが喚起されて、そういうふうに私の体験を描写している。
私の首はどんどんめり込んでいって、向こうに行ってしまったと私の体験としてそれが描写されているにもかかわらず、首が押しつけられて向こうに行ってしまっているとか、その後ろにいるお坊さんとか、全部そういうイメージがその瞬間に浮かぶようにその作品はできていると思いました。
つまりこの作品は非常に高次な映像をつくりあげたところが、たぶんこの作品のクライマックスであって、同時にそれが高次な映像を実現している箇所だと思われました。そのほかのところでは、少なくとも意味でもって物語や話が進んでいますし、それから入定の儀式で自分が一番左に並んでとか、その並んでいるところのイメージはとても喚起されるわけですが、その高次なイメージは、そこの箇所だけがどうも喚起するように思います。そしてこの作品の場合には、高次な映像を喚起したときがその作品のクライマックスだとなっているように思います。
ある文学作品は、入口があって、それからロスが言った五段階に該当するような物語の段階があって、その段階がどこかでクライマックスを迎えて、そのあとに受容、受け入れというのがある。そしてある作品の場合には、受け入れの段階で非常に高次な映像を喚起して、それでその作品が出口にやってきて、一つの文学作品は終わる。そう考えると、どんな文学作品でも一般的に持っている作品の流れ、要素の流れは、だいたい理解できるのではないかと僕は考えます。
その問題を文学作品についてだけではなくて、そのほかの問題、言ってみれば言葉の表現だけではなくて、手の表現、映像の表現、その他すべての表現は、そういう高次映像を要素的に分解して考えることによって、全部理解していくことができるのではないかと僕自身は考えます。そういうことをいまずっとやってきていますが、まだ全部終わったわけではありませんが、そういうことを通じて文学作品についての分析や、普通の都市なんかが持っている映像についても、そのほかの映画などについても、そういう場所から統一的に扱えるのではないかということで、僕自身は現在やりつつあるわけです。
ちょうどこちらに来るについて与えられたテーマが、「日本人の死生観」と、死と生についての考え方という課題であったので、それに関連して僕自身が現在やっている仕事の問題のもとになる大ざっぱな考え方みたいなものを申し上げました。死とか病気とか瀕死とかということについて僕は専門家ではないので、お聞き苦しい点もあったかと存じますけれども、僕自身はそういうところから僕なりのヒントを得て、それをすべての表現について理解していけないかということをやろうとして、いまは途中ですがやりつつある。そういうことをお話しさせていただきました。これで一応終わらせていただきます。(拍手)