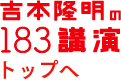言葉以前のこと
――内的コミュニケーション
1 母親と胎児の内的コミュニケーション
まず、いっとうはじめに第一章といたしまして、言葉、あるいは言語でもいいんですが、言葉以前のこと、内的コミュニケーション、つまり言葉を発しないでもって相手にわかる、そのわかり方の言葉っていうのはどういうふうにしてできるか、あるいはどこでそういうことができるようになるか、ということをはじめに申し上げてみたいと思います。
これは、みなさんもよく体験しているはずで、顔の表情をよんだら言っていることや考えていることがわかった、といった「わかりかた」があるわけです。超能力の人ですと、もっと、要するに、この人は今日どういうことがあったとか、どういう精神状態だとか、何がくっついているとか……テレビで宜保さんという人をみていると「あなたの家の玄関から入って右側に何があるでしょう」というと、嘘でないとすればそれは当たるわけですよ。つまり、イメージが見えるというわかりかたもある。イメージで見えることもありますし、言葉といいますか、何を意味しているのかがわかっちゃうということが、誰にでも大なり小なりあるわけです。まずは、どこでそういう能力が生まれるのかということを、順序を追ってお話してみたいと思います。
だいたい、この人間が……どこでかと一口にいってしまえば、おふくろさんのお腹にいるときに、その能力を獲得するわけです。どういうふうに、いつごろ獲得するのか、つまり人間が母親のお腹の中で、どういう成長の仕方、どういう感覚の発達の仕方をするかということを申し上げてみますと、現在までわかっているところでいえば、母親が受胎して、受胎してということは妊娠してということと少しだけ違いますけど、受胎してだいたい36日目前後に、お腹の子どもは人間である限り「上陸」する、つまり、魚類みたいな水生動物の段階から両生類の段階へ進むというようにされています。これを確定したのは、日本の解剖学者で、もう2~3年前に亡くなりましたけど、三木さんという人です。36日目くらいに、人間の胎児が上陸した時に、母親は悪阻になったり、ちょっとおかしくなったり、つまり大変な激動を体験するわけですけど、三木さんのいっているところによれば、人間が、というか動物が、水生動物から陸へ上がるとき、つまりエラ呼吸から肺呼吸になるわけなんですが、それがいかに困難な段階であったかが、母親の激動を考えてもよくわかるというふうに書いています。
そしてだいたい受胎して3ヶ月くらいたってから、胎児は夢を見ることをはじめるとされています。夢をみるといっても、その夢というのは、いわゆる逆説睡眠というか、レム睡眠といわれているものです。夢をみるということがはじまる。その次の段階、5ヶ月ないし6ヶ月の段階で、胎児は触覚と味覚というものをだいたいわかるようになり、6ヶ月以降になって音が、耳が聞こえるようになる。だいたい6ヶ月以降になると、母親の心臓の音とか、母親とか父親とか、しょっちゅう聞いている人の声というのを聞き分けるようになるというふうにされています。つまりここでもう、人間のもつべき感覚がそろってしまうわけです。
受胎後7~8ヶ月になると、人間が人間であるということなんですが、意識がちゃんと芽生えてくるとされています。そうすると、5ヶ月ないし6ヶ月以降の胎児というのは、だいたいにおいて父親と母親の声を聞きわけ、何を言っているかとか、それから、父親は別ですけど、母親がどんなショックを受けたか、つまり、母親の精神状態から、心の変化とか、感覚の変化というようなことはだいたい全部、胎児に伝わってしまうというふうになります。これは、いま比較的に医学が発達しているから、医学機械が発達しているからなわけでしょうけど、テレビみたいに映像にうつしてみることができます。つまり現在の段階では、母親の方になにかショックをあたえると、胎児がすぐにこういうように体を縮めちゃうみたいなことが、はっきり眼でみえるようになっています。ですから、だいたい5~6ヶ月以降から、感覚的なことはほとんどわかってきますし、それから母親の、少なくとも精神状態がどういう変化をしているかとか、母親の声がどういう声か、母親とよく話をしている父親の声がどうだ、ということがわかるようになっちゃっているということ。
ですから言ってみますと、母親と胎児との、内コミュニケーションというふうにいいますと、コミュニケーションは、5~6ヶ月以降の胎児ではすでに成立していることになります。我々が、誰でもそうですが、人の表情を見たら何を考えているかだいたいわかるとか、もっと鋭い人になると、今日こんなことあったでしょうなんていう、そういう人もいるわけです。また、超能力者とか、よく霊能者みたいにいわれている人はもっとわかっちゃって、見ていたり声を聞いたりしているとその人のイメージが出てきちゃって、「あなたの家はこういうようになっているでしょう」なんていうと、だいたいそれが当たっちゃうみたいなことは起こりうるわけです。
そういうことが可能なことの根拠は何かといえば、胎児の時の内コミュニケーションというものの過敏さ、鋭敏さというものが、内コミュニケーションの原型をなしています。たぶん、超能力者とか霊能者というやつは、自分でもって修行して内コミュニケーションの仕方を鋭敏にしている、そういう修練をしていると思いますけども、普通の人でも、誰でも、それほどじゃなくても、相手の表情を読んだら何を考えているかわかるというのはありうるわけです。特に恋愛状態みたいになっていれば、会って、動作ひとつ、言葉ひとつで相手が何を考えているか、どういうふうに思っているとか、そういうことがわかっちゃうことがありうるわけでしょう。これはみなさんが体験しておられるだろうと思います。
2 察知能力・思い込みと内的コミュニケーションの異常
これをもっと極端にいってしまいますと、思い込みというのもあるわけです。恋愛の中にもありますが、つまり「こいつは俺に好意をもっているに違ぇねえ」と思っていても、存外はずれちゃったり、見当違いだったということはありうるわけです。その場合には、内コミュニケーションの異常なわけで、つまり「思い込み」になっちゃうわけです。もっと、いわゆるお医者さんにかからなければならないみたいなご病人になりますと、幻覚がでてきちゃう。幻覚というのは、文字通り思い込みの極端なるものであって、何らかの意味でそうだとわかったと思っているから、あるいは、そういうふうになっていると思っている映像が幻覚ででてくる。もっとひどくなると妄想。妄想も一回きりなら、恋愛関係の時には誰でもやるわけですけど、妄想というのはひとつの体系を作っちゃって、思い込みがどんどんどんどんひとつの解釈の輪をつくっちゃうから、とてつもない所まで夢想がいってしまうということがあります。もっと病気がひどくなれば、分裂病の幻覚みたいなものがいちばん典型的にそうですけれども、内コミュニケーション、自分の全部の世界が思い込みと幻覚、つまり思い込みからでてくる映像といいますかイメージといいますか、それで全部覆われてしまう。それは精神の病というふうになっているわけです。しかし、その精神の病というのは元をただせば、受胎5~6ヶ月以降の胎児の時に形成が始まったということがいえるわけです。本格的にいっちゃえば、分裂病みたいな場合の治癒、治るか治らないかということですが、その人の精神状態みたいなものが、この受胎5~6ヶ月のところまでうまく遡れたら、たぶん治るんだろうというふうに思われます。つまり、それくらい難しいのです。とくにお医者さんはそんなに暇がないですから、その人一人にかかりっきりというわけにはいかないですから、分裂病というのはなかなか治りにくいなあということになるわけですけど、それはなぜかといったら、今申し上げた通り、極端にいえば受胎5~6ヶ月のところまで、つまり胎児の段階まで、その人の感覚とか意識とかの成り立ち具合を「こうだったよ」と遡れなければ、たぶん治らないと思いますね。
それくらい難しいものです。しかし元をただせば、非常に誰にでもある思い込みが元になっているわけです。その思い込みの元というのは察知能力です。つまり、相手の表情をみたとか、相手をみたら何を考えているかをだいたいわかるような気がする。特に親しい人や恋愛関係の人となると、その人の精神状態がすぐわかっちゃうというのは、元をただせば、正常な能力なわけです。言葉ではないんですが、それを内コミュニケーションといえば、すでに胎児の5~6ヶ月の段階から成り立つということがいえることになります。
では、内コミュニケーションの段階の範囲というのはどこまでかというと、それもみなさんご存知のように、1歳未満で初めて人間は言葉を覚えますから。受胎して10ヶ月して出産されて、乳児ということになるわけですけど、1年未満の段階の乳児までの間に、この内コミュニケーションの原型ができてしまうというふうに理解すればいいと思います。つまり、言葉ではないんだけど、言葉に似た、言葉以前の段階でそれができてしまう。どう考えても、胎児5~6ヶ月から1歳未満までの間以外にできる過程があり得ないわけですから、その段階までに内コミュニケーション、つまり言葉なき言葉といいますか、言葉以前の言葉みたいなものでわかってしまうという能力というのは、そこで形成されるというふうに考えるのがいちばんよろしいだろうと僕は思います。
3 心の核はどのようにつくられるか
そういう段階を過ぎまして、胎児というのは出産されて乳児になるわけで、出産の時は、これはまたみなさんがご承知のように、変化が2つあるわけです。ひとつは、今までいずれにせよ相当な人間の段階までちゃんときている、感覚もそなわり、意識もそなわりとなっているんだけど、しかし羊水の中に、胎内では液体の中にいたわけです。へその緒を通じて、血管もそうですが、母親の栄養が即流れてくるという形でつながっているんです。母親の心がそのまんま流れてくるという形でいたわけですが、出産して乳児になった時には、水中呼吸ですから大なり小なり魚と同じでエラ呼吸的なもので羊水の中に泳いでいた、というか浮かんでいた。羊水の中ということは人間の体温ですから、36・何度という母親の体温と同じ温度の液体の中にいたわけです。それが、出産したときにとたんに空気の中にでてくる。空気というのは、夏は31度とかになりますけど、冬は0度の時もありますし、5~6度の時もありますから、とにかくだいたいにおいて温度環境がまるで違うところにでてくるわけです。
それからもうひとついえることは、そこから肺呼吸に即座に転換しなければならないわけです。みなさんのお母さんはそういう体験をされているでしょうけど、生まれたばっかりの胎児は、典型的なことをいいますけど、お医者さんが足をもって逆さまにしてお尻をぴしゃぴしゃと叩くとオギャーなんて産声をあげる。その産声というのは要するに肺呼吸への転換ということになります。
内コミュニケーションということと、内コミュニケーションから外コミュニケーションに移る、移り行きの1歳未満のところの問題に、究極的には帰着してしまいます。それから、なんといいましょうかね。変ないいかたですが、人間の心の形、というのはそこで決定されてしまいます。
心の形というのがそこで決定されてしまうというと、一種の宿命論になってしまうようにお考えになるでしょうから申し上げますと、人間の精神というのは心だけでできているのわけではないんです。感覚も加わったり、心と感覚がからみあったりとか、理性とか知性とか、論理とか論理性とか、そういうのも加わったりして、全部でもって人間の精神というのはできていますから、必ずしも宿命論というのではないんですけれども、でも、人間の心の中にある非常に核の部分はそこで決まってるよ、とお考えになったほうが、僕はよろしいと思います。
みなさんの心の核というのは、そこで決まっているはずです。これはいつか何かのときにでてくるかもしれません。つまり、普通の平穏の生活の中では出てこないでしょうけど、なにかひどい目にあったとか、ひどい境遇になったとか、ひどい事件にぶつかったという時に、たぶんその時形成された内コミュニケーションから外コミュニケーションへの、1歳未満までに形成された心の自分の形というのは必ずでてくるとお考えになったほうがよろしいと思います。それくらい、ある意味では決定的なものだというふうに思います。
それは、克服するのがたいへん難しいところがあります。ものは考えようっちゃあ考えようなんですけど。例えば典型的にいいますと、太宰治とか、三島由紀夫さんでもそうですけれども、この人たちの、少なくとも胎児の時というのは聞いていないから僕はわかりませんけれど、作品の中に出てくる1ヶ月未満の時、あるいは数ヶ月、数週間の時の育てられかたというのは、ちょっと惨憺たるものだということがわかります。いってみれば、無事平穏ならいいけれど、これでもってお前生きろといったら無理じゃないかと。心は絶えず死にたい、死にたいと、生を否定するみたいなことがいつでもあって、それを克服するために、三島さんでも太宰さんでも強烈な意思力と能力とを発揮しまして、いい作品を書いたといえば書いたことになるわけですけど、それはご本人にしてみれば、人が端側で見るほど楽ではなくて、大変にきついことを克服する過程が、ああいう表現になっているとも考えられるわけです。しかし、結局の所は駄目だったよなというふうに、個人的にいえば、そういう理解の仕方をしてもよろしいんじゃないかと思います。もちろん別の理解の仕方もできるわけですし、僕もします。二人とも偉大な文学者です。偉大な作家です。つまり、そんなにめったに現れてこないぜというほど偉大な作品を残した人ですから、そういう面からみたら大変な人じゃないかという見方もできるわけです。けれども、ご本人の心の奥の底の底まで探ってみたら、大変に辛い「生」だったろうな、とうとう駄目だったよな、天寿を全うするという意味あいからいえば駄目だったよなという言い方も、内コミュニケーションの段階の問題からはいえる、ということになると思います。つまり、それほどきついし、それほど核になるものがこの段階で形成されてしまうということがいえると思います。
4 母の物語
問題は、また様々な病的な、極端に異常な、というところにも行きうるわけです。例えば、妄想であったり幻覚であったり、作為体験というのか、つまりどこから声が聞こえてきて、お前はこうしろ、ああしろと命令されているみたいなご病気の人がいるわけです。そういう体験は異常に属するわけですが、それらはたぶん、母親の、そういう段階での育て方というものの枠組みが非常に不安定だった、ということに由来するだろうなあと。不安定、何といいますか、行き来というか、壁といいますか。壁が低くなっちゃうんですよ。だから、正常だと思えるところからすぐに異常に、思い込みだといっていたものが妄想になっちゃうというところに、すぐに行っちゃうわけです。壁があるとそこからまた引き返せるんですけど、壁が低くなっちゃうんです。
なぜ低くなるのかというと、母親によってつくられる枠組み、物語といえば物語の枠組みがうまくいっていないと、枠組みが不安定であまり明瞭じゃないとなってきますと、壁が低いものだからすぐ正常から異常へというように、正常なところで踏みとどまるのが大変に難しい。思い込みの段階なら正常なんですが、僕はもちろんやりますしみなさんも、特に恋愛なんかの場合、思い込みというのはやられるでしょう。つまりその段階なら別に異常だとは言えないんだけども、それが妄想というところに行っちゃうと異常だということになるんですね。それは壁が低いから。その壁というのは、物語の枠組みが不安で曖昧だから。その物語は誰がつくるかといったら、乳児の段階ですから、母親がつくるわけです。
母親の物語というのはどのようにできているかというと、それは単純なことです。要素としてとりだせば、授乳したり、寝かしつけたり、排便の世話をしたりとか、ごく少ない要素からできている物語です。でも、その物語の内容というのはどこからできるかといったら、いうならば、父親と母親、夫婦の関係の中に、その物語の原型があるわけです。夫婦の関係が大変立派で、豊富な感情と理性と、それから豊富な物質的な基礎というのがあるとすれば、母親の物語は豊富になる。母親の物語が豊富になれば、母親の豊富な物語の精神状態の起伏というのは、乳児の中にちゃんと移し植えられますから、大変立派な物語を潜在的な核に植え付けられるということになると思います。もし、その母親と父親の物語が乱れていた、父親が浮気したためにものすごい状態だったとか、経済的なことが苦しくて大変だったとか、あるいはいろんな事故でもってうまくいかなかったとか、そういうことがあったら、やっぱり物語の枠がいろんな段階で乱れてしまうことがありますから。正常と異常の壁が低くなったり、不安神経症みたいな状態にすぐに陥ってしまったりとか、様々な形での、大きくなってから、まあ思春期によくでてくるんですけど、精神異常みたいなことになりやすいといったことになると思います。
5 子育ての及第点はどれくらいか
そうすると子どもの育て方としては、もし、1歳未満までの母親の育て方が大変立派で豊富であったならば、どんな酷い目にあったとか、どんな精神的なショックな状態になっても、異常になってしまうようなことはたぶんないと思います。たいていもちこたえると思います。どんなことがあっても。でも、そうじゃなければ、思い込みが妄想になったりとか、そういうふうに察知してこうだと思ったのが幻覚になってでてきたりとか、作為体験といいますか、人から命令されているみたいな、そういう形ででてきてしまうと思います。
元をただせば妄想体験。声が聞こえてきて、「神様の声が、ああせえこうせえいった」とか、新興宗教の教祖でもよくそういう人がいますが、誰それとわからない人の声なんだけど、自分に命令しているというような異常というものがあるわけです。それから、いつでも人が自分を監視しているとか、あの人たちが内緒話しているのは俺の悪口を言っているんだというふうな、誰でもそう思う事はあるんだけど、それが極端になると、別にその人たちが自分の悪口を言っているわけではないのに、あれは俺の悪口を言っているんだとか。僕の知っている人でもいます。タクシーに乗って運転手さんがタクシー会社の本部と連絡して、今どこを走っていて誰が待っててとかマイクでやっているでしょう。あれは俺のことを警察に訴えているんだという人がいますけどね。元をただせば母親、根本的な核は母親なんです。つまり、愛してもらいたい人、あるいはかつて愛してくれた人、そういう人が自分を追いつめる対象になるというのが原則、法則なわけです。つまり、被害妄想とか、恋愛妄想とか、追跡妄想とか、事と場合によっていろんないいかたがありますけど、それらの妄想という場合に、自分を追いつめるものは、かつて自分が愛したものだとか、自分の親しい人だとか、そういうものが一般原則になるわけです。つまり、そういう形で、内コミュニケーションの段階は様々なタイプをとりますけれど、元をただせば、母親と自分とか、乳児とか、全部の世界だったということからやってくる問題だと思います。
ただ、西洋型の育てられ方と、日本型の育てられ方を、いま言いましたような典型でいった場合には、たぶん違っちゃいます。あっさり、1ヶ月もたったら乳児なんてものは母親から離しちゃうんだという育て方がいいという考え方があります。それが今やられているのか知りませんが、そういう考え方というのは、ある面ではいいわけです。母親が悪くたって良くたってあまり関係ない。1ヶ月くらいで離しちゃって、公共施設とか病院とか、看護婦さんやシッターが育てちゃうんだから、母親が悪いなんて関係ねぇ、ということがありますから、母親が悪い場合の日本型に比べれば、そのほうがいいということになります。しかし、もし非常にいい母親だったら、もちろん日本型の育て方は、人類の理想的な育て方なんです。だけどたいてい、どんな親でもそうですけど、様々な事情がありましてね。100%いい育て方なんてできないんですよ。手をぬいたり、まずったりってことは、たいていどの母親、父親でもあるわけですよ。だけども、まず、55点以上の育て方をしたと母親が自信をもって正直にいえるのならば、それは立派な育て方といっていいんだと思います。そうしたら、その壁は相当高いから、思春期になって相当な目にあっても、乳児以降に、幼児時代にひどい目にあっても、たいてい大丈夫だと思います。
55%以上の育て方をしたよ、というのもなかなかつらいこともあるわけです。人間の夫婦なんてものはわかりませんから。長男を育てた時はよかった。次男、次女を育てた時はちょっとあの時はまずってたんだ。うちの亭主は浮気してて、こっちは正常な神経状態にいなかったという時に子どもが生まれた、ということもありうるわけだし、またそれが直って、三女が生まれた時には経済的にも豊かになったし、夫婦仲もなかなかよろしい、親戚にも問題なかった、そういうこともありうるわけです。ですから個々別々、なかなか100%いいということはなくて、50%以下という場合もありうるだろうし。55%以上だとはいえますよ、という育て方をしたら立派な親ということになるような気がいたします。そういう問題というのは、内コミュニケーションと内コミュニケーションから少し外コミュニケーションに移った時代、つまりまだ言葉が生まれない、言葉をしゃべれない以前の段階にあるたいへん大きな問題であり、また非常に根本的な問題であるというふうにいうことができると思います。
6 幼児期と生まれたときの記憶
人間の発達段階での区分というのは、心理学者など人によって多少違うんですが、1歳未満は乳児ということになりますし、お腹の中にいるときは胎児ということになります。それで、大体2歳から4歳、ないし5歳くらいを幼児というふうにいいます。自分が関心もっているから、僕は面白いなあと思っているんですけど、テレビで、わりあいに最近ですが、子どもたちに、生まれた時のことを覚えているか、つまり、おふくろさんのお腹から出てきた時のことを覚えているか、というふうにたずねていました。ご覧になった方もおられると思います。僕はいいましたように非常に感心をもっているから、よく見ていましたけれど、その場合に、2歳から4歳までの子どもにそれを聞きますと、たいてい憶えているという子どもが多いんですよ。そんなことありうるかとみなさん常識的に思われるかもしれないが、ありうるんです。つまり、ありうると考えるのが妥当なんですよ。2歳から4歳まで、心理学者、精神医学者が区別する幼児期までの子どもに尋ねると、なぜか覚えていると。どうだったと聞くと、「真っ暗で、こういうふうになって、ちょっと明るいところにでたんだ」というわけです。だけど、それを過ぎた子どもに聞いても覚えているという子は少なくなっちゃうんですね。だから、たぶんそこで無意識の中に、2歳から4歳までに無意識の奥の方にしまいこまれちゃうと理解するのがいいんだろうなと思います。
例えば、三島由紀夫さんの『仮面の告白』という、みなさんお読みになったかもしれないけど、そういう小説があります。その中に、三島さんが、母親とか家族の人に「俺は生まれた時のことを覚えている」といいはるところがでてくるんですよ。僕は、ああ、これは要するに後から、つまり4歳か5歳、あるいはもっとたってからカイユウ?で一種つくった、イメージでつくったんじゃないかなというふうに理解していましたけど、そのテレビを見ていてね、これは本当かもしれんなあと思いました。三島さんの『仮面の告白』では、いや、ぼくの覚え違いがあるかもしれないけど、自分は生まれた時のことを覚えている、産湯をつかったたらいのまわりに日の光が明るくこういうふうにアレしててといったら、母親かおばあさんかが、何いってんの、あなたが生まれたのは夜だったのよというふうにいわれちゃったと書いてあります。でも、たぶんそれは、要するに生まれた時の、胎内から出たときのイメージだと理解すると、それはあとから作った錯覚じゃないかという解釈じゃなくてよろしいんじゃないかと、僕は少し考え方を修正しました。
とても面白かったです。テレビで、確か、1、2回はやっているんです。まだきっとやるかもしれない。注意してご覧になっているとぶつかるかもしれません。そういう2歳から4歳まで、つまり心理学者のいう、だいたい幼児期までの子ども、だから保育園の子どもでしょうか、に聞くと、覚えているという子がかなり多い数で存在している。どんなだった? って聞くとだいたい「暗いところにじゅくじゅくしてて、それから明るいあかりがみえたんだ」と、こういうふうにいう。それはそういうものだと思います。そういう段階が「幼児期」という段階になります。
7 児童期――性的無意識の発現と禁止
その次が「児童期」とか「学童期」といってしまってますけれど、5歳から10歳くらいまでの段階を「児童期」とか「学童期」というふうに心理学者は区別しています。こういうのはどうでもいいっちゃどうでもいいんですけど、なかなか、こういう区別でいいのかなあと疑問になるんですが、一応、区別としてはそのようになっています。
「幼児期」は、なんといいますか、無意識の核のところはどんどんどんどん下の方に沈められて、無意識の奥のほうにだんだん入って行っちゃう、という段階だと思います。それが、5歳以降10歳くらいまでの「児童期」には逆のことを、少なくとも近代社会では、西洋でも日本でもやっているわけです。つまり、いろんなことを訓練してしまう。訓練というのはある意味で規制なんですよね。つまり、いちばん母親との関係というので、いろんな豊富な……例えば広い意味でのセックス、あるいはエロスというふうに考えると、「幼児期」というのは相当豊富な……「乳児期」には、母親の性的な体験という物語が、いろんな形で乳児の中に入り込んでいますから、相当豊富な、性的な内体験というのをしているわけです。極端にいうと、それはやっぱり外に現れると、相当乳児の性的なふるまいは無茶苦茶だと、無茶苦茶なふるまいをするわけです。それが「児童期」になりますと、だいたい逆に規制するようにいたします。つまり規制して、「これをしちゃいけませんよ」と学校でも教えますし、きっと親の方も教えるんだと思います。「こういうことをしちゃいけませんよ」とか、性的ないたずらを無意識にやっていると「おまえ、そういうことをしちゃダメなのよ、そういうことはばっちいのよ」とかいろいろ、そういう面もそうだと思います。それからもうひとつ、「知識」というのを外から入れていきます。学校がその通りです。つまり、1足す1は2、というようなことを、学校で意識的に入れていくわけです。それから、学校の道徳の時間みたいなものを通して、「こういう時にはこういうことをしてはいけない」とか、いろんな規則を、学校でもそうだけど、家に帰ってからもこういう遊びはしてはいけないとか、要するに「いけない、いけない」という規律というのも、この「児童期」あるいは「学童期」に逆に教え込むわけです。
この時に、教え込むと同時に、性的には大変豊富な内コミュニケーションの物語を母親から受け継いでるわけで、それを野放図に表に出したら相当無茶苦茶な性的なふるまいをするはずなんですけど、それも抑圧、つまり「これはいいけど、これはいけません」ということを、その年齢の段階で教えてしまうわけです。これが全体的にいえば、規律とか、禁止といいましょうかね、意識的な「禁止」のはじめの段階に入るわけです。それから「言葉」というのも、自然に覚えた言葉じゃなくて、きちっと教えちゃうし、本当は使いもしねぇような言葉も、また字も教えちゃったりするということがあるわけです。
8 学校教育への疑問
よけいなことですけど、この段階が、本当にこれでいいのか、ということは、大変疑問なことだと思います。まだそういう根本的な疑問に降着?するようなことがないもんだから済んでいると思いますけれど、大変疑問だと思います。
要するに、学校はいわゆる教育専門家みたいな者がいて、「学校はこうであった方がいい」とか「小学校はこうでなければならん、こうすべきだ」とかいろんなことをいいますけど、そんなのは極端にいうとといいかげんなのであって、根本的にそういうことを問うとすれば、この「学童期」といわれる4歳から5歳以降10歳までの間に母親から植え込まれたといいますか、刷り込まれた豊富な性的無意識というのを抑圧して、規律と知識を覚えせるということは本当にいいのかということを、本当に問わないといけないと思います。そんなことを本当に問う教育専門家なんていないわけですよ。もっといいかげんなところで済ませて「学校はこうでなければ、こういうのがいい」なんていっているだけ。そんなことは、極端にいうとどうでもいいんで、本当に問われることはそういうことなんで。だけれども、本当に問われなきゃいけないという段階にまだ当面していないから済んでいる、いわゆる教育評論家の言っている段階で済んでいると思います。それでまた結構でございましょうといえば結構でございますよ、ということになると思います。でも、本当に問われる段階がきたら、やっぱり本当に問題にしなきゃ駄目だぜということになるような気がいたします。
そのいちばんの兆候はやっぱり、現在の中学生くらいの、つまり「学童期」の終末、「前思春期」の入り口なんですが、そこらへんでおこる登校拒否とか受験みたいなものあるでしょう。受験の場合にも、いまどうなのかは知らないけど、うちの子どものなんかの場合には偏差値がある段階でわけられて、「この偏差値の段階だとこの学区のこの高校しか行けねえ」みたいなふうにもう決まっちゃう。で、「ここの高校に行ったら、もうここの大学にしか行けねえ」になっちゃうわけです。この大学じゃなくて違う大学に行きたいんだという場合には1年くらい浪人して予備校にで少し勉強して、そして行くという形になるわけです。そういう段階です。そういう段階でも区別されちゃうし、「おめえの偏差値だとどこにも入れねえぞ」みたいにそこでいわれちゃったら、もうやっぱり暴れるとか登校拒否する以外にやりようがないわけですよ。誰だってそうしますよ。そうでなければ、要するに塾に行くわけですよ、学習塾に。僕は統計を見て知っていますけど、大体中学生の5割以上、つまり半分以上は塾に行っていますよ。そして半分以上塾へいかなきゃならないような学校なんか辞めてしまえということになってしまいます。つまりそれくらい、中学段階では、相当危険な、危機の状態が進みつつあるということになってしまいます。
だから、何かが起こるととすればそこで起こるかもしれないと思っています。しかしそれを根本的に解く場合には、先ほどいいましたように、子育てをここにまで遡るか、もうひとつのやり方は、要するに大学を、大学の先生というのを変えちゃえばいいんです。大学の先生を変えちゃうというのは、大学の先生の意識を変えちゃう制度にしちゃえばいいんです。だからやっぱり、みなさんが文部大臣になっちゃうより他に方法はないと思いますね。文部大臣になっちゃったら、絶対に変えてくれたらいいと、それも通したらいいと思いますね。誰の損にもならないことですから。そうしたら、学校の受験地獄から何地獄、登校拒否、全部解消だ、と理屈上はそうなります。つまり、そういう問題が、この「学童期」の問題にはひかえています。
9 前思春期と人間ということの本質
後はもう、要するに「前思春期」の問題になります。いってみれば、いったん内コミュニケーションの時代に抑圧した、母親の性的物語が全部移し植えられたというその体験が再び解放される、というのが「前思春期」から「思春期」にかけての問題になります。これはもはや、ある意味では、父親、母親が止められない問題ですし、解放の問題になります。どれだけ解放されるかという問題。それはまた、みなさんも現に体験しておられる?時代?の問題になります。その性的な感じ、感覚、考え方というのはどこで入れられたかといったら、乳胎児期に入れられた、自分は母親から受け継いだものが核になっている、とお考えになったほうがいいと思います。それが解放されて、なおかつ意識的な考え方が加わって、「前思春期」から「思春期」へかけての問題がでてきます。これは、もう母親とかなんとかの問題ではなくなるかもしれないです。そういう問題とするには、遅すぎるという問題だと思います。つまり、そのくらいできちゃっているものをどれだけ解放するか、どれだけ節制するか、どれだけ抑圧するかというその人個々の性的な、あるいはエロス的な振る舞い方の問題というのは、それぞれ違ってくるでしょう。現にみなさんは違っているでしょうと思います。再び解放される問題。そこで、またもう一度、病、といいましょうか、妄想が幻覚になりといったことがまた起こりやすいんです。
「前思春期」になった時にもうひとつ、心を決める問題というものが生じます。みなさんはもう過ぎちゃったと思うけど、前思春期だから10歳未満みたいな時に、例えば、母親の性的な物語がとんでもねぇ物語だったという場合とか。あるいは具体的に、誰でもいいんです、男の子ならですよ、姉さんでもいいし、おばさんでもいいけど、性的ないたずらをされたりして、なんか逃れられないけど嫌だなあというような思いを、前思春期といいますか思春期に入りかけのところで、近親の人からそうされたとか。父親と母親の物語が元々あまりよくなかったんだとか、近親からのそういう体験というと、これはまた相当に響くような気がします。その人の心の形成の仕方に影響を与える。乳胎児の時ほどではないとは思いますけど、やはり相当な影響を与えるんじゃないかと思われます。
この時はしかし、もう自分の問題だ、あるいは自分の責任だといいますか。それがもし心の宿命だとしたら、それを自分はどう克服するかということが課題になります。その克服するということが、人間ということの本質になります。つまり、自分の心の宿命はこうなんで、これはどうすることもできないんだけれども、だけど、これを超えていくということが、人間が生きるということなんだ、と、思春期以降はそういうことになりますから、それは自分の責任だと。これを超えていくよりしょうがない。超えて自分をつくっちゃう、といいますか、意識的に豊富につくっていっちゃうというよりいたしかたがないわけです。それが成り立つ場合もあるし、三島さんでも太宰さんでもそうですけど、それをやったんだけど、やっぱり終わりを全うするというわけにはいかなかったよ、そのかわり、その過程で大変な、超人的な努力というか意思力をもって自分の病的な母親の物語を超えようとしたもんだから、その過程でこういう作品を残したんだよ、ということになるのかもしれませんし。それは、もういずれにせよ、その人々の責任ということになりましょう。
だから、心の宿命を克服するという意味では、誰のせいにもすることができないということになります。人のせいにできるのは、例えば経済、俺と誰それというのは、能力は全部同じなんだけど、俺のほうがどうしても不利だなあ、ということになりますと、この社会が不平等なんだという責任にしていい部分もあるわけでしょうけども、少なくとも内コミュニケーションの問題でいえば、もうこれでいたしかたないじゃないですか、ということになります。
10 音声・音韻は内臓器官の聴覚的象徴
もう少し、ちょっとだけ先へ行くと、なんとなく「言語」というところまでいくんですよね(会場笑)。言葉以前のこと、言葉という?ハリ?がでてくるんです。あっさり簡単にいいますと、人間の顔の表情というのがあるでしょう。顔の表情というのは、解剖学者に、全部がそういうわけじゃないですけど、僕は三木さんという人が偉い人だと思うけど、この人にいわせると、顔の表情というのは、人間でいえば、腸とか胃とか食道とかあるでしょう、その腸管がめくれて外に出ているのが人間の顔の表情だ、というふうに考えればよろしいそうです。内蔵の器官の視覚的な、目で見える象徴といいますか、それが人間の顔なんだ。つまり、顔というのは要するにその人の腸管といいますか、腸がめくれかえって外にでているものなんだ、というふうにお考えになればよろしいんだそうです。例えば、胃が悪いと顔色が悪いとか、憂鬱な顔をしているとかいろいろあるでしょう。つまり、胃腸が悪いとなんとなく青い顔をして冴えないということが表情に現れる。それは要するに腸管が末端においてめくれかえったというのが人間の顔の表情なんだというふうに考えればよろしいそうです。
それと同じ言い方をしますと、言葉の「音声」とか「音韻」というのは、内臓器官の、耳ですね、聴覚的な象徴であるという面があります。全部がそうじゃないですけど。だから、いちばん極端にいうと、胃が悪いとか腸が悪いと、その人の声がくぐもっている、ということは誰もが体験するでしょう。それから、精神的に面白くなければ声がくぐもっちゃう、そういうことがありましょう。つまり、そういう意味あいで、音声とか、言葉の音韻とかというものは、内臓器官の聴覚的な象徴というふうに考えられる面があるわけです。
11 母音は人類のあらゆる言語に共通している
それから、言葉にはもうひとつあります。それは「母音」です。日本語でいえば、現在では「あいうえお」というのが母音だというようにされています。そして、日本人でも、例えば、琉球・沖縄とか東北では、だいぶ蓋がされていますが、そういう所はだいたい3母音というふうに考えればいいわけです。つまり、3母音と、今の「あいうえお」だから5母音ですか、現在。だけど、万葉時代でいえば、その内の3つくらいの母音には甲類・乙類という区別があったという言語学者もいます。それから、もっと前だったら、例えば「あいうえお」の「あ」というふうに今はいっているけど、「えぁ[ae]」、つまり「え」と「あ」の間みたいないいかたがあるでしょう。つまり、その種の甲類・乙類は5母音全部にあったという人もいます。それから、逆にというか、5母音の中央の日本語のが、地方へいってなまって3母音になったんだという言語学者もいます。
僕はどう考えているかといいますと、元々3母音の言語というのがあって、なんでもいいんです、マレー・ポリネシアン系の言語であってもいい。いわゆる南島系の言語、ポリネシア、ミクロネシアからヤポネシアまで含まれる、そういう言語のうち、3母音のものがある。例えば、フィリピンのタガログ語みたいなものはそうですけど、そういう3母音の言葉というのは、わりに基層にある。それからもうひとつ、8母音か、5母音全部に甲類乙類あるとすれば10母音になりますけど、極端なことをいいまして10母音の言葉が大陸の方から入りまして、それがある時期に混合して、奈良朝時代から以降の「日本語」といわれている言葉になったんだという、おおよそのところは、僕はそう思っています。
でも、そんなことははっきり言える段階にはないわけです。人さまざまであるというのがアレなんですけど、ただ「母音」というのは、西洋語、印度・ヨーロッパ語といいましょうか、西洋の言葉というのがあるでしょう。英語だとかフランス語にももちろん母音はありますし、アフリカの言葉にもあるわけです。そうすると、「母音」というものだけをとってきますと、それが3母音であるか10母音であるかとか8母音であるかと数の違いはあるけれども、母音というものは共通じゃないか。人類普遍性というものが言葉にあるとすれば、母音だけじゃないかということは少なくとも言えそうに思います。
3母音と5母音は違うさ、というのはあるけど、「母音」はだいたい人類共通じゃないか。どんな言葉にも、民族語にも「母音」というのはあるし、それは似たり寄ったりじゃねえかということでは、共通性があるじゃないか。
12 母音の共通性と喉仏から上の共通性
そうすると、この共通性というのは、何らかの意味で人間の生理といいますか身体といいますか、それにかこつけようとするならば、それと関連づけようとするならば、関連づけられるのは、喉から上の共通性なんです。つまり、のどぼとけから上、というのは、感覚と筋肉が両方働いているところなんです。口の中の咽喉とか鼻とか、鼻の息の通し方とか、口の開け閉てとか、口の格好をかえるとか、そういうことになるわけです。それから、喉から上から有声音が出てくるとすると、喉を通らせるその音を、言葉を音があるものにしちゃうということでいいますと、その母音の共通性というのは、たぶん、人類の喉から上の共通性というのとは関連するのではないか、ということが言えそうな気がします。
ですから、たぶん、3母音5母音、口の開け方がどうだとかありますけど、その母音だけの共通性をとれば、人類は格好や何かは違うけれども、のどぼとけから上はそんなに違っちゃいねえという人類としての共通性というものがある。それで、音声というのはそこで出来上がりますから、またそこで文節化されて、言葉らしい意味のある言葉になりますから、それはやっぱり生理的にいうと、ここから上のところで共通性があるんじゃないか、ということがいえそうな気がします。
13 言葉とは何か
そうすると、「母音」というのはとても重要なことになるんです。つまり、音声が単に「あ」とか「い」といっているんじゃなくて、意味がある、文節化された言葉、単語とか文法みたいな構成ですが、そういうものになる場合に、共通の受け口になっているのはこの「母音」じゃないか、ということになるわけです。言語、言葉というものにとって共通の受け口になっているのはこの「母音」じゃないか。これについては、ヨーロッパ語であろうと、日本語であろうと、マライ語であろうと何であろうと、種類は多少、多い少ないはあっても、ほとんど変わらない。そうすると、だいたい言葉ができあがるとき、つまり人間でいえば1歳未満でまさに1歳を過ぎんとする時期に対応するわけですけど、そのころに母音らしきものの影が、なんといいますか、言葉の世界のところにちょっと現れはじめたというふうにイメージをとられればいちばんいいんじゃないかと思います。
そうすると、人間の言葉というのは、先ほど、音声、音韻は、内蔵器官の聴覚的な、つまり耳で聞こえる表象なんだというふうにいいましたけど、その表象と、それから元から上の方でできる、感覚器官が筋肉を動かしましてそれでもって言葉の音が違っちゃうという筋肉の動かし方と、そのふたつによって織られた織物が、要するに言語、言葉というものなんだ、というふうに考えられるでしょう。そう考えると考えやすいでしょう。僕はそう考えます。僕は、粗雑ですけど、自分の言語論というものの体系をもっています。それからいきますと、そういう考え方になります。言葉というのは、どんな言葉でも、内臓器官の聴覚的な表象というものと、それからのどぼとけから上の筋肉の動かし方、感覚ですけども、動かし方の両方でもって織りなされた織物が人間の言葉というものである、ということがいえるように思えます。
14 日本語の特質
後は、要するに、民族語というのは違うわけです。どうして民族語が違っちゃうかということをこれからいわなければいけないわけですけど、時間がないわけです。ただ、これは疑いをもつ人をいるでしょうけど、特質を申し上げます。角田(忠信)さんという人の『脳の研究』を見ますと、例えば「あ」なら「あ」という母音を検査、実験してみると、日本人とポリネシア人だけが、左脳、つまり言語脳で聞いている。西洋人とか、中国人でもなんでもいいんですが、他は全部、右脳で「あ」なら「あ」という言葉を聞いている。あるいは右脳でいっているともいいましょうか。ところが日本人のポリネシア人だけは左脳でいっている、という実験がある。こういう特質が、まず大雑把にいえちゃうことがあります。まだ実験していない人もいるわけだから、人種も民族語もあるわけだから、日本人とポリネシア人というふうにいっちゃうと、それだけが特別になっちゃったりするから疑わしいという人はたくさんいるわけです。そんなことをいうと、別の◯○?も疑わしいということがたくさんあるわけですけれど、いまのところいろいろ検査してみると、日本にいる西洋人も検査するし、中国人も、朝鮮の人も検査するし、もういろいろやっているんだけど、「あ」なら「あ」という母音をみんな右脳で聞いている。ところが日本人だけが左脳で、左脳って言語脳でしょう、言語脳で聞いている。どうしてかということに対して、日本語とかポリネシア語というのは「あ」なら「あ」というものだけで、つまり意味がとれちゃう。例えば「われ」「わたし」という言葉は「I」ですが、「わたし」という言葉は古典語で「あ」というでしょう。現代語の「わがために」というのに近いですが、「あがために」とかいうでしょう。つまり「あ」というのは、そのまんま意味のある「わたし」という意味になっちゃう。日本語はそういう、母音がそのまんま一音で意味のある言葉というのがあるから、それが多いから、だから左脳で聞いちゃうんだというふうに角田さんは説明しています。
もっとたくさん説明の仕方をこれからやらなければ終わりにならないはずなんですけど、時間が(笑)。角田さんの実験、脳波の電位差というものを計って、「あ」というものを、こっちが日本人でこっちがアメリカ人で、象徴的にいえば、アメリカ人でも中国人でも、日本人あるいはポリネシア人以外だったら誰でもいいんですけど、こういうふうになる。これが脳の電位差の違いであって、電位差の濃いところが脳がいちばん働いているところだ考えたらいいわけだから、日本人はここらへん、頭の左肩、左脳のところが濃くなっている、つまりここがいちばん働いているということになるぜといっているわけです。アメリカ人の場合、検査して「あ」というのを発音させたらこっちのほうがいちばん働いているぜということになっている。これは角田さんの本に、3つくらい著書がありますが、これは確か『脳の発見』という著書。三省堂かどこかいくとあると思います、そういう実験をしています。
もっといくつも、なぜそうなるかというのをいくつかもう少しいきたいわけですが、だいたいここらへんで時間が過ぎまして、一応終わらせていただきます。また学校当局がチャンスを与えてくれることがありましたら、この続きをやりたいと思います。一応終わります。