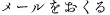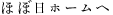| 貴史はiPhoneのディスプレイをしばらく眺めていた。 父は何を伝えるつもりで電話をかけてきたのだろうか。いま何処にいる、と問うためだろうか。すぐ戻って来い、と怒鳴りつけようとしたのだろうか。 いや、あの人はそういうふうに振る舞わないだろう、と貴史は思った。 父はいつも静かに何かを待っているような人だった。早起きで、読書家で、植物を愛でた。いまもきっと待っているだろう。息子からの連絡を。息子が厳しい現状を伝えてくるのを。息子が行き場をなくしてしまったことを白状するのを。 思えば、父はずっと祖父を待っていた。放浪する祖父が帰国するのを待っていただけでなく、祖父との新しい関係がはじまるのを待っていたように思える。けっきょく、その機会は訪れなかったけれど。 そして、息子との関係が新しくはじまる機会も、また失われつつある。 貴史は、iPhoneのボタンを押し、バーをスライドさせ、パスコードを入れてロックを解除した。 履歴から父親の着信へ折り返す。 「いまから帰る」 相手が出たのを確認し、それだけ言って、貴史は一方的に電話を切った。 喫茶デュラムセモリナに居合わせた人々は、そのとき、誰もが押し黙っていたので、その短い言葉をはっきりと聞き取ることができた。 「いまから帰る」 風変わりな銃を持った男は、たしかにそう言った。 「おい」と貴史はマリに言った。 「ハイ」とマリはテンション高く答えた。 鳥飼は、貴史が発したその短い言葉の響きから、当人の内面に何か大きな変化が生じたことを理解した。それは、声の大きさや言葉づかいといった表層の移ろいではなく、本質的な転換だった。鳥飼は興味深そうにうなずきながら貴史の観察を続けた。音ですべてがわかる、というのが鳥飼のモットーだった。 「その財布の中身を、倒れてる店長にあとで渡しといてくれ」 穏やかに貴史は言った。それを聞いて「え」と小さく声をあげたのは謙一である。それは、謙一の財布だった。むろん、中身も自分のものだと謙一は思っている。 「ひどい目にあわせたし、散らかしたしな」 貴史はそう言って店内を見渡した。どういうわけか、少ししみじみとした感じで。 「俺は帰る」 貴史は全員に向けてそう言った。入口のほうをちらりと見た。 「帰って、いろいろとやることがある」 貴史は晴れ晴れとしていた。 「間に合わないこともあるし、間に合うこともある」 確認するように、貴史は言った。 「もう間に合わないこともあるし、ぎりぎり間に合うこともある」 貴史はもう一度そう言って、喫茶デュラムセモリナをぐるりと見渡した。そして、手の甲で額の汗と血をぬぐう。ぬるりとした生々しい感触がある。 「おい、お前」と貴史は再びマリに言った。「ハイ」と頬を赤らめながらマリ。 「そういうわけで、俺は帰るから」 貴史はマリの目を見つめながら言った。その口調にやや個人的な印象があったのは、続く言葉に特別な意味を持たせたかったからだった。 貴史は言った。 「帰るから、お前、しばらく、ここを見張ってろ」 そう言って、貴史は3Dプリンタで出力したその風変わりな銃をマリに渡した。マリは両手でしっかりとそれを握った。ずっしりとした重みがある。 「うそ」とマリは思わずつぶやいた。自分の手の中に、それがある。うそでしょう? とマリは思った。 しかし、それは手の中にある。 うそでしょ、と由希子も思った。しかし、ニュアンスはマリと真逆である。何か、そこにはひどくよくない印象があった。まだしも保たれていた最低限の秩序のようなものが、気まぐれな闇の中にふっとかき消えてしまった気がした。 一方、謙一はマリの手に握られた風変わりな武器よりも、委任された金銭のほうが気がかりだった。それは、誰のものだ? 主張できる自分の権利はあるのか? 謙一はマリのそばに置かれた財布から目を離すことができなかった。 少し離れた席に座っている鳥飼は、マリが手にした銃を見ながら、貴史が入ってきたときに放った一発目の銃声を頭の中で再生していた。述べたように、それは空砲であるはずだ。しかしそれがマリの手に移った瞬間、まったく理屈に合わないことだが、自分の確信が揺らぐのを鳥飼は感じた。いや、そんなことはあり得ない。あり得ない、はずだ。 今村はまだ昏睡している。胸のあたりが規則正しく上下している。 そして、貴史は晴れ晴れとしていた。ここ半年くらいの間で、もっとも思考がクリアーだった。真鍮のドアノブを押す。貴史は、出て行く。 カラァァン、とドアベルが鳴った。夏の白い雲に吸い込まれるような澄んだ響きだった。 開いたドアから涼やかな風が蒸し暑い店内にびゅうと吹き込み、それが止むと、貴史はもういなかった。仄暗い店内に訪れる静けさ。かすかに、店から遠ざかる足音が聞こえる。 貴史は歩きながら、前を見ていた。もといた場所へ戻る道だったが、景色はまったく新鮮に感じた。しばらく停滞していたが、それは必要なことだったのだろうと貴史は思った。ぎりぎりのところだったが、まだなんとかなる。たっぷりとマイナスを背負い込むことになるが、まだなんとかなる。 貴史はすでに優先順位をつけはじめていた。すぐにできること。難しいがやるべきこと。あきらめること。話すべき人。捨てるべきもの。 忙しい、と歩きながら貴史は思った。 一瞬、涼しい風が吹き込んだ喫茶デュラムセモリナの店内を、再び不快な蒸し暑さが満たしていた。みな、ドアの向こうに消えた男の気配をうかがっていた。足音が遠くなり、やがて聞こえなくなった。それでもしばらく人々は押し黙っていた。 行きました、と鳥飼が行った。足音はもう聞こえない。引き返してくるような物音もしない。鳥飼は目を閉じて耳をすませ、何度もそれを確認した。 ふぅ、と由希子が安堵の息をもらした。謙一は緊張を解き、立ち上がってゆっくりとマリに近づいた。なにしろ、その財布は自分のものなのだ。いや、財布よりも、重要なのは中身だ。その十二万円は、いま誰のものになっている? 財布は、自分のバッグから由希子が取り出して貴史に渡し、貴史はそれをマリに預けて、中身を今村に渡してくれと言った。冗談じゃない。 がめつい印象を与えないように、自然に、と心がけながら謙一はマリに話しかけようとした。試合の中盤にポイントガードがボールを運ぶように、極めて自然に。 あのぅ、と話しかけた謙一への反応は、予期せぬものだった。 「来ないで!」とマリは叫んだ。長い髪を束ねたかわいいリボンに似つかわしくない、腹の底から湧いてくるような、ドスの効いた野太い声だった。 謙一は突然の大きな物音が苦手だったから、またしても「ひぁぅ」と叫んで泥中のザリガニのように素速く後ずさった。 その眉間を、風変わりな銃が狙った。 「動かないで!」 野太い声で叫ぶマリの目に怪しい光が宿っている。支配している、その快感を、マリはいま全身で味わっていた。たまらない。マリの口もとにうっすらと笑みが浮かぶ。 悪い予感が当たった、と由希子は感じた。 (次回、最終回。) |
| 2013-09-25-WED |

 |
 |
 |

 |
|||
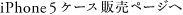 |
|||
 |
|||
|
|||
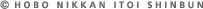 |