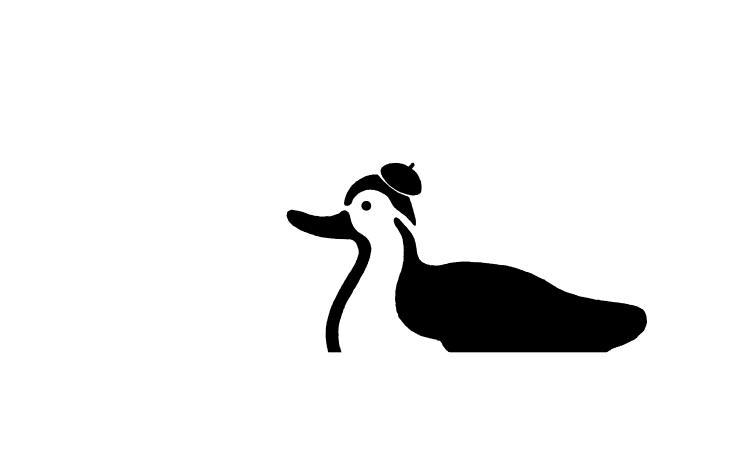歌川国芳「宮本武蔵の鯨退治」(部分)
橋本治さんは、
歌川国芳(うたがわくによし)の描いた
《宮本武蔵の鯨退治》について、
「タイトルを書くだけで興奮する作品」と表現しています。
どうしてそんなに好きなのか。
その理由は橋本さん自身が説明しています。
少し長くなりますが、
その「好き」がより伝わると思うので
引用させてもらいます。
「私が歌川国芳が描いた《宮本武蔵の鯨退治》を好きなのは、
この絵によぶんなものがないからである。
大きくせり上がった波、画面一杯の鯨――黒地に白い水玉模様が、
白い波しぶきを感じさせてロマンチックでさえもある。基調となる
色は、空のグレイを含めた白と黒、そして海の青。そこに、鯨の口
の朱色が、素晴らしいアクセントになっている。その朱色を効果的に
見せるように、画面両端下の「一勇斎(いちゆうさい)国芳画」の
落款(らっかん)を記すひょうたん形も朱色。この両端の朱色の
アクセントを底辺として、二等辺三角形の頂点を形成するように、
宮本武蔵がいる。彼の構える刀の柄が、ほぼ画面中央の頂点。そこ
へ向かって、波の線と鯨の背中が、右端から高まって行く。空を覗か
せる波の線の、直線に近いような円弧とは対照的に、鯨の背中は大胆
な曲線を描く。武蔵を乗せた黒い背中は、一度画面右下へ向かって
下がり、その”ため” を利用して、尻っ尾が大きく画面右上へとはね上
がる。横長の画面全体は、左の上端へ勢いよく進んで行くだけのシン
プルな構成だが、鯨の尻っ尾がうねるようにはね上がって、それが画
面全体を支配する海の水の不思議な重量感を演出する。当然、この時
の気候は嵐だろう。
嵐の海があって、画面一杯の鯨がいる。うねるのは、海ではなくて
鯨である。この鯨が、そのまま「嵐の海」を表現する。そこに、点景
として存在する主役の宮本武蔵。よぶんなものはなにもない。この、
よぶんなもののなにもなにもなさ加減が、私にとっては素晴らしいと
ころで、魅力的なところである。だから私は、この画面一杯に描きこ
まれた横三枚続きの錦絵を見て、「すっきりしている」と思うのであ
る。この絵自体は「すっきりしている」どころではなく、濃厚でごて
ごてしていると言ってもいいのだが、この絵を描く作者のエネルギッ
シュな姿勢が、いたってきっぱりすっきりしているのである。
(中略)
根拠なく、大鯨の背中に乗っかって、「なにしてるんだ、あんたは
?」と言いたくなるくらいに平然と刀を突き立てている宮本武蔵は、
そのまんま「威勢のいい魚河岸の兄(あん)ちゃん」であるのかもし
れない。おそらくは、「いなせ」の精神性――というか、行動美学を
そのまんま絵にしてしまったものが、《宮本武蔵の鯨退治》なのであ
る。
そういう、「気分がそのまま絵になった」というところがあるから、
私はこの絵が好きなのである。だからこそ、「歌川国芳とは、《宮本
武蔵の鯨退治》のような絵を描く画家なのである」と、私は言いたい
のである。」
(『ひらがな日本美術史6』新潮社、2004年)
これを読んだ時
「なるほど、こんなふうに浮世絵を見て、
こんなふうに好きになるのか。」
という新鮮な思いがしました。
つまり「自分の目で好きなようにみていい」と
言ってもらっているような気がしたのです。
むずかしそうに感じていた浮世絵鑑賞が、
ぐっと近づいてきてくれたように。
浮世絵のなかに、
「気分がそのまま」閉じ込められているとしたら、
こんなにその時代を感じられるものはないんじゃないか。
むずかしいことを抜きにして、
まずは実際に目で見て、
ぎゅっと凝縮された江戸の空気を、
そしてそこに描かれている「気分」を感じてみてください。
国芳のことを橋本さんはこう一言で表しています。
「我は躍動する文化なり」。
国芳が生きた江戸という時代には、
ほんとうの「文化」があって、
それは近代の到来とともに終わってしまいます。
その「文化」とは、
たぶん「その時代に生きる人たちのうねり」と
言い換えてもいいのだと思いますが、
その「うねり」は時代が変わっても
国芳の作品のなかにあり続けたと橋本さんは言います。
今回の大浮世絵展で
国芳の作品を見ることで、
かつて日本にちゃんとあった
「文化」に触れられるのではないでしょうか。
そこからまた、いまの日本を見つめる。
そんな機会になるとよいなと思っています。