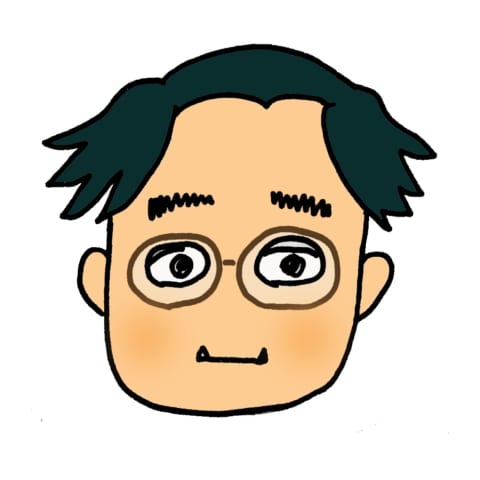前作「わたしは、ダニエル・ブレイク」(2016年)を最後に、
一度は表舞台から退くことを考えた
英国のケン・ローチ監督(83歳)が、
引退宣言を撤回し、
「いまどうしても伝えたい物語がある」と
再びメガホンを取った最新作――。

映画「家族を想(おも)うとき」は、
イギリスで(いや、新自由主義経済のグローバル化が進む世界全体で)
いまなお拡大し続けている経済格差、貧困の実態と、
いわゆるギグエコノミー(*)がもたらす
労働環境の過酷な現実を、
その流れにもてあそばれ、
引き裂かれる労働者家族の姿を通して描いた、
使命感にあふれる作品です。

原題は“Sorry We Missed You”。
届け先が不在である時に、
宅配業者が残していく“不在票”のメッセージです。
「残念ながらご不在でした」――。
舞台はイギリスのニューカッスル。
妻、16歳の息子、12歳の娘と暮らす4人家族の物語です。
夫のリッキーはフランチャイズの宅配ドライバー。
10年前に不況で失業し、その後は転職を繰り返してきましたが、
安い給料で人にこき使われるのには、すっかり嫌気がさしています。
借金を抱えた不安定な暮らしから一刻も早く抜け出して、
マイホーム購入の夢をかなえたいと願います。
そこで、工面の末に営業用のバンを手に入れ、
宅配ドライバーとして独立します。
個人事業主として物流会社と契約すれば、
「勝つのも負けるのも自分次第(2、3年死にものぐるいで働けば、稼ぎも溜まって普通の生活に戻れるはず。家族を幸せにできるに違いない)」
と思えばこその決断です。

ところが、“自営”、“独立”とは名ばかりで、
実態は大企業の下請けです。
本部からは過酷なノルマを言い渡され、
遅配やトラブル、アクシデントが生じれば、
すべてのリスクを背負います。
ペナルティーは厳しく重く、休むこともままならず、
1日14時間、週6日、
朝から晩まで追い立てられて酷使されます。
ポチればすぐに品物が届く、
便利で快適な現代の消費生活を陰で支えているのは、
こうした過酷なシステムなのです。
黒い携帯端末が、このシステムの“心臓部”です。
品物をスキャンするとそれがたちどころに登録され、
以後は届け先までの動きがすべて追跡可能です。
配送ルートも指示されますが、
顧客が指定した時間内に遅れず配達することが肝要です。
見方を変えれば、ドライバーの行動もこうして逐一管理、追跡されるのです。
ちょうど『潜入ルポ amazon帝国』(横田増生、小学館)
を読んだばかりだったので、
よけいリアルに伝わってきました。
“出陣前”の朝の集配センターの空気、
“ラストワンマイル”(業界用語で宅配ドライバーが顧客に品物を届けること)でのハプニング、
とりわけドライバー泣かせの事件など、
隣で起きていることのように思えました。

もっとも、マンチェスター出身で
マンU(マンチェスター・ユナイテッド)びいきのリッキーと、
地元ニューカッスルびいきの顧客との
玄関先での熱を帯びた舌戦は、イギリスならではのものですが。
さて、妻のアビーはパートタイムの介護福祉士です。
夫の営業用バンを買うために、彼女は自分の車を手放します。
そのおかげで介護先にはバスで移動するしかなくなって、
家にいる時間が奪われます。

交通費は自前、移動時間は賃金の対象にならないので、
訪問介護に12時間を費やしても、
6時間か7時間分の賃金しか受け取れません。
人手不足で、過密なシフトに振りまわされ、
満足のゆく介護ができないこともストレスです。
時間外でも呼び出されます。
こうして家を空ける時間がますます増えて、
子どもたちとのコミュニケーションは、
留守番電話のメッセージに頼るしかありません。
朝から晩まで働き詰めで、
時間に追われて気の休まる時もなく、
両親はともに疲労困憊していきます。
子どもたちは心の拠りどころを失って、
兄はやがて問題を起こし、妹は眠れなくなってしまいます。
支え合って暮らしてきた家族から笑顔が消え、
すれ違いの生活が続くなかで、一家の絆が壊れてゆきます。

映画の半ばで、夫婦がこんな会話をかわします。
リッキー:「何もかもうまくいかない。分かるか?」
アビー:「ええ、怖い夢を見るの、砂の中へ沈んでいって。
子どもたちが棒で引っ張るの。
でも、懸命にもがけばもがくほど、大きな穴の中へ沈んでく‥‥」
家族を守るため、良かれと思って選んだ仕事なのに、
家族と過ごす時間が失われ、
4人がバラバラに引き裂かれてしまう。
どうしてなのか? いったい何がいけないのか?
作品は深く、静かに問いかけます。
資本主義がもたらした現代社会の矛盾を衝(つ)き、
劣悪な状況に生きる社会的弱者を見つめてきた
ケン・ローチ監督ならではの作品です。
そしていつもながら見事だと思うのは、
マクロのテーマを扱いながら、
ミクロの視点で切り取った日常のディテールが輝くこと。
細やかな確かさが真に迫ります。
今回起用されている俳優は、
ほとんど演技経験のない人たちです。
ケン・ローチ監督は、有名俳優よりも、
無名、若手、舞台俳優を起用することを好みます。
リッキー役は、配管工として20年以上働き、
40歳を過ぎてから俳優を目指したという役者です。
アビー役も、40歳を過ぎてテレビで小さな役を務めただけ、
映画はこれが初出演という“抜擢”です。

俳優たちには事前に台本を渡さず、
彼らの自然な演技を引き出すために、
そのつどセリフや状況を伝える演出方法が取られます。
そもそも脚本を書く時に、結末を意図的に書かないことでも、
ケン・ローチ監督は有名です。
気がつかないうちに搾取され、
社会的に不当な扱いを受けているにもかかわらず、
告発する術(すべ)を知らない弱者の声を、
どうリアルに伝えるか。
「私は観客を驚かせたいのではなく、共感してもらいたい。
だから観客が登場人物と同じ部屋に居合わせたように撮ることを心がけています。
例えば、人物の顔を超クローズアップにしたりせず、
普段目にしている画格で撮っているんです」
(ケン・ローチ監督談話、朝日新聞2019年12月6日夕刊)

「順撮り」と呼ばれる撮影手法を用いることも特徴です。
登場人物の人生をたどるように、
シナリオの冒頭から順に撮影を進めていくのです。
シーンを重ねるごとに役者のなかで物語が生きた姿をあらわします。
役作りにはうってつけの手法です。
ケン・ローチ監督の初期作品に
「ケス」(1969年)という名作があります。
イギリス・ヨークシャーのさびれた炭鉱町で、
家にも学校にも居場所を見つけられず、
未来に希望を持てずに生きる少年を見つめた作品です。

この作品に関して、映画監督の是枝裕和さんが、ローチ監督におもしろい話を聞いています。
<ケン・ローチ監督の『ケス』という映画は、家族とも先生ともコミュニケーションのとれない落ちこぼれの少年が一羽のハヤブサを飼うことで成長していく物語です。
その映画のなかで、心が荒(すさ)んでいる少年の兄は弟をやっかみ、飼っていたハヤブサを殺してゴミ箱に捨てます。少年が帰宅すると、ハヤブサがいないことに気がつき、探しまわって、最後にゴミ箱のなかに死んだハヤブサを見つけるのですが、そのときの表情は芝居にはとても見えませんでした。
それで監督にお会いしたときに直接訊いてみたら、監督は「ハヤブサがいなくなったから探してくれ」と少年に伝え、本当に探させたのだそうです。もちろん本当に少年が大事にしていたハヤブサは殺せなかったので、それに似たハヤブサの死骸をゴミ箱に入れておいて、少年がそれを発見して抱きかかえるところを撮った。
僕はとても驚いて、「撮影後に少年との信頼関係が崩れると思いませんでしたか?」と尋ねると、監督は「一時的には崩れるかもしれないですが、それまでの僕たちの関係があれば修復できる自信がありました」と答えました。実際、『ケス』の撮影が終わったあと、少年はケン・ローチ監督の助監督になったそうです。>
(是枝裕和『映画を撮りながら考えたこと』、ミシマ社)
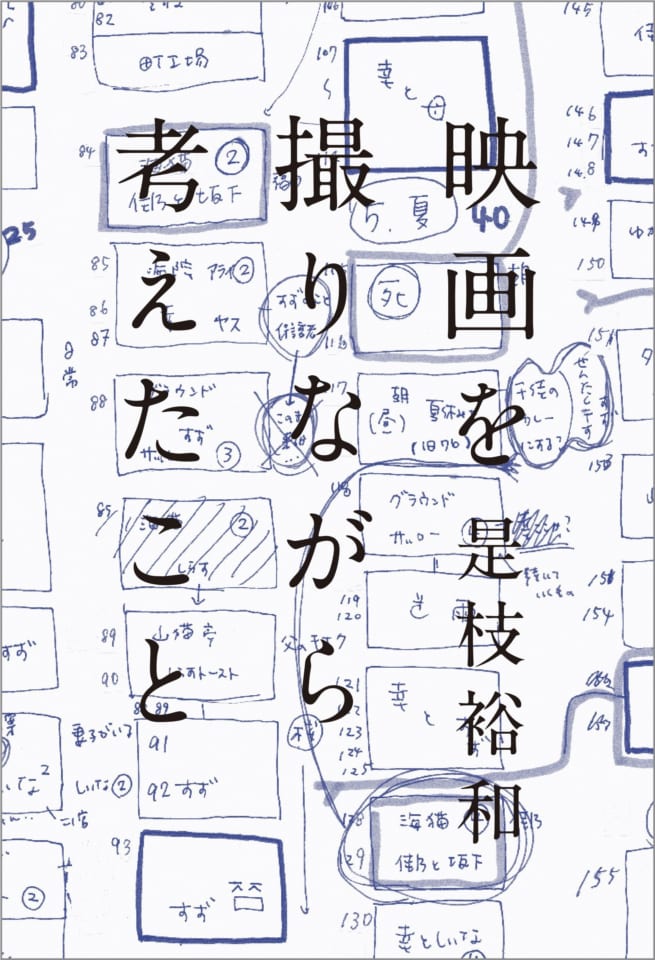
前作「わたしは、ダニエル・ブレイク」にも、
そういう胸に迫るシーンがありました。
貧困に苦しむシングルマザーが、
食料の配給を求めて、フードバンクを訪れる場面です。
子どもたちの前では空腹の素振りも見せなかった母親が、
あまりにお腹がペコペコで、
手渡された缶詰を、その場でいきなり開けてしまいます。
反射的に、手でむさぼるように食べ始めるのです。
取材で知った実話をもとにしたといいますが、
この場面にはただ圧倒されました。
この時、自分のふるまいが恥ずかしくなって、
思わず泣き出したその母親を
優しく抱きとめるフードバンクの女性がいます。
「恥ずかしいことではない」と温かく声をかける
ダニエル・ブレイクの姿にも感涙を誘われます。

出口がどこにもないような辛い現実であるにもかかわらず、
ほんの少し希望を感じさせる“何か”が心に残ります。
これもケン・ローチ監督ならではの持ち味です。
<『ケス』ではもうひとつすごいと思ったことがあります。少年は死んだハヤブサを抱いたあと、頬ずりしたりハヤブサの羽に涙を落としたりせずに、死骸を持って兄のところに行って差し出すのです。兄は嫌がり、少年はそんな兄にハヤブサを押し付ける。それが実にリアルでした。ここで感傷的にならないケン・ローチ監督の演出には本当に舌を巻くしかありません。>(是枝裕和、前掲書)
「家族を想うとき」のラストシーンも衝撃的です。
生きるためには、自分たちの暮らしを守るためには、
こうする以外にないだろう――
リッキーの懸命にもがく姿に、
監督の醒めた目と温かいまなざしを感じます。
そして、怒りと主人公たちへの愛情を――。

作品の後半、家出した長男の行方を探して、
古い子ども用自転車を必死で漕いでいく不器用で、
滑稽で、無様(ぶざま)であるから、
よけいに切ないリッキーの姿に、
心を揺さぶられずにはおかないように――。
*ギグエコノミー:インターネットを通じて非正規雇用者が単発の仕事を請け負う働き方や、それによって成り立つ経済形態のこと。
※2019年12月12日の「ほぼ日の学校長だより」より。