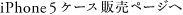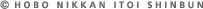マリは今日こそ何かが起こる予感がしていた。
きれいなカーブを描いてちょうどよくまとまった前髪、サイズがぴったりだった黄緑色のシャツ、昨夜はぐっすり眠れたし、左頬の裏にできていた口内炎も完治した。
おまけに今日の占いだ。マリの信頼する6つの占いが、すべて本日を「きっかけの日」と特定していた。ある雑誌は「これまでにない出会いがあるはず」と言い切ったし、あるサイトは「明るい服を着て外に出かけてみて!」と促し、とある説明の難しい情報源は「街外れで幸福のベルを鳴らせば未知への扉が開く」と伝えていた。
それでマリは希望に胸を膨らませて家を出た。ラッキーアイテムに挙げられていたリボンで長い髪を束ね、中学時代からトレードマークの赤いメガネをかけて通りを歩いた。前日までの長雨がうそのように空は晴れ渡り、午後を過ぎて気温は徐々に上がりつつあった。夏に向かって暑くなっていくこの季節がマリは大好きだった。
目の前の空をツバメが横切る。さらなる吉兆。ツバメはマリのラッキーバードだった。マリは、ラッキーナンバーやラッキーカラーはもちろん、ラッキーフードやラッキースポーツ、ラッキーファミレスやラッキーエアプレーンなども自分で定めていた。
毎日、我が身に幸運の訪れを期待するマリは、逆にいうと現在の自分の境遇を不当だと感じていた。あたしはあたしの運命のなかで主人公であり、主人公にはもっと主人公らしい状況があてがわれるはずだと固く信じていた。こんな、毎日トーストをかじって電車に揺られて割としっかり働いてそこそこ認められてとくに誰とも密接に語らうことなく帰宅して録画したドラマを観てネットして寝るような毎日が、あたしの物語の舞台だとはとても思えなかった。
あたしは、いつも待っている。すべてがあたしを中心にして新しくほどけていく瞬間が訪れるのを。平板な空気を金属音が切り裂き、裂け目から透明できらきら光る球体がぽろぽろとこぼれ落ちていくような日常からの転換を。なんらかの出会いと、ちょっとした混乱と、とっさの機転と、窮地と、興奮と、冒険と、瑞々しいエンディングを。むろん、総合的にはたっぷりの愛を。いろんな意味で。
マリは今後の展開を軽く思い浮かべるだけで頬が赤らんだ。
そして気づくと、マリは見知らぬ場所を歩いていた。以前、雑誌で紹介されていた輸入雑貨店を目指してうろうろしていたはずが、完全に迷ってしまった。
マリはiPhoneを起ち上げてマップをチェックしたが、そのあたりは電波の入りがあまりよくなかった。「ま、いいわ」とマリは思った。今日は何かがはじまりそうな日だからポイントになりそうな場所へ気ままに向かっているだけで、その雑貨店に本当に用があるわけではない。
マリは鼻歌交じりにiPhoneをスリープさせ、そのiPhoneのケースにプリントされている繊細な線画をうっとりと眺めた。濃いチャコールグレーの地に塔や水面や月や木や鳥が描かれているその絵が、マリは大好きだった。絵には「ある一日」というタイトルがついてた。なにかがはじまるかもしれないけれど、いまは静かに繰り返す日々の薄い膜の中に眠っている。そんなムードを醸し出すモノクロームの世界は、自分がいま居る日常の幻想面をデフォルメしているように思えた。
今日はあたしの、特別な「ある一日」になる。
マリは信じて歩いた。くちずさむのは軽やかな『東京音頭』。マリは東京ヤクルトスワローズの熱狂的なファンだったから、気分が高揚すると自然とこのメロディーが頭の中に流れた。目の前に緑色のビニール傘が無数に浮かんだ。あ、よーいよーい。
喉が渇いた、と思ったころ、目の前にぽつんと古い喫茶店が見えた。強くなる陽射し、古いアスファルトにくっきりと刻まれる影。古い喫茶店で冷たいアイスティーなんて、いいんじゃない? 近づくと看板に「喫茶デュラムセモリナ」と読めた。そういえば朝の情報番組で山羊座のラッキーアイテムはパスタだって言ってたじゃない。
──ひょっとしたら、ここがあたしのはじまりの場所かもしれない。
強い気持ちを込めてマリは扉を開けた。勢いがつきすぎたから、扉に備え付けられていたドアベルがジャガジュワワァンとけたたましく鳴った。同時に、店の中から「ひぁっ」という叫び声が聞こえた気がした。
まだドアベルの残響音が残る室内へ一歩踏み込んで、マリは自分が何か選択を間違ったかと戸惑った。喫茶店に入ったつもりだったけど、ここは一体?
まず、目の前のテーブルの上に老紳士が仁王立ちしている。紳士は上下が一体となった青いつなぎを身につけている。そして両手を天井に当て、なにやら難しい顔をしてなにかに集中している。向かって左手の窓際には男女の二人連れが座っていて、どういう理由か男のほうが中途半端に立ち上がっている。まるで何かに驚いてたったいま椅子から跳び上がったところみたいだ。カウンターのところでぎくしゃくと妙なお辞儀をしているのが店長だろうか。
喫茶店に入ったつもりだったけど、ここ、何? どうなってるの?
「……やってます?」とマリは小さな声で尋ねた。
今村は答えに困った。なにしろ、エアコンに中爆発の可能性があると言われたばかりで、先客の二人連れすら店から出てもらったほうがいいかと思案していたところだった。いや、あの、とモゴモゴ言いかけたところでテーブルの上から鳥飼がぴしゃりと言った。
「ハイ、やってます!」
え、と今村は思った。
「お一人様ですか?」とテーブルの上から鳥飼。
「はい」とマリ。
「お一人様、ご案内です」と鳥飼が眼下で戸惑う今村に告げた。反射的に今村は「かしこまりました」と鳥飼に向けて頭を下げた。それゆえ店内のヒエラルキーは完全に曖昧になった。
今村はマリを店の奥の席へと案内した。ひとまず中爆発のことは考えないことにした。マリは今村に導かれてテーブルとテーブルの間の狭い通路を静かに進んだ。進む自分を店中の人たちが見つめている気がした。奥の席まで来ると今村はマリのために椅子を引き、マリはわずかに会釈しながらそこに腰掛けた。今村は冷たい水とメニューを用意してマリの前に置いた。
マリはすこぶる気分がよかった。
こうしてメニューを開く自分にスポットライトが当たっている気さえした。みんながあたしを見ている。この古ぼけた喫茶店で、いよいよあたしの物語がはじまるのかもしれない。ラッキーガールの妄想は止まらず、マリは思わずグフフと笑った。またしても頭の中で『東京音頭』が流れ、緑色のビニール傘が波打った。
一方、謙一はバツが悪かった。彼は当初、目の前に座る由希子を煙に巻いて二人の関係をぼんやりと終わらせてしまおうと目論んでいた。しかし、コップの水を飲み干したりしている間にどういうわけか彼女に新たな魅力を感じてしまい、いまやどうにか関係を修復したいと思うようになっていた。そのきっかけを探ろうとしていたとき、突然背後でドアベルがジャガジュワワァンと鳴ったものだから、大きな音に弱い謙一は「ひぁっ」と短く叫んで飛び上がってしまったのだ。
謙一は座り直すと、うぇっほんうぇっほんと空咳をした。あわよくばさっきの奇声は、咳とかくしゃみの一環だと思ってほしかったが、由希子の視線は冷ややかで、そこにある種の軽蔑が含まれているのは明らかだった。
何か言わなくちゃ、と謙一は焦った。
「遅くなったらいまよりあとだよね」と謙一はつぶやいた。
冷静を装って口を開いたところ、まったく無意味な言葉が飛び出してしまったのだった。
「は?」と由希子は言った。オレはいったい何を言ってるんだと謙一は激しく自己嫌悪した。
「いやいや、なんでもないね、半分半分だね、ハハハハ」
動揺する謙一はさらに無意味な言葉を付け足しながら笑って誤魔化した。由希子はますます眉をしかめた。どうにか挽回しなきゃ、と謙一は思った。額から嫌な汗がドッとあふれ出た。
「カモミールティーはありますか?」とマリが訊くと、今村は申し訳なさそうに首を振った。今日のラッキーティーがないなんて、とマリは残念に思った。たぶん、ローズヒップもレモングラスもないだろう。どうしようかな、と悩みながら、マリは冷えた水を半分ほど飲み干した。なんだかちっとも考えがまとまらない。本当は冷たいコーラでも飲みたかったが、物語の中の主人公がはじまりの場面で注文する飲み物としては似つかわしくないように思えた。
メニューに書かれた文字を端から追っているうちに、ぽつりとページに汗が落ちた。ああ、それで考えがまとまらないんだ。マリは今村に向かって言った。
「すいません、ちょっと暑いんですけど」
今村は鳥飼に向かって訴えるような視線を投げた。鳥飼はテーブルの上で黙々と作業を続けている。今村は言った。
「申し訳ありません、いまエアコンがつかえないんです」
そういえば暑い、と由希子も思った。向かいに座る男もさっきから汗だくだった。テーブルの上で作業する鳥飼も汗をかいていた。
「あ、窓を開けますね」
今村は額の汗をぬぐいながら言った。
二つの窓を全開にすると、さぁーっと気持ちのよい風が通った。周囲に建物のないせいか、この店はずいぶん風通しがいい。
作業中の鳥飼も涼しい風を受けて気持ちがよかった。謙一の濡れた額を風が優しく撫でてて、彼はしばし中爆発のことを忘れた。由希子は新鮮な空気のなかで軽く深呼吸し、舌戦の再開に備えてコップを手元に引き寄せた。今村は柔らかく波打つカーテンを束ねながら、まだコーヒー豆を焙煎し終わってなかったことを思い出した。
喫茶デュラムセモリナは、ようやく喫茶店らしさを取り戻したようだった。
マリは店のいちばん奥の席からそれらの変化をうっとりと眺めていた。いま、あたしの意見によって、状況が著しく変化した。涼しい風が縦横に行き交い、人々に微笑みが戻った。この全体的な余裕と潤いは、あたしがもたらしたともいえる。
物語がはじまるのだわ、とマリはいよいよ確信して興奮した。
事実、本当の物語は次のドアベルの音によってスタートするのだった。否、重要なのはドアベルの後に鳴る物音である。
カラァンとドアベルが鳴って、男が喫茶デュラムセモリナに入ってきた。男の足取りは少しふらついているように思えた。男は後ろ手に扉を閉めると右腕を不自然な感じで真上に挙げた。その手に、特異なものを持っている。
パァン!
銃声。
(続く)
|