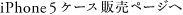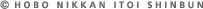貴史の祖父は変わり者だった。
学校の成績は優秀だったがまともに就職せず、英語もしゃべれないのに単身渡米して10年近く消息不明となった。家族や親戚は死んだものと思っていたそうだ。
30歳を過ぎたころにひょっこり帰国して周囲を困惑させ、進学塾を開いて大成功した。数年後、13歳下の祖母と出会って大恋愛ののちに結婚。やがて生まれたのが貴史の父親である。
進学塾が順調に生徒を増やし分校の数が二桁になったころ、祖父はどういうわけか新しい自動販売機の発明に乗り出し、ものの見事に失敗した。苦心の末に開発したざるそばの販売機は、よくできていたがわざわざ買う人がいなかった。進学塾は人の手に渡り、祖父はプラマイゼロのような状態になって、またしても旅に出た。海を渡り、世界中の大陸を1000ccを超えるモンスターバイクで旅して回った。留守中、さまざまな手続きに翻弄された祖母は夫を変わらず愛し続けたが、発見が遅れた病に蝕まれていた。祖父は妻の死に目に間に合わなかったどころか、その時期、連絡すらとれなかった。それで貴史の父は、祖父が亡くなったいまも祖父を憎んでいた。
一方、貴史は祖父が大好きだった。
少年時代、祖父はふらりと現れては貴史に旅のめずらしい話を夜通し話して聞かせてくれた。見たこともない怪しげな民芸品や、何に使うかわからないぴかぴかの工業製品をお土産にくれた。成長してからは、父の目を盗んで二人で遊びに行ったりもした。物心ついたころから成人するまで、少年時代の貴史は祖父と濃密な時間を過ごした。
「いつかいっしょに世界を回ろう」と祖父は言ったが、それは叶わなかった。貴史が大学を卒業する寸前に、祖父はアメリカとメキシコの国境付近で事故に巻き込まれて亡くなった。最後の最後まで面倒をかけて、と貴史の父はしきりにぼやいていた。祖父と父はまったく違うタイプの人間だった。しかし、二人が完全に反発し合っていたかというとそうでもないように貴史には思えた。たとえば、父は祖父の話をしなかったが、貴史が祖父から聞いた話を聞くときは妙にうれしそうだった。あるいは祖父が自分に愛情を持って接するとき、孫である自分の奥に父の姿を求めているように貴史は思った。もちろん、そういったことを二人に確認したことはない。
貴史は祖父のように生きたいと思い、それゆえ父と意見が分かれた。
大学を卒業したあと、貴史はしばらく何もしなかった。父は拒否されるのを承知でいくつかの職を貴史に勧めたが、貴史は断ることすらせずに漫然と日々を過ごした。
それでも30歳を迎えるころに貴史はコンピュータ関連のベンチャー企業に潜り込んだ。若くて将来性のある会社で、学歴や実直さよりも新しい価値観と野心を重んじた。新しい業界とともに新しい企業は成長し、貴史はその場その場で時代の波のようなものに乗りながら実績を築いていった。
35歳になった貴史に転機が訪れた。海外で開発されたまったく新しい技術のライセンスが宙に浮いていた。まだ大きな注目を集めていないが、数年のうちにその技術が世界的なイノベーションをもたらすことを貴史は確信していた。貴史は会社にライセンスの買い取りを強く勧めたが、創業社長は決心しなかった。
簡単にいうと、それは3Dプリンタにまつわる画期的な技術だった。3Dでモデリングされたデータを樹脂をつかって造形していく3Dプリンタは多くの分野で活用が期待されていたが、コストがかかりすぎるためまだ一部の大企業にしか扱えなかった。貴史が成功を確信した技術は、3Dプリンタにおけるコストを飛躍的に少なくするものだった。
貴史は独立を決意した。会社は当初、退社を認めなかった。貴史が会社の知的財産を少なからず持ち出すことになる可能性があったからだ。しかし貴史の決心は強固で、交渉の最終的な局面では法的な決着すらにおわせる踏み込んだ姿勢を見せた。最後は、自分たちと敵対しないことだけを約束させ、会社が貴史をあずかり知らぬ存在として見限る形となった。
貴史には夢があった。十分な貯えを築いたら、祖父のように世界を旅するという夢だった。これからの10年をそれに捧げるのだと貴史は思った。
かつて祖父が貴史にくれた外国のめずらしいお土産は、いつの間にか壊れたりなくなったりして失われていったが、祖父が最後にくれたものだけは貴史の持ち物のなかに残っていた。というか、それは捨てるに捨てられないもので、人に見せることはもちろん、存在を誰かに知らせることさえ憚られた。貴史はそれをなくさないように大事にこっそり持っていた。結果的に、貴史にとってそれはお守りのようになっていた。と同時に、それは祖父の形見でもあった。
「いいか、ほら、どうだ」
祖父はいつもそう言って貴史の手にめずらしいものを握らせるのだった。最後の機会にそれを渡したとき、祖父はいっそう悪戯っぽい笑みを浮かべた。「成人のお祝いだ」と祖父は言った。
手にしたものは、小さな容量のわりにずっしりと重たかった。箱を開けると毒々しい色をした薄紙。めくったところに冷ややかな輝きがあった。
「ほら、どうだ」
祖父の微笑みを、貴史はいまでもありありと思い出すことができた。
独立を目指す貴史には資本が必要だった。もといた会社からは当然、資本提供は得られない。話が通じやすそうなベンチャーキャピタルには、もとの会社が先回りして投資を断らせるようにしていた。
貴史は、父に頭を下げた。父は貴史の野心に祖父の影響を感じたから、はじめ取り合わなかった。実直に歩めと何度も諭した。これまでの貴史なら憮然として席を立つか、父の保守性を激しく攻撃するところだったが、今回ばかりは根気よく実家に通い続けた。新しい技術の先進性をかみくだいて説明し、資料もきちんとつくって事業計画をプレゼンした。やがて父は折れた。渋々、という姿勢を崩さなかったが、貴史に協力を約束したあとの父は少しうれしそうにも見えた。たとえば父親は、貴史が3DプリンタのサンプルのためにつくったiPhoneケースを自分のiPhoneにセットしてつかっていた。真っ赤なケースで、中央には貴史が大好きだったゲームのロゴがあしらわれている。おそらく父親はそのロゴが何を意味するか知らないだろう。
かくして、貴史は起業した。最初の1年は希望に満ちていた。つぎの1年は実利を生み、つぎの1年に段々と成長した。しかし4年目にあっさりと競合に追い抜かれた。新しい技術が新しい分野を切り拓くと、より新しい技術がさらに広い場所を大規模に刈り取っていくのだ。
会社の業績に悪い兆しが見えると、勘のいい人材から順番に去っていった。悪循環はそんなふうにして簡単にはじまる。社員は減り、作業所は一箇所に統括され、貴史は必死に手を打ったがことごとく裏目に出た。
そして夢が終わるときがきた。
降参の旗を振って、貴史はすべてを失うことになった。誰もいなくなった深夜のオフィスで、貴史は最後の雑務を呆然とこなしていた。
暗がりのなかで、貴史のiPhoneが着信を知らせた。鈍く視線を投げると、ディスプレイには父の名前があった。数日前から父は何度も貴史に連絡をとっていた。
貴史は電話に出なかった。やがて着信音は鳴り止み、しばらくしてまた鳴った。貴史はもうディスプレイを見ることすらしなかった。
深夜のオフィスで、貴史は機械的に作業を続けた。カタカタとキーボードを叩き続けた。雑務を頼む部下も相談する仲間もいないから、自分でやる以外なかった。
そして表計算のアプリケーションソフトがフリーズする。自然、貴史も凍りついてしまう。しばらく待つが画面はまったく復帰しない。貴史も、動かない。
深夜のオフィスにどろりとした時間が流れ、貴史はあきらめる。いろんなことを、あきらめる。時間の流れの真ん中に、ぽっかりと穴が空いたようだった。初夏の蒸し暑い夜、エアコンは低くうなり、オフィスの空間を過剰に冷やし続けた。来月の電気代を誰がどう払うのか、貴史は知らなかった。薄い和紙が水の中でじわじわ溶けていくみたいに、いろんなつながりが希薄になっていた。曜日や数字や、優先順位が、水のなかに溶けていく。机に並んだ缶コーヒー、絡み合ってるケーブル、何本ものボールペン。貴史は水のなかにゆらゆらと浮かぶデスクの上で、呆然とディスプレイを見つめていた。表計算のアプリケーションソフトはずっとフリーズしたままである。
貴史はデスクの引き出しを開けて、奥のほうから古い小箱を引っ張り出す。
「いいか、ほら、どうだ」
祖父の微笑みが、だんだんぼんやりとしか思い出せなくなっている。手のひらに乗せると、それは小さな容量のわりにずっしりとした重みがある。
「ほら、どうだ」
箱を開けると毒々しい色をした薄紙。めくると、変わらず冷ややかな輝きがある。
箱の中に整然と並んでいる、銃弾。
はたしてこれは本物なのだろうか? と貴史は思った。そのうちのひとつをつまみ上げ、じっと見つめる。鈍く光る、銃弾。はたしてこれは本物なのだろうか?
祖父が残した銃弾が実弾なのかどうか、貴史には確かめようがなかった。ハワイにでも行ってぶっ放してみるかとも思ったが、国外へ持ち出すリスクを冒すほどの探求心はなかった。というよりも、その宙ぶらりんな存在感こそが銃弾の最大の魅力であり、貴史は祖父の形見をそういう不思議なものとしておおまかにとらえていた。自分が所有しているというよりも、漠然とそこにあるという感じだった。
その意味では、貴史は祖父の銃弾のことを忘れてさえいた。存在を思い起こさせたのは、最近ネットに流れた海外のニュースである。
ニュースは「3Dプリンタでパーツを出力して組み立てれば、実弾を撃つことができる銃の3Dデータが公開された」と報じていた。
貴史は銃弾を箱に戻し、それを長く見つめた。いろんなものが実在感を失ってふわふわと漂っている夜のなかで、たったひとつ、新しい輪郭を与えられたものがある。貴史は持ち物を道にこぼしながら歩いてきたので、その新しいものと向き合うほかになかった。
貴史はフリーズしたPCを再起動させ、海外のアンダーグラウンドサイトからダウンロードしていたモデリングデータを呼び出した。
そして、貴史は3Dプリンタにデータを流し込む。深夜の冷え切ったオフィスに、精密機械が起動する独特のモーター音がした。
(続く)
|