
2018年1月に「ほぼ日の学校」は誕生しました。
そして、2021年の春に
「ほぼ日の學校」と改称し、
アプリになって生まれ変わります。
學校長の河野通和が、
日々の出来事や、
さまざまな人や本との出会いなど、
過ぎゆくいまを綴っていきます。
ほぼ毎週木曜日の午前8時に
メールマガジンでもお届けします。

↑登録受付は終了しました↑
2021年2月11日にこのページはリニューアルされました。
今までの「學校長だより」は以下のボタンからどうぞ。

河野通和(こうのみちかず)
1953年、岡山市生まれ。編集者。
東京大学文学部ロシア語ロシア文学科卒業。
1978年〜2008年、中央公論社および中央公論新社にて
雑誌『婦人公論』『中央公論』編集長など歴任。
2009年、日本ビジネスプレス特別編集顧問に就任。
2010年〜2017年、
新潮社にて『考える人』編集長を務める。
2017年4月に株式会社ほぼ日入社。
[ 河野が登場するコンテンツ ]
読みもの
・新しい「ほぼ日」のアートとサイエンスとライフ。
・19歳の本棚。
NO.152
森岡書店のリアリティー
「ヤマドリがひと声、ピピピーッと鳴いたその声で、山のすがたが目に浮かぶような、そんな仕事ができないものか」(うろ覚え)
作家の水上勉さんに言われたことがあります。思い返せば、その頃やたらと出版点数が増えていた各社の賑々しい新刊広告か、雑誌の盛りだくさんな目次を見ながらの会話だった気がします。1990年代半ばのことです。
「桐一葉落ちて天下の秋を知る」――などと思ったことを覚えています。
2015年5月、東京・銀座に森岡書店が誕生しました。茅場町で9年間営んでいたギャラリー兼古書店から、心機一転、銀座に引っ越してきた新生森岡書店のオープンです。「1週間に1冊の本だけを売る書店」というのがコンセプト。思い出したのが、先の水上勉さんの言葉です。

書店業界では、大型書店の出店ラッシュが一段落し、アマゾン一強時代が訪れます。その時に、あえてリアルな場を構え、販売書籍をわずか1点に絞り込み、「一室に一冊(A SINGLE ROOM WITH A SINGLE BOOK)」の小さなロゴを店の正面ウィンドーに掲げます。その思い切った決断に、多くの人が目を見張ります。
森岡書店が入居したのは、銀座1丁目にある鈴木ビルという築86年(1929年築)の古いビルの1階部分、わずか5坪のスペースです。

戦後もしばらくは木挽町(こびきちょう)と呼ばれていたあの界隈は、私が30年間勤めた出版社(当時、京橋)にも近く、とても馴染みぶかいエリアです。歌舞伎座裏から小道を抜けてきた、ひっそりと落ち着いた一画です。
周辺には、ギャラリーがいくつも入っている奥野ビル(本館が1929年、新館が1934年築)などの古いビルの“仲間”もいます。20~40年ほども前になりますが、あのあたりの静かな風情を味わいたくて、時おり散歩に出かけたものです。
1980年代のバブル期の地上げや、2008年のリーマン・ショックは、銀座にとっても危機でした。どうなることかと危ぶみました。それでも森岡書店がわざわざ移転してくるように、どこからか新しい風が吹き込まれ、おもしろい動きが巻き起こります。

「どんなに大変なときでも、夢や希望の方を見ようとするのが、銀座の街と人の特徴であり、それが受け継がれている」と、店主の森岡督行(よしゆき)さんも語ります(森岡督行『荒野の古本屋』、小学館文庫)
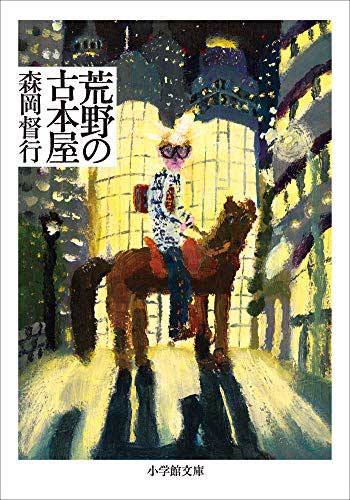
さて、森岡書店の活動ぶりです。究極のセレクトショップというだけではありません。店主が厳選した1冊の本が中核にありますが、そこから派生したさまざまな展示やイベントが開催されます。たんに本を売るのではなく、本の世界を深く探り、それを3次元に展開しています。
そして著者をはじめ、本に関わった編集者、デザイナー、カメラマン、また読者やメディアが自在に集い、交流するコミュニケーションの広がりがこの店最大の魅力です。人と人とをつなぐリアルな場としての書店です。そこで生まれたつながりは、いまや海外にも及びます。
銀座に店開きした時の最初の企画は、刺繍作家・沖潤子さんの作品集『PUNK』でした。1冊8000円の本が1週間で200冊売れ、展示された高額の作品もよく売れました。その後も写真集を置く時は、オリジナルプリントを飾ったり、料理本なら食品を売ったり、トークショーの機会を設け、1冊の本がはらむ物語や可能性を広げます。
本の世界を深掘りし、閃(ひらめ)いたアイディアを立体化して見せるのが、森岡書店のスタイルです。
7年前に、森岡さんが著した『荒野の古本屋』(晶文社)を読みました。1980年代に人気を博した『就職しないで生きるには』(同)をリバイバルさせた新しいシリーズの1冊です。
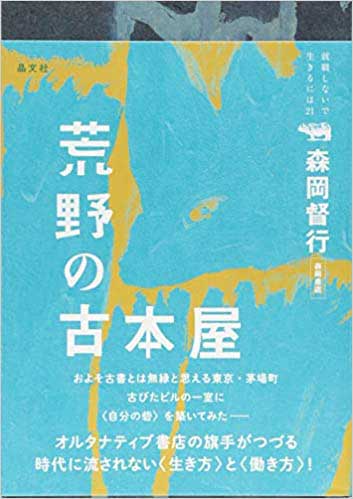
就職に背を向け、戦前に建てられた中野の古アパートに入居して、アルバイトと読書と散歩三昧の日々を過ごしていた若者が、神田神保町の老舗古書店「一誠堂書店」で8年間の修行を積み、32歳で独立します。
2006年1月、日本橋茅場町の古いビル(1927年築)の3階にある古美術店を訪れた際、ビルの佇まいに一目惚れした森岡さんは、立ち退きを考えていた店主に向かって、思わず口走ってしまいます。「ここで古本屋をはじめたい」と。
この物件との出会いを運命のように感じ、どうしてもここで古書店を開きたくなったというのです。独立開業の選択肢はそれまで念頭になかったにもかかわらず――。
こうして、茅場町でひとり立ちしたのが、2006年6月。開業資金は、貯金と退職金と借金を合わせた550万円。プラハやパリで写真集を買いつけ、半年で開業にこぎ着けます。ところが、あっという間に自転車操業すらままならない逼迫(ひっぱく)した経営状況に陥ります。
<もともと期待していたのは、路地裏に潜んでいるお店を探して訪れるようなお客さんだったとはいえ、さすがにこうもお客さんが少ないと自転車をこぐ気力が萎えてきた。店舗に向かう足取りも重くなった。往来ですれ違う人たちの一人ひとりが幸せそうに見え、自ずと私のこころは荒(すさ)んでいった。>

そんな心境の店主には、街の姿が「荒れ地」に見えます。
<アスファルトは乾いた土の大地。ビルは赤茶けた岩山。電柱は灌木(かんぼく)。すなわち、見渡すかぎりの荒れ地。風はそのあいだを土煙を巻いて、侘(わ)びしく吹き抜けた。住所はさしずめ東京都中央区無番地といったところだろう。私はそこに古本屋を開いてしまった。これでは、昔の映画のタイトルではないが、まるで「荒野の古本屋」である。>
これが書名の所以(ゆえん)です。ところが、進退窮(きわ)まったかと思えた時に、ウィーンから1本の電話が入ります。もっとも力をこめて集めてきた戦前の日本の対外宣伝誌『FRONT』に買い手がついたのです。
ここから運気が向いてきます。ビルの雰囲気を活かしたギャラリー業を始めると、“荒野”にもたくさんのお客さんがやって来ます。一誠堂書店のような職人気質の老舗の店をコンサバティブ書店と呼ぶならば、森岡書店は「本を売るだけでない本屋」――ギャラリーを併設したオルタナティブ書店と位置づけて、「お客さんとの出会い」「触れ合い」を大切に、それにはずみをつけていく仕事の基本姿勢が定まります。
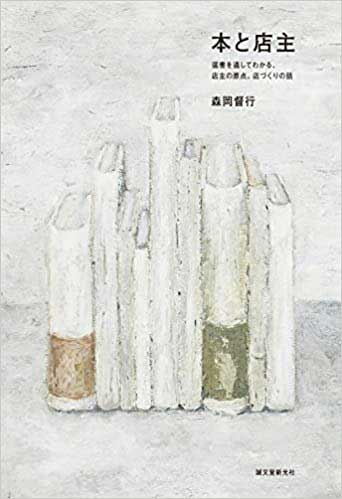
『荒野の古本屋』で驚くのは、この著者の独特の身体感覚です。大学卒業後の1年間、「本」と「散歩」に耽溺(たんでき)していた22歳の青年は、古本を求めて中野から神保町の古書店街に通うのですが、その電車の中の“身体体験”を綴ります。一見なんということもない文章ですが、如実に著者の個性を伝えています。
<ふだん、通勤で利用している人からすれば、どうってことないかもしれないが、私はこのルートから見える風景が好きで、いつもキョロキョロしてしまう。
進行方向右手には西新宿の高層ビルがよく見える。あたらしいビルが建設中のときは、その過程を確認したくなる。どんなかたち、デザインのビルが出現するのだろうか。楽しみだし、がっかりさせられることもある。>
<新宿駅の手前で中央線は山手線や埼京線と合流する。同じ方向に同じ速度で走っていると、別の線に乗っている人と目が合うことがあり、ちょっとしたご縁を感じる。>
お茶目な好奇心と想像力が、いかんなく発揮されるのが、「昭和16年体験」のくだりです。日本が太平洋戦争に突入した当時の臨場感を追体験したいと考えた森岡さんは、現代のメディアからの情報をできるかぎり遮断して、当時の新聞報道にどっぷり浸ります。1941年12月1日から15日までの朝日新聞をコピーして、昭和初期に建った古いアパートの一室で、56年後の同月同日、順を追って記事を読みます。
文庫本の解説で、酒井順子さんはこれを「過去留学」と称しますが、こんな発想を実行に移した人物を、私は誰ひとりとして知りません。
そして12月8日。朝刊紙面には、まだ同日未明の真珠湾攻撃のニュースはなく、スポーツ欄にラグビー早明戦の記事が大きく載っています。そして次ページをめくって最下段の広告欄に目をやると、「古本 誠実買入 一誠堂 東京・神田・神保町」の広告があります。
<ほかでもない古本。一九四一年一二月八日の真珠湾攻撃・太平洋戦争開戦の日に古本買います、ということだ。一誠堂とは、いまでも靖国通りに店舗を構えている一誠堂書店に違いない。(略)
この時流にあっても古本を求めて神保町を歩く人がいたのだろうか。それに朝日新聞の朝刊に広告を出すには、それなりに費用もかかるはず。私のなかで一九四一年一二月八日のイメージにラグビーと古本が追加された。>
なんと素晴らしい「過去留学」でしょう!
ましてや、それからほどなく1998年の1月初旬、朝日新聞で一誠堂書店の求人広告を見て、「応募するしかない」と決断するのです。こうして神保町の老舗古書店で刺激的な日々が始まります。偶然を引き寄せ、果敢に“巻き込まれる”森岡さんの嗅覚(きゅうかく)に感嘆します。
飾らない人柄、人懐(なつ)っこい愛嬌も、本の随所に感じられます。思わぬ出会い、ふとした会話が、おのずと次のステージをひらきます。
パリ、プラハでの古本の買いつけもそうですが、店で起こった万引き事件ですら、森岡さんの個性あっての物語です。茅場町・森岡書店の転機となったギャラリー併設のきっかけも、「ちょっとした勘違い」から生まれます。

神楽坂のカフェでお茶を飲んでいると、店主から「ちょっと」と声がかかります。振り返ると、そこに「ご婦人が立っておられ」ます。
<私は自分の名前を述べ「神保町の古本屋で働いています」などと、なぜいきなり紹介されたのだろうと思いつつも、ご挨拶をした。>
これが大きな勘違い。その方が帰ったあと、店主に言われます。「さっきのは紹介したんじゃなくて、ちょっと、じゃまだからどいてよ、と言おうとしたのよ」と。
ところが、この出会いが縁を結び、ギャラリー誕生の最初の写真展につながります。運だけではない何か不思議なプロデュース能力が、こうした縁を引き寄せているとしか思えません。
その基本にあるのは、1冊の「本」の力だと思います。人が作り、人が読み、人が伝える「ことば」の力を、この時代だからこそ強く信じたい、という森岡さんの身体感覚がそこにあるように思えます。
きょうも、神保町の一誠堂書店の前を歩きました。ここで黙々と修行を積んでいた若者の姿を、ガラス戸越しに思わず探したくなりました。

2021年2月11日
ほぼ日の學校長![]()
*「森岡書店」写真提供・森岡督行
*来週は都合により休みます。次回の配信は2月25日の予定です。
*ほぼ日の學校神田スタジオでの公開授業収録参加者を募集しています。募集授業一覧はこちらからご確認ください。(※感染防止対策を徹底した上で収録いたします。また今後の状況次第では急遽開催中止となることもございますので、ご理解の上ご応募ください。)
(また次回!)
2021-02-11-THU

