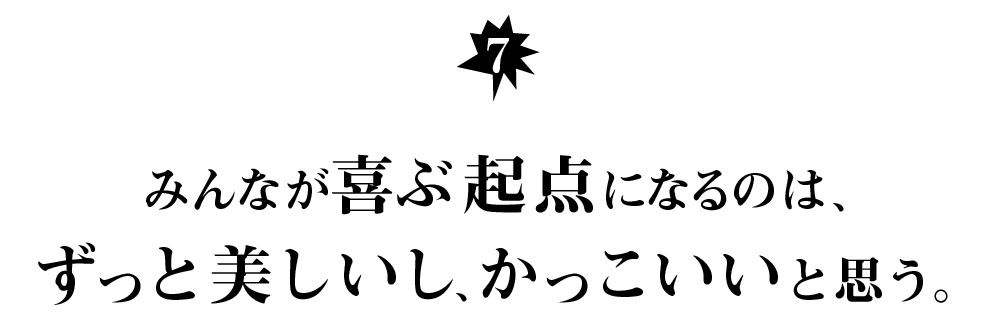「今年の藝祭に来てくださいませんか?」
東京藝術大学の学生のみなさんから
そんなご連絡をいただき、糸井重里が
「藝祭2022」のトークショーに登場しました。
控室でのおしゃべり+1時間強のトークという
短い時間でしたが、フレッシュなみなさんからの
さまざまな質問に、糸井が真剣に答えました。
これからのAI時代に、人間はどう生きたらいいのか。
「作りたい」と「売れる・売れない」の兼ね合いは。
ゲーム『MOTHER』と「母性」の関係について。
新しい手帳のアイデアを考えてみました‥‥など。
前半は、東京藝術大学の日比野克彦学長と
3名の学生というみんなでのトーク、
後半は4名の学生による糸井への質問の時間。
大学の授業のあと、学生と先生がほんとうに
話したいことを素直に話すときのような、
あたたかなやりとりになりました。
- ──
- 最後は芸術学専攻、美術解剖学研究室1年、
川目七生さんからの質問です。 - 皆さんは「ヘタウマ」って、ご存じですか?
創作活動において、技法の稚拙さがかえって
個性や味となっていることを指すことばです。
糸井さんはこの「ヘタウマ」文化を
牽引してきた方でもあります。 - 川目さんもこの「ヘタウマ」に影響を受けて、
自分の制作をなさったんですよね。

- 川目さん
- はい、わたしは原作が糸井さん、
作画が湯村輝彦さんの
『情熱のペンギンごはん』という
マンガをきっかけに「ヘタウマ」文化に触れ、
学部の卒業制作でも
その影響を受けて作品を作ったんです。 - なので「ヘタウマ」にとても興味がありまして、
80年代前後の「ヘタウマ」ということばが
生まれた背景を教えていただけたらと思いました。

- 糸井
- 正直なところ、
「ヘタウマ」というコンセプトを作ったのは、
やっぱり湯村輝彦さんなんですよ。 - そのころぼくはしょっちゅう湯村さんと
遊んでいたんですけど、あるとき、
「絵って『ウマウマ』と『ウマヘタ』と
『ヘタウマ』と『ヘタヘタ』がある」って
説明してくれたんです。
湯村さんも当時まだ若かったですけど、
「ぼくは『ヘタウマ』なのね」って言ったんです。 - 実は湯村さんって、
多摩美術大学の学生だったころに
イラストレーションで賞をもらったりしてるんですけど、
当時は和田誠さんに影響を受けた、
まったく「ヘタウマ」ではない絵を描いていたんです。 - だけど湯村さんはそのあと、黒人たちの
ソウルミュージックの世界に興味を持つわけです。
日本でいえば金糸銀糸の入った
キラキラの着流しの人たちが演歌を歌うような世界の、
アメリカ版みたいな。 - 品は良くないし、ある意味での音楽の
素養みたいなものがあるわけじゃないし、
だけどある人はそれを美しいと思うし、
ある人にはエロティックだし、っていう。 - そういう
「説明できないけどいいじゃん」
「いいからいいんだ」というものが、
ソウルミュージックの世界には、たっぷりあって。 - そこではレコードジャケットも
カルチャーとして
一緒に発展していったわけですけど、
これもまた、ものすごく絵を描ける人が
描いてるわけでもないし、
いいデザイナーやいいカメラマンが
ついてるわけでもない。
もう、街なかから出てきたような
「こういうのいいんじゃない?」が
そのままジャケットになっていたわけです。
書体も写真の撮り方もレイアウトも、
「どこから出てきたんだろう?」みたいな。 - ソウルミュージックのカルチャーには
そういう、「街のらくがき」に
近いようなものまで含めてあって、
湯村さんはそのカルチャーまるごとに
影響を受けていったわけです。 - そのとき、湯村さん自身が
「よりきれい」「より完成されてる」
「よりリアルである」といったことについて、
自分はもともと興味がなかったことに
気づいたんですね。 - そしてそのソウルミュージックの
カルチャーにあるような
「ヘタに見えるけれどもいいもの」を認めたい
と思って、自分の絵もそっちにいったんです。 - それを「ヘタウマ」と言って、
「糸井くんがそのあたりのことをなにか書いてる」
となって、ある雑誌で2人の共作で
「ヘタウマ宣言」みたいなものを書いたのが
「ヘタウマ」のもととしてあるんですね。 - それまではやっぱりアカデミズムから
価値が規定されていますから、
「ウマウマ」のなかでどちらがうまいか、
みたいな競争をしてたんです。
だけどそこに湯村さんがある種、
日本のポップアートのひとつの解釈を出した、
みたいに考えたんです。 - それで一緒に『情熱のペンギンごはん』という
本を出したわけですけど、
それをさくらももこさんや根本敬さんといった、
クラスのなかでもちょっと変わった、
だけど魅力的な絵を描くいろんな人たちが
「いいな」と思って影響を受けたという。 - その遺伝子が時代を超えて伝わって、
いまもちょっとずつのこっているわけですね。 - というのが、あなたにも
つながっているんじゃないでしょうか。
- 川目さん
- はい、知ることができて嬉しいです。
ありがとうございます。

- ──
- ‥‥と、いうわけで、
藝大生4名からの質問は以上です。
- 糸井
- もの足りないです(笑)。
- ──
- はい、司会のぼくも今日はずっと
「もうちょっと時間があれば」と
思っていました。 - なので最後に糸井さんから、学生たちに向けて
なにかメッセージをいただくことは
できますでしょうか。
今日は会場でもオンラインでも
たくさんの学生たちが見ておりますので。

- 糸井
- あの‥‥年寄りって面倒くさいもので、
悪い子にしてると「悪い子だ」って怒るんですよ。
ルールを守らないとか。
逸脱してて迷惑だとか。 - でも、いまの時代は
「みんながいい子すぎる」って
怒っているわけです。
「気概がない」とか「もっと暴れろ」とか。
でも、そういうことを言われてもめんどくさいよね。 - あまり社会を経験していない人の生き方って、
生きるのに都合のいい姿勢を選ぶのが当然ですから、
いまはみんな
「いい子にしてたほうがやれることが多いから、
いい子にしてる」ということだと思うんです。 - その意味では、みんなが「いい子だ」と
怒られる筋合いはないと思います。
いい子でいいと思う。 - ただ、その上で、自分のなかに
ちょっとしたいたずら心が生まれたときとか、
「退屈だな」と思ったときに、
どこかから何かが与えられるのを望むんじゃなく、
「退屈を打ち破ることを自分でやってみたいな」
と思うかどうか。 - それは表現に関わる場所に道を進めた人が
「やっていいよ」って言われているすごい特権だし、
ある意味、義務でもあり‥‥って言っちゃうと
気の毒だけど、そういうものだとぼくは思うんですね。 - だから、藝大のような場所にいる人たちは、
自分がそういう場所にいるのを
ときどき思い出すといいと思うんです。 - 消費者として
「なにか楽しいことをください」
「もっとおもしろいものをください」と言いながら
一生終えるのも別にいいと思うけど、
こういう場所にいるなら、それよりも
「ぼくがいま考えたこのゲーム、やってみる?」とか。 - たとえば、ジャンケンを考えた人がいたら、
そいつすごいよね。
大昔からいままで、人はずっと
グーチョキパーで何かを決めたりしてるわけだから。 - そのくらいのことを考えたことあるだろうか?
と思ったら、たぶんみんな、
ジャンケンに勝てるものなんか考えてないと思うんです。
芸術も、そういうことだらけだと思うんで。 - だからまあ、そこまで大きなことじゃなくても、
なにか自分が生んだもので
みんなをおもしろがらせることが
できたらいいよね。 - そのなかにはもしかしたら
「みんなを恐怖に巻き込んでみたい」
みたいな表現だってあるかもしれない。
まあ、そっちは行きすぎると「犯罪」があって、
そうなると罰を受けますから、
「その加減は自分でご判断ください」なんですけど。
罪になることをやってしまったら、
次のおもしろいことができなくなりますから。 - でも、とにかく
「自分がちょっと大損するだけだ」
みたいなことをやるときには、勇気を持ってほしいの。 - たとえば、やってみたいことがあるときに、
「アルバイトで稼いだ貯金が
全部なくなっちゃう」くらいのことなら、
迷惑がかかるのは自分だけじゃない。 - そんなふうに、迷惑がかかるのが
自分だけなんだったら、
「これをやると安全圏にいられなくなるかもしれない」
みたいなことでも、自己犠牲とか言わないで、
ちょっと突っ込んでったほうが、みんなが喜ぶよ。
もしかしたら迷惑になるかもしれないけど。 - やっぱりぼくは、
みんなが喜ぶことの起点になる人のほうが、
受け手として「もっとないですか」と言っているより
ずっと美しいことだと思うし、
かっこいいことだと思うんです。 - そのとき、ついついバカなことを
してしまうかもしれないけれど、
「提案するバカ」になったほうがたのしいよ。
提案するバカなら、
「しまった!」も含めて覚えられますから。
それは芸術大学の人たちには、
ぜひやってもらいたいことですね。 - そんなふうにぼくは思ってますね。
- ──
- 糸井さん、ありがとうございました。
- ということで、こちらでトークショーを
しめたいと思います。
糸井さん、登壇学生のみなさん、
聞いてくださったみなさん、
今日は本当にありがとうございました。 - 「藝祭2022」、
引き続き最後までおたのしみください。
- 会場
- (拍手)
(おしまいです。お読みいただき、ありがとうございました)
2022-11-22-TUE