
ロゴで大事なコンセプトを伝えたり、
色で心をつかんだり、
字詰めや書体で何かを予感させたり。
デザイナーさんの仕事って、
実に不思議で、すごいと思うんです。
編集者として、
なんど助けられたか、わからないし。
でもみなさん、どんなことを考えて、
デザインしているんだろう‥‥?
そこのところを、
これまで聞いたことなかったんです。
そこでたっぷり、聞いてきました。
担当は「ほぼ日」奥野です。
大島依提亜(おおしま・いであ)
栃木県生まれ。
映画のグラフィックを中心に、
展覧会広報物、ブックデザインなどを手がける。
主な仕事に、
映画
『シング・ストリート 未来へのうた』
『パターソン」『万引き家族』『サスペリア』
『アメリカン・アニマルズ』『真実』、
展覧会
「谷川俊太郎展」「ムーミン展」「高畑勲展」、
書籍
「鳥たち/よしもと ばなな」
「うれしいセーター/三國万里子」
「おたからサザエさん」
「へいわとせんそう/谷川俊太郎、Noritake」など。
- ──
- 大島さんには、石川直樹さんの連載
『世界を見に行く。』を、
書籍化していただいたことがあって。
- 大島
- あれはもう‥‥いつでしたっけ。

- ──
- 2012年です。
- 大島
- ああ、ずいぶん前なんですね。
- ──
- はい、「ほぼ日」での連載を、
いろいろあそべるおもちゃみたいな本に
仕立ててくださった手腕を、
「わあ、すごいなあ」と見ていたんです。
- 大島
- 楽しかったです。
- ──
- みんなでアイディアを出しているとき、
棚の奥のほうから、
古い世界地図を出してきたりして‥‥、
職業柄デザイナーさんとは、
よくお仕事させていただいてますが、
大島さんって、
「その部分」がぶあつく見えたんです。 - 図書館みたいな感じ‥‥といいますか。
- 大島
- とんでもないです。
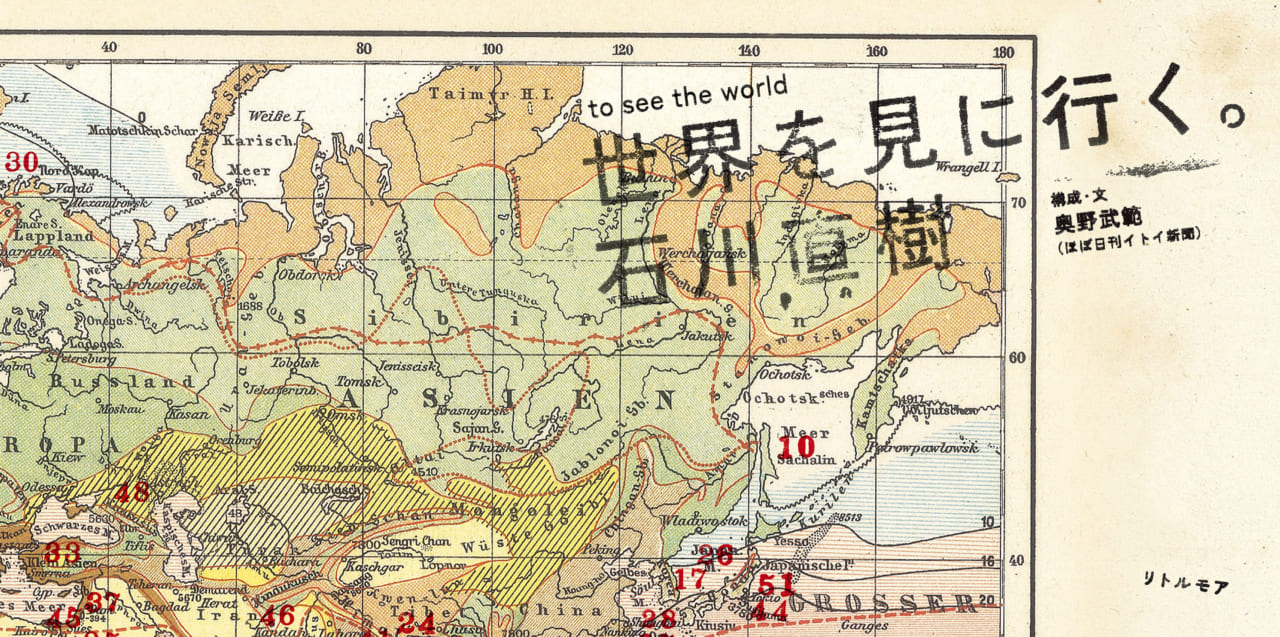
- ──
- で、本日おうかがいしましたのも。
- 大島
- ええ。
- ──
- 編集者として、デザイナーさんたちが、
どういうことを考えながら
デザインしているのか、
これまで聞いたことがなかったんです。
- 大島
- ああ、興味ありますか。
- ──
- はい。ぼくら編集の側には、
編集の意図というものが、一応あって。
- 大島
- そうですよね。
- ──
- デザイナーさんは、それを念頭に置いて
デザインしてくださるんでしょうが、
まったく予想だにしなかったデザインが、
あがってくることがあるんです。
- 大島
- はい(笑)。
- ──
- それは、まったく予想していなかった
デザインであるにも関わらず、
こちらの意図が、
ちゃんと汲まれていたりもするんです。
- 大島
- その人は優秀なデザイナーですね。
- ──
- 石川さんの『世界を見に行く。』は、
まさしく、その例でした。 - ああいう仕事をしてくださるときの
大島さんの
「あたまの中で起きているできごと」
を、知りたいなあと思いまして。
- 大島
- あたまの中。
- ──
- というのも、コンセプトというのか、
ぼくたち編集者が、
文章をこねくりまわして
ようやく表現しているようなことを、
マーク一発、
色一色で解決しちゃったりとか、
デザインとは不思議なものだなあと、
前々から、思っていたんです。
- 大島
- いやいや、
そんな鮮やかなお手並みじゃないです。 - 魔法使いでもありませんし‥‥。

- ──
- それと、もうひとつ。
- 今、デザインという言葉が指す領域と、
編集という言葉が指す領域って、
けっこう重なっている気がするんです。
- 大島
- 編集とデザインが重なる‥‥たしかに。
- ──
- 要素をあつめて方針を立て、
強調したり省略したり、並べ替えたり、
取捨選択したりして、
なにかを伝えようとしているところが。 - でも、絶対に違う部分もありますよね。
- 大島
- ありますね。
でも、その感覚は自分にもありました。 - そもそも‥‥自分のやってきたことが、
だいぶ編集っぽい気がします。
- ──
- あ、それは、どういうところが?
- 大島
- これは、映画の仕事をやっていることが
大きいと思うんですが、
映画の書籍‥‥この場合はおもに
劇場パンフレットのことですが、
それが「100ページ」を超えることって、
まずないんです。 - ようするに「全48ページ」のなかに
収めなきゃならないので、
この項目は、
あと2ページ削らないとダメですねとか、
編集とデザインが密に連携を取らないと、
本が完成しないんです。
- ──
- デザイン側がイニシアチブを執って、
編集の側に注文を出しているわけですね。
- 大島
- そういうやり方をして進めていかないと
収まり切らないので、
本来は編集領域の事柄まで、
だんだん考えるようになっていって‥‥。

- ──
- ぼくらのようなウェブの場合、
いくらでも詰め込むことができますよね。
- 大島
- ええ。
- ──
- ところが書籍や雑誌というメディアには、
「紙幅の都合」というものが
必ずあって、
そこから一文字こぼれてもダメなわけで。
- 大島
- はい。
- ──
- そこへ「収める」お手並を見ていると、
デザインというものは、
「設計」に近いのかなと思ってました。
- 大島
- 設計。
- ──
- 要素をうまく紙面に収める、という
技術的なことだけじゃなく、
手にとってもらえるような顔にする、
魅力を生むという部分も含めて。
- 大島
- なるほど、ぼくには設計という意識は、
あんまりありませんでした。 - それは、もしかしたら、ぼくの場合が、
同じデザイン職でも、
ちょっと異質だからかもしれません。
- ──
- 異質。
- 大島
- そう‥‥異質だと思うんです。
- これも映画の仕事に顕著なんですけど、
自分にとってのデザインって、
どこか「翻訳」に近いのかなあ‥‥と。
- ──
- 翻訳?
- 大島
- つまり、たとえば、海外の映画の
日本版ビジュアルをつくる際、
具体的にこれ、今やってる作品ですが、
ほとんどの部分は、
すでに、
あちらの誰かがつくったビジュアルで。

- ──
- ああ‥‥。
- 大島
- そこに邦題などを載せているわけです。
- その場合、
自分のデザインの意匠っていうものは、
どこにあるんだろうと。
- ──
- おお、なるほど。
- 大島
- そう考えると、
翻訳しているような気分になるんです。
- ──
- デザインしているというより。
- 大島
- 海外のビジュアルに
日本語を載せるときっていうのは、
ま、単純に
どのような書体にしたら、
内容との齟齬を生むことなく、
日本の人たちに
この映画を伝えることができるか‥‥。 - そういうことを、考えてるんです。
- ──
- その作業が、クリエイトというより、
トランスレートのようだ、と。
- 大島
- 手を動かしながら意識しているのは、
デザインそのものより、
翻訳的な気配りのほうが大きいです。 - もちろん、そのことを意識した結果、
もともとのデザインを、
ガラッと変える場合もあるんですが。
- ──
- つまり、変えたほうが「伝わる」と
判断したときには、変える。
- 大島
- この『アメリカン・アニマルズ』という
映画は、実話がベースになっています。
- ──
- ええ。
- 大島
- アメリカの図書館に、有名な鳥類画家
ジョン・ジェームス・オーデュボンによる
『アメリカの鳥類』
という貴重な画集が収蔵されてるんですが、
それを、
4人のアホな大学生が盗もうとする話です。
- ──
- ほおー‥‥。
- 大島
- 4人の大学生の顔の部分は、
そのオーデュボンの絵から取ってるんです。 - このビジュアルがすでに成立していたので、
自分の仕事としては、
そこに日本語のタイトルを載せた以外、
グラフィックについては、
もう‥‥ほとんど、何もしていないんです。

- ──
- でも、それもデザイン的な判断、ですよね。
「何もしない」というのも。
- 大島
- はい。
- ──
- そして、「何もしない」というのは、
デザイナーさんにとって、
むずかしい判断なのではないでしょうか。
- 大島
- そうですね。
- とくに、この映画については、
もともとのビジュアルが格好よかったんで、
それを使えるならば、
お引き受けしますって感じだったんですが。
- ──
- そうなんですね。
- 大島
- その場合、お引き受けしますと言っても、
自分のデザインは、ほぼ出番がない。
- ──
- デザインというものは、やっぱり、
まず見た目、視覚情報なんだと思うんです。 - そこで「ほぼ何もしない」という判断には、
かなりの勇気が必要なのでは。
- 大島
- だから「ぼくのデザインなんです!」とは、
言いあぐねますよね。 - だからこそ「翻訳」だと思っているんです。
そのことが、ひとつ。
- ──
- ええ。
- 大島
- それに‥‥これは言い方が難しいんですが。
- ──
- はい。
- 大島
- ぼくにとっては、
「デザイン」よりも「映画」自体のほうが、
だんぜん重要なんです。

(続きます)
2019-09-17-TUE

