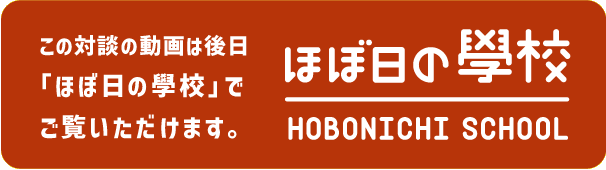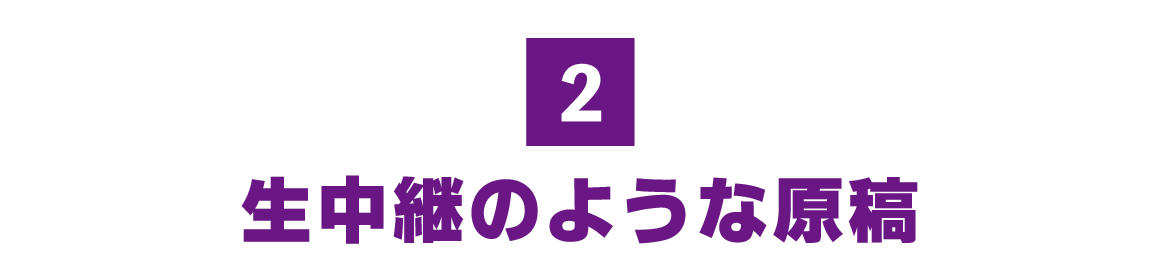スポーツジャーナリストの石田雄太さんと
糸井重里によるスペシャルトークを
「前橋ブックフェス2024」でおこないました。
アスリートへのインタビューで
スポーツファンの支持を集める石田さんが
いま、もっとも求められていることといえば、
そう! 大谷翔平選手のことばでしょう。
根っからのスポーツファンとして、
元テレビディレクターとして、
それからライターの技術を磨いた職人として、
3つの視点を持つ石田さんが、
インタビュアーの姿勢を語ってくださいました。
石田雄太(いしだゆうた)
1964年、愛知県生まれ。
青山学院大学文学部卒業後、NHKに入局し、
「サンデースポーツ」等のディレクターを務める。
1992年にフリーランスとして独立し、
執筆活動とともにスポーツ番組の構成・演出を行う。
著書に『イチロー、聖地へ』
『桑田真澄 ピッチャーズ バイブル』
『声―松坂大輔メジャー挑戦記』
『屈辱と歓喜と真実と―
“報道されなかった”王ジャパン 121日間の舞台裏』
『平成野球 30年の30人』
『イチロー・インタビューズ 激闘の軌跡 2000-2019』
『大谷翔平 野球翔年I 日本編 2013-2018』
『大谷翔平 ロングインタビュー
野球翔年 II MLB 編 2018-2024』などがある。
- 糸井
- 石田さんとは以前、
ほぼ日で雑誌『Number』の1000号を記念した
展覧会のゲストにお招きしたことはありました。
でも、ふたりでしゃべるのは今回がはじめてですね。
今日も打ち合わせをしていませんし。
- 石田
- はい、そうですよね。
今日はよろしくお願いします。

- 糸井
- 石田さんが書いたスポーツの文章は、
この会場にいるみなさんの
目にも触れることがあると思いますけど、
書き手が前に出る機会ってあまりないですよね。
- 石田
- ああ、少ないですねえ。
しゃべることは仕事でもないし
得意でもないので、
今日はお手柔らかにお願いします(笑)。
- 糸井
- ぼくはいろんな人と対談のような形で
お話をしていますけど、
「聞き手同士」で話すような機会も
じつは結構多いんですよ。
石田さんはもとから雑誌の世界にいたわけではなくて、
テレビ局のご出身なんですよね。
- 石田
- はい、そうです。
- 糸井
- テレビは後で活字にするものじゃないから、
その場で捕まえるか、逃すか、
というやりとりを見てこられたはずですよね。
石田さんにとっては
テレビの世界で育って、書き手になったことが、
じつはとても有利だったんじゃないかなあと思って。
- 石田
- ああ、なるほど。
何かを伝える仕事をするときには、
「書く」という方法と「映像」という方法、
その2種類があると思うんですよ。
ぼくの場合は書くことを望んでいましたが、
映像から入ってしまったんです。
でも結果的には、映像から入ったことによって
いくつもいいことがありましたね。
というのも、テレビの世界では
裏方のディレクターをしていました。
ところが、書き手はテレビで言うところの出演者、
つまり、インタビュアーを務めなきゃいけません。
- 糸井
- うん、うん。そうですね。
- 石田
- もともとは出演者を演出する側だったので、
こんなことを聞いてほしいなと期待しながら
裏で見ている立場だったんですよね。
映像とともに何かを伝えるなら、
ことばはできるだけ少なくしたかったんです。
映像の力って、やっぱり強いですから。
どうしても映像で表現できない情報だけを
最小限のことばで伝えるっていうのが、
テレビの考え方なんです。

- 糸井
- それって、書籍とは真逆ですよね。
- 石田
- ええ。まさに真逆でしたね。
実際、ぼくが映像の仕事をしていたときには
「活字って自分では見ているだけで、
なんでも書けるからいいよなあ」
なんてことを思っていたぐらいで。 - ところが、いざ自分が活字の世界に入ってみたら、
「映像の仕事は、映像がなければ、
ないからしょうがないじゃんって言い訳できたけど、
活字は全部を見ておかなきゃダメだ!」って。
それから、活字も大変だぞと思ったんです。
- 糸井
- ああ、そうだ。
- 石田
- 映像の強さを思い知らされていたおかげで、
ことばが映像に追いつくにはどうしたらいいだろうって
考えることができたんじゃないかなと思うんです。
きっと、そこで考えられたことが、
他の書き手とちょっと違う色を
作ってくれたのかもしれませんね。
いまだに映像の仕事もしてはいるんですけど、
映像から入って活字にきたことで、
その両方の仕事をやってきたということが、
自分の色になってくれているのかなと思います。
- 糸井
- 石田さんの歩みを簡単にまとめようとすれば、
「映像出身でライターになった人」
という話になっちゃうんですけど、
最初から映像出身の人なんていないですよね。
つまり、石田さんの場合は
NHKに就職したから映像の人になったわけで、
高校生やら大学生やらで
ドキュメンタリーを撮っているなんて人は、
ほとんどいないわけだから。
- 石田
- そうですね。
- 糸井
- なにかを取材に行って、
緊張感のある場面を映像に収める仕事なんて、
石田さんがもっと若かった頃には
そんなになかったはずなんですよ。
今だったらYouTubeのおかげで、
映像がずいぶんとカジュアルになりましたけど、
当時は大きなカメラが回っているところで
撮られていたんですもんね。
思えば、テレビカメラがある状況なんて
日本中にあんまりなかったわけですよね。
- 石田
- そうですねえ。
やっぱり、多くの人は撮られ慣れていませんでした。
ですが、じつは撮られ慣れていないほうが、
不思議なもので、本当の姿が撮れるんですね。
- 糸井
- そうかあ、なるほど!
- 石田
- 今は、どうもみんなが撮られ慣れ過ぎていて、
カメラの前でどうやって振る舞ったらいいかを
わかり過ぎちゃっているんですよ。
ドキュメンタリーとはいえども、
本当の姿を映像で捕らえるっていうのは、
むしろ難しくなってるような気がしますね。
- 糸井
- ああー、そうかぁ。
おんなじ広い紙に絵を描くにしても、
紙の枚数が限られていれば、
なにかがそこに込められますよね。
- 石田
- あ、そういうことですね。
活字にとっても、もちろん同じなんですよ。
「本当」っていうものを描き出すのが、
いろんな意味で難しくなってるなあと
ここ何年かで特に感じていますね。
- 糸井
- そのお話からすこし飛躍しますけど、
今って人工知能とかコンピューターで、
マスのデータを取っておいてから
なにがウケるかを調べて、
その結論へと持って行くようなことをしますよね。
できあがりから逆算して作ることに
みんなが慣れてきちゃっていると思うんです。
テレビ制作も、そうなりつつありますよね。
- 石田
- ええ、それはありますね。
- 糸井
- 絵コンテが先にできていて、
期待されるセリフぐらいのことは用意してあって、
そこまでの長い時間の中で、
見逃されてよかったなって思うところもある。
石田さんは活字の世界に移ったお陰で、
テレビの作り方が変わっていくのと
付き合わずに済んだんじゃないかな。

- 石田
- たしかに、いろんな選手に話を聞いていても、
ぼくの頭の中でイメージできる範疇の答えであるうちは、
やっぱりおもしろくないと思うんですね。
膨らんでいくとか、広がっていくとか、
予定調和じゃない話が出てこないと。
それにいかに食らいつけるか、
そこからこちらの想像力を膨らませて、
その話を広げていくのがおもしろいんです。
- 糸井
- ああー。
- 石田
- あるいは、選手が話しながら
ヒントを出してくれていることもあるんですよね。
すると、こういうことを聞かれたいのかなあと
予想できるんですよね。
ぼくは、インタビューをする前に
必ず設計図を書いてから臨んでいるんですけど、
インタビューがはじまったときにはそれを閉じます。
目線を外すと、負けたような気になるので。
- 糸井
- へえーっ!
- 石田
- 目線を外さないっていうことは、
取材をするときに、すごく意識していることです。
自分の書いたメモなんか見ていられませんから。
- 糸井
- そうですね。
- 石田
- インタビューの設計図は作っても、
途中で確認はできないし、しないようにしています。
設計図は一回作るけれど、そこから外れていく。
外れていきっぱなしだと
作品として困ったりすることもあるので、
どこで設計図通りに戻すか、
そういうことを考えながら話しています。
結果的に最終的に設計図通りに戻ったけれど、
あ、やっぱりここが広がったな、
あそこで広がったなとなっていくんです。
- 糸井
- ああ、表現に関わるところでは
みんなおなじようなテーマでぶち当たるし、
逃げるし、なんとかしたいと思っていますよね。
(明日につづきます)
2024-12-12-THU