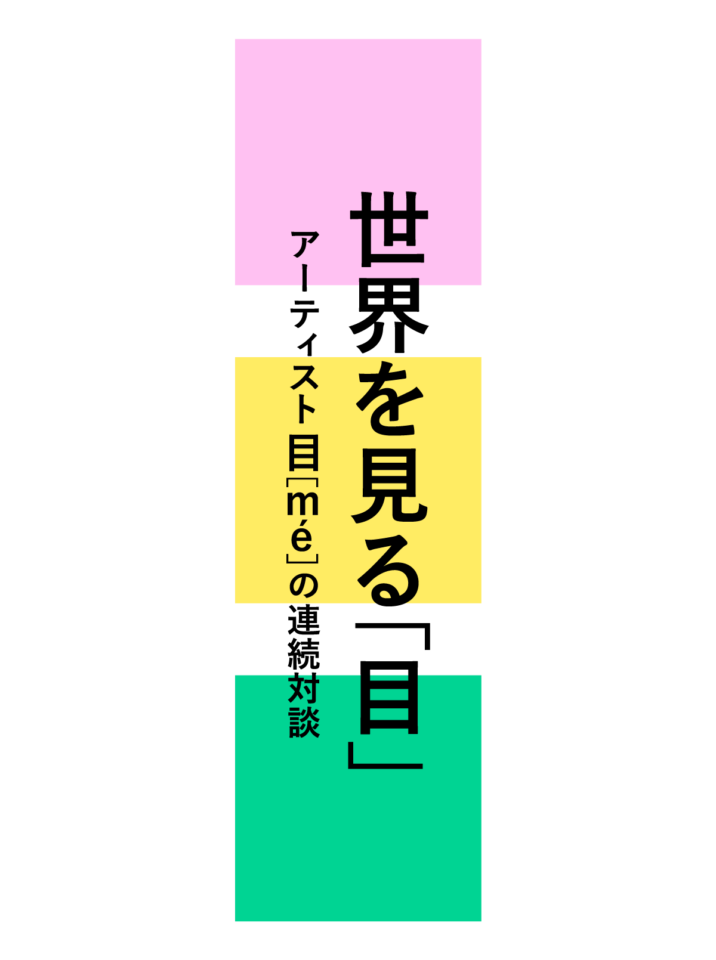
アーティストの荒神明香さん、
ディレクターの南川憲二さん、
インストーラーの増井宏文さん、
3人を中心とした
現代アートチーム目[mé]。
2020年夏、彼らは
《まさゆめ》というプロジェクトを
実施する予定でした。
東京の空に、
実在の「誰か」の顔を浮かべるというもの。
そのプロジェクトを前に、
「ほぼ日曜日」では、
街と人のつながりについて、
「見る」ことについて、
東京の風景について、
目[mé]のみなさんと、
3人のゲストを迎えたトークセッションを予定していました。
しかし、4月にはほぼ日曜日はお休みとなり、
このトークセッションは
それぞれの登壇者がオンライン上で顔を合わせ、
配信で行うことになりました。
直接会えない状況のなかで交わされた言葉たちを
ここに採録します。
- 南川
- 他者を通して「見る」活動や研究のなかで、
伊藤さんにいろんな知覚が蓄積されて、
どう変わりましたか?
次に見たいものはありますか?
- 伊藤
- 言語的にインタビューをして、
その人の感じ方を言葉で教えてもらうんですけど、
身体にかえってくることがありますよ。
インタビューした方が
目も見えず耳も聞こえない方で、
その方がなくなったとき、
ふっとその人の感じ方になったんです。
全く同じというわけではなくて、
全身がインターフェイスで、
身体のどこに字を書いてもその字が読める。
家族が帰ってきたのも廊下の振動でわかる。
全身の触覚をとおして世界を知覚するというのが、
ふっと訪れた。
身体を研究している者の弔いの仕方なのかもしれないけど。
- 南川
- 生物学の超個体みたいですね。
普段、若いアリが怠けて、老人アリが働くけど、
老人アリが死ぬと遠くにいる若いアリが
察知して働き出すっていう。
個体を越えて知覚している感じ。 - 自分たちはなぜ作品を見せてるかというと、
鑑賞者を通じてものを見たいんですよね。
- 増井
- 作品を作るプロセスでも同じで、
主体的に作れば作るほど
見えなくなってくるときがある。
そういうときには、
南川と荒神に来て見てもらって、
作品を捉え直すんです。
それは、目が別の人にあるだけで、
僕が見ているということだと思う。
- 伊藤
- そこは、
障がいのことを研究する面白さと似ていますね。
「見える」「聞こえる」がネットワーク化しているんです。
見えないから人をつかって見るのもそう。
能力を個に帰属させないで、周りの人を取り込む。
障がいって、したいことができないということだから、
みなさんそのぶん、まわりをとりこむ達人なんですよ。
- 荒神
- 私、以前聞きそびれたことがあって、
生まれつき全盲の人にとっての
幽霊はどういうものなのかが知りたい。
- 南川
- それ、伊藤さんに聞く!?
- 伊藤
- わからないですけど、
中途失明の人は怖いって言いますね。
ただ、千円札をみんなが千円だと思うのも、
幽霊を見ているようなものじゃないですか。
文化的な感じ方は生理的な知覚によらない、
ということだと思います。
- 南川
- すべてのマイノリティを含めたユートピア、
すべての人にいい状態ってあると思いますか?
たとえば階段ひとつとっても、
目の見えない人のほうが多ければ
存在しないだろうなと思うんですが、
いろんな感性の人が
共存する世界ってあると思いますか。
- 伊藤
- 難しいですね。
2つあって、
コロナウイルス以降みんなが考えている、
世界中の人が否応なくつながっているというのがひとつ。
自分が外出するかどうかが感染拡大に影響して、
それがすごく遠くの人に影響するかもしれない。
環境問題とかもだけど、
自分の行動が連鎖的につながっていく。
いいことも悪いことも含めて
自分たちは一個の生命体であるというか。 - もう1つ、
環境と生命は常に一体になっている気がします。
障がい者運動ってたとえば、
段差がある環境が自分の体にフィットしていないから、
環境と身体のギャップを埋めようというものですよね。
その結果、環境が変われば生活が変わる。
ユートピア的に止まることってなくて、
地球の進化と生命の進化は相互で、
ずっと変え合うことが続いていくんじゃないか。
そういう意味では終わりはない気がしますね。
- 南川
- 第1回のトークでも話したんですが、
荒神がコロナ以降、また面倒なことを言い出して、
眼球のパースが変わったって。
- 増井
- また言ってたの?
- 荒神
- うん。
歩いていて、パースが抜けたような気がして。
視覚的なパースだけじゃなくて
状況の見通しについてとか、
制限の向こう側になぜ行けないのかって考えると、
それは、死があるからなんですよね。
コロナ以前の日常では遠く感じていた
死の概念がにじりよってきたのかな、って思うんです。 - 境界線の向こう側が見通せてると思ったんだけど、
もっと根本的に「なぜこうやって暮らしてるの」
「なぜ満員電車で通勤してたのか」
「そもそもなにをやってたのか」って、
生死にまったくとらわれない、
人間の向こう側みたいなものの見通しが変わったような感覚。
- 南川
- その向こう側に行くとどうなるの?
- 荒神
- 向こう側からみてる視線を手に入れられるんじゃないかな。
- 伊藤
- 昔は、三途の川ってどこにでもあったんですって。
近所の川のことをみんな三途の川って呼んで、
川の向こう側にあの世がある、
というパースで昔の人は生きていたらしい。
それに似た話ですかね。
- 南川
- 淵が現れた、ってことなのかな。
伊藤さんは《まさゆめ》については
どんなふうに感じますか?
- 伊藤
- それこそ、三途の川になったらいいんじゃないかな。
顔を見るってことは、顔から見られるってことですよね。
見られるという視点を獲得できると思うと面白いですよね。
厳密にはどこを見てるかわからないという面白さもあるし、
顔の中が空洞ということも重要で、
わからないなにかがそこにあるという感覚がすると思うし。
- 増井
- 荒神が夢で見た「顔を空に浮かばせていた大人」は
自分やったんやな。
- 南川
- 顔に見返された人は、
もしかしたら見ている人を見ているのかな。
それは引き続き考えていきたい。
- 増井
- いつも僕はこういうトークに参加せず
制作現場にいるんですけど、
現場にも面白いことがいっぱいあるんです。
ものがある瞬間から急に作品として見えたり、
作品をたった2cm動かすだけでみんなが
「ワーッ!」となることもあって。
そういうのもいつか見せたいなと思いました。
- 荒神
- 目隠しして全力で走るって、
踏み出すのにすごく勇気がいる。
改めてこの状況ってどういう状況なんだろうと
別の角度から見るってすごく勇気がいると思うんですけど、
どう見ているのか、見返されているのか、
考えるのにいい時間な気がします。
まだまだずっと話していたい。
- 伊藤
- 緊急事態宣言が出た日の夜、月が明るくてきれいでしたよね。
地球のパンデミックを月が見ている感じがした。
「顔が見返す」の大規模バージョンですよね。
人類がこの視点を獲得したのは、
1960年代にアポロが月に行ったときだと思います。
地球がすごく美しくて壊れそうな存在に見えた。
そこから環境問題とか、宇宙船地球号の考え方とか、
いろんな変化があったと思います。
人間の生理的な視覚には限界があるから、
拡張ってすごく大きなインパクトを持ってる。
「限界の先の視点」がいま大切で、
《まさゆめ》はそういう問題と
リンクするプロジェクトだと思います。
(おわります)
2020-06-21-SUN
-
目 [mé]
アーティスト 荒神明香、ディレクター 南川憲二、インストーラー 増井宏文を中心とする現代アートチーム。
個々の技術や適性を活かすチーム・クリエイションのもと、特定の手法やジャンルにこだわらず展示空間や観客を含めた状況/ 導線を重視し、 果てしなく不確かな現実世界を私たちの実感に引き寄せようとする 作品を展開している。
主な作品・展覧会に「たよりない現実、この世界の在りか」(資生堂ギャラリー 2014 年)、《Elemental Detection》(さいたまトリエンナーレ 2016)、《repetitive objects》(大地の芸術祭 越後妻有アートトリエンナーレ 2018)などがある。第 28 回(2017 年度)タカシマヤ文化基金受賞。2019 年は、美術館では初の大規模個展「非常にはっきりとわからない」(千葉市美術館)が話題を呼んだ。 《まさゆめ》とは
年齢や性別、国籍を問わず世界中からひろく顔を募集し、選ばれた「実在する一人の顔」を東京の空に浮かべるプロジェクト。現代アートチーム目 [mé]のアーティストである荒神明香が中学生のときに見た夢に着想を得ている。
東京都、 公益財団法人東京都歴史文化財団 アーツカウンシル東京が主催するTokyo Tokyo FESTIVAL スペシャル13の一事業。
公式サイト
![トークセッション#02 伊藤亜紗×目[mé] 「見る」ということ 3 「見返す」視点](/n/s/wp-content/uploads/2020/06/2-3a.png)
