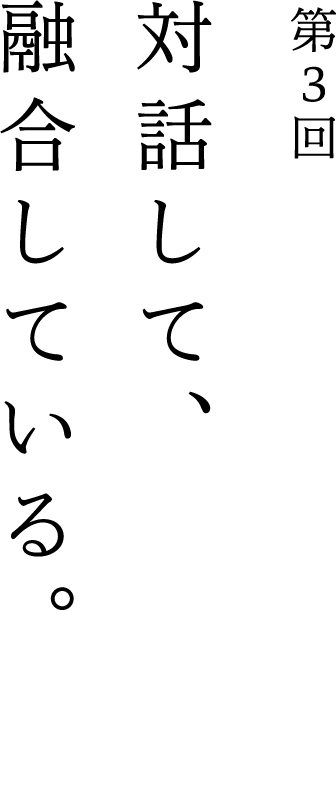- ──
- 自分は、池松さんの映画のなかでは、
『無伴奏』が好きなんです。
ご本人的には、
あの作品については、いかがですか。
- 池松
- 好きですよ。
あんまり理解されなかったですけど(笑)。
- ──
- あ、そうですか。
自分は、いちばん好きなくらいです。
- 池松
- 本当ですか。それは、うれしいです。
ぼくも、すごく好きな作品だから。
抒情‥‥っていうんでしょうかね、
ああいう物語って、
なかなか理解されないのかなあ。
自分の力不足はもちろんありますが。
- ──
- 60年代という時代って、
ある種の「あこがれ」があるんです。
自分はその時代に生まれてないけど、
社会全体が熱を帯びていて、
なにより、
若者たちがすごく真剣に生きていて。
- 池松
- ええ。そこにはたぶん、たくさんの‥‥
それこそ、たくさんの
「無名の物語」があったでしょうね。
- ──
- で、池松さんが演じていた大学生の
ちぎれるような懸命さが、
そういう時代に、
すごくぴったりあっていると思って。
こういう若者きっといただろうなと、
そんな気持ちになりました。
- 池松
- ぼくも
あの時代を生きたわけではないし、
知らないことばかりだけれど、
演じていると、
自分の過去に触れるような瞬間が、
何度か、あったんです。
- ──
- あ、そうですか。
- 池松
- 自分の記憶と結びつくような‥‥
それこそ、
うまく言葉にできないんですけど。
なんとなく、手触りを知っている、
においを嗅いだことのある、
そういう記憶に触れる映画でした。
- ──
- 演じるに際しては、
いまみたいな「個人的な経験」を
手がかりにすることも?
- 池松
- そうですね。ありますね。
ほかの俳優がどうやっているのかは
知らないんですけど、
自分の場合は、ある記憶とか感覚‥‥
たとえば、
この場面でこのセリフを言うには、
小学校のころの、
あの夕暮れの放課後に見た気がする、
みたいな感覚。
- ──
- ええ。
- 池松
- それさえあればやれると思ってます。
逆に、自分のなかをたぐっても、
何の手がかりもない、
ちょっとわからないという役は、
自分がやるべきではないし、
そもそもやれないと思っていますね。
- ──
- 演じるって、どういう感覚ですか。
- 池松
- 完全に自分に引き寄せるんじゃなく、
反対に、
その役になり切るのもちがうんです。
自分自身と役との間に、
まったく新しい人間をつくるような、
自分とキャラクターが
対話した上で、融合するような‥‥。
- ──
- はー‥‥。
- 池松
- そういう感覚があります。
2時間なら2時間の映画が終わった、
その時点でかたどられる何かを、
自分は、
つかもうとしているんだと思います。
- ──
- あ、最初から、
その人がいるわけではないんですか。
- 池松
- はい。
- ──
- それは、徐々に、生まれてくる。
- 池松
- ええ。
- ──
- それが「演じる」ということ。
池松さんにとっての。
- 池松
- そう、ですね。
- ──
- ぼくたちは、
池松さんとキャラクターの中間点に、
新たに生まれた人間を見ている。
またぜんぶ、見返したくなりました。
- 池松
- 本当ですか(笑)。
- ──
- それを知ったら、もう一回ぜんぶ。
- 池松
- 原作のある作品もたくさんあるので、
作品によっては、
キャラクターに寄っていったり、
あるいは逆に、
自分自身に近かったりしていますが。
- ──
- 池松さんには
他の誰かになりたいという願望って、
ありますか?
- 池松
- ん‥‥1日くらいだったら、
ブラピになってみたいとかあるけど。
- ──
- 尾崎豊さんにはなってましたけどね。
- 池松
- ですね(笑)。映画のなかで。
ただ、誰かになったところで
自分自身は変えられないですもんね。
自分の嫌なところって、
もう何百個も何千個もありますけど。
- ──
- あ、そうですか。
- 池松
- でも、そういうことを受け入れずに
生きていくことって、
人間に‥‥
少なくとも俳優にできるんですかね。
むしろ、自分の嫌なところさえも
受け入れて、
武器にしていくくらいじゃなければ、
太刀打ちできないと思う。
- ──
- 誰に?
- 池松
- いや、映画というものに。

<つづきます>
2019-09-28-SAT