

人生の終わりの時間を自宅ですごす人びとのもとへ、
通う医師がいます。
その医療行為は
「在宅医療」「訪問診療」と呼ばれます。
これまで400人以上の、
自宅で死を迎えようとする人びとに寄り添った
小堀鷗一郎先生に、
糸井重里がお話をうかがいます。
通う医師がいます。
その医療行為は
「在宅医療」「訪問診療」と呼ばれます。
これまで400人以上の、
自宅で死を迎えようとする人びとに寄り添った
小堀鷗一郎先生に、
糸井重里がお話をうかがいます。
(C) HOBO NIKKAN ITOI SHINBUN
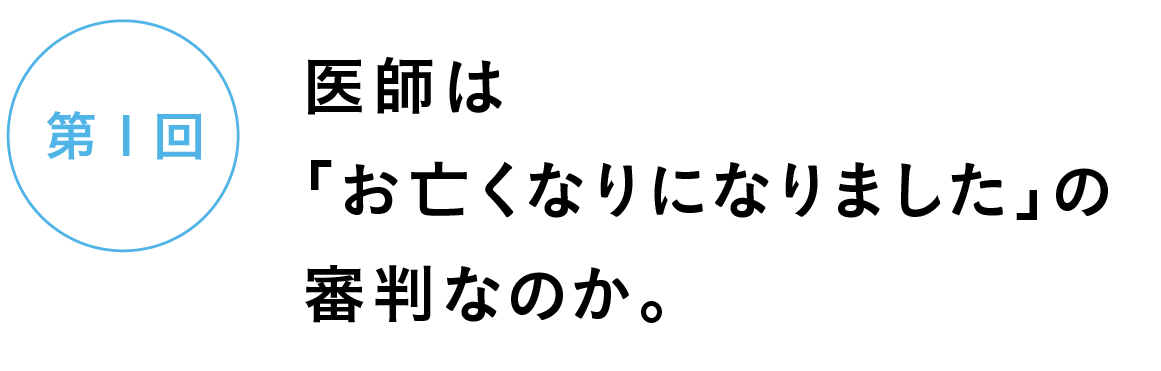

- 糸井
- 今日は暑い中ありがとうございます。
- 小堀
- こちらこそありがとうございます。
ぼくは10分ぐらいしゃべると、
声がおかしくなるんですよ。
- 糸井
- それは、かれるんでしょうか。
- 小堀
- そう。もともとは黙って手術をしてた人間だから、
しゃべる生活には慣れてないんです。
仕事がものすごく混んだときなんか、
夕方には声が出なくなります。
- 糸井
- いまのこの時間も、本当だったら
診療をしてらっしゃるときですよね。
- 小堀
- いえ、訪問診療のない日が
週にいちどはあるんで、今日は大丈夫です。
- 糸井
- 貴重な日にありがとうございます。
先生の御本を読んで、
ドキュメンタリーも拝見しました。
医師である先生が「臨終の場」から
外に出てしまうシーンがあって、
やけに心に残ってるんです。
- 小堀
- ああ。
- 糸井
- お医者さんというのは、
患者の死ぬ瞬間を確認して
「お亡くなりになりました」とおっしゃるのが
普通だと思っていたので。
- 小堀
- ぼくも以前は
「その場から座を外す」なんてことを
考えもしない人生を送っていました。
こういう生活(訪問診療)は14年ほど前、
まったくのゼロからはじめたのでね。
あの「外に出る」のはつまり、
この道の先達がやってきたことなんです。
- 糸井
- ああ、そうなんですか。

- 小堀
- ある在宅診療の先生の活動記に、
こんな記述があるんです。
「臨終の場で、席を外しますといって
マンションの階段の下でナースと待った」
ってね。
これを読んだ当時、ぼくも「え!」と驚きました。
- 糸井
- わざわざお医者さんが外に出るんですものね。
- 小堀
- おっしゃるとおり、本来、
医者は臨終には立ちあうものです。
けれども、外に出て待つ先生がいるんだと知って、
「ああ、たしかにそれはいい」と思いました。
ぼくはこれまでたくさんの方を
看取っているし、
死亡診断書もずいぶん書きました。
まず前提として、ぼくは常日頃、患者さんに
「夜中は行かないよ」と言っています。
そういうこともあって、実際にぼくが
息を引き取る場面にいたのは数名だけ。
必ずぼくが死に立ちあわなくてはならない、
というものではありません。
みなさんに説明すると、
たしかにそれで通るんですよ。
そういうことも、先達を真似てるだけなんです。
亡くなるときにぼくが立ちあった「例外」は、
奥さまが認知症で
ご主人が亡くなることがわからなかった場合。
そしてもうひとつはご家族が
知的障害の息子さんだけの場合でした。
彼に「手を握っててよ」と伝えても、
やっぱり握ってるだけになる。
お母さんが死ぬということがわからない。
だから息を引き取るまでの数時間、
ぼくは彼といっしょにいました。
そういう数例を除いては、席を外しています。
- 糸井
- では、その場に立ちあうことのほうが
めずらしいんですね。
- 小堀
- はい。
数年前から真似て、
そうやっているだけです。

- 糸井
- ぼくにとってあのシーンは、
感じるものが大きかったです。
- 小堀
- それはぼくも、
そう思って、やってるんです。
- 糸井
- お医者さんは、生と死の真ん中で
「審判」のように存在しているものだ、
ということに慣れていました。
考えてみれば「死」は
お医者さんのものではありませんよね。
患者が亡くなるときに外に出る先生を見て、
「この先生はそこのところを考えてたんだ」
なんて思いまして。

- 小堀
- ぼくは昔、糸井さんがいまおっしゃったような
医者の生活をしていました。
とくに若い時分は、自分が主治医じゃない場合でも、
当直してたら、
患者が亡くなる間際には
病室に行かなきゃいけなかった。
我々はよく
「お亡くなりになりました」と言いますけど、
ぼくはいろいろ言うのは嫌だから、
たいてい「どうも」にしていました。
「どうも」と言うと、その雰囲気で察して
「あっ」と泣き崩れる人もいる。
それが普通で、常識でした。
- 糸井
- はい。
- 小堀
- 先輩たちからは
「とにかく慌てて言うな」と教わりました。
亡くなったと判断してもそのあとすぐ
「おお」なんていって、
大きな息をしたりすることがある。
そんなことになれば、
医者として、つまり、糸井さんがおっしゃるところの
「審判」の権威が失墜します。
- 糸井
- そうですよね。
- 小堀
- 「亡くなられました」と言ったとたん
モゾモゾ動いたりされてもいけない。
当直の夜なんかは知らない患者さんですよ、
うんと時間をかせいでね、
もう聞こえない心臓の音を聞いて、
充分大丈夫だなと思ってから「どうも」と言う、
そういうことをずっと積み重ねてきました。
ただね、それを
望んでいる方々もたくさんいる、
という現実を
忘れちゃいけないです。
- 糸井
- そうでしょうね、そうだと思います。
- 小堀
- 医者が最期まで看る。
みなさんそれを期待します。
- 糸井
- ドキュメンタリーでは、
娘さんがお父さんの喉をさわって最期を知る、
という部分がありましたが‥‥。

(C)NHK
- 小堀
- でも、病院では違います。
最後に医師が馬乗りになって心臓マッサージし、
さらにぼくたちは、心臓に直接
ボスミンというアドレナリンを注射しました。
そうするとちょっと脈拍が出るんですよ。
- 糸井
- 波形としてあらわれる。
- 小堀
- ええ。
当時はそれが常識で、
それをやらなきゃ冷たい医者だと言われました。
でも、いまでもそうなんです。
一般の傾向からすれば、
「最期まで手を尽くしてくださった」というのは、
つまりはそういうことです。
それが多数派だということは、
忘れてはいけない事実です。
だからこそ世の中では「病院死」が多い。
変わってはきましたが、在宅の死を望む方は少ない。
我々のような在宅診療に関わる人間を
知っていただくという問題と、
世の中一般のみなさんが
死をそう捉えているということは、
別のことだと思っています。
病院死を望むのは日本だけではありません。
世界じゅうで、同じような傾向がみられます。
(明日につづきます)
2019-09-19-THU
小堀鷗一郎医師と在宅医療チームに密着した
200日の記録
200日の記録

(C)NHK
小堀先生と堀ノ内病院の在宅医療チームの活動を追ったドキュメンタリー映画です。
2018年にNHKBS1スペシャルで放映され
「日本医学ジャーナリスト協会賞映像部門大賞」および
「放送人グランプリ奨励賞」を受賞した番組が、
再編集のうえ映画化されました。
高齢化社会が進み、多死時代が訪れつつある現在、
家で死を迎える「在宅死」への関心が高まっています。
しかし、経済力や人間関係の状況はそれぞれ。
人生の最期に「理想は何か」という問題が、
現実とともに立ちはだかります。
やがては誰もに訪れる死にひとつひとつ寄り添い、
奔走してきた小堀先生の姿を通して、
見えてくることがあるかもしれません。
下村幸子監督は、単独でカメラを回し、
ノーナレーションで映像をつなぐ編集で、
全編110分を息もつかせぬような作品に
しあげています。
9月21日(土)より
渋谷シアター・イメージフォーラムほか全国公開。
『死を生きた人びと
訪問診療医と355人の患者』
小堀鷗一郎 著/みすず書房 発行
訪問診療医と355人の患者』

さまざまな死の記録を綴った書。
2019年第67回エッセイスト・クラブ賞受賞。
いくつもの事例が実感したままに語られ、
在宅医療の現状が浮びあがります。
映画とあわせて、ぜひお読みください。
『いのちの終いかた
「在宅看取り」一年の記録』
下村幸子 著/NHK出版 発行
「在宅看取り」一年の記録』

下村幸子さんが執筆したノンフィクション。
小堀先生の訪問治療チームの活動をはじめ、
ドキュメンタリーに登場する家族の
「その後の日々」なども描かれています。
(C) HOBO NIKKAN ITOI SHINBUN




