




谷崎潤一郎の初期短編である「恐怖」は
主人公の語り手が
「鉄道病」という奇ッ怪な病気に罹ってしまう話だ。
「鉄道病」などというと、
熱心な鉄道マニアの類を連想されるかもしれないが、
谷崎の描く「鉄道病」は
より肉体的・精神的に深刻な症状を呈する、
文字どおりの「病」であった。
鉄道病。
それが、どのようなものかは作品の冒頭に描かれる。
「友達のN──さんの話に依ると、私の此の病気──ほんとうに今想い出しても嫌な、不愉快な、そうして忌ま忌ましい、馬鹿馬鹿しい此の病気は、Eisenbahnkrankheit(鉄道病)と名づける神経病の一種だろうと云う。(‥‥中略‥‥)汽車に乗り込むや否や、ピーと汽笛が鳴って車輪ががたん、がたんと動き出すか出さないうちに、私の体中(からだ)に瀰漫(びまん)して居る血管の脈搏(みゃくはく)は、さながら強烈なアルコールの刺戟を受けたときの如く、一挙の脳天へ向かって奔騰し始め、冷や汗がだくだくと肌に湧いて、手足が悪寒(おかん)に襲われたように顫(ふる)えて来る。(‥‥中略‥‥)『誰か己を助けてくれェ!己は今脳充血を起こして死にそうなんだ。』私は蒼い顔をして、断末魔のような忙(せわ)しない息づかいをしつつ、心の中でこう叫んでみる。(‥‥中略‥‥)アワヤ進行中の扉を開けて飛び降りをしそうになったり、夢中で非常報知器へ手をかけそうになったりする。それでもどうにか斯(こ)うにか次の停車場まで持ち堪(こた)えて、這々(ほうほう)の体(てい)でプラットフォームから改札口へ歩いていく自分の姿の哀れさみじめさ。戸外へ出れば、おかしい程即座に動悸が静まって、不安の影が一枚一枚と剥がされて了(しま)う。私の此の病気は、もちろん汽車へ乗って居る時ばかりとは限らない。電車、自動車、劇場──凡(すべ)て、物に驚き易くなった神経を脅迫するに足る刺戟の強い運動、色彩、雑沓に遭遇すれば、いついかなる処でも突発するのを常とした」
はじめてこの作品を読んだとき、わたしは、
「鉄道病」などどいうものは、谷崎の創作なのだろうと嗤(わら)った。
荒唐無稽も甚だしい、病、病人を冒涜しているとさえ、思った。
なぜなら、鉄道に乗るというごく日常的な行為によって
「体中(からだ)に瀰漫(びまん)して居る血管の脈搏(みゃくはく)は、さながら強烈なアルコールの刺戟を受けたときの如く、一挙の脳天へ向かって奔騰し始め、冷や汗がだくだくと肌に湧いて、手足が悪寒(おかん)に襲われたように顫(ふる)えて来る」
という身体的反応を来すことなどありえないと思ったのだ。
わたしは、白けた気分で本をポンと放り出し、
この奇妙な短編のことは、ながらく忘れ去ることになった。
数年後、わたし自身が、当の「鉄道病」に冒されるまでは。

私見によれば、「鉄道病」とは、つまり、
今でいう「パニック障害」のことではないかと思われる。
それは、鉄道やエレベーター、混み合うバスの中などで
にわかに発症する。
具体的には、動悸が激しくなり、
このままでは死んでしまうという強い恐怖にとらわれる。
狭い空間の「内部」から今すぐ逃げ出して「外部」へ出、
思い切り息を吸い込みたい。
そういう激しい衝動に、駆られる。
極端な閉所恐怖症‥‥と言えば、実際に近いだろうか。
そう、わたしは、谷崎が「恐怖」で描いた「鉄道病」、
「パニック障害」に冒されてしまったのだ。
そうしてはじめて、
パニック障害とは「内部の病」であると思い知った。
すなわち、「内部」は、正体不明の恐怖をもらたし、
「外部」は、母のような安心を与えてくれるのだ。
しかし、ここで注意したいのは
「外部」もまた「別の内部」にすぎないという逆説。
電車という「内部」から這い出しても、
そこは「駅舎」という「別の内部」へと
直ちに、貌(かお)つきを変えてしまうのである。
「内部A」から「外部」に出たとしても、
そこは、姿形を変えた「内部B」でしかない恐怖。
その絶望的なループは、
宇宙空間にでも飛び出さないかぎり、永遠に続いてゆく。
つまり、パニック障害のわたしにとって、
「外部」とは、どこかにある「実在」では、ありえない。
それは「内部から出るプロセスそのもの」なのだ。
そして、パニック障害の発作を抑える「外部」とは、
「内部B」ではなく、
「内部Aから出るという行為それ自体」なのである。
* * * * *
谷崎は、不規則な生活を送っていたために、
「鉄道病」にかかったとされているが、
わたしの場合は、少々、事情がちがっていた。
地下鉄に乗っていて、たまたま人身事故に遭遇してしまい、
一時間ほど車内(紛うかたなき内部!)に閉じ込められた。
そのとき、はじめて、
上記のような発作──軽症だったが──に、襲われたのだ。
以後、毎回というわけではないものの、
時どき、電車に乗っていると
パニック障害による発作を発症するようになった。
そうした体験から読み直してみると、
谷崎の「鉄道病」の描写がいかにもリアルなので、
「恐怖」という小説は、おそらく、
谷崎自身の実体験を描いたものだとの確信を得た。
罹ったものにしかわからない恐怖が、
行間に、にじみ出ているように感じたからである。

ただし、谷崎の「鉄道病」と
わたしのパニック障害とでは、さまざま、異なる点がある。
まず、(当時、京都在住だった)谷崎は、ある用事で
どうしても電車で大阪まで出かけなければならなくなるが、
「鉄道病」に見舞われ、なかなか乗車できない。
そこでウイスキーを購入し、酔った勢いで気を紛らわせて、
パニック症状をごまかそうとする。
しかしながら、谷崎の努力は、敢え無く水泡に帰す。
アルコールの力くらいでは
パニック症状に打ち克つことは、できなかったのだ。
わたしに、そこまで追い詰められた経験は、ない。
酒にすがりたくなるという、
谷崎の切羽詰まった気持ちは痛いほどわかったが。
ふたつめのちがいは、谷崎が車中で席に腰掛けるより
吊り革にぶら下がっているほうが
「いくらか運命の手を弛められて居るように感じる」
と描写する点である。
わたしの場合はまったく逆。
座席に座れたほうが断然、精神が落ち着くのだった。
さて、小説の結末はこうである。
ウイスキーの効果もなく、乗車できずにいた谷崎は、
偶然、友人のK氏と出くわす。
友人は、谷崎に、しきりに鉄道への乗車をすすめる。
しかたなく車内に足を踏み入れた谷崎は、
吊り革にぶら下がったまま、ウイスキーをあおる。
それまで、なんの効き目もなかったそれらの行為が、
このときは、有効となった。
そして、
「ひょッとしたら、無事に大阪へ着けるかも知れないという安心が、其の時漸く私の胸に芽ざした」
という、小説のエンディングへと続いていく。
そもそも、冒頭の
「ほんとうに今想い出しても嫌な、不愉快な、そうして忌ま忌ましい、馬鹿馬鹿しい此の病気」
という記述からして、
谷崎が「恐怖」を書いたのは、病気が快復したあとのようだ。
谷崎の「鉄道病」は、治癒したのである。
思うに、重要だったのは、
「私=谷崎」が「ひとりではなかった」という点だと思う。
K氏という信頼できる友人が、そばにいてくれたおかげで、
「鉄道病=パニック障害」の発作に、襲われずにすんだ。
そしてそのことが、「鉄道病」治癒へのきっかけとなった。
なぜそう思うかというと、
同じような経験が、わたしにもあるのだ。
今でこそわたしは
電車にもエレベーターにも乗れるようになっているが、
快復の過程で、興味深い経験をしている。
それは、以下のような経験である。
あるとき、尊敬するW大学のT教授と電車に乗り込んだ。
思い返せば、そこは、
当時のわたしにとって「最難関」の「混雑した電車」だった。
にもかかわらず、T教授がそばにいてくれたこと、
おそらく、そのことが大きな理由で
パニック障害の発作に見舞われなかったのである。
信頼のおける人物がいてくれる、という安心感が、
「鉄道病」=「内部の病」を克復して、
精神の通気性を高め、わたしの呼吸を楽にし、
「外部」へと、心の扉を開いてくれたのだと思う。
医学的には、なんら根拠のない解釈かもしれない。
しかし、患者としての経験から、
わたし自身は、鉄道病について、パニック障害について、
以上のように、感じている。
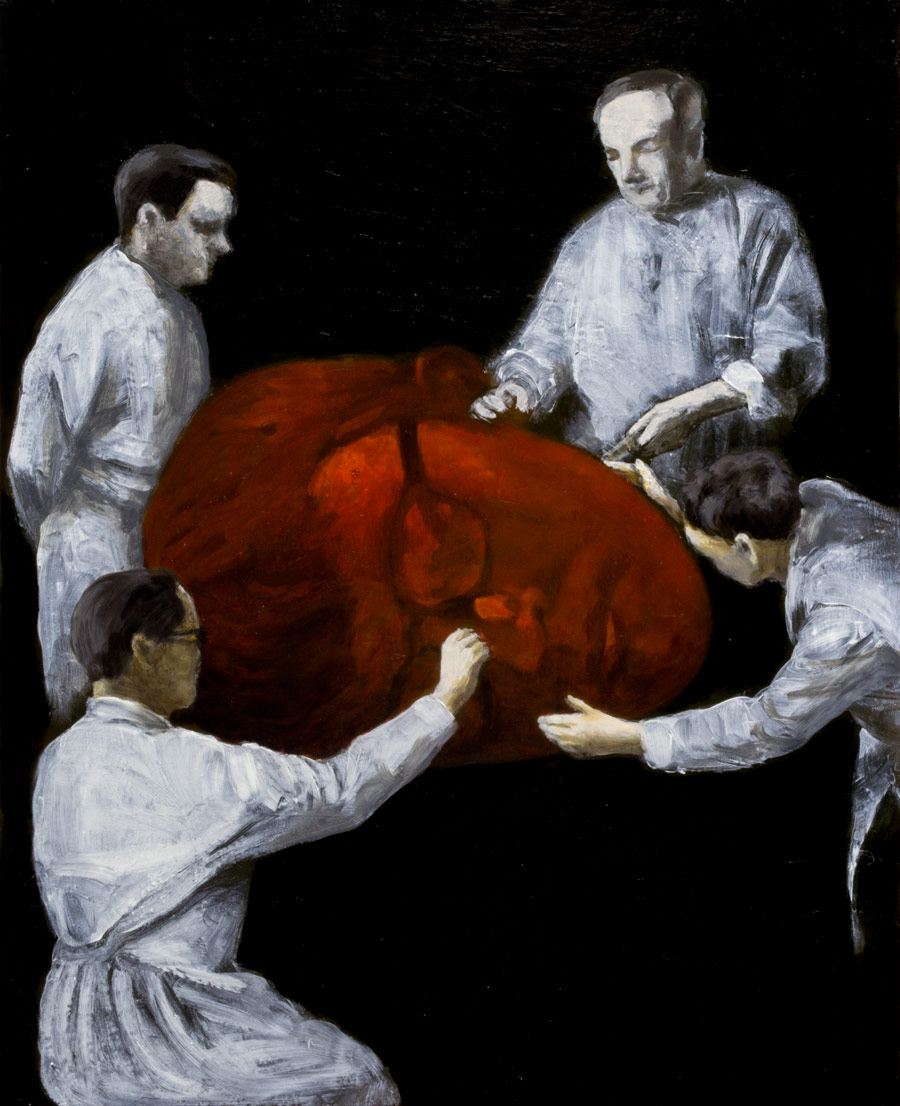
<次回をおたのしみに>
2016-06-17-FRI