

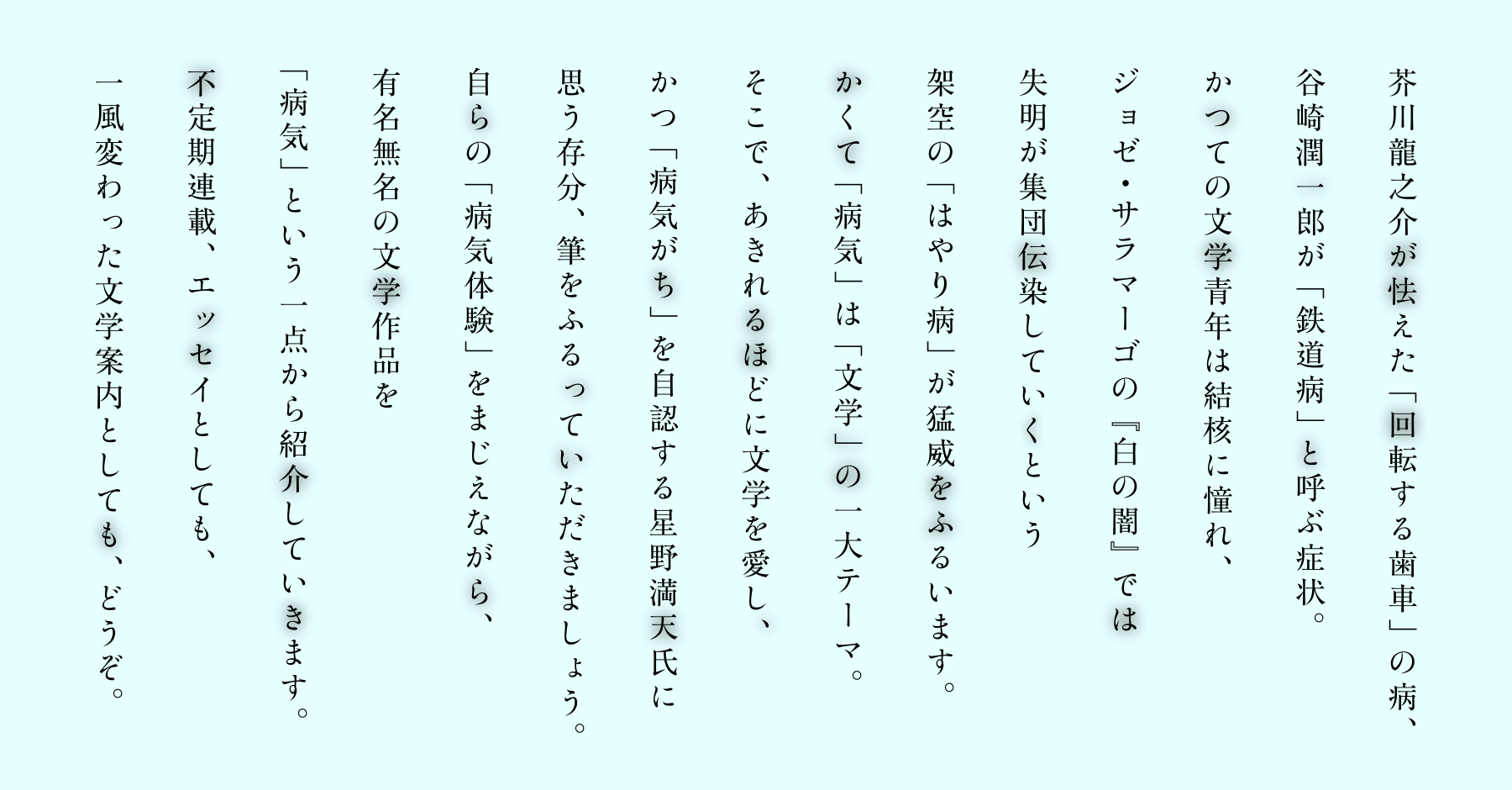



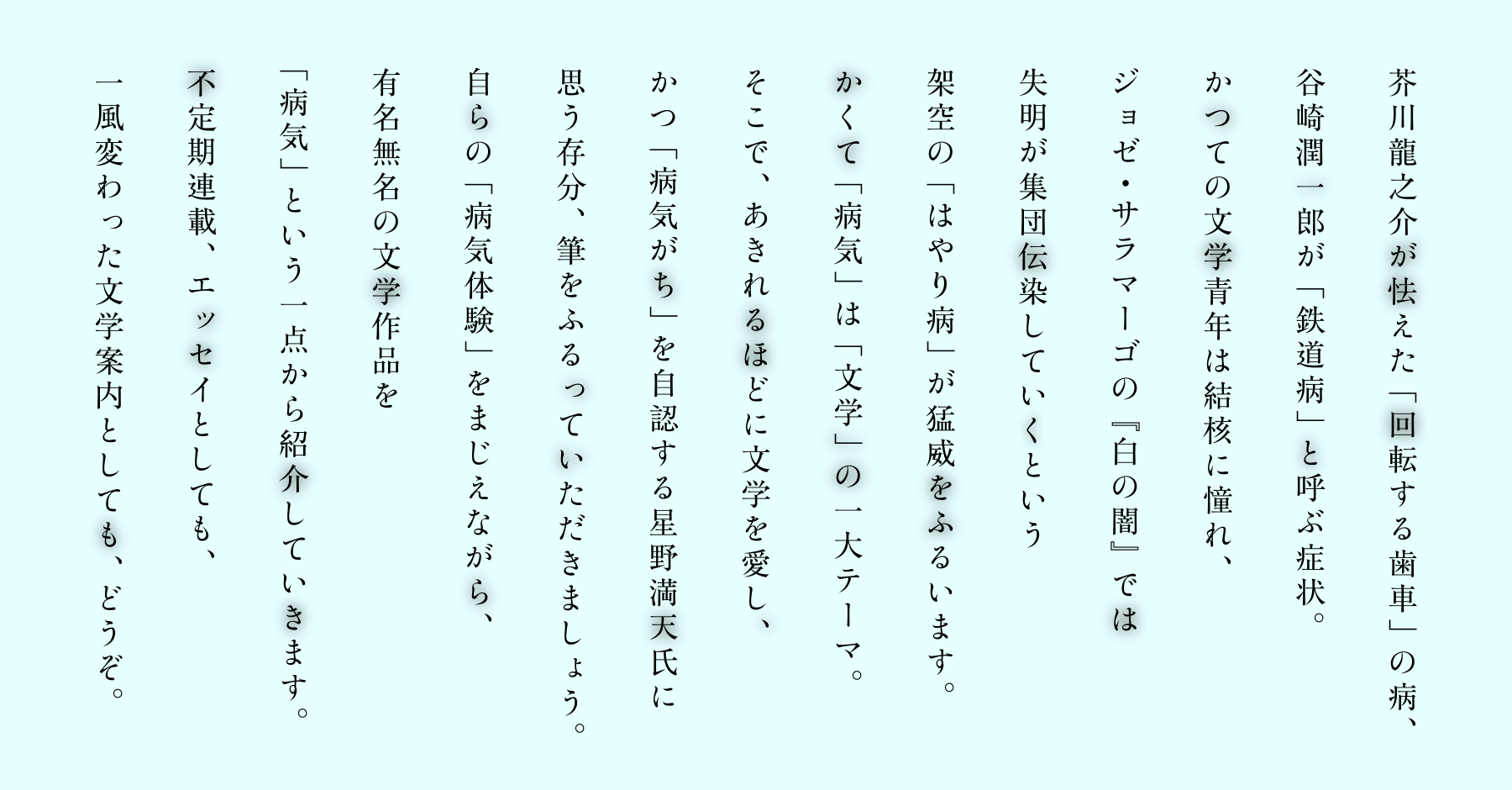


1963年生。東京大学教養学科卒業。
文学好き、散歩好き、病気がち。
大学卒業後、国際交流基金の職員となる。
のち独立、現在はフリーライター。
これまで発表した企画に
「散歩の賜物」「日本文学の中の韓国」
「谷崎潤一郎の『痴人の愛』に登場する大森界隈」
「星飛雄馬は「巨人の星」となったのか」
など。
現在、取り組んでいるのは、
「宮部みゆき」と「小津安二郎」と「文学散歩」。

室生犀星(むろう・さいせい、1889-1962)は
「ふるさとは遠きにありて思ふもの/そして悲しくうたふもの」
の詩で有名な、金沢出身の詩人・小説家である。
この作家は、胃潰瘍による入院を経験しており、
そのときのことを作品に書いている。
「黄と灰色の問答」という短編小説が、それである。
胃潰瘍だから、当然、胃の苦痛が描かれるのだが、
わたしの印象に残ったのは、別の箇所だ。
それは「排泄障害」である。
排泄障害が胃潰瘍の症状のひとつなのかどうか、
わたしにはわからない。
しかし、とにかく、入院中の犀星は、
排尿と排便、とりわけ前者に苦労しているのだ。
苦労している、というと、
犀星の苦しみを表すのには不十分であろうと思う。
なにしろ、深夜、尿意をもよおしてベッドから出、
(たぶん病室に設置された)便器へ向かうと、
たちまち尿意が消えうせ一滴たりとも出てこない。
そのような状態が一晩中続くというのだから、
事態は深刻である。
病室は建物の3階にあるのだが、
ベッドからわずか2メートル半のところに窓がある。
苦しむ犀星は
そこから飛び下りれば楽になれる‥‥とまで考える。
排泄障害によって、自殺まで考えてしまうのである。
「たつた二メートル半で窓わくの硝子戸がらくに開くのである。彼はこんなふうに窓といふものと自分とをむすびつけて、考へたことが今までになかつた。彼は寝台から下りて便通があるやうでない苦痛状態からまたもとの寝台に上り、上るとすぐもよほしてまた下りて行つた。(中略)水を呑むとまた小水をもよほし、小水をもよほしても容易に出るものではない、彼は無念無想といふことを考へ出してみたが、小水はちびつとも出なかつた。小便の出ないといふことはこんなに苦しいことなのか、そしてまた同時に便通もぴたつと止まつたきり、うしろも前も通じるものがなかつた」
小説のなかでは、
やがて、親切な看護婦(看護師)さんに協力してもらい、
懐炉で膀胱をあたため、
なんとか、わずかばかりの尿を排出することに成功する。
非常に説得力を感じる。
排泄障害の苦しみが、
作家の経験にもとづいて描かれているからだろう。
この小さな小説は、犀星の数ある作品のなかでは、
必ずしも「傑作」とは言えないかもしれない。
しかし、わたしにとっては、
排泄障害の苦悩を描いた貴重な作品なのである。
なぜなら(例によって)わたしも、
かつて、ひどい便秘に悩まされた経験があるからだ。
便秘というと単に「排便のない状態」を指すだけの
ごくシンプルな症状であって、
便意をもよおすまで放っておけばいい‥‥
くらいに考える人も少なくないのではないだろうか。
じつは、わたし自身も
「あの便秘」に苦しめられるようになるまでは、
その程度の認識しか持っていなかった。
実際は、そんな悠長な話ではないのだ。

いまとなっては忘れてしまったのだが、
当時のわたしは、何らかの薬を常用しており、
その副作用で便秘が深刻化していた。
健康人なら、毎日「快便」があるのだろうが、
そのときのわたしは
一週間に一度あるかないか‥‥という有り様。
思い出すままに、
なるべく差し支えのない表現で、
その当時の「状況」を書き出してみたいと思う。
まず犀星同様、最初は(およそ一週間ぶりに)
いくらかの便意をもよおす。
そこでトイレに駆け込み、排便をこころみる。
ところが、いざ‥‥という段になって
便意そのものが、ウン散霧消してしまうのだ。
びろうな話で、はなはだ恐縮ではあるが、
出口付近まで下りてきたものが、
そこでピタリと停止してしまうのである‥‥。
これは、通常なら「ありえない状態」である。
そんなところでストップ、
文字どおりウンともスンとも言わなくなってしまう。
その後は、少なくとも半時間くらいかけて
「次なる便意」をもよおすよう、
狭くるしい便所のなかで、
さまざまな「努力」を続けるしかないのだ。
こうして四苦八苦しながらようやくことを済ませ、
ほんの束の間、楽になれるのである。
しかし、まだ安心はできない。
今度は、いつあの「中途半端な便意」が
やってくるのか‥‥という緊張状態が続くのである。
もちろん病院へ行き、下剤を処方してもらっている。
毎日服用していたが、効果はまったくなかった。
さすがに犀星のように
自殺まで考えるようなことはなかったものの
(もっとも、わたしの部屋は2階なので、
飛び降りても
せいぜい骨折がいいところであるが)、
日常生活に、著しい支障を来していたのには、
ほとほと困り果てた。
なにせ、
そのような状態では、気軽に外出もできない。
それでも、あるとき、
どうしても外に出ざるを得ない用件があった。
喫茶店で、友人と面談する必要があったのだ。
友人には「便秘」である旨、伝えておいたのだが、
あにはからんや、
彼との面談中「あの便意」に見舞われたのである。
わたしはトイレに駆け込み、せいぜい「努力」した。
ただ、友人を待たせているので、
悠長に半時間も「努力」しているわけにはいかない。
顔や首、背中、脇の下‥‥体中に脂汗をかきながら、
なんとか、わずかばかりの「成功」を得た。

ここで、
犀星が少量の尿を排出することに成功した場面を、
以下に抜き出してみよう。
「こんどこそ一しづくでも出してみせるといふ気持は、あせあぶらの彼の顔にあふれて出た。彼が容器にさし向つて眼を閉ぢ、そしておもむろに気張つて見ると、思ひきや尿はつかれはてたやうにほとほとと落ちて来た、つぎの瞬間にもほんの少々であるが尿は容器にそそがれ、彼はこれこそ生きるちからが試めされたやうな気がした(‥‥)」
どうだろう、「大小」のちがいこそあれ、
わたしも、犀星と似たりよったりな状況であった。
事後、ほうほうの体で喫茶店の席に戻ると、
長らく待たされた友人は、
精根尽き果てたような顔のわたしをじっと見つめ、
ひとこと「たいへんだね」と言った。
そこには「同情」というより、
何か、滑稽なできごとにでも遭遇したような‥‥
つまりは「苦笑」があった。
実際には、どれだけ「苦しく、つらい」ものであれ、
便秘・排泄障害という疾患にたいして、
人は、ある種の「滑稽」を感じてしまうのだろうか。
犀星の「滑稽」は、
もちろん、彼の小説のなかには描かれていない。
小説のなかの彼は、真剣そのものだからだ。
だが、作品を俯瞰してみると、冒頭近くにこんな一節がある。
それは入院の準備で、持参するものを用意しているシーンだ。
「(‥‥)煙草、茶器、菓子、なぞも彼は何よりも先に鞄に入れたが、病院でお茶を喫み煙草をふかすつもりらしいと彼は自分自身をいやな男のやうな気がした」
胃潰瘍で入院するというのに、
「彼=犀星」は「お菓子」をカバンに入れているのである。
胃潰瘍の治療に行くのに、カバンにこっそり忍ばせる菓子。
それは、具体的にどんな菓子であったのか。
わたしは、
「文学と食べもの」──たとえば「室生犀星とスイーツ」──を
調査・研究していることもあり、
その菓子が何だったのか、どうしても気になったので
あれこれ調べてみると、
犀星の娘でエッセイストの室生朝子(1923-2002)の文章に、
その「答え」を見出した。
彼女は、あるエッセイのなかで、
父=犀星が入院するときのようすを、こう書いているのだ。
「玉露の小さい缶とお茶道具一式、不二屋(ママ)のかまぼこ形のチョコレート二本と洗面道具を持っていった。まるで旅にいくような仕度であり、医者も看護婦も呆れ、直ちに禁じられてしまった」
(室生朝子「大森 犀星 昭和」リブロポート、1988)
胃腸が悪くて入院するというのに、
「かまぼこ型の不二家のチョコレート」を、持参したのだ。
チョコレートというものが、
胃や腸にどのような影響を及ぼすのかはわからないが、
少なくとも治療の足しになるとは思えない。
朝子の書くように、たしかに子どもの遠足のようでもある。
何が言いたいかというと、
つまり、室生朝子の筆は、このときのできごと全体を、
父親の苦悩への同情というより、
のんきな病人の
「ユーモラスなエピソード」として描いているのだ。
ひょっとすると犀星は、人生の「最後の晩餐」の一品として
大好きな「かまぼこ形のチョコレート」を、
ひっそりと、カバンに忍ばせたのかもしれない。
病院にチョコを持っていくといっても、
父のほうは、いたって「真剣そのもの」だったのであろう。
じつの娘には、そんな父の姿が「滑稽」に映った。
かように、その地獄のような苦しみとうらはらに、
「便秘」という病気には、
どこか「滑稽」がつきまとってしまうのだ。
娘・室生朝子のエッセイと突き合わせて考えると、
そうした「便秘=滑稽」説が、
この深刻な入院小説にもあてはまるのではないだろうか。
われわれ「当事者」にとっては、
人生すべてを占領されてしまうほど深刻であるのに‥‥。
さて、話をわたし自身のことに戻すと、
結局、医師に相談して、
ひどい便秘の原因となったと思われる
薬の服用を中止することで、
あの地獄の苦しみから解放された。
いまでは、かつての自分が信じられないくらい、
毎日「快食快便」を続けている。
本当に、ありがたいことである。

<次回をおたのしみに>
2017-02-28-TUE