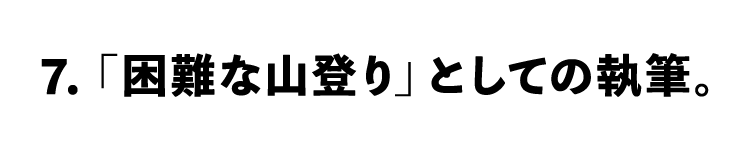性や下ネタのパワーワードが
これでもかと登場する作風の小説家、
木下古栗(きのした・ふるくり)。
過剰な表現の数々に、読みながらつい
「ハハ‥‥」と失笑してしまいます。
その不思議な作品の魅力に惚れ込んだ
ほぼ日編集部の田中が、小説の創作方法について、
ご本人に話を聞きにいきました。
書かれる内容は、徹底的にバカバカしく軽い。
だが文章は妙に美しく、知性を感じる。
独自の表現には何か理由があるのでは‥‥
と思ったら、やはりそこには
はっきりとした意思がありました。
取材には最新刊『サピエンス前戯』の
担当編集者、渡辺さんも同席。
黙々と高みを目指す、孤独な山登りのような
創作の一面をのぞかせてもらいました。
※このコンテンツには性や下ネタの露骨なワードが
登場する箇所があります。苦手な方はご注意ください。
木下古栗(きのした・ふるくり)
小説家。1981年生まれ。
顔出しはしていない。
ナンセンスな下ネタやシュールな展開、
独特の言語センスから
エロ・バイオレンス・パロディを多用する
異色の作風が特徴──とWikipedia。
(2021年6月現在)
2006年、某新人文学賞を受賞しデビュー。
最初の単行本
『ポジティヴシンキングの末裔』(早川書房)から、
独自のやりかたで小説技法の探求を続ける。
『グローバライズ』(河出書房新社)は
「アメトーク!」の「読書芸人2016」の回で
光浦靖子さんが絶賛。
そのほかの短編集には『生成不純文学』
『人間界の諸相』(ともに集英社)がある。
最新作は初の長編小説集『サピエンス前戯』
(河出書房新社)。
こちらは表題作のほか
「オナニーサンダーバード藤沢」
「酷書不刊行会」を収録。
- ──
- ぼく、過去の作品もけっこう好きなんですけど、
特に好きだったのが「生成不純文学」で。 - 「文学とは何か」をテーマに作家と編集者が
いろんなやりとりを交わすものですけど、
何度も時間が巻き戻って、
そのたびに同じシーンで違う内容が語られる
不思議な構造もおもしろくて。
作家は湯呑をつかんで残っていた茶を森崎に浴びせかけた。森崎は一瞬だけ目をつむったが、さらに力をこめ、肩も腕も、歯を食いしばった顎までもぶるぶる震わせて顔面から液体を振るい落としながら、なおも容赦なくプチトマトを貪り食い続けた。その濡れそぼった顔面めがけて、作家は握り締めた湯呑みを投げつけようと腕を振り上げた。その瞬間、森崎は頭を思い切り下げてお辞儀した。勢いずれた湯呑は肩口に当たって跳ね、卓上を少し転がって床に落ち、控えめに割れる音が立った。ほんの束の間、力む震えが止まったかと思いきや直後、顔を振り上げた森崎は眉の吊り上がった鬼気迫る形相で一段と強力に容赦なくプチトマトを貪り食った。
(『生成不純文学』収録「生成不純文学」より)
- 古栗
- さっきも言ったように、有名な作家のなかでは
カフカに影響を受けてるんですけど、
カフカって
「ある文章を書いたあと、それをひっくり返す」
というテクニックの使い手で。 - たとえば長編の『審判』は、
主人公がなぜかわからないのに逮捕されてしまって、
どうにか裁判から逃れようとするというだけの話で。
それでいろんな人に会いに行って、
無罪になるためのヒントを求めて
長話をしたりするんですけど、
しかし結局、何の成果もなかった‥‥となる。
その「しかし、成果なし」という展開によって、
それまで書かれたことが
ある意味でひっくり返されて、無に帰すんです。 - 文章のレベルでも
「こうこうこうすればあなたは無罪になれるんです。
しかしそれは見せかけの無罪で」
とか、前に言ったことを
「しかし」とか、逆接でひっくり返してしまう。 - こういうひっくり返しのテクニックを、
もっと大胆にやったらどうなるか、
というのが「生成不純文学」なんです。
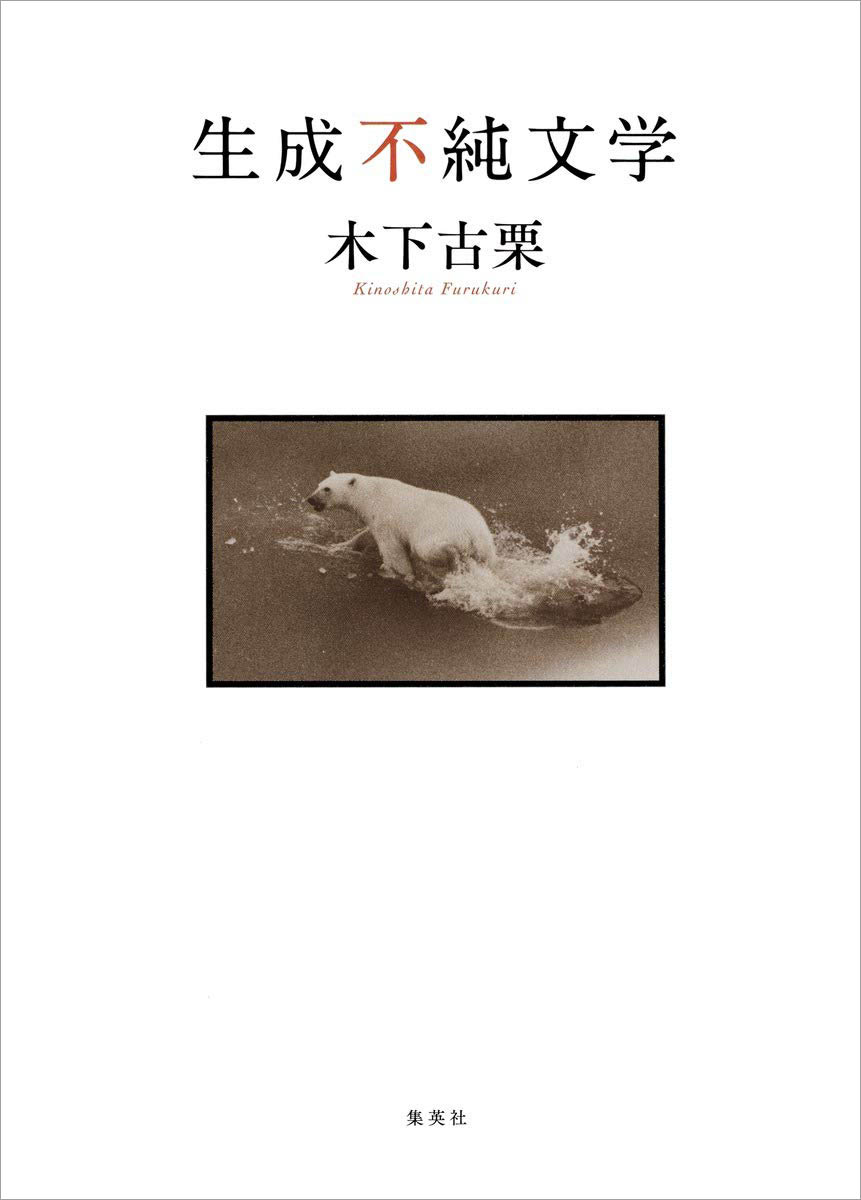
- 古栗
- たとえばカフカの『審判』で、
「悪いことは何もしていないのに
逮捕されてしまったのだ」
と書いたあとに、
「しかし、逮捕などされていなかった」
とひっくり返したら、基本的な設定自体がなくなって、
普通はその作品自体が成り立たなくなる。 - でも、そういうレベルでの大胆なひっくり返しを、
場面が生成されていく仕組みに取り入れて、
ダイナミックなひっくり返しの連続自体が
作品になったらどうだろう‥‥
こういう興味で書いたものなんです。 - だから自分の場合、影響を受けるときも
あくまで文章の書き方とか、
言葉の使い方とかに触発されるだけで、
内容とかテーマ的なところには
興味が持てないんですね。
社会問題とかについて考えたいなら、
その道の専門家の本を読みますしね。
- ──
- 古栗さんが「このありかたはいいな」と思う
作家や芸術家の方はいらっしゃいますか?
- 古栗
- もう亡くなってしまったんですけど、
イギリスで主に活動したアメリカ人の音楽家で、
スコット・ウォーカーという人がいるんです。
すごいダークで実験的な音楽なんですけど、
聴いていると笑っちゃうんですよ。
パーカッションとして、
たしか豚肉の塊を拳で殴る音とかが入ってるんですね。
メイキングとかを見ると、
それをすごいマジメにやっていて。 - 豚肉を殴ってるのって、異常だし怖いじゃないですか。
でも結局は創作にすぎないから
バカバカしくもあって、実際には脅威じゃない。
だから笑える。

- 古栗
- あといつかのインタビューで、
たしかフランス人の記者か誰かに
「あなたの音楽は現代音楽とか、
前衛音楽を引き合いに出されたりもするけど、
でも私はあなたはソングライターだという感じがする」
みたいなことを言われていて。
それでスコット・ウォーカーも
「そう、自分は”歌”という形式でやっている」
みたいに返して。
すると記者のほうは
「でも、普通とは別のやり方をしている
”歌”を作ってますよね」
みたいな。完全にうろ覚えですけど。 - そんな感じのやりとりを読んだとき、
「これってカフカに似てるよな」って思って。 - カフカってたしかに普通じゃない書き手なんですけど、
さっきも言ったみたいに、代表作のほとんどは、
リアルタイムに直線的に進んでいく。
思いつくまま、頭に浮かぶ場面をただ書いていくだけ
という感じで、究極にシンプルなんですよね。
ある意味では普遍的な小説の書き方というか。 - スコット・ウォーカーも
「(普通の意味での)メロディがない」
とか言われちゃうような、
暗くて一般性のない音楽を作っているんですけど、
でも歌詞と歌唱があって、
「歌」というシンプルな、普遍的な形式なんです。 - 二人とも現代音楽とかポストモダン小説にあるような、
いかにもな複雑な実験性はなくて、
すごく普遍的でシンプル。
それでいてぜんぜん普通じゃなくて、尖鋭的。 - それってどういうことかというと、
そこに「普遍的な尖鋭性」がある
っていうことじゃないかって。
自分もそういうのを目指したいとは思いますね。
- ──
- たしか古栗さんがなにかのインタビューで
「一人でいる人に勇気をもらう」
というようなことを、
言ってらっしゃったと思うんですけど。
- 古栗
- 人間ってよく「社会的動物」とか
言われるじゃないですか。
あとは「感情で動く生き物」とか。
だから社会としてネットワーク的に、
共有する価値観とか共感の海みたいなものが
すでに広がっていて、
生まれたときからそれに浸っている。 - だから馴染みのない場所に行ったり、
不慣れな新しい関係のなかに飛び込んだりすると、
心細くなったりしますよね。
分かりやすく言えば、
縄文時代にタイムスリップするとか、
まったく未体験の業界に転職するとか。
そこでは他の人たちはすでに共有しているもの、
共感しているものがあるんだけれども、
自分はまだそれに浸っていないところも出てくる。
要するに、多対一になって、
自分がむき出しの一人になるような。 - それってもちろん、実生活ではなるべく
味わいたくないですよね。
とくにその「一人性」がどんどん強まって、
ツラくなってくるような場合は。
祖父母の世代とかを見ていて、長生きして
親しい同年代がみんな死んでしまったとかになると、
こんなに世の中にいっぱい人がいるのに、
すごく一人になってくるんだなって。
寂しいですよね。 - 創作において、
リアリティのなさを追求したりっていうのは、
むしろ積極的にそういう方向を
目指すようなところがあるんですよね。
社会性とか共感性をなくしていくというか。
するとその意味では当然、
マイノリティになっていって、
その果てに一人になっていく道が見えてくる。 - 創作って山登りであると同時に、
その登る山自体を作っていく感覚なんです。
だからどんどん山を高く鋭く隆起させていくと、
人里から遠くなって、空気も薄くなって、
植物の姿もなくなっていって、
まわりには誰もいなくなる。
それはあくまで創作の話にすぎないんですけど、
でもやっぱりツラいところもあるわけです。
世間的な価値はぜんぜんないことに
力を注いでいますから。 - でもそのとき、遠くに他の山が見えて、
それも鋭く隆起していて、
そのてっぺんに誰かが小さくぽつんと見えたら。
こっちの山も一人きりだけど、
向こうの山も一人きりですよね。
「ああ、あの人も一人だけで
あんなに高く山を隆起させて、
そこに登ってきたんだな」と遠くから感じて、
それに勇気づけられるというか。 - あるいは、その山を隆起させた創作者が
もう死んでいても、
その尖った高い山を見るだけで
「こんなに山を尖らせた人がいたんだな」と‥‥。 - 分かりますかね?
- ──
- はい。なんとなく。
- 古栗
- それは創作じゃないことでも、感じることもあって。
- たとえば何年か前、こんな話を聞いたんです。
ある女子高生が新入生でクラスに入ったら
当然、自分以外、全員LINEをやっていて。
どんどんみんなコミュニケーションを取って
仲良くなっていって。
でもその女子高生はLINEが嫌いで、
やらなかったから、ハブられていると。
でも「私はあんなもの嫌いだから絶対にやらない」と
一人だけ貫いているらしくて。 - そんな話を聞いて、
ちょっと勇気づけられましたね(笑)。
(つづきます)
2021-06-28-MON
-
<書籍紹介>
サピエンス前戯
木下古栗・著
[Amazon.co.jpのページへ]3作品を収録した、長編小説集。
表題作「サピエンス前戯」は、
全自動前戯器「ペロリーノ」を販売する
サイバーペッティング社の代表・関ヶ原修治が
たまたま出会った脳科学者とともに
人類と前戯について考えをめぐらせる話。2つめの「オナニーサンダーバード藤沢」は
ある作家の文体を模したような
一人称単数で語られる、自慰をめぐる冒険。3つめの「酷書不刊行会」は、
多くの人に文学に親しんでもらうため、
世界の名作文学のタイトルを
ポルノ風に転換したリストを作る話。失笑しながら奇妙な物語を読みすすめる、
不思議な読書体験をすることができます。