
2018年1月に「ほぼ日の学校」は誕生しました。
そして、2021年の春に
「ほぼ日の學校」と改称し、
アプリになって生まれ変わります。
學校長の河野通和が、
日々の出来事や、
さまざまな人や本との出会いなど、
過ぎゆくいまを綴っていきます。
ほぼ毎週木曜日の午前8時に
メールマガジンでもお届けします。

↑登録受付は終了しました↑
2021年2月11日にこのページはリニューアルされました。
今までの「學校長だより」は以下のボタンからどうぞ。

河野通和(こうのみちかず)
1953年、岡山市生まれ。編集者。
東京大学文学部ロシア語ロシア文学科卒業。
1978年〜2008年、中央公論社および中央公論新社にて
雑誌『婦人公論』『中央公論』編集長など歴任。
2009年、日本ビジネスプレス特別編集顧問に就任。
2010年〜2017年、
新潮社にて『考える人』編集長を務める。
2017年4月に株式会社ほぼ日入社。
[ 河野が登場するコンテンツ ]
読みもの
・新しい「ほぼ日」のアートとサイエンスとライフ。
・19歳の本棚。
NO.154
翻訳者、いまは昔
常盤新平さんの自伝的な短編集『片隅の人たち』(中公文庫)を読みました。常盤さんといえば、1987年に小説集『遠いアメリカ』(小学館P+D BOOKS)で直木賞を受賞しますが、私がその名前をしっかりと記憶に刻んだのは、まだ小説を書く前の、新進気鋭の翻訳家としてです。
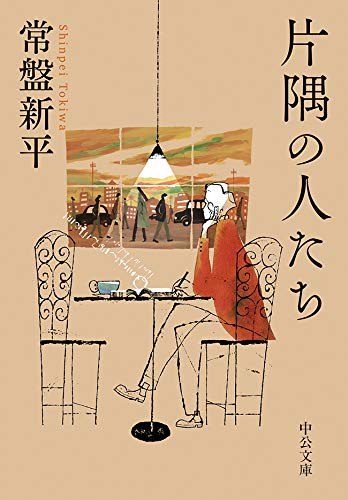
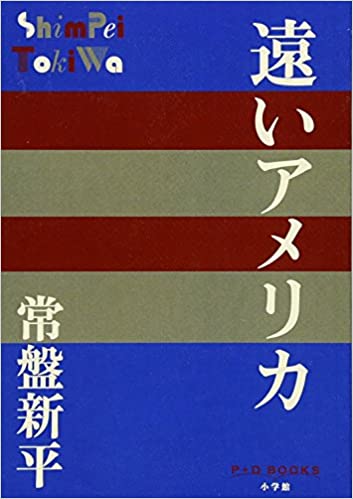
1970年代に刊行されたゲイ・タリーズ『汝の父を敬え』(新潮文庫、品切れ)、あるいはボブ・ウッドワード&カール・バーンスタインの『大統領の陰謀』(ハヤカワ・ノンフィクション文庫)といった現代アメリカのみずみずしいノンフィクション作品を矢継ぎ早に紹介する颯爽たる翻訳者、というイメージです。
作家トム・ウルフの「ニュー・ジャーナリズム論――小説を蘇らせるもの」(「海」1974年12月号、中央公論社)の訳出も衝撃的でした。新しいアメリカ文化の息吹を伝える意欲的な翻訳家のひとりとして、常盤さんはまばゆく映ったものです。いまでも懐かしさがこみ上げます。
ご本人に初めてお会いしたのは、1980年5月のこと。才気煥発(かんぱつ)な語学の達人というイメージとは裏腹に、ポツリ、ポツリと朴訥に話すシャイな人柄です。刊行まもない新著『アメリカの編集者たち』(集英社)の話題をひとしきりした後は、好きな食べものや競馬の話など、むしろ雑談を楽しんだ記憶があります。

『片隅の人たち』はその前史にあたる時代――『遠いアメリカ』に描かれたのとほぼ同時期の1950年代から60年代――を舞台にして、主に海外ミステリーを翻訳していた人たちの生態を、ほのぼのと愛情深く描きます。
どの一篇をとっても「うたた今昔」の感がありますが、いずれの作品にもあの時代ならではの熱気とエネルギーを感じます。
一世を風靡(ふうび)した評論家、『ぼくは散歩と雑学がすき』(ちくま文庫)の植草甚一さん、『EQMM(エラリー・クイーンズ・ミステリ・マガジン)』編集長の都筑道夫さんなど実名で登場する人たちがいる一方で、誰かをモデルにしたとおぼしき個性的な面々が姿を見せます。
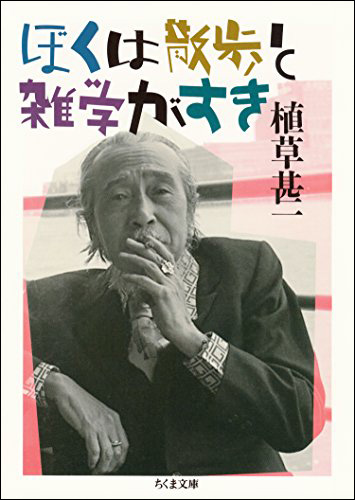
すぐに特定できるのは、主人公の翻訳の師である中田耕治氏、「黒眼鏡の先生」として描かれる、映画字幕やレイモンド・チャンドラーの翻訳などで知られる清水俊二氏、上司として登場する加藤正実は、初代「SFマガジン」編集長として、日本にSFという未踏の領域を切りひらいた福島正実さんのことだとわかります。
登場人物に共通するのは、「変った人」という特徴です。わかりやすく言えば“インテリやくざ”の匂いのある、どこか拗(す)ねたような屈託を抱え、世の中の流れから「下りた」感じの人たちです。
喫茶店を仕事場にしている人が多いのも、当時の時代背景を物語ります。
<夕方になると、僕が勤めている出版社へ毎日のようにやってくる翻訳者は吉祥寺に住んでいて、朝の十時ごろ家を出ると、まず吉祥寺駅の喫茶店で一、二時間仕事をし、それから中央線に乗り、西荻窪でおりて、喫茶店でまた一、二時間、翻訳し、中野まで一駅ごとに下車して、喫茶店に直行し、だんだん神田駅に近づいてくるのだった。中野から電車に乗る時はちょうど五時ごろで、神田駅に着くと、会社にやってきて、僕の上司である加藤さんにできただけの原稿をわたし、コカジに行って、加藤さんを待つのだった。そのあとは僕の上司と二人で酒を飲みに行くのである。>
「僕が勤めている出版社」というのは早川書房で、コカジは、2006年まで営業していた神田駅前の小鍛冶洋菓子店です。私もずいぶん、ここで早川書房の人と会いました。
それはさておき、翻訳者たるもの、じつに律儀で勤勉なのですが、「例外なく変った人」というふうに描かれます。
結婚してひと月もたたずに離婚した人は、「新妻が食事がわりに、バナナしか食べさせなかったから」逃げ出したとか、銀行員を辞めて翻訳家になった人は、世界文学全集の1冊を翻訳した印税200万円を前借りし、まずダブルベッドを買い、残りのお金を持って「奥さんと二人で日本全国の温泉をまわった」とか。
別の本には、「これから首を吊りたいのだが、あいにくロープがないので、そのロープを買うため、前借りさせて欲しいとあわれな声で電話してきた翻訳者」とか、「ガードナーのペリー・メイスンを一冊訳しおえて、早川書房に届けたあと、新宿の暴力バーでそのメイスンものの印税をそっくりとられてしまった」御仁などが登場します(『翻訳出版編集後記』、幻戯書房)。
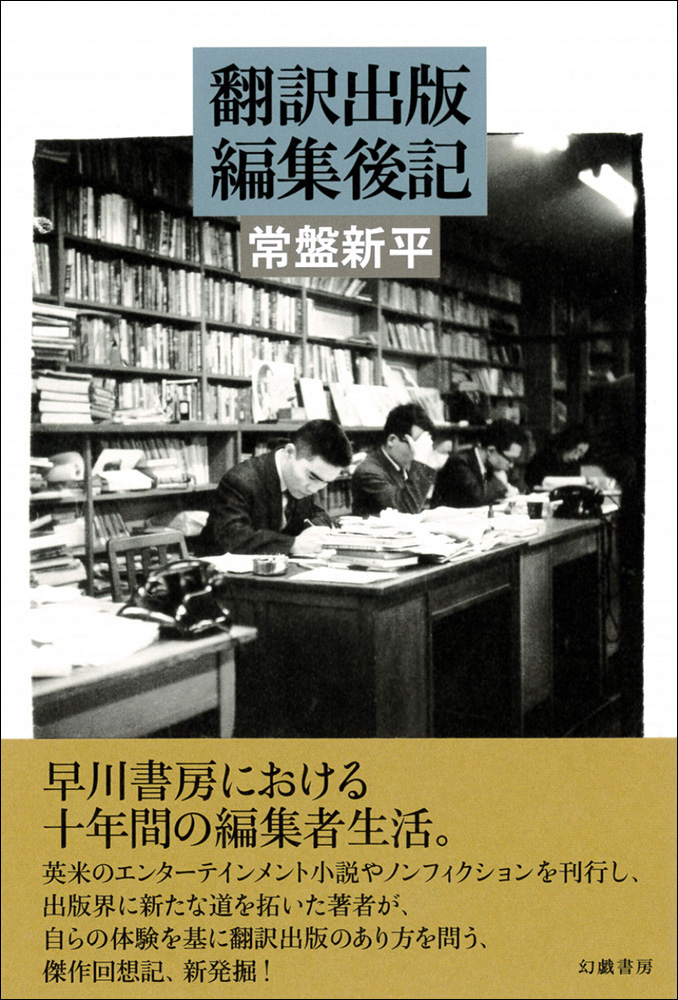
『片隅の人たち』には、「クリスティーの翻訳がうまい、ある詩人が結婚式の式場や披露宴の会場を予約したのに、肝心の花嫁が決まらなくて、誰かに泣きついたというゴシップ」が暴露されています。これは早川書房の社内で現に起こった出来事です。
当時の社長だった早川清氏が、自らこの事件に言及しているのもケッサクです。
<いわれてみるとまったくその通りで、花嫁の全然きまっていないうちに、挙式日と会場(日活国際ホテル大宴会場)を予約し、それを明記した披露宴の招待状を大量に出した男が現にわが社にいたのだ。これも当人の努力? と周囲の協力で、当日までに辛くも花嫁をみつけて、関係者のひとりである僕をほっとさせた事件が十数年前にあったのだ。信じられない話だろうが、事実は厳として事実で、珍無類の出来ごとだった。つくり話でないあかしのために、すでに時効と断定して、氏名をあきらかにしてしまえば、当時小社の編集長だった、詩人田村隆一である。>(「悲劇喜劇」1974年8月号の編集後記、宮田昇『戦後「翻訳」風雲録』(本の雑誌社)による)
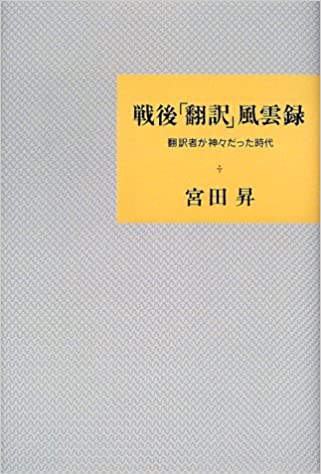
ご祝儀ほしさに自らの結婚話をでっち上げたわけですが、いかにも田村隆一さんらしい(翻訳者・編集者というより詩人の)逸話です。ちなみに、「周囲の協力」というのも、唖然とする内容なのですが、それは割愛(!)するとして、当日、披露宴では桂文楽が「明烏」を演じ、森繁久彌が「枯れススキ」を歌って、会場は大いに盛り上がり、招待客も満足して帰ったといいます。
ま、こんな世界に飛び込んでしまった常盤さん。翻訳なんて「まともな人間のやる仕事ではない」――「僕は世の中からはずれていた。どん底にいるような気がしていた」「時代から取り残されていた」と綴ります。
<私自身はしょうがなくて翻訳者になったところがある。翻訳しかできなかったし、翻訳で食ってゆけるものなら、それにこしたことはないと思っていた。しかし、これはやくざな商売だと覚悟していた。>(前掲『翻訳出版編集後記』)
とはいえ、それをどこかおもしろがって、楽しんでいたのも事実です。
「みんな変な人」であるのに加え、誰しもお金がなかった点も共通します。いくら翻訳の達人だとはいえ、翻訳者の収入は高が知れたもの。探偵小説の部数はせいぜい5千部。定価が250円とすると、印税8パーセントだと、訳者の手に入るのは1部20円、それに部数をかけると10万円、1割5分の源泉徴収税を引けば、手取り8万5千円。早川書房では、これを発売3ヵ月後から、月1万2千円の分割払いにしていたとか。
ひとりの翻訳者が年間にこなせるのは、平均すると3、4冊。翻訳探偵小説がベストセラーになることはめったになく、100冊のうち99冊が初版どまり。海外ものミステリーの市場がいかに小さかったかと驚きます。
<入社して一週間ほどしたころ、僕は名古屋の大学の先生を神田駅のプラットフォームまで迎えにいった。その先生は翻訳が完成した原稿を持って上京したのだが、名古屋駅で入場券を買って、東京駅に着き、そこから迎えに来てくれと電話してきたのだった。僕は神田駅で入場券を買い、それで改札口を通ると、プラットフォームでうれしそうににこにこしている先生に入場券をわたし、先生はその入場券で、僕は定期で改札口を出た。>
「みんな変っていて、それに貧乏だった」というのが、主人公の感想です。「貧乏だけれども、自由があるから満足していた」とも。だからこそ、ミステリーの翻訳に打ち込んでいる人たちの同志的な仲間意識も格別です。
先輩翻訳者の平岩さん。ふたまわり以上も齢のはなれた人が、喫茶店でモーニングサービスを一緒に食べながら、間もなく結婚しようとする主人公に語りかけます。「ま、女房みたいな女がいたから、私のような者でも生きてこられた」「ところで、君はどうなの」と。
<僕が苦笑する番だった。平岩さんもにやにやしている。なぜかこの朝の、一九五七年十一月の、陽の光がユタの窓から降りそそぐ朝のことをいつまでも忘れないような気がした。平岩さんの姿に僕の未来をかいまみたようだったのだ。といって、髪結の亭主になるつもりはなかった。ただ、五十を過ぎたとき、僕も白ばらみたいな喫茶店で珈琲を飲みながら、スポーツ紙や週刊誌を読み、ウェイトレスに言葉をかけて、暇つぶしをするのではないか。それは僕の願望かもしれなかった。ひっそりと無事に、そして気ままに暮してゆきたいという願望。>
出版界の片隅で、ひっそりと好きな探偵小説を訳しながら、つましく生きていく人生行路。そんな憧れすら抱いていた常盤さんの身辺が、ある時、大きく変わり始めます。ちょうど早川書房を退社して、翻訳家として独立する時期に重なります。「1969年は翻訳出版の転機だった」と述べるように、このあたりを境にして、日本の出版界は大きな変貌を遂げていきます。
<常盤新平が、ハヤカワ・ノヴェルズやその他で、翻訳出版に成功したことが、それを促したともいえる。>(宮田昇「『後記』の後記」、前掲『翻訳出版編集後記』解説)。
宮田昇さんがそう証言するように、「かつてはマイナーだった翻訳出版も、大手を初め多くの出版社が参入するまでに拡大」します。翻訳出版のアドヴァンス(契約時前払い印税)が125ドルという、なかば“固定相場”の時代から、3千ドル以上が当たり前というバブルの時代に突入します。
アメリカと日本の距離が一挙に縮まり、アメリカ旅行が日常茶飯事のようになります。『片隅の人たち』では、「翻訳小説なんて読者が少ないからね。(略)うちの家内なんて読まないよ。片かながまじってると読みにくいんだって」と言われたミステリー市場に、劇的な変化が訪れます。翻訳ものが身近になります。
<‥‥翻訳がよくなったということのほかに、片仮名に対する抵抗感がなくなったからでもある。片仮名が自由に使えるようになった。十五年前、二十年前はなんでも日本語にしなければならなかった。現在は片仮名ですますことができる。『ゴッドファーザー』でも、『マネーチェンジャーズ』でも一昔前だったら、題名に編集者が苦労するところである。>(前掲書)
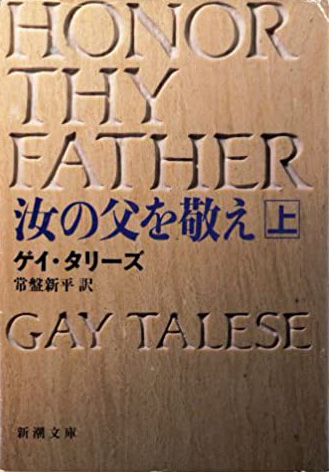
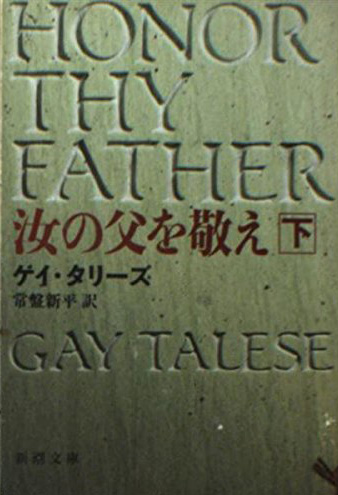
『ゴッドファーザー』はもとより、映画化された『ラヴ・ストーリィ』『ジャッカルの日』などが爆発的な売れ行きを示します。翻訳家志望者が昔では考えられないほどに増え、その後の海外ミステリー・ブームへと時代は向かいます。
<僕はハンバーガーなるものをまだ食べたことがなかった。その形も知らなかったけれど、碇さんはカウンターで大学ノートの末尾の頁にハンバーガーを描いてみせた。
「うちで売ってる雑誌の広告で見たのですよ。丸いパンを横から切って、そのあいだにハンバーグをはさんで、それに玉ねぎやトマトをのせて食べるんですよ」>
高い食べものではなさそうだし、小説に出てくる私立探偵が、カフェテリアとかコーヒーショップでハンバーガーを食べているとこが好きなんです、と言って、貧乏でひとりぼっちの、世の中からあぶれたような男たちに親近感を覚えます。
そんなカルチャーギャップも、いまは昔。インターネットを通じて、小説の細部を確認したり、疑問を原著者に直接ぶつけたりすることも可能です。
<沙知と結婚したあと、彼女は僕がじつにしばしば手を洗うのに呆れた。この癖がついたのは、碇さんの古本屋に通った結果である。彼の店で買った「プレイボーイ」でもページをめくっていると、手が汚れてくるのだった。>
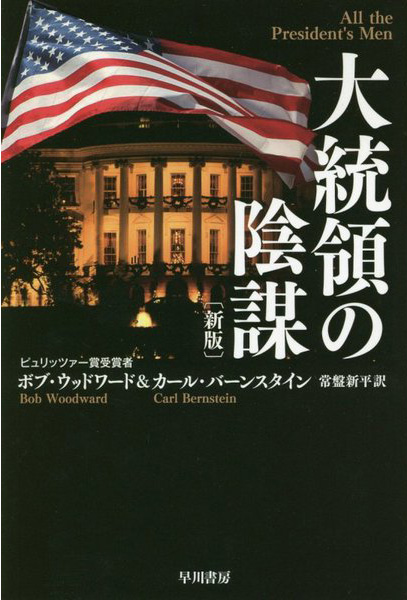
渋谷百軒店(ひゃっけんだな)にあったその古本屋には、おそらく米軍の飛行機や船で横田基地や横須賀に入ってきたアメリカの雑誌の最新号やペーパーバックが、ばかに安い値段で売られていました。主人公は「宝の蔵」へ入る気がして、勇んで日参するのです。
<この古本屋の名前をいまだに知らない。はたして名前があったのかどうか。夏は暑いし冬は寒い店だったけれども、そんなところへ毎日のように通ったのは、おそらくそこに新しい、しかし薄汚れたアメリカがひっそりとあったからだろう。>
こんな先人たちの汗とロマンがあったおかげで、いまの多士済々(たしせいせい)な翻訳の世界が生まれ、その恩恵に私たちも浴しています。常盤さんの淡々とした述懐が、それだけに胸にしみてきます。
「じつにしばしば手を洗う」のではなく、いまの翻訳家たちにはどんなクセがあるのでしょう? 「変った人」って誰なのでしょう? ふと何人かの顔を思い浮かべます。
2021年3月11日
ほぼ日の學校長![]()
*来週は都合により休みます。次回の配信は3月25日の予定です。
*ほぼ日の學校神田スタジオでの公開授業収録参加者を募集しています。募集授業一覧はこちらからご確認ください。(※感染防止対策を徹底した上で収録いたします。また今後の状況次第では急遽開催中止となることもございますので、ご理解の上ご応募ください。)
(また次回!)
2021-03-11-THU

