
2018年1月に「ほぼ日の学校」は誕生しました。
そして、2021年の春に
「ほぼ日の學校」と改称し、
アプリになって生まれ変わります。
學校長の河野通和が、
日々の出来事や、
さまざまな人や本との出会いなど、
過ぎゆくいまを綴っていきます。
ほぼ毎週木曜日の午前8時に
メールマガジンでもお届けします。

↑登録受付は終了しました↑
2021年2月11日にこのページはリニューアルされました。
今までの「學校長だより」は以下のボタンからどうぞ。

河野通和(こうのみちかず)
1953年、岡山市生まれ。編集者。
東京大学文学部ロシア語ロシア文学科卒業。
1978年〜2008年、中央公論社および中央公論新社にて
雑誌『婦人公論』『中央公論』編集長など歴任。
2009年、日本ビジネスプレス特別編集顧問に就任。
2010年〜2017年、
新潮社にて『考える人』編集長を務める。
2017年4月に株式会社ほぼ日入社。
[ 河野が登場するコンテンツ ]
読みもの
・新しい「ほぼ日」のアートとサイエンスとライフ。
・19歳の本棚。
NO.159
安野光雅さんのこと
「こんな日がこようとは‥‥」と、思わず感激を口にしたのは松岡和子さん。場所はロンドンのレストランです。旅先で、憧れの絵本作家とディナーをともにするような日がこようとは‥‥。20数年前に、感無量の面持ちで画家の安野光雅さんに告げたといいます。
詳しくは『繪本 シェイクスピア劇場』(安野光雅・画/松岡和子・文、講談社、1998年)の「あとがき」(安野光雅)に譲りますが、松岡さんはいまもきっと、同じ感激を安野さんに伝えたかっただろうと思います。

先日、最終巻の『終わりよければすべてよし』が刊行され、1996年から始まった個人訳『シェイクスピア全集』(ちくま文庫、全33巻)が25年をかけて完結しました。シェイクスピアの全37戯曲をひとりで翻訳するという偉業! 日本では、坪内逍遥、小田島雄志に次いで3人目、女性では初の快挙です。

各巻のカバー装画・デザインを担当したのが安野さん。1冊完成するごとに、ランチを一緒にとりながら「次も頑張ろうね」と励まし合うのがならいだったとか。それが途切れたのは、『ヘンリー八世』が刊行された2019年2月のこと。その頃から安野さんの体調がすぐれなくなり、そして昨年12月24日、ついに別れの時が訪れます。

「こんなことなら、もっとちゃんと、1作1作について安野さんのシェイクスピア観を聞いておけばよかった」――松岡さんはいかにも悔しそうに語ります。
想をこらした33点。安野さんらしい淡彩の表紙絵がずらり並ぶと壮観です。

「1枚1枚が、実にたくさんのことを語りかけてくる。シェイクスピア劇はあまたの人物が登場し、複雑なプロットで構成されている。そこから安野さんが何をピックアップし、どんなふうに絵にしたか。そんな思いで眺めていると、興味は決して尽きません。少し負け惜しみになりますが、お元気なうちにしっかりお話を聞けなかった代わりに、残された絵と語り合うことが、これからの楽しみになると思います」
全集完結までの道のりを、先日松岡さんは、ほぼ日の學校主催のトークイベント<「覚悟がすべて」な人生>で、たっぷり語ってくださいました。

「シェイクスピアはあまりに大きな存在なので、何度も逃げようとしたけれど、その都度追いかけられて引き戻された」――切っても切れない劇作家との縁(えにし)や、「覚悟がすべてだ(The readiness is all.)」というハムレットのセリフが、どんな時に松岡さんの心を支え、足元を照らし出す灯火(ともしび)の役割を果たしたか‥‥。
おそらくこの先も、シェイクスピアの言葉は、私たちの日常生活のなかにふと浮かんできて、大切な気づきや啓示を与えてくれるのではないか。芝居の文脈を離れてもなお、自分に言い聞かせたくなるような力強いメッセージを投げかけてくれるのではないだろうか――。
四半世紀を捧げ、個人全訳を達成した人とは思えない、
さて、たまたま時を同じくして、安野光雅さんの『絵のある自伝』(文春文庫)を読み返す機会がありました。日本経済新聞連載の「私の履歴書」がもとになった1冊です。初読の際にそんな予感はなかったのですが、この10年近くというもの、何かの拍子にここに出てくるエピソードや場面が、ふいに頭に浮かんできます。私にとっては、まるで玉手箱のような不思議な1冊になりました。
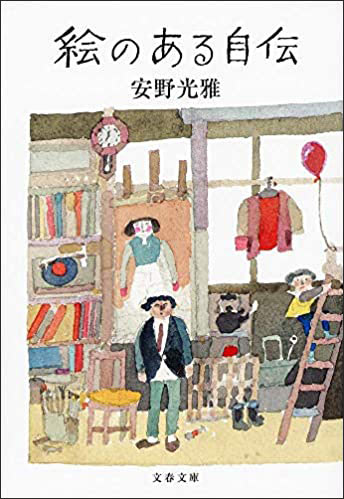
「フーテンの寅さん」顔負けの啖呵売(たんかばい・巧みな口上でものを売りさばくテキ屋稼業)をなりわいにしていた姉婿(あねむこ)の義一。
<二男三女が生まれたが、一人だけ父の素質を受けついだらしい子をのぞいて、みんな本当にいい子に育った。学芸会で熊に扮した息子に、父は「人間ちゅうもんは熊になっても金太郎なんぞに負けてはならぬ」といい渡した。投げとばされた金太郎は泣きだし、学芸会は無茶苦茶になったという。>
あるいは、小学1、2年生の時の同級生だったつえ子のこと。父子家庭で、父親は発破(はっぱ)の事故で失明し、近隣の加持祈禱(かじきとう)をしながら暮らしていました。
<わが家でも井戸替えをしたとき、水の神に祈ってくれた。祈禱が終わると、供えた生米を空になげて手のひらにうけ「何粒ありますか」と聞き、その米の数で何ほどかのことを占うのだったが、わが家では信用していなかった。わたしは家に来たつえ子と遊んで祈禱が終わるのを待った。彼女は父と自分を杖でつなぎ、目の代わりになるのが仕事だった。>
<つえ子は明るい子でよく笑った。これ以上失うものはない、笑うしかないという悟りでも持っていたのだろうか。色が変わるほど洗った洋服、お下げ髪、二つの前歯が目立っていた。>
3年生で別のクラスになって以来、ずっと話すこともなかった彼女に、テレビ番組で60数年ぶりに再会します。
<つえ子さんは結婚し、四人の男の子に恵まれ、みんな大学にやった。農業をやっているが、畑をおそうイノシシの他に心配はない、などといった。>
この「ご対面」をお膳立てしたのが、NHK松江放送局にいた、どうやら私の大学時代の級友らしいことも驚きでした。
魚屋をしていた兄夫婦の家の隣は、土建業の頭領の家で、ここの奥さんは「土間にでんと座って回転焼き(今川焼き)を焼く」のですが、「この手順を、猥談仕立てにして、おばさんが聞かせるんだから、随分勉強になった」と安野さん。
<一人息子がいていまや若い衆となり、これも鳶(とび)職かなにかをやっているが、これが帰ってくると、急ににぎわしくなり、親子みんなが何か食べながらまた猥談が始まる。光ちゃんも上がれというが、逃げ出すほどのすごく楽しい家だった。>
「逃げ出すほどの」というフレーズ。底抜けに楽しそうで、遊びに行きたくなりますね。
「結婚のこと」に出てくる田中稔之(としゆき)画伯の若き日の姿。どこかの島で、釣った魚を食べようとしますが、七輪の火をおこすための団扇がありません。
<田中稔之くんはうちわがないので七輪を持ってはしった。おかずは釣ってきた魚。島の娘さんたちはよくまあだまって見ていたな>
七輪を抱えて走る好男子の絵と、安野さんの手書きの文字が躍動します。
安野さんが、まだ若い父親であった頃。自宅に指圧師を呼んで、肩を揉んでもらっていました。顔をしかめて痛みに耐えていると、当時3歳だったお嬢さんが、どこからか物差しを持ち出してきて、指圧師の頭をぶったといいます。
<自分の子どもの、四歳までのありようは、そこを支点とし、その後の子どもがするであろうあらゆることと釣り合いがとれているというが、本当にそうだとおもう。この子どもたちのしてくれたことに、わたしは一生をかけて報(むく)いたいとおもっている。>
こういう話がふんだんに出てきます。戦争が始まり、高等小学校を出ると、父親の言いつけで「手に職がつく」旧制の工業高校に進みます。就職先は九州の炭鉱。やがて兵隊に取られ、いまも頭には、“軍人精神注入棒”で上官に殴られた傷跡が残るとか。
戦争が終わり、代用教員になった頃のあたふた。ある著名な教育者の言葉を真に受けて、身ひとつで上京してみたら、大いに当てが外れて困ったとか。それでも「田舎へ帰るわけにもいかず」、やがて教員の試験にパスして三鷹市立第五小学校の校長に拾われて‥‥と、描きようによっては、つらく、みじめな苦労話になりかねない世界を、まるで魔法の粉をかけたように、ほのぼのとしたユーモラスな物語に仕立てています。
軽快なテンポで語られ、率直であってかつ程(ほど)がよく、まさに安野さんならではの淡い色調の、おおらかで心優しい物語が、つつしみぶかく差し出されます。
画家として独立するのは、ようやく35歳の時。それまでは美術の教師をしながら、美術の教科書づくりや、挿絵、装丁の仕事を引き受けていました。
ところで、日頃から絵心の欠如を嘆き悲しんでいる私は、もし幼き日に安野さんのような美術の先生に出会えていれば‥‥と夢想するのですが、安野さんが実際に教えていた武蔵野市立第四小学校で、生徒として図画工作を習った人たちが、当時のことを回想しています。
<図画工作の先生は三十歳を出たばかり。島根県津和野に生まれ、戦後、上京して小学校の先生を務めながら絵を描いていた。三鷹市立第五小学校で教えた後、武蔵野市立第四小学校に移ってきていた。
この先生、生徒には絶大な人気があった。担当していた図画工作の授業はもちろん楽しいのだが、それよりも、脱線して語り出すお話が、落語を聴いているようにおもしろかったからだ。先生が話し始めると、生徒たちは耳をそばだてて聞き、佳境にさしかかると思いっきり大声で笑った。(略)
ある時、絵を描かずにイタズラしている生徒がいた。手元にあった独楽(コマ)を回して、そこに絵の具をたらし、飛沫(ひまつ)を飛ばしたのだ。それを見た先生は、怒るどころか、「ちょっと貸せ」と独楽を回し、色の散り具合を真剣に見つめるのだった。イタズラ好き、遊び好きの先生ならではの反応だ。
この小学校の卒業アルバムには、ジェラール・フィリップのような風貌をした先生の写真がある。他の先生は背広、ネクタイで姿勢を正しているのに、ひとりだけノーネクタイ、セーター姿にズック靴で、「面倒くさいな」とでも言いたげな表情で写っている。>(松田哲夫『縁もたけなわ』小学館)
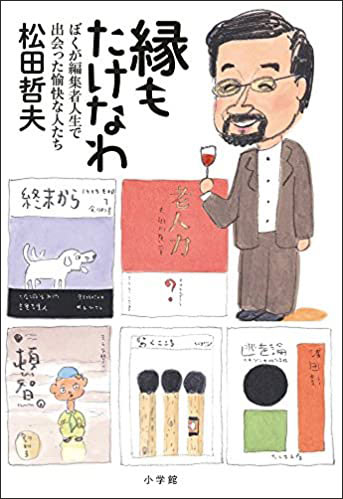
<天然パーマとギョロリとした目がやせた身体の上にのっている、というのが当時の印象である。(略)
先生の授業は、クラスの皆が待ち焦がれていた。戦火を生きのびた木造二階建て校舎の、一階の西端にあった図画工作室に向かう時のわくわくした気持ちは、よく覚えている。
教壇の向かって右端に立って話す先生の姿が、そのよく通る声とともに今もくっきりと目に浮かぶ。先生の人気は、類い稀なユーモアによるものだった。得意中の得意である二等兵物語に、生徒たちは皆、授業中ずっと笑い転げ、時々シュンとした。シュンとしたのは、先生の笑い話に抒情や悲哀が時折含まれていたからだった。>(藤原正彦、安野光雅/藤原正彦『世にも美しい日本語入門』ちくまプリマー新書より)

長い文章を引きましたが、当時の教室がありありと目に浮かび、そこにいたくなるような気がします。安野センセイの授業を受けていたら、私に絵心が芽生えたかどうか、はわかりませんが、授業を待ち望んだのはこの2人とまったく同じだろうと思います。
自分が体験したことをどのように昇華し、ユーモラスに語るか。目にしたものから何を受けとめ、どこをとらえて表現するか――。絵心はともかく、その物語や身振り、語り口、表情に笑い興じながら、きっとそこに、感動を分かち合うひとつの作法を学んでいたような気がします。
安野さんの話は、意味や論理、ましてや教訓に集約されません。「旅の絵本」という章に、こんな文章が記されています。
<文字は説明的な意味を持っているが、絵は説明ではない。
詩も違う気がする。ことばで書くほかないが、そのことばの説明的な意味から逃れようとしているようにさえ見える。(略)
壁を飾る絵に、題名はあっても文字はない。わたしたちの見る風景の中にもそれを説明する文字はない。(略)絵や音楽をことばの説明を仲立ちにして見たり聞いたりしようとするのは、ことばに頼りすぎた者の悪い癖(くせ)である。>
小さい頃から絵描きになりたくて、絵描きがどういうものかも知らないけれど、とにかく絵さえ描いていればゴキゲンだったという安野さん。その絵を一生描き続けた幸福感とともに、安野さんが最後まで追い求めたいと願った夢、あるいは厳しく抗(あらが)おうとしていたもののおぼろな輪郭が、手触りとして感じられてくるところが、『絵のある自伝』のおもしろさです。
<誰もが大志をいだくだろう。
少年のころ「あの旗のところまで」と思い描いた大志はいまもかわらない。(略)
それなのに、まだおもう。あの旗の立っているところはまだまだ遠いらしいのだ。>
これが掉尾のことばというのも、この本の“息の長さ”
2021年6月10日
ほぼ日の學校長![]()
*松岡和子さんのシェイクスピア作品完訳を記念して、5月30日に神田ポートビルでおこなわれましたトークイベント、「「覚悟がすべて」な人生/松岡和子さんが語るシェイクスピアの言葉」の様子を配信しております。くわしくはこちらからどうぞ。
(また次回!)
2021-06-10-THU

