
2018年1月に「ほぼ日の学校」は誕生しました。
そして、2021年の春に
「ほぼ日の學校」と改称し、
アプリになって生まれ変わります。
學校長の河野通和が、
日々の出来事や、
さまざまな人や本との出会いなど、
過ぎゆくいまを綴っていきます。
ほぼ毎週木曜日の午前8時に
メールマガジンでもお届けします。

↑登録受付は終了しました↑
2021年2月11日にこのページはリニューアルされました。
今までの「學校長だより」は以下のボタンからどうぞ。

河野通和(こうのみちかず)
1953年、岡山市生まれ。編集者。
東京大学文学部ロシア語ロシア文学科卒業。
1978年〜2008年、中央公論社および中央公論新社にて
雑誌『婦人公論』『中央公論』編集長など歴任。
2009年、日本ビジネスプレス特別編集顧問に就任。
2010年〜2017年、
新潮社にて『考える人』編集長を務める。
2017年4月に株式会社ほぼ日入社。
[ 河野が登場するコンテンツ ]
読みもの
・新しい「ほぼ日」のアートとサイエンスとライフ。
・19歳の本棚。
NO.160
センセイの蓄音機
6月21日の昼夜2回、「はじめての蓄音機――三浦武さんの手回し演奏会」というイベントを行いました。

三浦さんは、大手予備校・河合塾で国公立大クラスの「現代文」を担当している現役講師です。キャリアはすでに25年。
「これまで何人もの生徒の人生をいい意味で狂わせてきたことで有名」「現役生からも浪人生からも絶大な人気がある」「彼の授業を受けた生徒は、本が読みたくなる、学ぶことが好きになる」という話を耳にして、初めてお会いしたのが、2013年の春でした。
細かい経緯は省きますが、初対面でいきなり蓄音機の話になりました。予期した通り、いわゆる好事家の“趣味”のレベルを超えていて、氏の生き方そのものと抜き差しならない本質的なテーマであることが伝わってきました。
結果として、どういうことが起こったのか? 次に聴かせてもらった蓄音機の音に、私がたちまち虜(とりこ)になってしまったのです。
以来、何度となく歴史的な名演奏(クラシックが主ですが、ジャズあり、シャンソンあり)の名盤を、三浦さんの絶妙な解説つきで堪能させてもらいました。ほぼ日がまだ青山にあった頃、会社まで蓄音機持参で来ていただき、デモンストレーションをお願いしたこともありました。

その時は、坪内逍遥がみずから訳したシェイクスピア『ベニスの商人』を朗読しているレコードを聞き、それから徐々にヴァイオリン、ピアノの楽曲、そしてジャズ、シャンソンといった順に、何曲かを試聴させていただきました。
<大きくもない箱から響き出てくる曲は、
なんとも言えず豊かにふくらみがあって、
耳から気持ちよさが入ってくるわけです。>
次の日の「今日のダーリン」に、糸井さんがその感動を記しています。とりわけ驚いたのが、この一曲――。
<で、で、です、なかでもびっくりしたのが、
ルイ・アームストロングの演奏でした。
「サッチモという愛称のだみ声のおじさん」くらいしか
思ってなかったというのが正直なところでした。
彼の歌う「この素晴しき世界」はCMなどにも使われて、
いい歌だなぁと思っていた人も多いとは思いますが。
ところが、歌がはじまる前のトランペットの音が、
正確で・繊細で・温かくて・切ないんだなぁ‥‥と、
かなり大盛りなほめ方をしたいくらいすばらしかった。
やさしいのだけれど、突き刺さってくるような表現です。
ラッパの音で、涙がにじんだもの、こんなのはじめて。
これはおそらく、蓄音機のおかげだったのだと思います。
家に帰ってから、彼の曲をあらためて聴いたけど、
あんなにしびれなかったですから。
長く生きてきて、まだ初めてことだらけですねぇ。>
(「今日のダーリン」2017年8月31日)
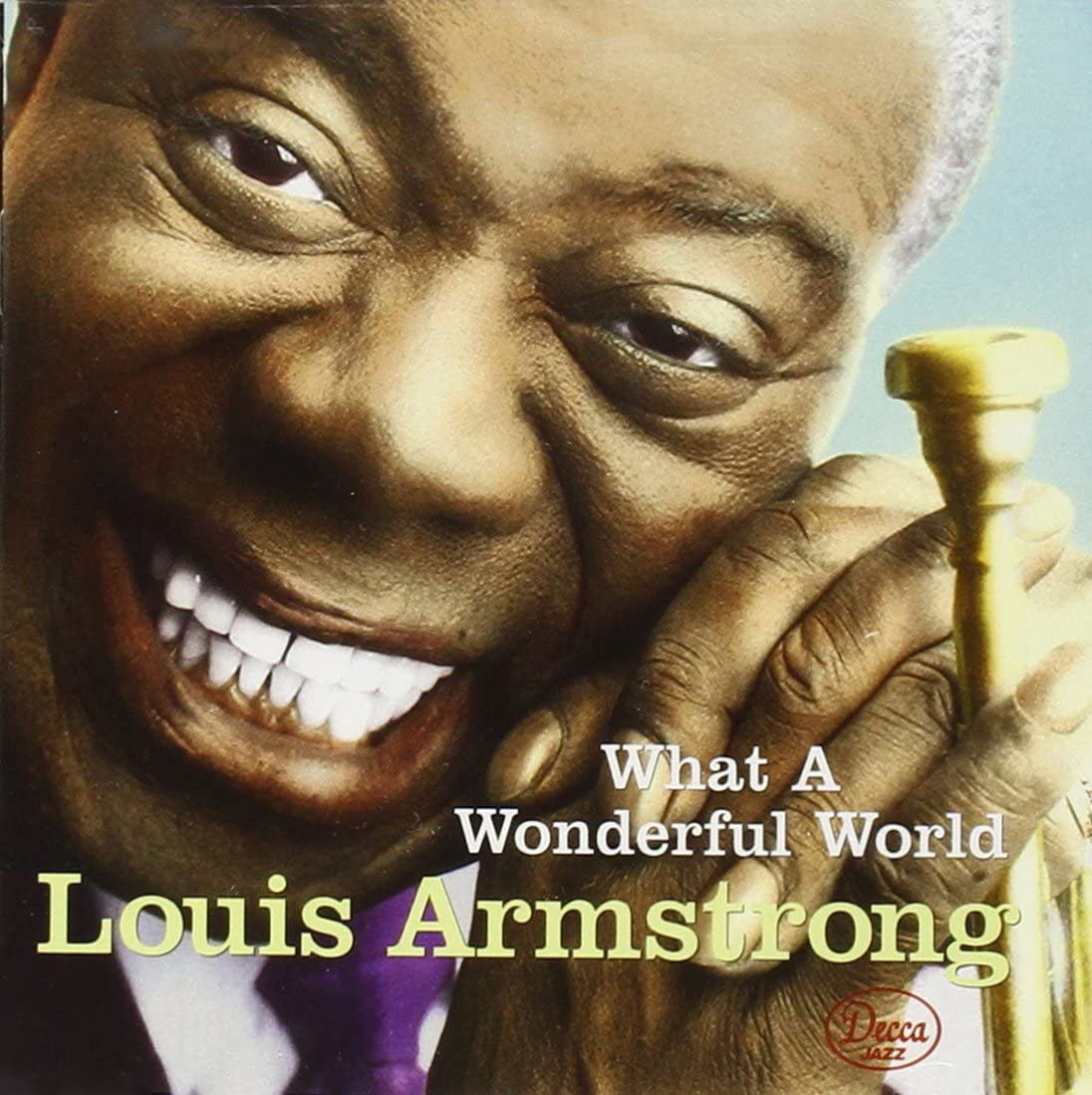 『What A Wonderful World/ルイ・アームストロング』
『What A Wonderful World/ルイ・アームストロング』
大袈裟にいえば、その時以来の宿願が、今回ようやく実現したと言っても過言ではありません。三浦さん愛蔵の蓄音機を2台ほぼ日の學校の教室スタジオに持ち込んで、貴重なSPレコードのコレクションから「はじめての人に、ぜひ聴いてほしい!」という名盤を選りすぐり、ドラマチックな解説とともにたのしい講義にしてくださいました。
授業の様子は「ただいま製作中!」にも即日レポートされましたが、三浦さんの解説をさらに深読みしたいという方には、三浦さんがいま連載中の「ヴァイオリニストの系譜――パガニニの亡霊を追って」(小林秀雄に学ぶ塾同人誌 「好*信*楽」)をご案内しておきます。
ジネット・ヌヴーという、30歳で航空機事故死したフランス人女性ヴァイオリニストと三浦さんが運命的な出会いを果たした1989年8月11日の話(その六「蓄音機の一撃~ジネット・ヌヴーと出会った夏」、エディット・ピアフと彼女の恋人であったプロボクサー、マルセル・セルダン、そしてセルダンとヌヴーを乗せたエール・フランス機が1949年10月28日未明、大西洋上の島に墜落した事故のこと(その五「パリのヴァイオリニスト~ジネット・ヌヴー」)、初めて日本が迎えた世界的なヴァイオリニスト、ミッシャ・エルマンを東京で聴いた「浪人生」の小林秀雄、翌月に京都で聴いた「浪人生」の梶井基次郎の話(その三「浪人時代の記憶~ミッシャ・エルマン」)等々です。
ほぼ日の學校での名調子とはまたひと味違う、三浦さんのパセティックな(悲哀を誘う)文章が、音楽と切り結ぶ人間の切実なドラマを描き出します。
さて、予備校で受験勉強を教えるかたわら、昼休みなどに生徒を集めて蓄音機を鳴らしているという三浦さん。同じ連載のなかで、みずからの予備校観、文学観についても語っています。少し改行を加えて、引用します。
<予備校で現代国語などを教えていると、時々不遜なヤツがやって来て、「先生、文学なんか読んで何か意味があるんですか」などとおっしゃる。
形式上は質問だが、これは「文学になど意味はない」という反語であり、一種の抗議である。
わざわざ言いに来るヤツは僅かだが、そう思っている諸君は少なくないだろう。
なるほど君には意味がないのだろう。
それは君が人生の危機を知らない幸福者だからだ。
奈落の淵に置かれた人間は、文学とか芸術とかを求めるものらしいぜ?
生きるに必要なものを求め尊重するのは当然だ。
それは生物として生きる人間にとって必然的なことだ。
ということは、ひょっとしたら、生きるに必要のないものこそが、生物としての人間ではなく、それを超えて、人間としての人間を成り立たせているのかも知れないじゃないか。
君は、物事を合理的に考えようとしているのだろうが、どうせならそれを合理主義として徹底してみたらいい。
純粋に必要ということだけを価値として考えるなら、自分が、この宇宙にたった一回存在するということ自体、無意味だということになるんじゃないか?
そのような虚無に陥らぬために、文学の切実な意味を知ってそれに賭けた人間の感動をわかっておくというような、そんな経験もまた必要なものかも知れないよ?>(その二 「運命愛のひと~ダヴィッド・オイストラフをめぐる系譜」)
三浦さんには、ほぼ日の恒例だった「勉強の夏、ゲームの夏」(2017年8月25日)にご登場願ったこともあります。この時、同業の塾講師の方から寄せられた「国語の学習法」についての質問に、こう答えています。
「本を読むことは、とても大事です。
なので、やっぱりおすすめは、
本を読むことですかね。
でも本を読むのが
苦手な子もいると思うので、
そういう人は「人の話を聞く」というのも、
読書と近い体験になりますね。」
「僕の授業は90分の授業で、
本文解説と称して60分しゃべります。
でも、解き方を教え込むのではなくて、
読み方や視点を伝えるための話なので、
授業後は、
小論を1本読んだような気分になると思います。
そして、もっとその作家を知りたくなる。
毎年、近代文学史という
2時間の特別講義をしているのですが、
翌日、みんな文庫本を持っていますよ。」
三浦さんの担当するクラスは、学力的にはトップレベルの生徒が多いと聞きます。したがって、情報処理能力はとても高いそうなのですが、どうも著者の思考の態度に学ぼうとする発想がないのではないか。書き手に対する謙虚さや敬意が欠けているのではないか、とある時に話してくれたことがあります。だから自分は文章を読む時に、著者に対する敬意をもって、丁寧に文脈をたどる読み方を心がけている、と。

「近代作家への敬意を、
本気で伝えていますから、
古いとか難しそうという先入観が
なくなるのだと思います。
あとは、
作家の映像を見せるのもいいですね!
芥川龍之介の木登り姿とか。」
「完成した文章だけでなく、
作家の顔や肉体をみると、
書いた人の人間性が見えてきて、
おもしろいです。
そうすると、
その小説を批評するのではなく、
作家の作品に対する愛に
包まれるといいますか。
書かれたことを理解するのではなく、
書いた人を理解するような
人間愛が生まれるんです。」
蓄音機の講座は、この先シリーズ化しようと考えています。古いレコードを蓄音機で聴くという体験が、本を読むこと、文学に親しむこと、学ぶということにいかに密接に関わってくるか、追い追い明らかにしたいと思います。
最後に今回、衝撃的だったひとつの出来事を報告しておこうと思います。夜の部の最後の最後に、それが起きました。
<エディット・ピアフは男から離れられない女だ。そして離れずには済まない女だ。>
三浦さんは先の連載(「その五」)にこう記しているのですが、そのピアフのもっとも有名な歌「愛の讃歌」(1950年)を聞いているさなかに、それは起きました。先述したように、ピアフは1949年10月28日、ニューヨーク・ラガーディア空港でパリからやってくる恋人マルセル・セルダン(そしてジネット・ヌヴーらの一行)を待ち受けていました。傍らには女優のマレーネ・ディートリッヒが寄り添っていました。

『The Platinum Collection/エディット・ピアフ』
しかし、パリ・オルリー空港を発った飛行機が、ニューヨークに到着することはありませんでした。
「この青空が崩れ落ちても、この大地が割れてしまっても、あなたの愛さえあれば、わたしはかまわない‥‥」――あなたが死んで遠くへ去っても、あなたの愛があるなら、わたしはかまわない‥‥。甘美なメロディーとは対照的に、激しいことばの並ぶ歌詞。
永遠に帰らぬ人となった最愛の人マルセルに捧げた愛の誓いではないかと、「愛の讃歌」については語られます。しかし、この歌詞が完成していたのは、実はセルダンの死の前年だったといわれます。
ピアフは、この時すでに、カサブランカに家庭をもつセルダンとの「別れ」を心に秘めていたのではないか。「愛の讃歌」というのは、本当は「終わり」の歌ではなかったのか。
三浦さんがそう解説して、「愛の讃歌」に聴き入っていたまさにその時、レコードに突然、終焉の時が訪れます。
何百回、いや何千回聴かれたのかはわかりませんが、聴かれる度に盤面を削られていったSPレコードが、ついに「事切れる」瞬間にわれわれは立ち会うことになったのです。思わず声を上げてしまいました。厳粛な思いに襲われました。
「あなたの燃える手で‥‥」と岩谷時子さんが日本語に訳した「愛の讃歌」を歌い続けたのは、越路吹雪さんです。彼女は、1953年にパリに3ヵ月滞在し、ピアフのステージを4月23日、5月7日の2度観ます。
5月7日
「ピアフを二度聞く。
語ることなし。小林さんも感激していられた。
私は悲しい。夜、ひとりで泣く。
悲しい、淋しい、私には何もない、何もない、私は負けた。
泣く、初めてパリで」
彼女は日記に、こう綴ります。この時の小林さんとは、かつてエルマンの初来日を「浪人生」で聴きに行った、文芸批評家の小林秀雄です。彼は作家・今日出海とともにヨーロッパを旅行中でした。
思えば、三浦さんと私が初めて会うきっかけになったのも、小林秀雄です。「私は文学が好きだ」というセリフを広言することはなかったにもかかわらず、「私は音楽が好きだ」と告白することについては、生涯、躊躇(ちゅうちょ)することがなかった小林です(杉本圭司『小林秀雄 最後の音楽会』新潮社、参照)。
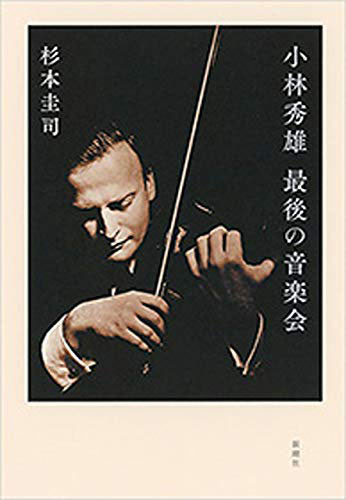
蓄音機で鳴らすSPレコードは、いろいろな人の存在感をありありと再現してくれます。過去の遺物と思われた古い箱やレコードが、鮮烈で実在感のある音を奏でます。そして、50~100年昔の空間が、当時のままに立ち上がってくるような錯覚を与えます。
かつてそこにいた人が起こした空気の震えをいまに伝える、魔法の箱としてそこにあります。
2021年6月24日
ほぼ日の學校長![]()
*7月10日(土)に神田ポートビルの「ほぼ日の學校」にて、大野裕之さんの「ディズニーとチャップリン」と題したレジェンド二人について、ひもとく授業を開催予定です。ただいま、チケット発売中です。くわしくはこちらからどうぞ。
(また次回!)
2021-06-24-THU




