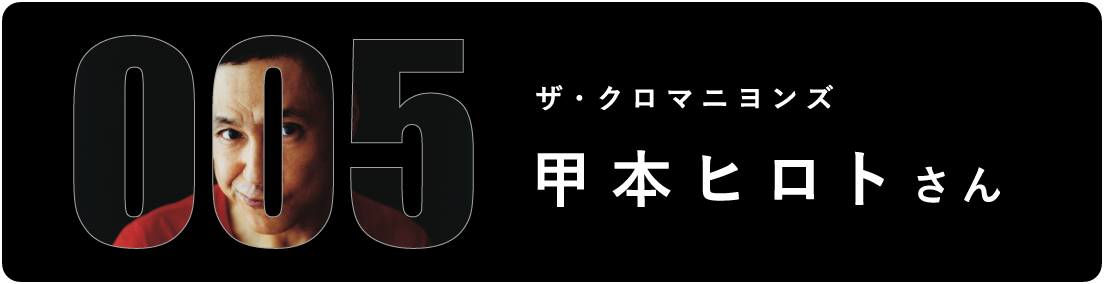ザ・クロマニヨンズの甲本ヒロトさん。
バンドとは? 音楽とは?
歌って何で人の心を撃つのでしょうか。
‥‥なんて、それらしいような、
ロックの取材っぽいことを聞いても、
まあ、だめでした。
「ヒロト」が、「ロック」について、
ただ、アタリマエのことを言うだけで、
「バンド論。」なんて浅い器を、
気持ちよくひっくり返された気分です。
とくに「前説」はありません。
ロックンロールが聴きたくなりました。
全6回の連載。担当はほぼ日奥野です。
甲本ヒロト(こうもとひろと)
2006年7月の「出現」以来、すでにシングル18枚・アルバム13枚・全国ツアー15本など精力的に活動してきたザ・クロマニヨンズのボーカリスト。過去、クロマニヨンズのギタリスト・真島昌利とともに、ザ・ブルーハーツ、ザ・ハイロウズとしても大活躍。一般のファンだけでなく、多くのミュージシャンからも熱狂的な支持を受けている。2020年12月には、最新アルバム「MUD SHAKES」を発表。新型コロナウィルス感染拡大の影響から、同月「配信ライブ」をはじめて開催。変わらぬザ・クロマニヨンズの音楽、変わらぬロックンロールを配信し、全国のファンから大反響を得た。2021年2月20日には「ザ・クロマニヨンズ MUD SHAKES 2021」を開催。
- ──
- ヒロトさんは、パンクロックを聴いて、
いますぐ、ぼくにもできると‥‥。
- ヒロト
- 思った。楽器をやったこともないし、
音楽の知識もなかった。 - 作詞だってしたことはない。作曲も。
- ──
- それでも。
- ヒロト
- できると思った。パンクを聴いたとき、
「あ、これならできる、誰よりできる」
って思ったんです。
- ──
- 誰より。
- ヒロト
- でね、親に、すぐ言ったの。
それが中学2年か3年のころなんだけど。 - 「お父さん、日本の法律では、
子どもは、中学まで行けばいいんだろう」
「ぼく、中学を卒業したら家を出て、
ひとりでロックやって暮らすから」って。
- ──
- ロックの宣言! お父さんは‥‥。
- ヒロト
- 「おまえ、失敗したらどうすんだ」って。
- だから、ぼくは
「失敗したら、死ぬだけだ」
「死にゃいいんだろう、大丈夫だ」って。
- ──
- わあ。
- ヒロト
- 「かんたんだろう、そんなこと。
だってぼく、これしかやりたくないんだ。
だから高校へ行っても意味がないよ。
中学は3年、きっちり卒業します。
そしたらもうぼく、好きなことをやるよ。
ロックンロールをやって生きていくんだ」
って。 - いきなりそんなこと言われて
「わかった、応援してやる」なんて親は、
どうかしてる。いまなら、わかります。
- ──
- はい、たしかに。
- ヒロト
- でも、そのときぼくの中では、
絶対にロックンロールしかないと思って、
それしかないと信じていたから、
親と揉めたんだよ。大ゲンカになってね。 - 親も、大変なことになったぞって。
それまで、おねだりも何にもしないほど、
おとなしい子どもだったのに、
なんで急にそんなこと言い出すんだって。
- ──
- ええ。
- ヒロト
- ぼくには、どんな言葉も響かなかった。
絶対に、自分が正しいんだと思ってた。 - そんで、最終的に、
お父さんをブン殴っちゃったんですよ。
- ──
- えっ、あ‥‥そうでしたか。
- ヒロト
- 顔面を。グーで。
- ──
- グ、う、わー‥‥‥‥はい。
- ヒロト
- そのときの感触、まだここにあります。
- それで、これは、ちがうと思ったんだ。
ロックって、こんなことをしてまで、
やるもんじゃないだろ、絶対ちがうよ。
そんなようなことを、
なんかフィジカルに感じたんですよね。
- ──
- 親を殴ってまでやるもんじゃない、と。
ロックンロールというものは。
- ヒロト
- それで、納得はいってなかったけれど、
親の言うことを聞いて高校へ行った。 - で、上京の口実で大学受験して、
親を騙して、なんとか東京に出てきた。
- ──
- そこまでは、バンドはやらなかった?
- ヒロト
- アマチュアでやる気がなかったんです。
- まわりには、いくつかバンドがあった、
高校生のときには。
でも、そこに混ぜてもらったりだとか、
仲間を集めたりする気はなかった。
- ──
- どうしてですか。
- ヒロト
- 最初から本気でやるつもりだった。
1曲目から
オリジナルを歌おうと思っていた。
- ──
- 1曲めから!
じゃ、曲はつくってあったんですか。
- ヒロト
- ない。
- ──
- ない‥‥?
- ヒロト
- ないけど、それは「ある」んだよ。
- 曲はつくるっていうものじゃない。
すでに「ある」んで、
それが、不意に、出てくるだけで。
- ──
- ああ、なるほど。
- ヒロト
- ロックンロールってそういうもの。
- 竹馬とおんなじなんだよね。
ジッと見てて乗れると思った瞬間、
もう乗れているんだ。
練習しなくたって、やれるんだよ。
- ──
- パンクを聴いて
「誰よりもやれる」と思ったのも、
同じことですか。
- ヒロト
- そう、でも一回、上京する直前に、
おもしろいことが起こった。
- ──
- 何ですか。
- ヒロト
- ぼく、わりと進学校に通ってたんで、
バンドやってた連中、
みんな高校3年の夏休みくらいから、
受験勉強をやり出したんだ。 - でも、ぼくはブラブラしてたら、
何人か、まだバンドやりたい連中が、
メンバーを探していたんだよね。
- ──
- ええ。
- ヒロト
- で、「ヒロトは、なんもせんの?」
って聞くから、
「うん。なんもせん」と言ったら、
「音楽、好きなんだろ?」って。
「好きよ」って。 - そしたら
「じゃ、歌ってみる?」と言われて。
- ──
- 言われて!
- ヒロト
- 友だちのバンドで歌ったんですよ。
あそびはんぶんの気持ちで。 - でも、そのとき、こう言ったんだ。
「ぼく、歌ってもええけど、
絶対にオリジナル曲しか歌わんよ」
そう言って、はじめて
即席で2曲、オリジナルをやった。
- ──
- そこが、ヒロトさんの、はじまり!
- ヒロト
- 鼻歌で歌って、こんな歌っつって。
じゃあやってみようかって。 - 夏休みの自主コンサートみたいに
披露したりした。
そのバンドがみんな上京したんで、
何回か、その仲間と
ライブハウスでやったりしていた。
- ──
- あ、それがつまり
ラウンドアバウトというバンド?
- ヒロト
- うん、うん。すごくいい仲間です。
- ──
- はじめて歌を歌ったとき、
どういうことを、感じたんですか。
- ヒロト
- いけると思った。
- 人の歌をコピーするんじゃなくて、
そもそもコピーしたことないけど、
ああ、いいなあ、
自分のやりたいことをやるのって、
こういうことなのかって。
- ──
- ひとりでロックをやっている人も
いると思うんですが、
バンドでと思ったのはなぜですか。
- ヒロト
- ぼくを惹きつけた音楽の大部分が、
バンドの音楽だったから。
カッコいいんですよ。
ただ、ただ、カッコいいんだよね。 - 何をどうカッコいいと思うかって、
人それぞれだけど、
ぼくには、バンドがカッコいい。
それはもう、怪獣と同じくらいに。
- ──
- 怪獣レベル。
- ヒロト
- そう、ベムラーみたいな感じだね。
あれになりたかった。
ぼくは怪獣になりたかったんだよ。
- ──
- 冒頭でもおっしゃってましたが、
そういう「バンド」に、
いまだに、憧れているんですか。
- ヒロト
- 憧れています。あんなふうになりたい。
- だから‥‥やりたいっていうより、
ぼくは「なりたい」んだね。やっぱり。
- ──
- なりたい。バンドの人に。
- ヒロト
- ぼくにはやりたいことがあるんですって、
そういう言い方をするけど、
ほんとは、なりたいものがあるんだよね。
- ──
- ただ、ぼくらからしてみると、
ヒロトさんはもう、
バンドの人になっていると思うんですが。
- ヒロト
- いや、なってないよ。
だって、いま、ふつうの人じゃない。
- ──
- ぼくの目の前にいるのは、
あの有名な「甲本ヒロト」ですけど‥‥。
- ヒロト
- ちがうちがう、ちがうんだよ。
こうしてふつうに生きているときは、
バンドの人でもなんでもない。
4人で集まって、
ステージの上でガッってやった瞬間、
そこに「バンド」が現れるんだ。 - だから、いまここで、
あなたの前でしゃべっているぼくは、
ただのバカなんです。
- ──
- あっ‥‥そういうことですか。
- ヒロト
- あれになりたいから、またやるんだ。
- ──
- つまり、その都度その都度、
バンドの人に「なってる」んですか。 - ライブのたびに、ヒロトさんは。
- ヒロト
- そうです。
- ──
- 何十回も、何百回も。憧れの人に。
- ヒロト
- そうです。
- たった1回で満足するわけじゃないし、
あれになりたくなくなったら、
バンドなんて辞めているよ。そうだよ。
(つづきます)
2021-02-23-TUE