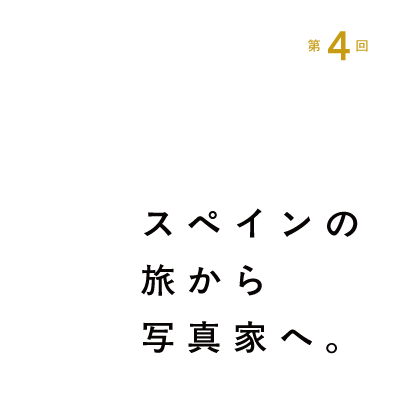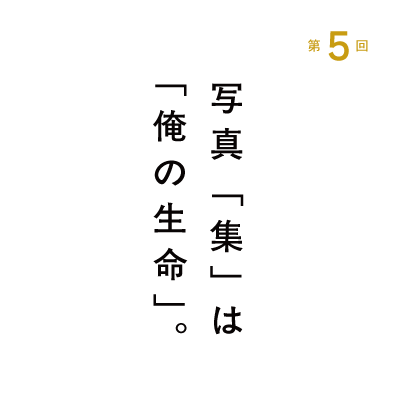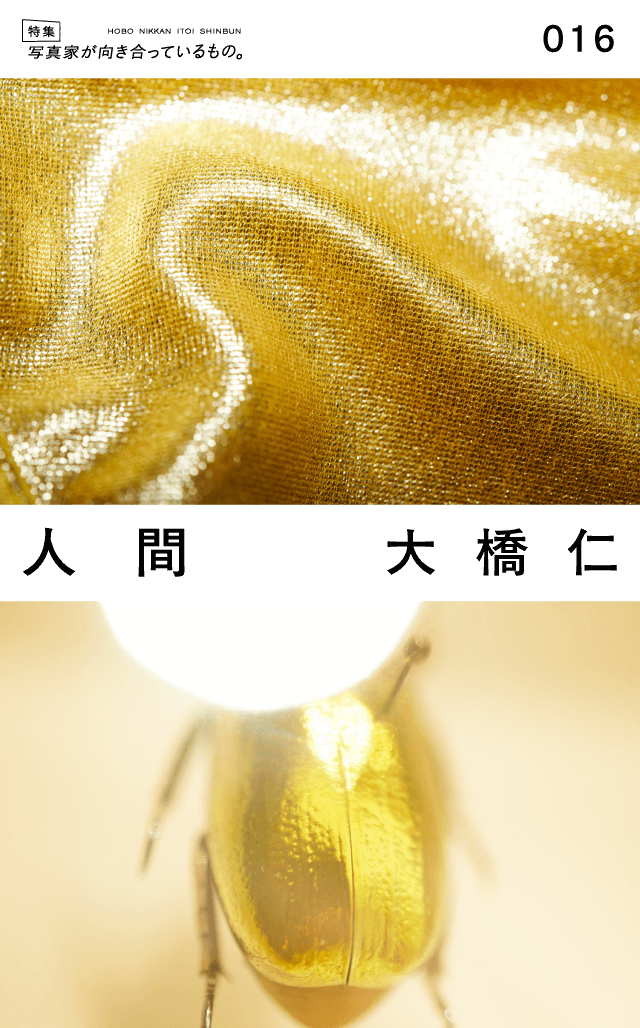
この写真家にインタビューできなければ、
この現代写真家インタビュー連載には、
決定的な「欠け」があると思っていました。
なのに、長らくできなかったのは、
その作風のせいか、
勝手に「怖い人」というか、厳しい人、
激しい人じゃないかと思っていたからです。
実際の大橋さんは、
自分の欲求に対して真摯で真面目で、
人間や生命の不思議や謎を探り続けている
少年探検家のようでした。
センセーショナルな写真集で
世間を賑わせている側面ばかり見ていては、
「大橋さんの写真」のことを、
理解しきれないままだったろうと思います。
全7回、担当はほぼ日の奥野です。
- 大橋
- 大丈夫ですかね‥‥こんな話で。
ここまでしゃべっておいて、何ですが。
- ──
- 大丈夫じゃないでしょうか。たぶん。
こんなにもまじめに考えている
生命の根源の不思議についての話ですし。
出てくるのはパンティとかだけど。 - それにいまって、性教育とかについても、
家庭でもオープンに話したりとか、
徐々に考え方も変わってきていますし、
闇雲にタブー視するのは、
少し時代に合っていない気もしますしね。
- 大橋
- あ、そうですか。
- ──
- ただし、大橋さんの話って、
まじめなんだけど、
なぜだか、どこかに、
ちょっとした「おもしろエッセンス」が
効いてるんですよね(笑)。 - 昔からそういう子どもだったんですか。
- 大橋
- まず、うちの実の親父なんかが、
性についてはだいぶオープンだったんです。 - お前は、お父ちゃんとお母ちゃんが
「俗にいうところの女性器の名称」をして
生まれたんだからな‥‥って、
ことあるごとに吹き込まれていたんです。
うちの中では
「俗にいうところの女性器の名称」って、
ふつうに使われていて、
子どものころの自分にとっては、
すごく当たり前の自然な言葉だったんです。
性について、
まったくフタをしない家庭だったんですよ。
- ──
- うちとは、ぜんぜんちがうなあ。
- うちはテレビの「バカ殿」とかで
エッチなシーンが出てきちゃったら最後、
「しーん」みたいな家だったんで。
何だかもう、恥ずかしくて恥ずかしくて。
- 大橋
- そういう育ち方も関係してるのか、
自分の生命が、そそられるほうというか、
呼ばれるほうへ
フラフラ~って寄っていっちゃうことが、
自然なんです。
- ──
- そういう大橋さんが、
「写真」を表現の手段にしたというのは、
どういうきっかけがあったんですか。
- 大橋
- 精神的に写真を撮ってみようと思えたのは
荒木経惟さんの影響ですが、
たまたま親父がカメラ好きだったので、
機材を買う手間もなく
撮影をはじめやすかった部分はありますね。 - 親父は印刷屋さんをやっていたんですけど、
当時、中判のカメラとか持ってたんです。
プラウベルマキナとか、小西六のセミパールとか。
- ──
- あー、プラウベルって
石川直樹さんが使っているカメラですよね。
ボディが薄くて蛇腹の、かっこいいやつ。
- 大橋
- そうそう、一般の人は持ってないような。
雑な扱い方してたんで、
レンズにカビ生えちゃったりしてたけど。 - ぼくが18歳のときに、父親の計らいで、
「一人旅せえや」みたいなことで、
お金を出してくれて、
スペインへ一人旅へ活かせてくれまして。
 大橋仁『はじめて あった』より
大橋仁『はじめて あった』より
- ──
- 素敵なお父さんだなあ。
- 大橋
- そのときに持っていったのが、
キヤノンの「AE-1」ってカメラでした。 - それには60mmマクロの接写レンズが
ついてたんだけど、
つまり、いちばん最初に出会った
そのレンズが、
のちの自分の「接写好き」とかにも、
影響を与えていると思うんですよ。
- ──
- 今作を象徴するパンティもコガネムシも、
接写ですもんね。 - 写真家としての大橋仁さんに、
めちゃくちゃ影響を及ぼしていそうです。
- 大橋
- ふつうのレンズだと寄れないところまで、
マクロレンズでは寄れちゃうから。
無限の視覚を手に入れた、みたいな感じ。 - あのとき、望遠レンズを渡されてたら
どうなってたんだろう。
遠くのものしか撮らない人っていうか、
被写体から
やたら距離を取る写真家になったかも。
- ──
- すごく長いレンズで、
遠くのパンティを撮っていたかも‥‥。
- 大橋
- ただのヤバい人じゃないですか。
- ──
- でも、「最初の道具」が、
その後の自分を決めてるっていうのは、
おもしろい話ですね。 - 写真家さん以外でもいろいろありそう。
はじめて手にしたギターが、
レスポールかストラトかでちがうとか。
- 大橋
- おふくろの味じゃないけど、たしかに。
- そのレンズで育ったから、
何を撮るか、どう撮るか‥‥みたいな
影響があると思います。
- ──
- で、スペインでは何を撮ったんですか。
- 大橋
- 日常の場面だとか、
現地でできたスペイン人の友だちとかですね。 - アンダルシアのちいさな街に、
父親の友人がいるというので
2週間ほど滞在をさせてもらったんですが、
行ってみたら、
父親の友だちの友だちの友だちの‥‥みたいな、
父親のことさえ、
ほぼほぼ知らない人だったんですよ(笑)。
- ──
- ほとんど無関係の人ですね、それは(笑)。
- 大橋
- アンダルシアのアロラという街で
当時で50才過ぎの男性の日本人画家と、
けっこう年下の日本人の奥さま、
それにちいさな息子さんお一人のご家庭でした。
旦那さんと奥さまは
20才くらいの歳の差夫婦で、
ふたりで世界中を放浪して暮らしていたそうで、
とても暖かく迎えてくれて、
途中から親戚みたいになってました。 - 全旅程で言うと、スペインに1か月、
フランスに20日でした。
- ──
- あ、そんなに長い旅だったんですか。
- 大橋
- マドリードから入ってアロラ、
マラガってピカソが生まれた場所を経て、
バルセロナのほうへ向かいました。 - いま「ロマ」と呼ばれてるんでしたっけ、
ジプシーの人たちを撮ったりしながら。
- ──
- ええ。
- 大橋
- 彼らは差別されていて、衝撃的でした。
アロラの日本人画家の旦那さんに紹介された
同い年のホセ・マヌエールってやつがいて、
田舎暮らしで貧しいんだけど、
何かもう、すごく性格のいいやつでね。 - ジェントルマンだし、日本人のぼくを
やさしくもてなしてくれたりとか。
- ──
- おお。
- 大橋
- 夜になると
プールサイドがディスコになる場所があって、
あるとき、そこでみんなで遊んでたんです。
そのとき、そのやさしいホセ・マヌエールが、
ある2人の男の子を、
絶対に席に座らせなかったんです。
何でだろうと思ってたら、
彼らふたりジプシーの子だったんです。 - ぼく、事情を知らなかったから、
椅子を持ってきて、
「きみらも座んなよ」ってすすめたら、
ホセ・マヌエールが
「いいんだよ、ジン。
あいつらは立ってる。一緒には座らない」
って。
- ──
- へええ‥‥そうなんですか。
- 大橋
- あれはエグかったなあ。
- だって、ふたりも会話に入ってるんだよ。
ニコニコしながら。
輪の中にいるメンバーではあるんですよ。
それなのに差別されてるんです。
何だろう、根の深いものが、
すぐ身近にあるっていう感じがしました。
- ──
- そういうところから、
大橋さんの写真ははじまってるんですね。
- 大橋
- キヤノンが主催していたコンクールの
「写真新世紀」にも、
ジプシーたちの写真を出してます。
あとは、
当時付き合ってた女の子のつむじとか。
- ──
- つむじ?
- 大橋
- 接写でつむじとか目のアップを撮ってた。
当時、裸は撮ってませんでした。 - そのころ、
世の中的には女性のセルフヌードが流行ってて、
作品として
発表してる女性もたくさんいたんだけど、
あんなの、よく撮れんなぁって思ってた。
自分の裸なんて、
よくもまあ人の前にさらせるもんだなと。
- ──
- そのときは、そう思ったんですね。
- 大橋
- そうなんですよ。思ったんですよ。
自分をさらして恥ずかしい、
すげえなぁと思って、
びっくりしたもんです、まだそのころは。
- ──
- じゃあ、そのあとに、
1作目の『目のまえのつづき』を出した。 - それが20代の半ばくらいですか。
- 大橋
- 26のときです。
- 18、19くらいから撮りはじめた作品が
けっこう貯まってたんですが、
義父の自殺未遂に遭遇したのが、21のときなんです。
その前後5、6年のできごとを収録したのが、
1冊目の写真集でした。
- ──
- 表紙からして、
めちゃくちゃインパクトがありましたよね。 - シーツに染み込んでいく、
お父さんの真っ赤な「血」の写真ですけど。
でも、その場面を撮ったのが21歳で、
そこから本になるまでに
5年くらいかかってるのはなぜなんですか。
- 大橋
- 義父が自殺した場面を撮ったときには、
何も考えてなかったんです。 - 驚いて、反射的に、
ただただ夢中で撮っていただけで、
もう、写真だとか作品だとか何だとか‥‥
ましてや
写真集を出すなんてことは、まったく。
- ──
- そうですよね‥‥それは。
- 大橋
- でも、そうこうしているうちに、
グラフィックデザイナーで
マッチアンドカンパニーの町口ってやつに
声をかけられたんです。
- ──
- 造本家の町口覚さん。
- 大橋
- それまでの自分は、
パルコのギャラリーでグループ展やったり、
リクルートの「ひとつぼ展」で
入選したりとかは、まあ、していたんです。 - で、あるとき会場で町口が声をかけてきて、
そこになぜか
当時の青幻舎の安田(英樹)社長もいて、
「写真集、出さへんか」
みたいなことになったんですよ、たしか。
- ──
- おお。
- 大橋
- そう言われて、はじめてその気になった。
24、25くらいのときです。 - で、一気に編集して出したって感じです。
- ──
- 曖昧な質問になってしまいますけど、
それから長く、
大橋さんでしかないような写真を
撮り続けてきたわけじゃないですか。
- 大橋
- ええ。
- ──
- いま、「写真」って、
どういうものだって思っていますか。
- 大橋
- うーん‥‥たまに考えるんです。
「撮らなくなることが、あるのか?」
とか、
「自分のなかから、
写真が消えるときが来るのか?」とか。 - つまり「反応・衝動」みたいなものなんです。
食欲とか性欲なんかと同じように、
内側から「湧いてくるもの」なんです。
- ──
- 大橋仁にとって、写真とは。
- 大橋
- 生きるうえで必要な、反応と衝動と欲求。
- だから、それらが湧かなくなったときが
「終わるとき」なのかな。
- ──
- 大橋さんの「生命活動」みたいなものが?
- 大橋
- そう。
 大橋仁『はじめて あった』より
大橋仁『はじめて あった』より
(つづきます)
2024-11-10-SUN
-
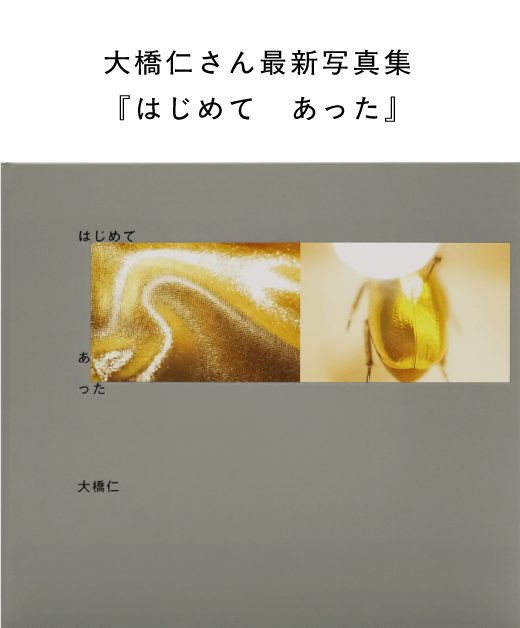
荒木経惟さんをして
「これが現代アートだ」と言わしめた作品
『そこにすわろうとおもう』から10年、
大橋仁さんが
「過去の3作品とくらべて、自分の頭の中、
脳細胞やメンタルやDNA、
生命の記憶の領域へ足を踏み入れてる感じ」
と位置づける第4作。
写っているのは金のパンティとコガネムシ。
(もちろん、それだけではありませんが)
このインタビューを読んで、
もし「大橋仁」という写真家、
というか「人間」に興味を持たれましたら、
ぜひ、手にとってみてください。
みなさんの感想を、聞いてみたいです。
販売サイトは、こちらです。