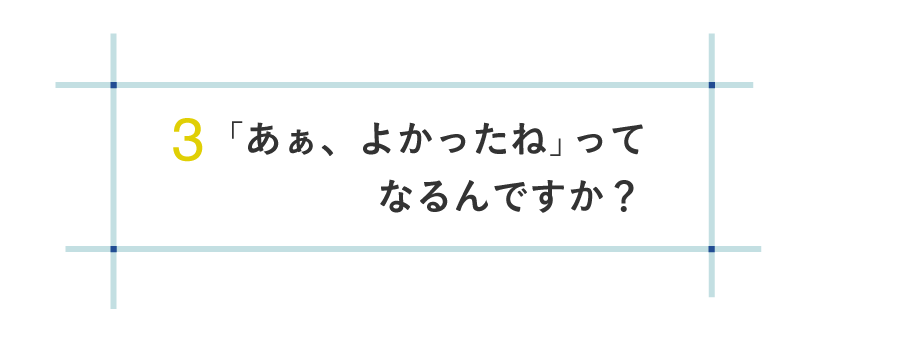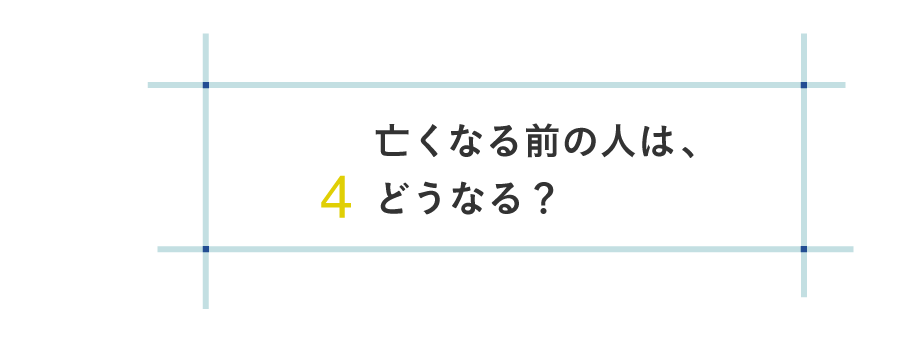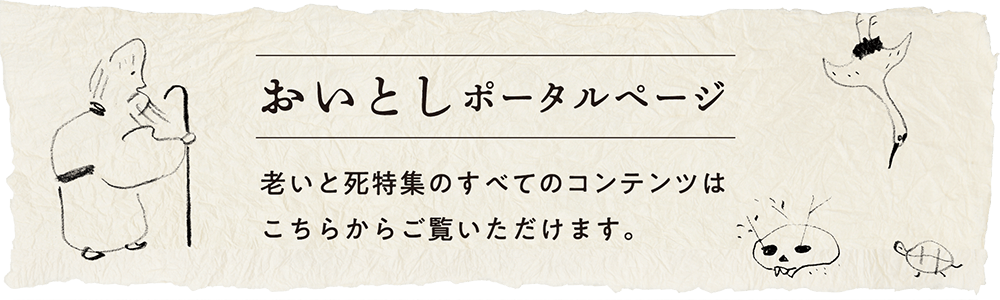たとえば高齢の親が、病気などによって
「終末期」にさしかかった場合、
どう考え、どう行動していけば、
いちばん幸せな最期を迎えられるのだろう?
ほぼ日の「老いと死」特集、
第3弾は、緩和ケア医の西智弘先生と、
がんの当事者である
写真家の幡野広志さんによる
「終末期医療」のお話です。
よい死を迎えるためにはどうしたらいいか、
患者と家族が知っておきたいことについて、
いろいろと教えていただきました。
西智弘(にし・ともひろ)
一般社団法人 プラスケア 代表理事
川崎市立井田病院 腫瘍内科 部長
2005年北海道大学卒。
川崎市立井田病院にて、抗がん剤治療を中心に、
緩和ケアチームや在宅診療にも関わる。
2017年には一般社団法人プラスケアを立ち上げ、
代表理事として、
「暮らしの保健室」「社会的処方研究所」の
運営を中心に、地域での活動に取り組んでいる。
著書に、
『がんを抱えて、自分らしく生きたい
──がんと共に生きた人が
緩和ケア医に伝えた10の言葉』
(PHP研究所)、
『社会的処方──孤立という病を
地域とのつながりで治す方法』
(編著、学芸出版社)、
『だから、もう眠らせてほしい
──安楽死と緩和ケアを巡る、私たちの物語』
(晶文社)など多数。
幡野広志(はたの・ひろし)
写真家。血液がん患者。
1983年、東京生まれ。
2004年、日本写真芸術専門学校中退。
2010年から広告写真家・高崎勉氏に師事、
2011年、独立し結婚する。
2016年に長男が誕生。
2017年多発性骨髄腫を発病し、現在に至る。
著書に
『なんで僕に聞くんだろう。』(幻冬舎)
『ぼくたちが選べなかったことを、
選びなおすために。』(ポプラ社)
『ぼくが子どものころ、ほしかった親になる。』
(PHP研究所)
『写真集』(ほぼ日)
『ラブレター』(ネコノス)など。
最新刊は
『うまくてダメな写真とヘタだけどいい写真』
(ポプラ社)。
- 幡野
- 本人が望んでるわけでもなくて、おそらく誰も
したくもされたくもないのに、
ある意味「強制的な延命」をして、
「心臓停止した90歳の人に無理なマッサージをやる」
って、どうなんですかね。 - 90歳の患者さん、心臓止まりました。
心臓マッサージしました。
やって肋骨が折れました。
内臓傷ついてます‥‥という状態で
息を吹き返したら、その後どうするんですか?

- 西
- 困るんですよ。
- 幡野
- 実際に息を吹き返すことってあるんですか。
- 西
- あります、あります。
- 幡野
- そのとき、たぶん肋骨折れてますよね?
内臓に刺さったりすることもありますよね。
- 西
- ありますよ。
- 幡野
- で、息吹き返しました。
みんな「あぁ、よかったね」ってなるんですか?
- 西
- まぁ、そのときは。
- だけど、本人は苦しいじゃないですか。
そのつらさもあるし、それでたとえば
「じゃあこれからもとの元気な姿に戻っていきますか?」
っていうと、かなり厳しいわけですよ。 - もう90歳で、心肺停止とかになって、
でもギリギリ生存したときに
「じゃあ、口から入ってる管を抜けないから、
首を切ってここから管入れましょう」
「人工呼吸器外せないよね」といった話になっていったときに、
「この患者さん、誰が看るんですか?」という。 - 「お家にお返ししますんで、ご家族で、
子供で、どうぞ」ってやると、
「いやいや、うちでは看れませんよ」となって、
結局家族も不幸になっていくんです。 - 本人だって、家族に負担かけようなんて
望んでたはずがないのに、それで苦しむとか。
- 幡野
- それ、結果的にどういう状況になるかを
知らなかったからですよね。
- 西
- だから延命を望んだにもかかわらず、
「生きてるのは嬉しいんだけど、
介護させられるのはダメです」みたいな。 - それもあるし、
「じゃあお金出して介護施設に入れますか?」
と言ったら「お金はありません」となって、
「じゃあ、どうするつもりなんですか?」って言ったら
「‥‥‥‥」というのは、ときどき発生します。
- 幡野
- うーーん。
- 西
- だから家族が「延命、延命」って望んだとしても、
「じゃあその行きつく先は、誰がどう
責任をとってやっていくつもりですか?」
となると、そこはノープランで。 - 「生きてるだけですばらしい」みたいなところしか
見ないようにして、
その先の誰が面倒をみるかとか、お金とかに関しては、
まったく何もタッチしない。
- 幡野
- 病院とかで、そういう教育的なことを
する方っていないんですか?
- 西
- いないです。
- 幡野
- まぁ、したとしてもトラブルが起きそうですもんね。
- 西
- はい。だからけっこう家族が
「もう看れないから」とか言って、
そのままバックレちゃうとか。
- 幡野
- え?!
- 西
- 生かすのはいいんだけども、
ほんとに家族と連絡とれなくなっちゃって、
「病院に365日入院」みたいな方、いますよ。
- 幡野
- ああ、社会的入院ですね。
- 西
- ほんとならば
「家族のほうで転院させてください」
「介護施設に入れてください」
「家に引き取ってください」とか
ぼくらもお願いするんだけど、
「できませんので」とか言われてしまって。 - だから家族の方も、最初は
「なにがなんでも延命を」だったのが、
途中からはおそらく
「なんだか面倒なことになってしまった」
という感じなのかもしれなくて。
- 幡野
- まじですか。
- 西
- だから、自分で引き取る気もないし、
お金を出して介護施設に入れる気もないから、
「もうこのまま病院で、最期まで
置いといてくれたらいいんですけど」という。
- 幡野
- うーん‥‥。
- 西
- だけどそれはいまの医療システムではできないので、
病院からも「困る」って言うんですけど。
- 幡野
- それが80、90歳の方ですよね。
人間が80、90年も生きて、
最期がそれって、
「ご本人は望んでたのかな?」って
考えてしまいますよね。
- 西
- ご本人、そんなに望んでないと思います。
そんな状態で、家族から見放され、
医療者からも煙たがられ、誰も来ず。 - まぁ看護師が来ますけど、
「そこでただひたすら生かされてるだけの
人生を望みますか?」って聞かれて、
「いや、私はそれでも生きてるほうがいいですね」
と言う人って、
まぁ、ほぼいないと思うんです。 - だからやっぱり事前に話し合うとか、
「自分はこういった状態のときはこう生きたいんだ」
とか考えておいたほうがいいんですよ。

- 幡野
- ぼくはがん患者なんで、
自分がそっちの立場に陥る可能性があって。 - ぼくはわりと早々に
「家族親戚と縁を切る」という選択をとったんです。
親もそうだし、よく知らないおじさんとか
おばさんとか、いとことか。
なぜかみんな「親族」というだけで、
口出しする決定権を勝手に
持ってる気持ちになっちゃうんですよ。 - だから「いや、何十年か前にちょっと
会っただけだったよな?」
というような人が口出ししてくる。
そういう相手に、自分の最期を
決められちゃう可能性があるわけです。 - ぼくが死にかけました、親族が集まります。
「じゃあこのままゆっくり死んでいきましょうか」
みたいになったときに、そういう人が
「いやちょっと待て! 延命すべきだろう」
みたいになる可能性ってありますよね。 - だからそれを防ぐために、結局もうこっちとしては、
危険度の高い家族と距離をとるしかない。 - ぼくは妻にも
「もしなにかあって、ぼくの意識がほぼなくなって、
もう死にそうってとき、絶対に連絡しないでほしい」
って言ってるんです。
連絡したら来ちゃいますから。 - 来てしまったらもう、
「カリフォルニアから来た娘症候群」といった
言葉とかもありますけど、
それまでまったく付き合いのなかった
親族が急にやってきて、
いろいろ口出しをする可能性がある。 - そういうことを防ぐには、こっちが先に選ぶというか、
「関係を切る」しかないんですよね。 - だけどなんだかそれって、
あんまり健康的じゃないんですよね‥‥
いや、病人だからすでに健康的じゃないんだけど。
- 西
- (笑)
- 幡野
- でも患者さんって、みんな親族に連絡しがちですよね。
- 西
- うん。病気がわかったとき、
親族に連絡する方は多いです。
- 幡野
- 病院の椅子とか喫茶店とかで
「実はこのたび肺がんになりまして‥‥」
とか電話してる人、よく見るんですよ。 - だけどそういう姿を見るたびに
「それ、言わないほうがいいんじゃないかな」
ってぼくはちょっと思ってしまう。
自分の経験を思うと、メリットは薄いかも。
- 西
- ただ、これは全然統計とかじゃなくて
ぼくの感覚での話ですけど、
最近ぼくの診てるがんの患者さんたちだと
「ほんとに親しい人以外には言わない」
という人が増えてきてるとは思います。
団塊の世代ぐらいの、70歳ぐらいの人たち。 - 家族でもほんとに親しい人だけ、
「配偶者と子供にしか言ってません」みたいな。
とりあえず兄弟とか、他の親族には言わない。
- 幡野
- そうなんですね!
- 西
- で、「ほんとに本人の意識がなくなって、
もう亡くなるかもしれないくらいのときには
言っていいよ」みたいなルールにしてる人たち、
けっこういます。
- 幡野
- でもなんか親族とかって、
伝言ゲームで伝わっていきませんか?
- 西
- いや、だからそれはもうほんとに、
「本人」とたとえば「妻」、
その2人しか知らないんです。
それで「絶対ほかの親族には言うな」って。
子供は知ってる場合があるけど。
- 幡野
- なるほどね。これまでの常識とは別に、
脈々とそういうライフハックが生まれてるんですね。
- 西
- うんうん。
- 幡野
- ただそういうのも、地域と年齢で
ちょっと違うような気はします。 - うち、東京でも田舎のほうなんで、
近隣で病気になってる人の話は、
ぼくの耳にすら入ってきますから。
- 西
- おそろしいですね。
- 幡野
- だからもう絶対に言いたくない。
- 西
- 昔の人だとやっぱり、
親族とか近所の人に言うとかって
けっこうありますよね。
- 幡野
- たぶん昔の人たちが周りに言ってたのは、
社会制度の不備が理由だったのかなと思うんです。
健康保険だって、できたのは戦後ですよね。
だからその前の世代は
「親族間で助け合いましょう」とか、
親族、兄弟、仲間でなんとかする時代だったのかなと。 - いまは、そんなことをしなくていい
時代だと思うんですけれど。

- 西
- そうですね。昔に比べると、
だいぶ個人主義的な感じになってきてるから、
昔みたいに広くいろんな人に伝えるケースは、
少なくなってきたように感じます。
- 幡野
- 正直ぼくもがんになったとき、
最初、友達とか仕事の人が
たくさんお見舞いに来てくれて、
ありがたいはありがたかったけど、
すべての人たちに対応することが
大変ではあったんです。電話もすごくて。
- 西
- そういう点も、たしかに少しずつ
変わってきてるとは思います。 - 葬儀とかもそうじゃないですか。
昔だと、ほんとに会ったこともない
親戚の葬式まで行ってましたけど、
最近そういうの、ないじゃないですか。
「内々で済ませました」とかよく聞きますよね。
- 幡野
- そうですね。
- 西
- 要はその、たいして親しくもない関係で葬式に来て、
お悔やみの言葉をかけるのも嫌だし、
かけられるのも嫌だ、みたいな。
「そこはもう親しい人たちだけで」
みたいな感覚の人が増えている感じはします。
(つづきます)
2024-07-18-THU