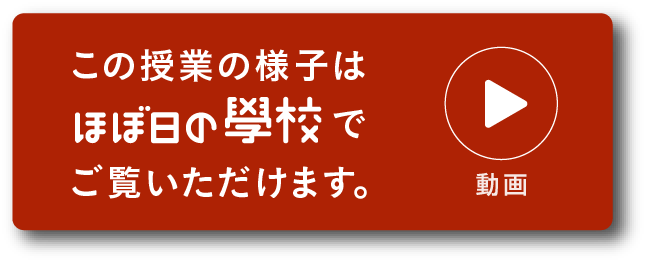エミー賞・ゴールデングローブ賞をW受賞した
ドラマ「SHOGUN 将軍」の音楽を担当した
作曲家の石田多朗さんが、
雅楽の魅力を教える授業を
ほぼ日の學校でしてくれました。
「雅楽のコンテンツをやりませんか?」
という一通のメールを石田さんが
ほぼ日に送ってきてくださって、
糸井重里がそのメールに興味を持ったことから
はじまったこの授業。
石田さんが出会ったとき受けた“ワクワク感”を含めて、
雅楽の魅力を熱く語っていただきました。
今日から、7回にわたってお届けします。
雅楽という広大な森にいるような
不思議な気持ちになる授業です。
石田多朗(いしだ・たろう)
1979年アメリカ合衆国ボストン生まれ。
上智大学にて国文学・漢文学を専攻後、
東京藝術大学音楽学部に入学。
2018年、株式会社Drifterを設立。
雅楽の楽曲制作などを通して、
これまでにない日本の音楽のあり方を日々研究・制作し、
発表をする。
2024年、ディズニー製作のハリウッドドラマ
「SHOGUN 将軍」
(作曲Atticus Ross、Leopord Ross、Nick Chuba)の
日本伝統音楽に関する総合アレンジャーとして参加。
エミー賞とゴールデングローブ賞のW作品賞受賞に
貢献するとともに、
エミー賞の作曲賞、メインテーマ賞の2部門で
ノミネートを果たす。
また「SHOGUN(将軍)」のサウンドトラックは、
グラミー賞「最優秀映像作品スコア・サウンドトラック」部門にノミネート。
- 石田
- ここで雅楽を実際に聴いてみましょう。
こちらは「伶楽舎(れいがくしゃ)」という
日本を代表する雅楽の団体です。

- 石田
- 楽器をご紹介すると、
右上の上に向いているのが「笙(しょう)」。
その左側で、両手で吹いているのは、「篳篥(ひちりき)」、
その左側が、横笛が「龍笛(りゅうてき)」、
龍笛の前がお琴で、「箏(そう)」と言います。
右側でギターのように鳴らしているのが、
「楽琵琶(がくびわ)」、で、
楽琵琶の前が、「鞨鼓(かっこ)」という、
横をとんとんとんと叩く楽器。
中央にある太鼓が「楽太鼓(がくだいこ)」。
その左の太鼓が「鉦鼓(しょうこ)」と言います。

- 石田
- このように楽器が並んでいて、
どの楽器も個性の固まりです。
「せーの」で演奏すると、このようになります。
1分ほどかけてみたいと思います。
- 石田
- これで、雰囲気を思い出していただけましたでしょうか。
- これだと複雑でちょっとわかりづらいかもしれないので、
「笙」の音楽だけをかけます。
聴いて胸に湧いてくる感想を聞かせてもらっても
いいでしょうか。
演奏は中村華子さんです。
- 石田
- 一人ずつ、感じたことを伺っていいですか。
どう思われました?
- 乗組員1
- 息継ぎしているかなとちょっと心配になりました(笑)。
- 石田
- それで言いますと、笙はハーモニカと同じで、
吹いても吸っても音が鳴る仕組みになっていて
永久に音が鳴り続けているように
聞える仕組みになっています。
- 乗組員1
- そうでしたか。どのタイミングで
呼吸をしていいかわからなくて‥‥。
吸い込まれそうになって聴いていました。
- 石田
- なるほど。ありがとうございます。
糸井さん、どう思われましたか。
- 糸井
- 僕もちょっと同じことを思ってました。
とにかく呼吸と演奏がぴったりになっている。
演奏者の息づかいと音楽が一緒っていうように、
すごい肉体的なものだなと感じました。
あと、もう一つは一人パイプオルガンみたいでしたね。
- 石田
- ちなみに、音楽的な感想っていうのは湧いてきます?
- 糸井
- 音楽的感想というか、
自然の中にいるみたいな気持ちになりました。
- 石田
- あ、すごい、それは鋭いです。
ありがとうございます。
- 乗組員2
- 私もパイプオルガンを聴いているような気持ちになって、
近くから聞こえる音もあれば、
遠くから聞こえる音もあるような、不思議な感じがしました。
- 乗組員3
- 一つの楽器で、複雑な音色が出ていることを
不思議に感じました。
聴く前は、たくさんの人が一斉に吹くことで
あの音が出るのかなと思っていたんですけど、
一人であの音が出ることを知りました。
印象としては、吸い込まれそうな気持ちになりました(笑)。
- 乗組員4
- 複雑な音の重なりのように感じました。
でも、馴染みはある感じがしました。
- 石田
- あ、わかります。ありがとうございます。
- 乗組員5
- 複雜な音で、
失礼な言い方かもしれないですけど、
何を思って演奏しているんだろうと思いました。
- 石田
- あ、そうですよね。そのクラシックの曲みたいに、
「今、悲しいな」とか、「今、楽しいな」じゃないような
雰囲気を感じるっていうことですかね。
ありがとうございます。 - この音楽を後で、もう一度かけますね。
そこでまた感想を聞いてみたいと思います。

- 石田
- ここで、雅楽の歴史を
ざっくりとお話をさせていただきます。 - 1400年ほど前にシルクロードを伝わってきた音楽文化が、
韓国あたりから日本に流れ込んできました。
日本にはもともと「国風歌舞(くにぶりのうたまい)」
という歌があったんですけど、
それとミックスをされて、
平安時代の中期頃、8世紀頃に雅楽は完成しました。 - 雅楽は、驚くべきことに、
その後1300年ほどほとんど変化せずに、
演奏されつづけている音楽なんです。
これは、世界でもまれなことです。
韓国で雅楽に近い音楽はあったのですが、
時代と共にどんどん変化していったようです。 - 大昔の音楽研究をするなら日本に来たほうがいいと、
いまフィリピンの研究者が
日本に雅楽を研究しにくるぐらい、
変わらない形で温存されてきました。 - ではなぜ雅楽が温存されてきたのか。
私は、当初、日本はものすごく保守的で、
「変化させたくない」という理由で温存されてきたのかなと、
最近まで思っていたんです。
ですが最近、考えを改めました。
このことは後ほどお話させてください。 - 雅楽はこの1300年間、
ほとんど形が変わってないことを
覚えておいていただければと思います。 - ちなみにバッハは17世紀から18世紀を
またにかけた作曲家です。
バッハが活躍する約1000年ぐらい前に
すでに雅楽ができていたのは、
本当に恐ろしいことだと思います。

- 石田
- 「SHOGUN 将軍」のサウンドトラックは
ロサンゼルスの3人の作曲家たちと
一緒に制作しました。
私が担当していた邦楽のアレンジは、
相性が合っていたのか、
だいたい「オッケー」って感じで、
すーすーっと作業が進んでいたんです。 - でも、ひとつだけ、
「これは要らない」って言われた音楽があって。
それは和太鼓だったんです。
和太鼓のドンドンドンドン、ドンドンドンドン‥‥
みたいな音楽を聴いてもらったときに、
「ノーサンキュー」って言われたんですよ。
「いや、めっちゃいい音だよ。
日本の和太鼓ってすごくいいんだよ」と
私は言ったんですけど、
「日本の音楽に求めているのは、マジックだ」
と言われたんですよ。 - 太鼓の音は素晴らしいんだけど、良さがわかる。
良さがわかるからノーサンキューで、
ほしいのはマジックだと。
つまり、手から炎が出るとか、頭にハテナマークが出るけど
成立している音楽を求められていると私は受け取ったんです。 - 雅楽ができた平安時代について考えてみると、
貴族が和歌を詠んだり、
亀の甲羅をあぶってヒビが入ったから引っ越ししたりとか、
呪術と政治と医学と文学がわかれておらず、
ミックスされた状態だった。
そんな時代の音楽だったわけです。 - もちろん、当時は当時で
貴族と平民のようなわけ方はあったと思うんです。
だけど現代とはわけ方が違ったんだと思うんですよね。
例えば、現代だと男・女でバキンとわけると、
男でも女でもない人が困るということが
だんだんわかってきた時代です。
雅楽を勉強しているうちに
いろいろなことを「わけるのは合っているのかな」と
思うようになってきました。 - 現代は、わけた後に修復しようとしている時代
と思うんですが、
私が持っていた「わかる」とか「わける」とかの感覚は
本当にいいことなのかなと。
何かを無くしてわかるようにしているのではないかと
だんだん思ってきました。 - その「SHOGUN」の作曲家たちとは、
「わからない」とか「わけない」ということ大事にして、
レイヤーを薄く、重ねていくような
作曲法を取ることにしました。
真田広之さんの後ろで、
うわーんとムードを作るようなイメージで作曲したんです。
そういう考えを元に作曲した雅楽は、
「SHOGUN」のなかでいい効果を発揮したと思っています。
(つづきます)
2025-02-20-THU