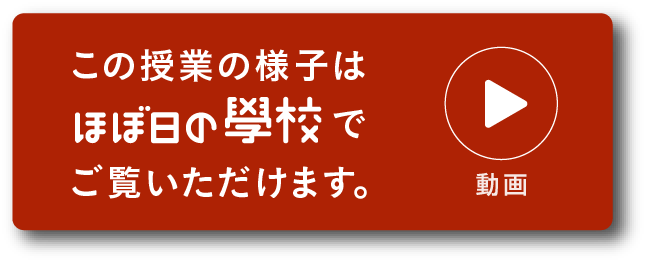エミー賞・ゴールデングローブ賞をW受賞した
ドラマ「SHOGUN 将軍」の音楽を担当した
作曲家の石田多朗さんが、
雅楽の魅力を教える授業を
ほぼ日の學校でしてくれました。
「雅楽のコンテンツをやりませんか?」
という一通のメールを石田さんが
ほぼ日に送ってきてくださって、
糸井重里がそのメールに興味を持ったことから
はじまったこの授業。
石田さんが出会ったとき受けた“ワクワク感”を含めて、
雅楽の魅力を熱く語っていただきました。
今日から、7回にわたってお届けします。
雅楽という広大な森にいるような
不思議な気持ちになる授業です。
石田多朗(いしだ・たろう)
1979年アメリカ合衆国ボストン生まれ。
上智大学にて国文学・漢文学を専攻後、
東京藝術大学音楽学部に入学。
2018年、株式会社Drifterを設立。
雅楽の楽曲制作などを通して、
これまでにない日本の音楽のあり方を日々研究・制作し、
発表をする。
2024年、ディズニー製作のハリウッドドラマ
「SHOGUN 将軍」
(作曲Atticus Ross、Leopord Ross、Nick Chuba)の
日本伝統音楽に関する総合アレンジャーとして参加。
エミー賞とゴールデングローブ賞のW作品賞受賞に
貢献するとともに、
エミー賞の作曲賞、メインテーマ賞の2部門で
ノミネートを果たす。
また「SHOGUN(将軍)」のサウンドトラックは、
グラミー賞「最優秀映像作品スコア・サウンドトラック」部門にノミネート。
- 石田
- 雅楽を聴いたときに、
第一印象としてなじみの音楽というより
遠い音楽と感じる人が多いかなと思っています。 - 私が雅楽を勉強しはじめたとき、
変わったところだらけで、
他の音楽と共通点を見つけるほうが難しいと思いました。
雅楽はそのぐらい変わっている音楽です。 - 雅楽がどれだけ変わっているかを挙げると
100個くらいあるのですが、
今日は7つに絞ってお伝えします。 - とりあえず7つのポイントをお伝えするので、
まずは聞いていただければと思います。
そしてそのあと、
なぜ雅楽がこんなに変わっているのかということの、
私なりの解釈をお伝えします。

- 石田
- 先ほど聞いてもらった曲は
「越天楽(えてんらく)」という曲です。
雅楽ではすべての曲を合奏で演奏します。 - クラシックの楽譜は縦に線が引かれていますよね。
複数人で演奏するときは、
線のところで一斉にテンポを合わせますよね。
テンポが合っていることがいい演奏なんですけど、
雅楽は笙も篳篥も龍笛も、全員が必ず常にずらします。 - バシンと合わせると、みんな笑っちゃうぐらいだそうで、
それぞれがタイミングをずらして、
ぬるぬる、ぬるぬる演奏します。
タイミングが合っちゃうと
演奏できなくなっちゃうそうです。 - 楽譜を見るとタイミングが合っちゃうから、
楽譜を見ずにタイミングをずらして演奏する
という特徴があります。

- 石田
- 2つ目は指揮者がいないこと。
これは特に海外の人が驚きます。
「これだけの人数で演奏するのに、
前で指揮棒を振る人がいないなんて、誰に合わせるの?」と。 - 雅楽の演奏者は隣の人を見たり、
周りの雰囲気を感じたりして、
「あの人がこうやってるから、こうする」とか、
「あの人の演奏がちょっとゆっくりだから
私が引っ張っていこう」のような感じで、
関係性で音楽を作っていくという特徴があります。
一人のリーダーに引っ張ってもらうのではなく、
周りに合わせて演奏するのはちょっと日本っぽいですよね。

- 石田
- 3つ目は、雅楽の演奏者たちと関わるなかで、
私が知ってびっくりしたことです。
先ほどかけた「越天楽」っていう曲は
全員同じメロディを演奏しているんです。
もう一回、聴いてみましょう。
- 石田
- 龍笛も打楽器も同じ曲を演奏している、
つまり同じ歌を歌っているつもりなんです。
演奏家に聞くと、全員が同じフレーズを吹いている、
それが違う形になっているだけっておっしゃるんです。 - 例えば、オーケストラの曲の場合、
ピッコロ、フルートは高い音を担当しています、
コントラバスは低い音を担当しています、
今回、バイオリンがメロディを担当していますというように、
それぞれの楽器に役割がありますよね。 - でも雅楽の演奏家は全員、ユニゾンで演奏しているんです。
つまり、何が起きるかというと、
ここから篳篥がいなくなってもまったくかまわない。
演奏が成立してしまいます。 - 先ほど、笙を一人で演奏している映像を見ました。
あれも複数で演奏する曲なんですが、
一人ずつ引っ張り出して「演奏して」とお願いしても、
一人ずつ演奏できます。
なぜなら、同じメロディを吹いているから、
何も関係ないんですよ。 - これはすごい変わっていて、
アメーバみたいだなと思ったんです、
演奏者が一人、二人いなくなってもまったくかまわない。
でもオーケストラの場合は
コントラバスだけが演奏していると、
ちょっと成立していないってなっちゃうと思うんです。
雅楽は、一人で演奏しても成立するんです。

- 石田
- 4つ目が、テンポの特徴。
先程聞いてもらった音楽は短かったので
わかりづらいんですけど、
8分くらいの曲だとわかりやすいです。
はじめからおわりまで、
曲のテンポが基本的にずっと上がり続けます。 - ずーっと上がり続けていって、
最後かなり速くなって、バンと終わる。
テンポが必ず上がっていく音楽は
世界的にもかなり珍しいです。

- 石田
- 雅楽にも「調」があります。
クラシックでいうハ長調、ト長調のような調が、
一応あります。

- 石田
- 左側の調子のところ、
上から双調(そうじょう)、
黄鐘調(おうしきちょう)、
壱越調(いちこつちょう)、
平調(ひょうじょう)、
盤渉調(ばんしきちょう)、
これが調の名前でそれぞれが、季節、方位、五行など
特徴が決まっているんです。 - 例えば、一番下の盤渉調は、
季節が冬、方位は北、五行でいう水と、
調と他の要素がもう固まっているんです。 - 「今日は冬だから、盤渉調の曲を演奏しましょう」という
ことが当たり前のように行われています。
さらにややこしいのは、あまり強い拘束力はないこと。
「別に冬に(春の)双調をやっても、いいか」
という感じで演奏してもいいのが、日本っぽいところです。
でも基本的には、定まっています。

- 石田
- 6つ目が、この笙という楽器について。
細い竹が17本、集まってできています。
口から息を吹き込むと、
息がリードが付いた竹にあたり
音が出る仕組みになっています。

- 石田
- この竹はドレミファソの順に並んでいません。
音程がバラバラ音程が並んでいて、
素人が演奏しようと思ってもどうなっているか
わからないくらいです。 - おそらく西洋の文化だと、
ピアニカみたいに音の順に並べると思います。
なぜなら、演奏しやすいから。 - でも、雅楽は決してこの形を崩しません。
なぜかというといろいろな理由があると思うんですが、
ひとつは、笙は鳥である鳳凰が舞っている姿を模していて、
それを崩したくないのです。
鳥が舞って、羽をぱっと開いた瞬間の形に留めたいから、
形をずらさないんです。

- 石田
- こちら「龍笛」という楽器です。
横笛なので形はフルートと似ているんですが、
龍笛のいい演奏は、
50%が楽器の音、残りの50%は息の音を漏らすことです。
息の音を漏らすのは
クラシックだと、「下手くそ」って言われてしまうんです。
ちょっと注意深く聴いてみてもらっていいでしょうか。
- 石田
- 「フゥゥゥーッ」っていうのが入っている。
聞こえます?
龍笛を演奏しているのは伊崎善之さんで
とても上手な方です。
雅楽の楽器は、龍笛に限らずなんですけど、
楽音だけをきれいに取り出すみたいなことはなく、
基本的にノイズがもうたんまり入った状態で
演奏をしていくという特徴があります。 - 以上、7つのポイントをお伝えしました。
頭がちょっと疲れてきますよね。
雅楽には特徴がまだまだたくさんあるんですが、
今日はこれくらいにしておきます(笑)。

- 石田
- で、先ほど申し上げましたように
雅楽の作曲をはじめてしたときには
毎日、知れば知るほど謎だらけで
取り付く島もないという感じだったんです。 - でも、これだけほかの音楽と被らない、
こんなにずれているということは、
「立脚しているポイントが
私が今まで知っていた音楽と根本的に違うとしか思えない」
と感じたんです。 - 雅楽は特徴を出そうとして出しているわけではない。
ということは、
その立脚ポイントを知るべきだなと思ったんです。
(つづきます)
2025-02-21-FRI