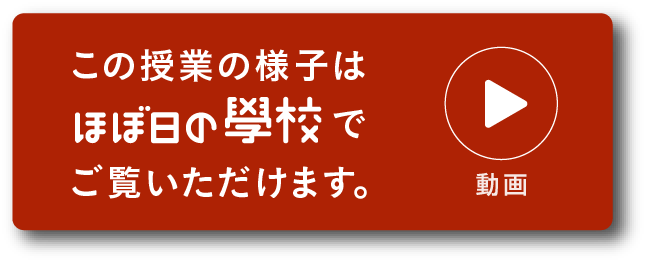エミー賞・ゴールデングローブ賞をW受賞した
ドラマ「SHOGUN 将軍」の音楽を担当した
作曲家の石田多朗さんが、
雅楽の魅力を教える授業を
ほぼ日の學校でしてくれました。
「雅楽のコンテンツをやりませんか?」
という一通のメールを石田さんが
ほぼ日に送ってきてくださって、
糸井重里がそのメールに興味を持ったことから
はじまったこの授業。
石田さんが出会ったとき受けた“ワクワク感”を含めて、
雅楽の魅力を熱く語っていただきました。
今日から、7回にわたってお届けします。
雅楽という広大な森にいるような
不思議な気持ちになる授業です。
石田多朗(いしだ・たろう)
1979年アメリカ合衆国ボストン生まれ。
上智大学にて国文学・漢文学を専攻後、
東京藝術大学音楽学部に入学。
2018年、株式会社Drifterを設立。
雅楽の楽曲制作などを通して、
これまでにない日本の音楽のあり方を日々研究・制作し、
発表をする。
2024年、ディズニー製作のハリウッドドラマ
「SHOGUN 将軍」
(作曲Atticus Ross、Leopord Ross、Nick Chuba)の
日本伝統音楽に関する総合アレンジャーとして参加。
エミー賞とゴールデングローブ賞のW作品賞受賞に
貢献するとともに、
エミー賞の作曲賞、メインテーマ賞の2部門で
ノミネートを果たす。
また「SHOGUN(将軍)」のサウンドトラックは、
グラミー賞「最優秀映像作品スコア・サウンドトラック」部門にノミネート。
- 石田
- 雅楽を知るにつれて、
「雅楽は、今まで知っていた音楽と
立脚しているポイントがあまりにも違う」と感じました。
「あまりにも違うとしか思えない」と。
それで、私なりにいろいろ調べてみました。 - 雅楽のことを説明するために、服の話をしますね。
平安時代の成人女性の衣装に
十二単(じゅうにひとえ)があります。 - 十二単のことを調べると、
当時のお洒落というのはいかに自然に似ているか、
自然に近いかが大事なポイントだったらしいんです。
例えば、「森がテーマ」とすると、
葉っぱの薄緑、緑、土の茶色、木通(あけび)の紫色
というように服の色を重ねていき、森を表現する。
月が見えてきたら黄色の服を使うとか、
自然を十二単で表現するのが
どうやらお洒落だったようです。 - いわば自然のコスプレですよね。
自然のコスプレがいちばん素晴らしいとされていたようです。
このことは文献にも残っているんです。 - これは、ある意味、自然崇拝とも言えます。
当時は、今よりも自然だらけの環境だったと思うんです。
だけど、今より自然崇拝の気持ちは強く、
自然と同化したいとか、自然がカッコイイっていうのが、
当然のものとなっていたと知りました。
それを知って「ひょっとすると、雅楽も同じことなのかな」
と思ったんです。 - 雅楽を知るまで、音楽というのは、
「私から糸井さんに曲を捧げます」というように
人から人に伝えていくのが音楽だと思っていたんですね。
人から人に伝えて、感動する、何か動きが起こるというのが
音楽だと思っていたんです。
私はもちろん、そういう音楽も大好きなんですけど、
どうやら雅楽の人たちは、
自然に対して訴えかけるもの、
もしくは自然と人間の中間のものとして
雅楽をつくろうとしていたんじゃないかなと思った瞬間に、
いろんなことが氷解していき、
いろんなことが理解できるようになりました。

- 石田
- 先ほどの、雅楽の7つのポイントも説明ができます。
1番目が、「全員があえてタイミングをずらして演奏する」
ということでした。
このことを、海でも氷河でもどこでもいいんですけど、
森を例にお話をさせていただきます。 - 森にいて心地いいときを思い出すと、
鳥がピヨーと鳴いていて、風がサーと吹いていて、
遠くで人が歩いているような音がカサカサッと聞こえて、
ランダムに音が鳴っているときだと思うんですよ。 - 自然の中にいて、
カエルと鳥と葉っぱが同時に音を鳴らしたら、
「なんか違う」と思いますよね。
森はランダムにいろんなものが鳴っているのが美しいし、
心地いいと人間は感じると思うんです。
心地良さを追求してジャストで合わせることは、
おそらくやらないんだろうなと私は思いました。 - 2つ目が、
大人数で演奏するのに指揮者がいないことです。
生物学者の南方熊楠の本などを読むとわかりやすいのですが、
森は何か一つの生命が
すべてを統括するようにはできていなくて、
それぞれの虫や生き物が自分のために生きていますよね。
それが集まって一つの生態系になっていく。 - 雅楽が生態系のようになっていると考えたとき、
日本人は「指揮者を立てよう」とは言わないと思います。
先ほど、雅楽の演奏者は
「日本人っぽく、周りの息を読んでいる」と
言っていたんですけど、根本的なところでも
日本人の考え方が表われている音楽だと思っています。 - 3つ目は
「全員が同じメロディを演奏しているつもり」という話。
いろんな生命が森の中でそれぞれの生き方をしているけれど、
それぞれが生命や生態系を維持するという意味においては、
皆、同じことをしている。
テントウムシとアリは、
交互に助け合っているんでしょうけど、
たぶん誰も役割分担していると思って
生きていないはずなんですよね。
「俺は葉っぱを落とす係」とかは思ってなくて、
それぞれが自由に生きているだけであって、
結果的に上手くいきましたという話だと思っています。
そういったところも、私が雅楽が好きなポイントの一つです。 - 4つ目は、
「テンポが上がっていく」というところ。
この特徴は雅楽の本ではよく書かれているのに
理由は一切書かれてないので、
私が作曲しているうちに会得した感覚をお伝えします。
どんな音楽でも繰り返しの部分があるんです。
クラシックでも4小節繰り返す場合、
基本的に同じテンポで繰り返すんですね。
テクノやロックも繰り返しますよね。 - 雅楽も同じように「繰り返し」があるんですよ。
だけど繰り返したときに
最初は長めに演奏して、次には少し短めに演奏するんです。
そしてその次も少し短めに演奏します。 - このことが何を意味するのかわからなかったんですけど、
ある日、わかりました。
5歳のときの1年間と、
40歳のときの1年間って体感がぜんぜん違う。
時間でいえば、まったく同じなんですけど、
体感が半分ぐらいに感じる。
そのことと、雅楽で演奏を繰り返すときの長さが
連動するように感じました。
そう考えると、雅楽って自分たちの生活や自然を
具体的に表現しているのではと思いました。

- 石田
- 日本人に共通する観念として
「物はいつか滅びる」というのがあると思うんです。
今日の朝「おはよう」と言ったのと、
明日の朝「おはよう」って言ったのはちがいがあって、
今日より明日のほうが一歩死に近づいている。
その辺の感覚がすごく鋭敏だったのだと思っています。
そういったことを音楽で表現するために、
雅楽ではテンポが上がっていくのではないかというのが、
今の私の考えです。 - 調と季節が決まっているのも当てはまりますよね。
音楽を自分たちと自然の中間に置くときに、
盤渉調という冬のものを
極力、夏には演奏しないというのも、
自然と自分たちとのバランスを取っていこうとする、
わかりやすい例だと思います。 - そして、楽器の笙について。
この楽器が鳳凰という鳥の形を模していて、
その形を崩さない。
「ピアニカのように順に音が並んでいるほうが演奏しやすい」
と言っても、
今までの話からもおわかりいただけるように、
やらないですよね。演奏しにくくても、
この鳥の形というのが大事だから、そこは崩さない。 - 先ほどの龍笛の、きれいに音だけを出すのではなく、
息の音やノイズを混ぜていくのも、
息の音が、風の音にも聞こえる。
つまり楽器の音にあえて自然の音を混ぜているのだと
私自身は納得しました。

- 石田
- 私が雅楽を知ったときに、
世界の半分しかわかってなかったのかなと思ったんです。
それまでの私が思っていた音楽というのは、
人が人に対してアピールしたり伝えたりするもの、
もしくは自分に対してアピールしたり伝えたりするものだと
思っていました。 - まさか、私たちの祖先である日本人という身近な存在が
自然に対して音楽をやっているとは知らずにいました。
身近といっても1200年、1300年前の人たちですけどね。 - そのことを知ったときに自分の世界がぐんと広がったし、
人生をちょっと生きやすくなった気がしました。
自分の先輩たちは
こんなふうに生きてきたんだなと思ったときに、
すごく生きやすくなったのを強く覚えています。
(つづきます)
2025-02-22-SAT