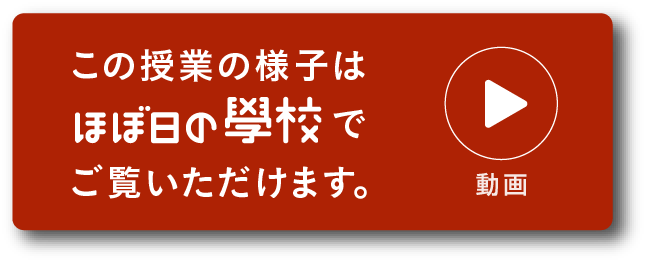エミー賞・ゴールデングローブ賞をW受賞した
ドラマ「SHOGUN 将軍」の音楽を担当した
作曲家の石田多朗さんが、
雅楽の魅力を教える授業を
ほぼ日の學校でしてくれました。
「雅楽のコンテンツをやりませんか?」
という一通のメールを石田さんが
ほぼ日に送ってきてくださって、
糸井重里がそのメールに興味を持ったことから
はじまったこの授業。
石田さんが出会ったとき受けた“ワクワク感”を含めて、
雅楽の魅力を熱く語っていただきました。
今日から、7回にわたってお届けします。
雅楽という広大な森にいるような
不思議な気持ちになる授業です。
石田多朗(いしだ・たろう)
1979年アメリカ合衆国ボストン生まれ。
上智大学にて国文学・漢文学を専攻後、
東京藝術大学音楽学部に入学。
2018年、株式会社Drifterを設立。
雅楽の楽曲制作などを通して、
これまでにない日本の音楽のあり方を日々研究・制作し、
発表をする。
2024年、ディズニー製作のハリウッドドラマ
「SHOGUN 将軍」
(作曲Atticus Ross、Leopord Ross、Nick Chuba)の
日本伝統音楽に関する総合アレンジャーとして参加。
エミー賞とゴールデングローブ賞のW作品賞受賞に
貢献するとともに、
エミー賞の作曲賞、メインテーマ賞の2部門で
ノミネートを果たす。
また「SHOGUN(将軍)」のサウンドトラックは、
グラミー賞「最優秀映像作品スコア・サウンドトラック」部門にノミネート。
- 石田
- 雅楽のコンサートが始まる前などに、
「どうやって雅楽を聴いたらいいかわかりません」とか
「どのように聴けばいいんでしょうか?」って
よく質問されるんです。 - この質問をする人は、
音楽が人に対して
何かしらのメッセージがあると考えているのだと思います。
例えば、長渕剛さんの「とんぼ」を聴いたら、
うわーっと気持ちが盛り上がる。
その感覚はものすごくよくわかるんですけど、
音楽ってそれだけではないのかなと思っていまして。 - 例えば、みなさんが3年ぶりに海に行ったとします。
3年ぶりに海に行ったら、
遠くにうわーっと海が広がっているのを前にして
「うわー、楽しい」と思う人もいれば、
「ああ、なんか悲しいなあ」と思う人もいれば、
「今すぐ泳ぎたい」っていう人もいるし、
「海、嫌いなんだよね」っていう人もいる。
同じ海なのに、
それぞれの人がそれぞれの感想を抱くと思うんですよ。 - でも、よくよく考えると、
海はただ海水があるだけで、
海は人に対して何かを言っているつもりはまったく無い。
海に「お前は何を言いたいんだよ」って言う人、
誰もいないですよね。
おそらく雅楽って、それと同じ聴き方でいいと思っています。
「雅楽が何を言いたいのかわかりません」
と言われたときに、
「そんなこと考えなくていい」とか、
「意味なんて無いんですよ」という答えになると思います。
ただ、自然を表現していたりするだけなので、
星空を見る感じでただ聴く。
心に「ああ、なんか懐かしいなあ」とか、
「ああ、気持ちいいなあ」とか
感じることがあるかもしれませんが、感じ方はそれぞれ。
聴き方すらない。
なので、理解しようとする必要がない音楽だと、
私は思っています。

- 石田
- ということで、最初に笙の音を聞きましたが、
ここでも同じように聞いてみましょう。
どうですか、変わるかな?
- 石田
- 最初と感じ方が変わった方っています?
糸井さん、どうですか?
- 糸井
- 大きさがすごく変わって聞こえました。
- 石田
- 音楽が広く感じたということですか?
- 糸井
- はい、ものすごく大きくなりましたね。
- 石田
- 星空のように見えますよね。
ふわーって感じで。
- 糸井
- 最初は、演奏として聴いていたんですけど。
- 石田
- なんか途中で、こう、ふーっと虫が飛んでるっぽいなとか、
思いました?
- 糸井
- ええ。
- 石田
- ありがとうございます。
どうですか、変わりました?
- 乗組員1
- ほんとに変わりました。
さきほどは吸い込まれそうで、
そばにいない感じがしたんです。
いまは身近な音に聞こえて、
音が近づいた感じがしました(笑)。
- 石田
- あ、なるほど、さっきの糸井さんとまた逆で、面白いですね。
糸井さんは、うわーっていう感じで広がった。
この方は、すごく身近に感じた。
たぶん、みんな、ばらばらでいいんじゃないのかなと
思っているんです。
- 乗組員2
- 最初は、離れている感じがしたんです。
遠い世界だなと感じていたんですけど、
今、聴いたら、近づいた感じがしました。
- 石田
- あ、よかったです。よかったです。
皆さん、できれば、今度、雅楽を聞きに行ってください。 - 今の話は忘れてもらって、
うわーっと浴びるように聴くと、
雅楽奏者たちが
「あ、自分たちに対して演奏してない」って、
よくわかります。 - 皇居で年に2回ほど、楽部の方たちが演奏する会があって、
陛下の前で演奏するその会がいちばん重要な演奏会だと
思ったんですが、
じつはその演奏会ではなく、
何も無い空間で夜中に長時間、何も無い空間に向かって
演奏するのが
いちばん大事な演奏だと話を聞いたことがあります。 - それ、つまりもう、それが象徴ですよね。
そもそも、人に向かって演奏してなかった。
それが国の音楽としてあるっていうことが、
非常に私は面白いなと思っています。

- 石田
- ここからは、今日の最後の話です。
- 1400年前に日本に流れ込んできて、
平安時代中期に完成した音楽がそのまま残っているのを、
最初は超保守的だからだと思っていたんですよ。
でも、たぶん違うなと気が付きました。
いまはおそらく「超積極的保存」だと思っています。 - どういうことかと言いますと、
日本人の感覚は、先ほども申しましたように、
大昔は亀の甲羅の割れ方で何かを決めるとか、
呪術的なところがあったり、
今の私たちとは、だいぶ感覚が違いますよね。
そのときに生まれた雅楽という音楽があって、
そこから時代を経ていくと、
同じ日本人ではありながらも、
かなり感覚は変化していると思います。 - 音楽で言うと、
例えば、尺八は、ブーッと音を鳴らして、
無音になって、また吹き始めるみたいに、
そういう幽玄の世界みたいなものがありますよね。
雅楽の世界でも、一応「残楽(のこりがく)」といって、
オーケストラで演奏していて
少しずつ楽器を減らしていく演奏っていうのがあるんです。
ずいぶん減らしていって、
龍笛だけになるのかなと期待したんですけど、
聴いていただくとわかるんですけど、
ほとんど減らないですよ。
ちょっと減って、また戻るんです。
だからそんな変わったように感じなくて。
これは、おそらく先ほどの森の話で言うと、
その森の中で、一つの生命が消えようが、
森自体は大して変わらないっていう、
超現実的な感覚を表現しているような気がしていて。 - さらに、音楽では強く弾くことをフォルテといって
弱く弾くのをピアノと言いますが、
雅楽にはフォルテしかないんですよ。
弱く弾くというのはなくて、全部、フォルテです。 - で、それが超現実的な感じで、
途中で鎌倉、室町や江戸‥‥と時代を経るにつれて、
人間中心の社会になってきているような気がしていて。
自分っていうのはもちろん大事なんですけれども、
だんだん、個とか人間という存在が
大きくなりすぎているのが現代だと思うんです。 - 例えば、SNSでは当然、人間対人間の話になっていますし、
いま、AIが発達してきて、
人間の脳が地球を覆い尽くすようなイメージになっている。
面白いんだけど、
内心「ほんとにそれでいいのかな」と感じたり、
「ちょっと、いびつだな」と感じたりすることがあるんです。 - ここからは私の予想なんですけど、
平安時代に天才がいて、
「この平安時代の自然観はいずれ無くなるだろう」と考えた。
いずれ無くなるからと
雅楽を箱に入れて保存したんじゃないかなと思うんです。 - 現代のように「人間パワーがマックスになってしんどいよ」
と感じる人がいるときに、
自然観を開封するために
温存したんじゃないかなっていうのが、私の予想です。 - 雅楽の話を聞いたら、
ちょっとすっきりしませんか? スカッとしません?
今、そのスイッチを押すタイミングなのかなと思っています。
それが、私が雅楽を知ってワクワクした理由だと
思っております。
ありがとうございました。
- 一同
- (拍手)
(つづきます)
2025-02-23-SUN