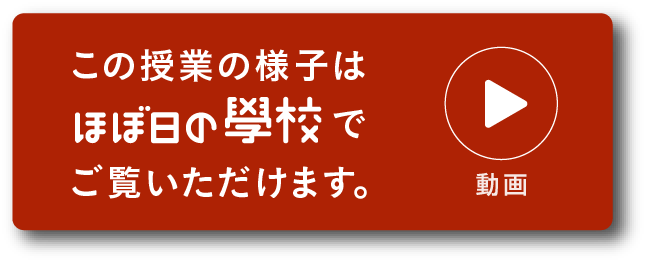エミー賞・ゴールデングローブ賞をW受賞した
ドラマ「SHOGUN 将軍」の音楽を担当した
作曲家の石田多朗さんが、
雅楽の魅力を教える授業を
ほぼ日の學校でしてくれました。
「雅楽のコンテンツをやりませんか?」
という一通のメールを石田さんが
ほぼ日に送ってきてくださって、
糸井重里がそのメールに興味を持ったことから
はじまったこの授業。
石田さんが出会ったとき受けた“ワクワク感”を含めて、
雅楽の魅力を熱く語っていただきました。
今日から、7回にわたってお届けします。
雅楽という広大な森にいるような
不思議な気持ちになる授業です。
石田多朗(いしだ・たろう)
1979年アメリカ合衆国ボストン生まれ。
上智大学にて国文学・漢文学を専攻後、
東京藝術大学音楽学部に入学。
2018年、株式会社Drifterを設立。
雅楽の楽曲制作などを通して、
これまでにない日本の音楽のあり方を日々研究・制作し、
発表をする。
2024年、ディズニー製作のハリウッドドラマ
「SHOGUN 将軍」
(作曲Atticus Ross、Leopord Ross、Nick Chuba)の
日本伝統音楽に関する総合アレンジャーとして参加。
エミー賞とゴールデングローブ賞のW作品賞受賞に
貢献するとともに、
エミー賞の作曲賞、メインテーマ賞の2部門で
ノミネートを果たす。
また「SHOGUN(将軍)」のサウンドトラックは、
グラミー賞「最優秀映像作品スコア・サウンドトラック」部門にノミネート。
- 糸井
- ものすごく面白かったです。
- 石田
- それはよかったです。
- 糸井
- 僕、個人と雅楽の話をつなげて話したいんですけど、
いいですか?
- 石田
- はい、もちろんです。
- 糸井
- 最近、俳句に急に興味が出てきてまして。
俳句は17音しかないのに、
季語がいちばん大事なんですよ。 - 季語を入れることで自己表現する部分が
圧倒的に減るんですね。
でも季語を疎かにしたらその俳句はもうダメなんです。
このことは一見、不自由なんですけど、
それをずうっと、「あと残り数文字しかない」というところで、
俳句の世界は続いてきているんですよね。 - それで、「ただ、在る」ということに対する認め方に、
僕は今とても興味があって。
先ほど、石田さんがおっしゃったように
契約だとか、約束だとか、規則だとか、
人と人との間の問題が多くなりすぎて、
それが本当に行き詰まっているなと思うんです。

- 石田
- ほんとうにそうですね。
先ほどの笙のことでちょっと思い出したんですけど。
俳句が17音と似てるんですが、
笙の竹は17本しかないんですよ。
- 糸井
- あ、17。俳句の音と同じですね。
- 石田
- そうなんです。笙は17音しか出ないと思いきや、
穴が2つ塞がってるんですよ。
つまり、15しか出ないんです。
そして、いちばんびっくりしたのが、
もともと17音、出ていたらしいです。
それを途中で減らしたんです。 - チェンバロがピアノになると「鍵盤が増えました」とか
「こんな音域、出ますよ」というように、
「可能性を広げる」っていう言葉は
選択肢を広げるものだと思ってたんですよ。
でも「音を減らす」ということは、
季語とちょっと似ていると思うんですけど、
減らすことによって道しるべになると。
季語もおなじように、私の予想ですが
道しるべかなと思っています。
- 糸井
- 道しるべですか。
- 石田
- 可能性は広がれば広がるほど、
なかなか先行きが見通せないところがある。
雅楽は、平安時代あたりに輝かしい黄金時代があるので、
そこに未来の人が到達しようとしたときに、
「いくらでも音が出ますよ」だとわからなくなると。
より鋭敏に、余計なものを削っていって、
「やるのは、ここだけでいいよ」って、
「ここからだと、平安時代、見えるでしょう」
という道しるべのために削ったんじゃないかなと思っていて。
俳句の季語の話も、
おそらく先達から「そこは残せよ」ということなのかな
と思いました。
- 糸井
- その意味では、ちょうど昨日、
画家の横尾忠則さんとお会いしたんです。 - 横尾さんは右手が腱鞘炎になってるんですよ。
しょうがないから左手を使って絵を描いたんだけど、
左手は右手の技術を持ってないので下手だと。
でも、「下手で、上手く描けないのがいいんだよ」と
前に言っていたんです。 - 昨日、再びその話になって、
右手が不自由になったおかげで、左手が助ける出番がきたと。
つまり、横尾忠則という個人の中で、
右手を左手が助けるっていうことが起こった。
右手が左手に助けを求めるっていうことで、
一人の中で助け合いが始まったんですねっていう話になって。 - さらにもうちょっと言うと、
「左手が絵を描くのを上手になっちゃうのは、どうですか?」と聞いたら、
「それは困る」と(笑)。
困るなあと思いながら、描いているんだと話していました。
それで「いっそ、右手で描いた絵と左手で描いた絵の2枚
描けばいいのかな」と横尾さんが言うわけですよ。
それ、「ああ、それ、やったことありますか?」と聞くと
「思うんだけど、やんない」と。
「やるときが来たらやると思う。
でも、これはアイデアだからダメなんだよ」と言ったんです。
- 石田
- アイデアはダメだと。
- 糸井
- 頭で考えたことや規則が生まれそうになったことに対して、
横尾さんはとにかく逃げ回るんですよ。 - それの話をした後に、今日の雅楽の話を聞いて、
意図的な人間の上下とか序列とか、本来関係ないですよね。
笙が順番に並んでないっていうときの
順番って何かって言ったら、
音が高くなる、低くなるっていうことで、
高い低いが順番かというのも、人が決めたことですよね。
- 石田
- その通りです。
- 糸井
- 鳳凰の形であることが大事だと。
音が高い低いだとかは
技術やあとからつくった体系みたいなものだから
それを全部、無かったと言っているのが、
めちゃくちゃかっこいいなと思って。 - 今日、この話が聞けたことが、
なんだかすごく、ありがたかったです。
- 石田
- かっこいいですよね。よかったです。
- 糸井
- あと、家で雅楽を聞いてみたら、
どういうふうに自分は感じるんだろうと思います。
試してみたいですね。
- 石田
- ぜひやってみてください。
雅楽の演奏者たちは、
場所を気にするというか、楽しむんですよ。
もともと平安時代も屋外で演奏していたので、
先ほど言ったように自然音が入ったりする。
それを楽しんでいます。 - 例えば、ご自宅で電車の音が聞こえるんだったら
電車の音とともに聴いてみたりとか、
森の中で車の窓を全開にしてかけてみるとか、
音量を下げるとか、すごい楽しいです。 - じつは、雅楽を楽しむというテーマの話も
してみたかったんです。

- 糸井
- 雅楽のコンサートみたいなものは、あるんですか。
- 石田
- 頻繁にやっています。
今回協力してもらった伶楽舎さんも
毎月のようにやっていますし、
宮内庁も年に一度だけ数百人だけ入れる
コンサートをやっていたり、探せばいっぱいあります。
- 糸井
- 面白そう。
それは、どんなシチュエーションで聴くんですかね?
あの「録音しますから絶対に咳払いしないで‥‥」
という感じでしょうか?
- 石田
- 雅楽の人たちは、敷居が高そうに見えて、
ものすごいフレンドリーです。
むしろ屋外で演奏するときは、
子どもが遊んでいたりする音が入るのもうれしいみたいです。
ノイズ、大好きです。
意図せぬ音とか、ノイズとかが入るのは
ぜんぜん嫌がらないですね。
気難しさは皆無です。
- 糸井
- ノイズもOKだとか、
そのあたりの哲学を演奏者は
どうやって共有しているんですか?
- 石田
- 雅楽の本っていっぱいあるんですけど、
そういうことはまったく書いてないんです。
「テンポが上がる」までで話は止まっていて、
私が先ほど話したことは、
演奏者と仲良くなって7年目ぐらいにちょっと聞ける。
で、「SHOGUN 将軍」がブレイクして、
みんな嬉しいから言うみたいな感じで、
少しずつ、少しずつ、話してくれて。
内々では話しているんですよね。 - 雅楽自体も、基本的に口伝でして。
楽譜化がほとんどできないものなので、
たぶんみなさんおしゃべりが好きなんですけど、
そのおしゃべりで、
いつの間にか共通のムードができている雰囲気です。
規律はないですね。
- 糸井
- 雅楽の演奏者は、
もともと西洋音楽をやっていた方々なんですよね。
- 石田
- そうですね。西洋音楽をやっていた方が多いです。
- 糸井
- その人たちが、
自分の今までの音楽と違うものを
呑み込んでいくのに
誰も教えてくれないんですよね。
- 石田
- そうですね。
みなさん、古い音楽とは思ってないとおっしゃいます。
新しい音楽だと思ってコンサートで聴いて、
楽しくてワクワクやっているっておっしゃいますね。
古い音楽を守るとかっていう意識ではやっていない。
- 糸井
- 継承者は、足りているんですか?
- 石田
- 少ないです。少ないから、
「SHOGUN 将軍」などで雅楽がフォーカスしてもらうのを、
非常にありがたいって言っています。
ただ、最近私のほうに取材に来るのは、
20代の方ばっかりです。
若い方が興味を持ってお話を聞きに来てくれています。
- 糸井
- 音楽でいうとロックっていうものが
一つの神だった時代があったと思うんです。
とくに若者にとって。
なぜ神だったかっていうと、
工業社会のシンボルだったからだと思うんです。
形のあるものがあって、ある程度、構築されているものを
ロック。つまり「殴る」ですよね。
ロックでロールで、
つまり形のあるものに対して反撃ができるっていう
可能性を出したのが、ロックだから。 - つまり、工業社会が限界を迎えて
ロックが終わりつつあるっていうのは、
つまり工業社会じゃなく情報社会になった。
生きていく人が情報で生きていく人が増えたと思うと、
今、流行っているような音楽になっていくのは必然だから。
ああ、工業社会とロックが結びついていると思ったときに、
その時代の遺品にすると不滅になるとも思うんですね。 - だから、雅楽が変えないできたことのおかげで、
無くならずに済んだ気がします。
遺品にしてしまったことで、なくならなかった。
- 石田
- ああ、なるほど。
雅楽を変化させないでよかったですよね。
(つづきます)
2025-02-24-MON