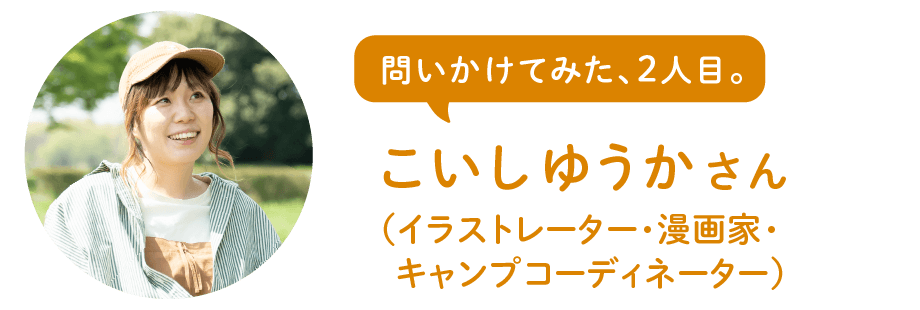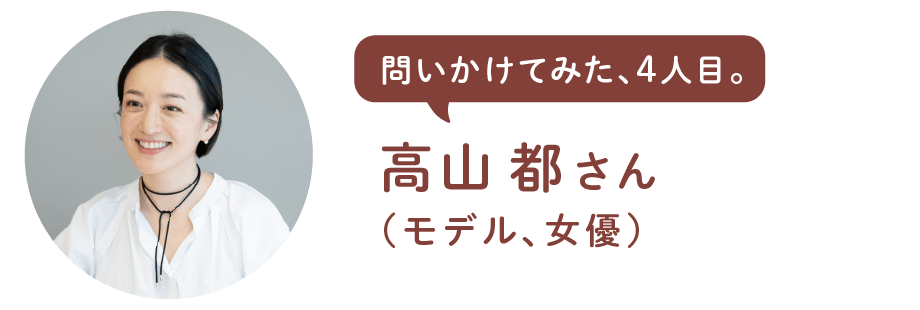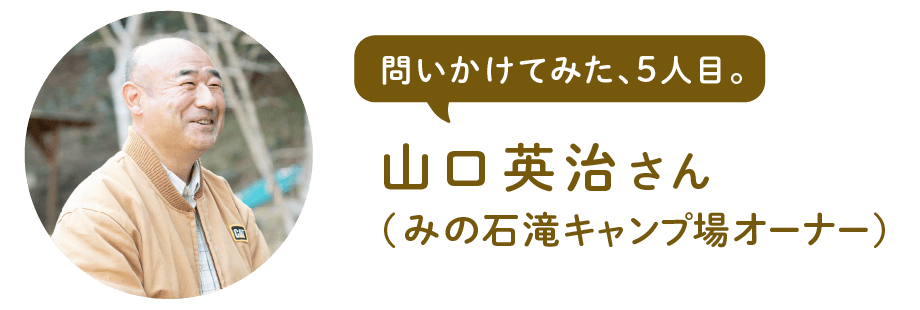キャンプのプロジェクトをはじめるまえに、
きちんと考えておきたいこと。
手間もかかって、準備も後片付けもたいへんで、
危険な目にあう可能性もあるのに、
「どうしてキャンプをするんだろう?」
今回、問いかけてみたのは、
株式会社ゼインアーツ代表取締役社長、
キャンプギアクリエイターの小杉敬さんです。
小杉さんは、30年ちかくにわたって
大手アウトドアメーカーで開発に携わったのち独立。
現在は長野県松本市を拠点に
テントやタープなどのギアをつくっています。
ご自身も登山やキャンプを趣味にしている小杉さんは、
人が自然のなかへ向かう理由を、
「人間の本能」に関係があるのではないかと
語ってくださいました。
やっぱり「Why Camp?」っておもしろいテーマです。
小杉敬(こすぎ・けい)
1972年新潟県生まれ。
1993年、大手アウトドア用品メーカーに就職、
数々のキャンプ道具の開発を手がける。
2018年に独立、長野県松本市を拠点に
株式会社ゼインアーツを設立した。
機能と藝術の融合をコンセプトに掲げ、
手がけたアウトドア用品は予約時点で完売、
グッドデザイン賞ベスト100にも選出されるなど
人気を博している。
- ──
- テントを立てたり寝袋に寝たり、
なぜ大変な思いをしてキャンプに行くんだろう?
と、いろんなかたに質問しています。
小杉さんはどのようにお考えですか?
- 小杉
- ゼインアーツをはじめるにあたって、
「そもそもどうして人は山に行くんだろう」
と考えてみたことがあるんです。
当時はまだ大手アウトドア用品メーカーに
勤めていたのですが、
その問いを整理してから独立しようと。
- ──
- どんな答えに辿り着いたのかお聞きしたいです。
- 小杉
- ぼくは会社員時代から、
いまゼインアーツがある松本市から近い
八ヶ岳や北アルプスによく登っていたんです。
ある日、雪に覆われた八ヶ岳を縦走している途中に、
ふと後ろを振り返ったら、
ものすごい、絶景が広がっていたんですよ。
人がひとりもいなくて、天気がよくて、
つもった雪が、風の音さえ吸収して
シーンとしていて。
目の前に広がったその景色が、
もう、めちゃめちゃ神々しかったんですね。
「これは人の領域じゃない、神の領域だ」って。
- ──
- おおお。
- 小杉
- 美しすぎて、圧倒されて、
自然と涙が流れました。
そのとき「‥‥ああ、そうか」と。
「俺はこの景色が見たかったんだ」と気がついて。
そう思うと、登山やキャンプを好きな人って、
精神性みたいなものはそれぞれまったく別物なのに、
美しい景色を求めているのは
共通しているなと思ったんです。
- ──
- ああ、なるほど。そうですね。
- 小杉
- 登山が好きな人とキャンプを好きな人って、
似ているようでぼくはかなり違うと思っていて、
キャンプしかやらない人は
「なんで登山なんてめんどうなことをするんだ」
って言うし、登山しかやらない人は
「車のそばで飯を食って何がたのしいんだろう」
みたいなことを言いますね。
- ──
- (笑)
- 小杉
- ぼくは両方やるんですけど、
両方を体験してみると
見えている景色も、
その景色を美しいと感じる心も同じなんです。
ただ、アプローチの方法に
違いがあるだけなんですよね。
そう考えると、キャンプや登山をする人に限らず、
自然を美しいと感じるのは、
人って、みんな同じなんじゃないかなと。
そう思ったとき、もっと多くのみなさんに
あの美しい景色を見てほしいと思いました。
だからぼくは、アウトドアギアを通して、
たくさんの人を自然の入り口にお誘いしたい。
それがやりたかった仕事なんだと。
気持ちの整理ができて、5年まえに
ようやくゼインアーツのスタートが切れました。

- ──
- なぜ、人は
美しい自然に魅了されるのだと思いますか?
- 小杉
- 人間って、原則的に自然から食物を得ていますよね。
ということは、自然を保護していかないと、
我々の生命が絶たれてしまうかもしれないわけです。
だから、人間の本能として
自然を愛でて「ああきれいだね」と、
感じられる心があるんじゃないかなと思うんです。
でも、コンクリートに覆われた都市で過ごしていると、
「自然によって生かされている」という本能が
だんだん薄れていくような気がしていて。
- ──
- ああ、なるほど。
スーパーに行けば野菜も肉もなんでもそろいますし、
それがもともと、自然界にあったものだなんて
いちいち考えないですよね。
- 小杉
- その揺り戻しとして、
「山行きたいなぁ」とか
「キャンプしたいなぁ」となるんじゃないかなと。
アウトドアをレジャーとしてたのしむ人って、
人口密度が高い都市や先進国に多い傾向があるんです。
そういう点からみても、
文明や機械化によって失ったものを取り戻す行為、
なんじゃないかという気がしています。

(つづきます)
2023-07-07-FRI