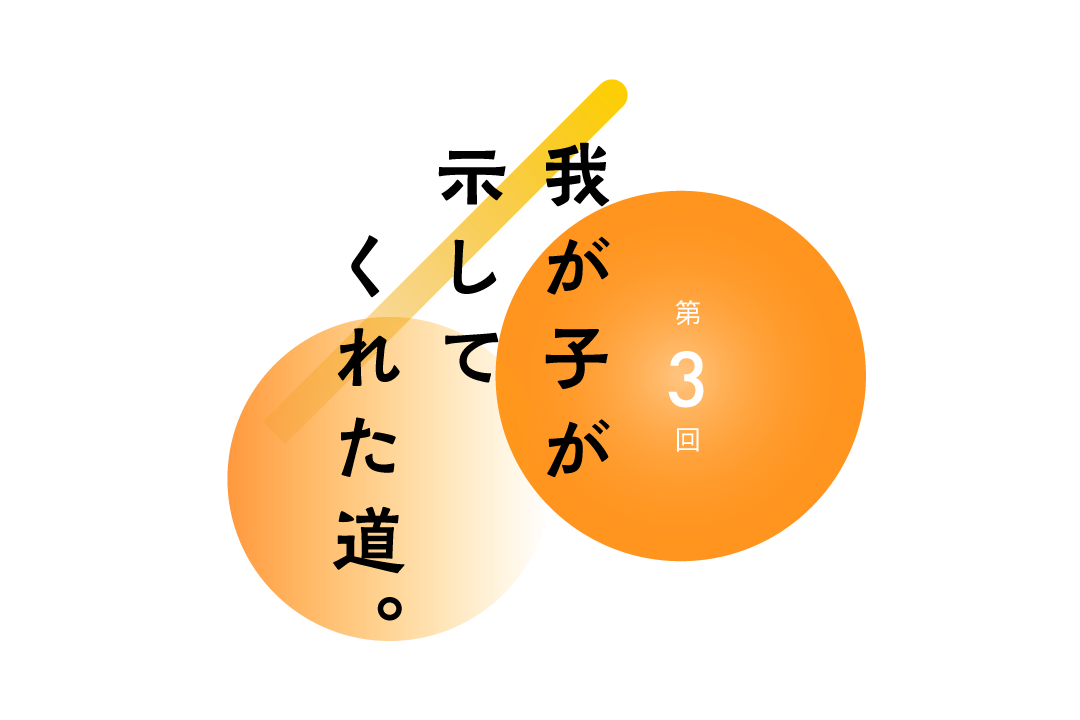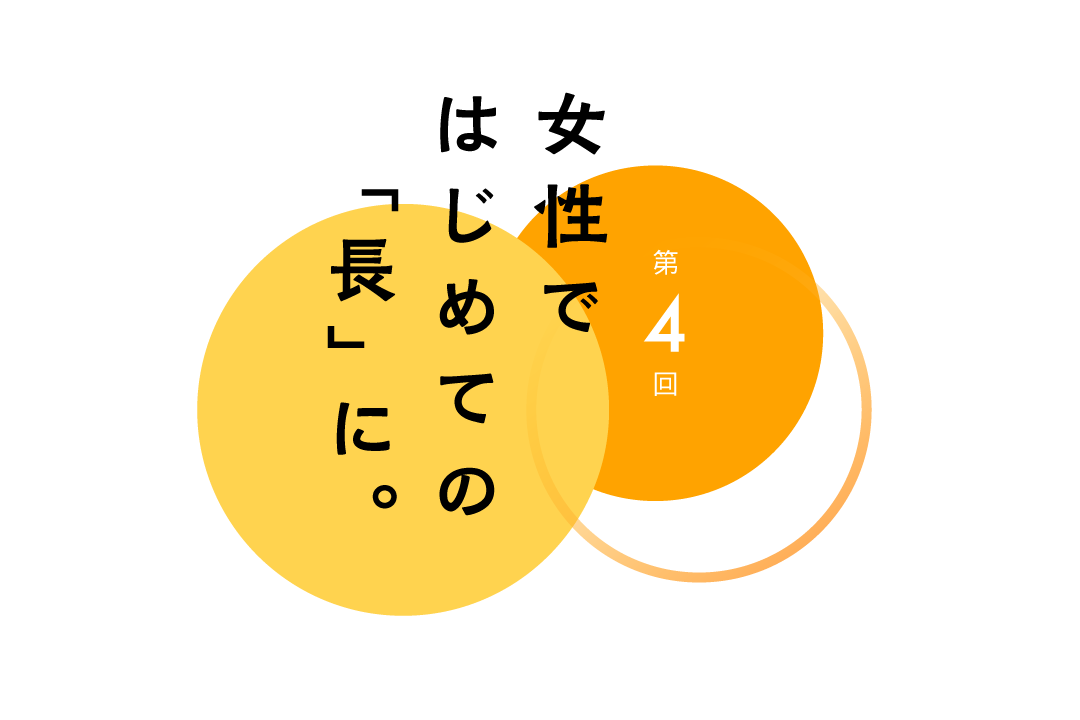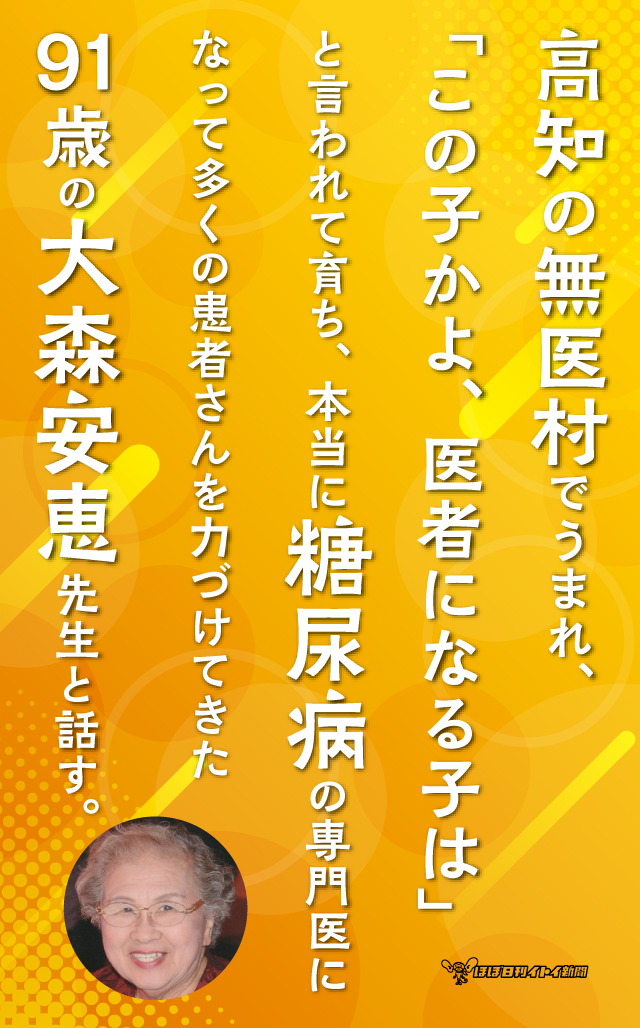
こんにちは、ほぼ日の奥野です。
大学時代の恩師である坪井善明先生から
「少し前、お医者さんを引退した大森安恵先生が
ヒマらしいから話を聞いてみてよ。
91歳で超元気、めちゃくちゃおもしろいから。
よろしく。ガチャッ!」
というお電話をいただきました(笑)。
はたして、恩師の言葉は、本当でした。
大森先生は、高知の無医村にうまれ、
村の人たちから、なぜか
「この子かよ、医者になる子は」と言われて育ち、
やがて本当に医者となり、
日本における「糖尿病と妊娠」という分野を
切り拓いてきた方でした。
全5回、ゆっくりお付き合いいただけましたら。
大森安恵(おおもりやすえ)
高知県安芸市出身。1956年3月、東京女子医科大学卒業。1957年7月、糖尿病を専門とする東京女子医科大学第二内科(中山内科)入局。以来、糖尿病の臨床と研究に従事。1960年12月、自らの死産の経験がきっかけとなり、糖尿病と妊娠の臨床と研究を開始。1964年2月、東京女子医科大学病院において糖尿病妊婦より初めての出産例を経験。1964年9月、「ステロイド糖尿病の成因に関する研究」で医学博士を取得。1981年4月、医局長、講師、助教授を経て、同大学第三内科(糖尿病センター)教授。この間カナダのマックギル大学、スイスのジュネーヴ大学に留学。1985年12月、「糖尿病と妊娠に関する研究会」を池田義雄、松岡健平と共に設立。1991年4月、東京女子医科大学第三内科主任教授兼糖尿病センター長。1997年3月、定年により名誉教授。1997年5月、女性ではじめて日本糖尿病学会会長を務める(第40回)。1997年6月、東京女子医科大学特定関連病院済生会栗橋病院副院長。2001年4月、糖尿病と妊娠に関する研究会を日本糖尿病・妊娠学会に変革。その理事長をつとめる。2005年から名誉理事長。2002年4月海老名総合病院(旧東日本循環器病院)糖尿病センター長。2007年2月糖尿病と妊娠に関して国連でスピーチ。2010年12月WHOにおけるGDMガイドライン作成委員が世界中から13名選ばれ、その一人として活躍。2019年3月海老名総合病院糖尿病センターを退職。受賞歴:1975年、吉岡弥生賞、1982年、エッソ女性のための研究奨励賞、2001年、坂口賞、2008年、米国のサンサム科学賞、2010年、Distinguished Ambassador Award、2012年、ヘルシィーソサイエティー賞、2014年、糖尿病療養指導鈴木万平賞。
- ──
- 先生が、専門分野として
糖尿病を選んだのはどうしてですか。
- 大森
- わたしたちの時代は一般医といって
何でもやるお医者さんが多かったんです。
でも、
専門性を持たなきゃならないという、
そういう時代にもなってきていました。 - だから、わたしも何をやろうかって、
学生のころから考えていたんです。
- ──
- ええ。
- 大森
- そしたら糖尿病を専門とする先生が、
女子医大の内科にいらしたんです。
中山光重先生という、
とっても有名な方なんですけれども、
一般の患者さんももちろん診ますが、
専門は、糖尿病。 - そこで何らかの専門性を持ちたいと
思っていたわたしも、
中山先生の内科に入ったんです。
- ──
- 糖尿病を勉強していこうと、決めた。
- 大森
- はい。
- それで、医者になって3年目のころ、
結婚して妊娠したんですが、
死産になってしまったんです。
- ──
- えっ、そうなんですか。
- 大森
- はい。女子医大って大学病院だから、
入ったらすぐに
学位論文を書いて学位を取るために、
修行させられるんです。 - わたしも妊娠してお腹が大きいのに
実験ばっかりしていたら、
どうしてか、
子どもが死産になってしまったんです。
- ──
- そうだったんですか。
- 大森
- 喪失の悲しみは、想像以上でした。
- 仕事が大変なときに妊娠したもので、
よろこびより困惑してしまって、
つい自然流産を願ってしまいました。
その罪悪感と、
わが子を失った悲しみの深さは、
まったく想像していないものでした。
- ──
- そうでしたか‥‥。
- 大森
- また、ちょうどそのころ、
糖尿病で妊娠された女性がおふたり、
続けざまに来院しました。
おふたりとも死産の経験を持っていました。
そのときに、ある教授が
「これ、読んでみて」って
1冊の本を貸してくれたんです。 - そこには、1921年に発見された
「インスリン」を注射すれば、
ヨーロッパでは、
糖尿病患者でも
子どもが産めるんだということが、
書かれていたんです。
そのときに、世界には
「糖尿病と妊娠」という分野があるって、
はじめて知ったのです。
- ──
- それで「糖尿病と妊娠」を専門に。
- インスリン発見前の時代に、
糖尿病の女性が妊娠した場合には、
どうしていたんでしょうか。
- 大森
- おそらく、ほとんどの場合で、
子は死産になっていたと思います。 - 母体も危険にさらされたでしょう。
- ──
- そうなんですか。インスリンって、
いつ日本へ入ってきたんですか。
- 大森
- 発見されてから
1年も経たないうちに入って来て、
使われてはいたんです。
大正12年のことです。 - でも、妊婦で
糖尿病の治療をしようという人が
いなかったんでしょうね。
おなかが大きくなっても、
子どもが死んじゃったりしていて。
- ──
- つまり、インスリンを打てば
妊娠しても大丈夫だという常識が、
日本にはまだなかった‥‥と。
- 大森
- 糖尿病の女性が妊娠することじたい、
そうなかったんだと思います。 - 昭和14年かな、
糖尿病の女性が妊娠したという記録が
残っているんですけれど、
やっぱり、亡くなってしまっています。
- ──
- 母子ともに危険に陥る可能性が
高いということで、
糖尿病に罹ってしまったら、
妊娠などできません‥‥というのが、
当時の常識だった、と。
- 大森
- そうですね。自分の子どもの死産と、
糖尿病の患者さんの死産とが重なり、
「ああ、わたしは、これをやるんだ」
と決心しました。 - 日本でも、糖尿病の女性が
妊娠できるようにしたいと思いました。
そこで「糖尿病と妊娠」という分野に
取り組みはじめました。
それが、1960年くらいのことです。
- ──
- ええ、ええ。
- 大森
- 当時、日本では、
糖尿病にかかってしまえば何もできない、
運動もしちゃいけない、
何とかと何とかは食べちゃいけない‥‥。
- ──
- 女性だったら、妊娠もしちゃいけないと。
それでも、妊娠してしまった場合は‥‥。
- 大森
- 人工流産させられるか、
母子ともに亡くなってしまうか、でした。 - でもね、ヨーロッパに目を向けてみたら、
そんなの嘘だった。
糖尿病があっても子どもが産めたんです。
- ──
- 天地のような開きがありますね。
- 大森
- とにかく、糖尿病は大変な病気でした。
子どもだって、糖尿病に罹るんですよ。
いつか、わたしのところに、
10歳の女の子が
泣きながらお母さんと来たことがあって。 - わたしは、「泣くな」って言ったんです。
「糖尿病って言ったって、
インスリンを打つというただ一点だけが
他の人とちがうだけで、
あとは変わったところがないのよ」って。
- ──
- はい。
- 大森
- 彼女は、いま、大変に活躍していますよ。
カナダに留学したんだけど、
「糖尿病があっても変わったことはない。
インスリンを打たなきゃいけないけど、
ただそれだけ。だからふつうにしなさい」
って、糖尿病の集会でも言ってるみたい。
- ──
- 先生に言われたことを、他の患者さんに。
- 大森
- いま、彼女は50歳だから、
40年前のわたしが、そう言ったのね。 - 彼女が結婚したとき、お母さんが
「あのとき泣くなと言われたけども、
いまはうれしくて泣きます」
っておっしゃってね、泣いてました。
- ──
- 先生は、そうやって
日本における糖尿病の通念や常識を、
変えてきたわけですが、
人々の考え方を変えるのって、
ものすごく大変だったと思うんです。
- 大森
- 糖尿病って紀元前からあった病気で、
罹ってしまった人は、
みんな死んだという記述もあります。 - でも、1921年に
バンティングとベストのふたりが
インスリンの抽出に成功した。
それでようやく光がさしたんです。
- ──
- じゃあ、まだ100年ちょっとの歴史。
- 大森
- そうです。
- でも、注射を打つようになってから、
みんな、いまのように
長生きできるようになったんですよ。
- ──
- 糖尿病と妊娠の問題については、
日本では先生が光を示したんですね。
- 大森
- わたしのおなかのなかで
夜空の星になってしまった我が子が、
死をもって、わたしに
糖尿病と妊娠の道を啓示してくれた。 - そう、思っているんです。

(つづきます)
2024-03-20-WED
-
大森安恵先生を紹介してくださった、
坪井善明先生インタビューはこちら。