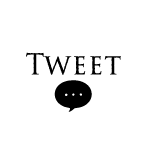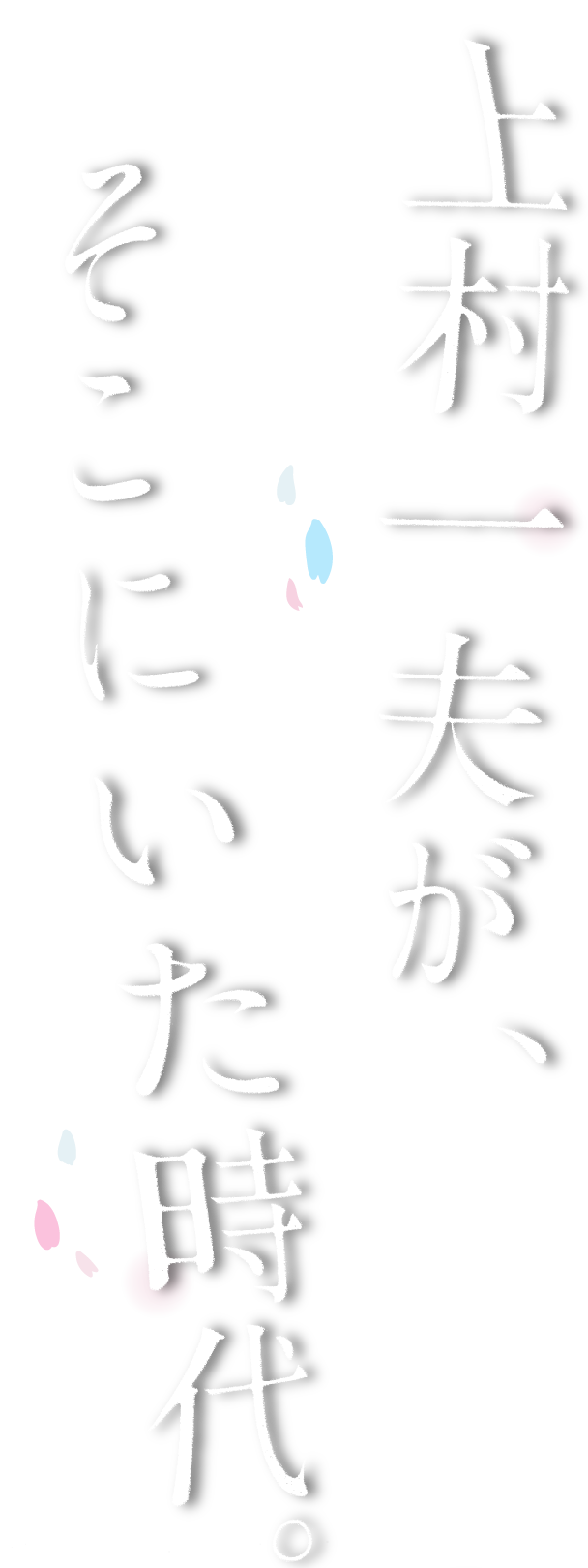

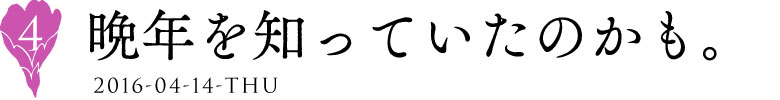

- 糸井
- 展示されている上村さんの描いた絵を改めて見たら、
おなじ女の人を描いてますね。
- 上村
- そう見えますか(笑)。
- 糸井
- この女性は、現実にはいない人ですよね。
- 上村
- そうですね。
- 糸井
- 急に聞くんですけど。
お母さんはこういう人だったんですか。
- 上村
- うちの母は、それを言われるのが
いちばんイヤみたいです。
全然違うんですよ。

- 糸井
- 全然違うんですか。
- 上村
- 着物なんてまったく着ないような人なんです。
- 糸井
- そうなんですか。
でも、この着物を描けるというのは‥‥。
- 上村
- 父のお母さんが五反田でバーをやっていて、
お姉さん2人も、お店を手伝っていました。
みんな、お着物でお店に立って、
父の描くマンガのイメージの人だったんですね。
父は、結婚して生活をするなら、
家族は至って普通がいいって、いつも言ってました。
なので、マンガは架空の世界ですよね。
- 糸井
- 架空ですね。だから、女性像も架空だし。
たぶん、自伝的な作品の「関東平野」でも、
上村さんが目を閉じたときに見える自伝ですから。
「そんなもんじゃないよ」っていうくらい、
頭の中のものが出てたんだと思います。
- 上村
- そうなんですかね。

「離婚倶楽部」 ©上村一夫
- 糸井
- こうやって展覧会をやったおかげで、
たくさんの絵をいっぺんに見られました。
マンガは1冊ずつしか出ないわけだから、
いっぺんに見ることって、まずないんですね。
さらに言うと、原画がただの原稿じゃなくて、
原画そのものが「持つ」んです。
原画で、「ちゃんと絵ですよ」っていうふうに
描いていたことがわかりました。
改めて見ると、修正に使うホワイトの数が
ものすごく少ないじゃないですか。
- 上村
- はい。ホワイトは少ないと言われますね。
「線に迷いがないよ」って。
だから、うちにもほとんど、
下絵とかも残っていないんです。
バーッと描いて終わり、みたいな。
- 糸井
- すごいですよね。
- 上村
- ほんとに。最近になって、すごいなと思います。
- 糸井
- 今、浦沢直樹さんが、
『漫勉』っていう番組やってますけど。
- 上村
- あれ、おもしろいですね。
- 糸井
- 浦沢さんは生きている人しか取材できないけど、
上村さんを訪ねてほしいですよね。
- 上村
- それは見てみたかったですよ。
すごく、そう思います。
- 糸井
- 架空だけど、やれないのかな。

- 上村
- どうやってですか(笑)。
- 糸井
- 浦沢さんみたいに、自分が描いている人だったら、
「ここの速度っていうのは、このぐらいですよ」とか。
「ここ、全然、下絵ないじゃないですか!」とか、
たぶん、全部見抜けると思うんですよ。
その意味では、上村さんが描いた絵を前にして、
いない上村さんと「漫勉」を‥‥。
あっ、提案しときます。
- 上村
- ぜひお願いします(笑)。
父が亡くなって30年も経つんで、
わたし、父の記憶ってもう、
ほんとに薄まってきちゃっているんですけど、
サラサラサラッて描いていたのを、
すごく覚えているんですね。
音と、手先の動きは、割と覚えてます。

- 糸井
- 会場には色紙の絵が展示されていたんだけど、
色紙っていうのは、かなりの速度で描くから、
本職の方でも「お、上手ですね」みたいになるんです。
上村さんの色紙は、絵が完全に本物ですよね。
- 上村
- そうですか。
たしかに、こうやって父の展示をしていると、
「昔、ベロベロに酔った上村さんに
絵を描いてもらったんです」と言って、
色紙を見せてくれる方がいるんですけど、
ベロベロだったはずなのに、すごくきれいな女の人が、
涙を花びらにして‥‥という絵を描いていて。
描いてもらった人もびっくりしていました。
それを見て、「ああ、本物なんだな」って思いました。
- 糸井
- いやあ、恐ろしいですよね。
そんな上村さんでも、
デビュー作の頃には、まだ迷いが見えます。
マンガ家になる前の、デザイナーだった当時から
ちゃんと絵の描ける人だったのは確かなんだけど、
展示を見て、「あ、やっぱりこういう時代もあるんだ」
と思って、かえってうれしかったです。
- 上村
- あ、そうですか。
- 糸井
- 「パラダ」なんて、たぶん読んでましたよ。
阿久悠さんも、上村さんのマンガとおなじように、
「ナイフを光らせて男を待ってた」みたいな
歌詞を書いていましたからね。
上村さんと阿久悠さんは、
自分を売り出すときの狙い目が的確でした。
阿久悠さんは、作詞の方法論を
持っていた方だと思いますし。
それでも晩年になると、
阿久悠さんの歌謡曲も、上村さんの劇画も、
需要が少なくなる時代にさしかかっていました。
だから、上村さんがもっと長く生きていたら、
悔しさみたいなのを味わったかもしれません。
享年45歳。
すごく若いけど、よかったのかもしれないね。

「パラダ」 ©上村一夫
- 上村
- ほんとに、そうなんです。
- 糸井
- 平成を知らないで亡くなったんですっけ。
- 上村
- そうなんですよ。
父は1986年の1月に亡くなりました。
昭和を駆け抜けた感じですね。
父が亡くなってから、
うちにいっぱい写真が戻ってきたんですが、
ほとんど酔っぱらって、楽しく飲んで歌って、
という写真ばっかりでした。
それを見たときに、
おおいに描いて、おおいに飲んで、
これでよかったかなって、やっと思えました。
- 糸井
- あと、上村さんのマンガには、
いいセリフや文章も、いっぱいあるんですよね。
- 上村
- はい。詩的な文章がありますね。
- 糸井
- 正直に言いますと、
当時のぼくは、上村さんがそういう文章を書くのを、
「またかっこつけて」って思ってたんですよ。
どうしてこの人は、年寄りを演じるんだろうって。
ぼくは年下ながら、
まだ似合わないんじゃないかなと思っていたんです。
それはね、ぼくが、ちょっと醒めたガキで、
生意気なことを思っていたんですよ。
でも今、上村さんのマンガの文章を読むと、
その文章がよかったと思えます。
- 上村
- そうですか。
- 糸井
- あの頃が、上村さんの晩年だったんだよ。

- 上村
- あとになってみると、晩年ですよね。
父のマンガって、子どものときには読まなくて、
亡くなってから初めて、
「同棲時代」とかを読んだんですよ。
ちょっとびっくりしちゃいました。
「お父さんは何をわかっていたのか」と思って。
今見るとびっくりしますね。
- 糸井
- あのときにもう、自分が早く年を取ることを、
本人が知っていたんじゃないかっていう気がするね。
太宰治のデビュー作が『晩年』でしたが、
マネしたわけではないだろうけど、
おなじような人なんだなって今ごろ思い出しますね。
だから、文章をまとめて、
抜きだすだけでもおもしろいかもしれないしね。
- 上村
- そうですね。

「同棲時代」 ©上村一夫
(つづきます)
2016-4-14-THU