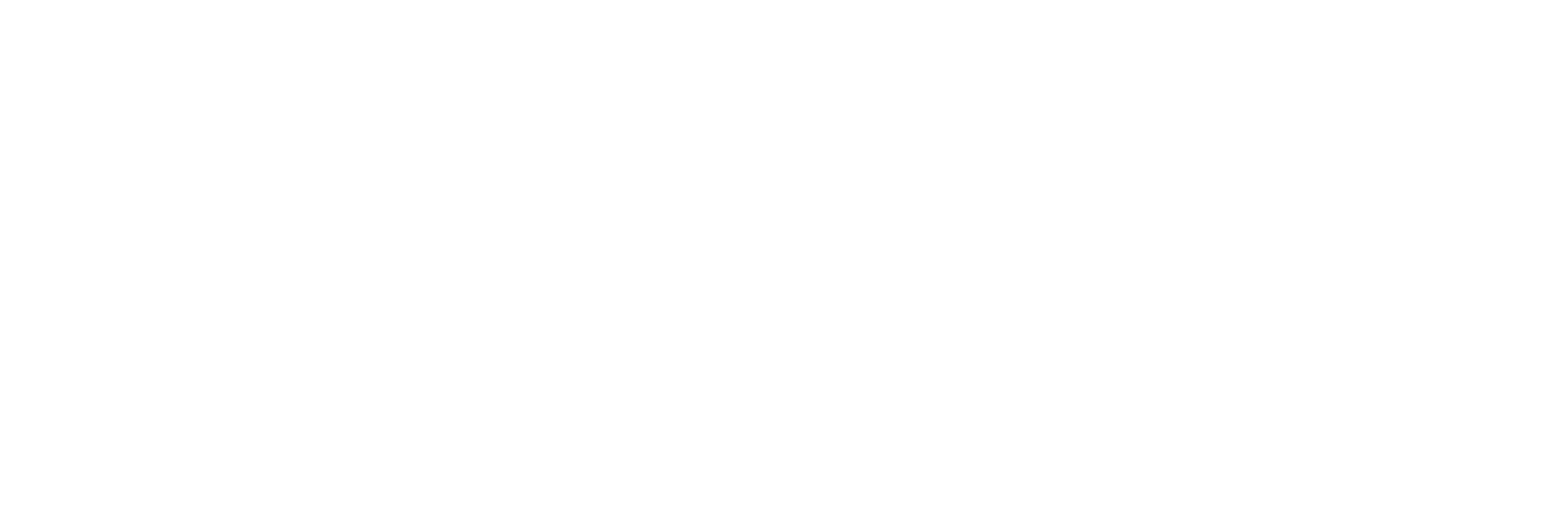消えたミスタータナカ
(浅生鴨)
僕が他のメンバーより一足先にネパールへ入ったのは、
空港に着いた幡野さんたちが、到着口から出て来る様子を
動画で撮影しようと考えていたからで、
特に事前にあれをやっておきたいとか、
これを見たいというものもないので、
ひと通りぶらぶらと歩きまわって、
なんとなく街の佇まいを把握したところで、
ひと息入れたくなった。
もしも、ここに一週間ほど滞在するのであれば、
僕ももう少しだけ深く街を知ろうとするのだけれども、
わずか二日半の滞在では、
せいぜい自分の巣穴の周辺を理解するので精一杯だろうし、
それ以上のことは、たとえわかった気になったとしても、
本当は何もわからないままだと思っているので、
あまり無理はしないことにしていた。
そもそも僕は観光名所に興味がないし、
めんどうくさがりだし、
できれば一箇所でじっとしていたい人間なのだ。
僕と同じく一足先にカトマンズへ入った田中さんは、
何台ものカメラを提げて、
あちこちの歴史遺跡や名跡をがんがん回っているどころか、
遊覧飛行機でエベレストを見に行くのだというから、
これは僕にはとても無理な話で、
僕と同じ生き物なのに、どうしてこうも違うのか不思議だ。
あの好奇心の旺盛さというか、
積極性と行動力には本当に驚かされるし、
僕もあんなふうにできたら楽しいだろうなと思う。
たぶんできないけれど。
ともかく二日目の昼、街の中を歩いているうちに、
偶然幡野さんたちが泊まる宿の看板を見かけた。
明後日は早朝に出発するので、
僕も明日の夜はこちらへ宿を移すことになっている。
そういえば田中さんが、さっきチャットに
「これから一度ホテルへ戻ります」と書いていたな。
だったらせっかく近くまで来ているのだし、
合流していっしょにお昼でも食べよう。
さっき安食堂も見かけたし。
僕はホテルのレセプションで声をかけた。
一枚板で作られたカウンターはずいぶん年季が入っていた。
木目が美しい。
「ここに泊まっているミスタータナカをお願いします」
「お部屋番号は?」
「わかりません」
「では調べましょう」
フロントスタッフがしばらく宿帳を繰るのだが、
なかなかミスタータナカが見つからないらしい。
「いつからお泊まりですか?」
「僕と同じ日程なので昨日からのはずです」
「ああ、ありました。ミスタータニダですね?」
「ちがいます、ミスタータナカです」
「ミスタータナカは、いませんね」
僕はちょっと不安になってきた。
「明日の予約を確認してもいいですか?」
確認してもらうと、
幡野さんのマネージメントをやっている小池さんの名前で、
人数分の予約がちゃんと入ってた。
どうやら僕も人数には含まれているようなので、
ひとまずホッとする。
それなのに、どうして昨日から泊まっているはずの
ミスタータナカだけが見つからないのか。
まさか偽名? いや、あの人ならやりかねないぞ。
おもしろさを優先して、偽名で泊まってもおかしくはない。
「日本のパスポートで泊まっているはずです」
「ふむ」
フロントスタッフが再び宿帳を繰る。
ここの宿帳はパソコンではなく、大判のノートなのだ。
彼は指を出して、細い罫線の間に
ペンで書かれた細かな字を追っていく。
「ミスターイトウですか?」
「ちがいます」
「日本のかたですよね?」
「日本のかたです」
「ミスタージョワリは?」
「それは日本のかたじゃないですね」
こんな不毛なやりとりをしばらく続けたのだが、
フロントスタッフはどうしても
ミスタータナカを見つけることができなかった。
何かがおかしいのだ。
「では、ミスタータナカにメールを出します」
僕は申しわけなさそうな顔をするスタッフに笑顔を向けた。
「彼と連絡がとれるまでここにいてもいいですか?」
「もちろんです、サー」
僕はロビーのソファにゆったりと腰を下ろし、
田中さんにチャットを送信した。
「今ホテルにいるのですが、お昼ごいっしょしませんか?
ところで、田中さん何号室なんですか?」
あとは返事を待つだけだ。僕は首を伸ばして周囲を見た。
小振りだけれどもきれいなロビーだった。
僕の向かい側のソファーでは、
これからトレッキングに向かおうとする宿泊客が
荷物の整理をしていた。
壁にかけられた写真を見る限り、どうやらこのホテルを
ヒマラヤ登山の拠点にする人も多いらしい。
ピン。手元で通知音がなった。
僕はあわててスマホを見る。
「僕はそのホテルには泊まっていませんよ。
空港近くのホテルに宿泊しています。
今晩、ご飯食べましょう」
あああ、なんということだ。
てっきり田中さんはここに泊まっているとばかり
思い込んでいたのに、僕の勘違いだったのか。
いったい、どこでどう間違えたのやら。
僕は平静を装ってスマホをポケットに入れ、
ちらりとレセプションへ目をやった。
カウンターの向こう側にいるフロントスタッフ全員が
僕の様子をじっと伺っている。
そんな気がしてならなかった。
「ミスタータナカとは連絡が取れましたか?」
そう言って、さきほど宿帳を繰ってくれた
スタッフが近づいてきた。
「これはサービスです、サー」
優しく微笑みながら彼が渡してくれたのは、
ミルクティーの入ったカップだった。
「いえ、まだです。ミスタータナカは返事をくれません」
僕はそう言ってからミルクティーをそっと口にした。
砂糖とスパイスのたっぷりと入った、
甘くて辛いミルクティーだった。