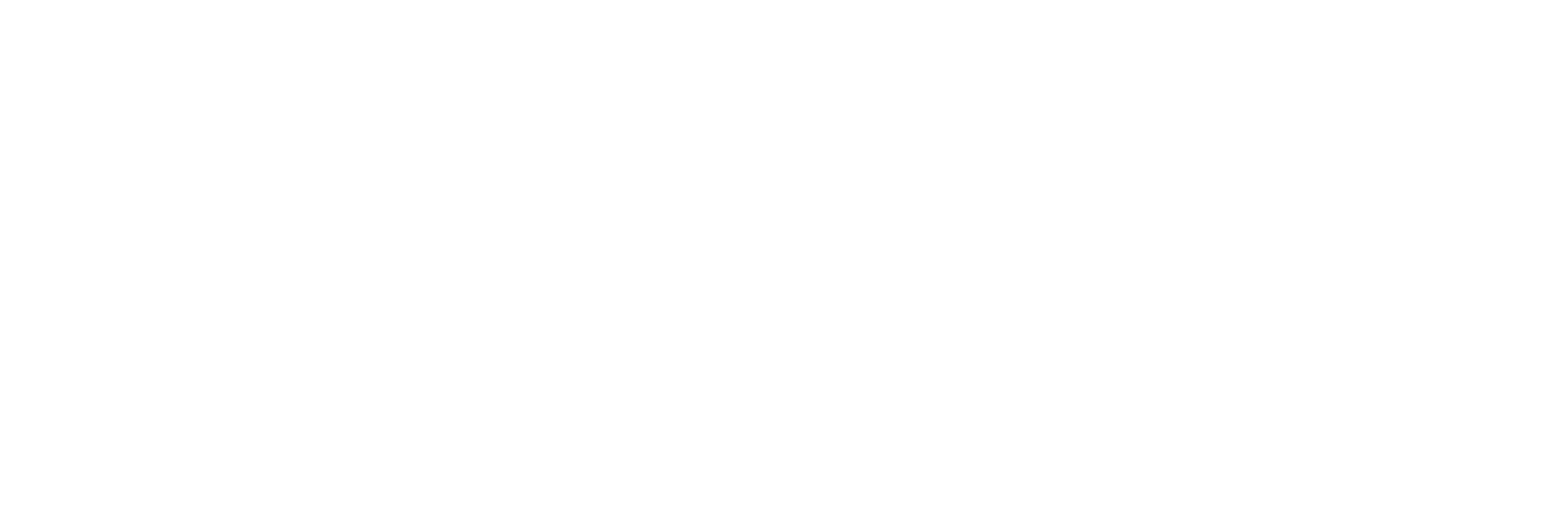黄色いバス
(浅生鴨)
山を抜ける大きなカーブを曲がったところで車が停まった。
崖のてっぺんを削ってつくったような広場に、
小さな商店が六、七軒ばかり並んでいる。
ドライブ・インとは言えない程度の
ちょっとした休憩所だ。
店の半分はシャッターが閉じられていて、
もう営業はしていないようだった。
開いている店はどこも茶を出し、駄菓子を売っている。
どうやら、ここで僕たちは朝食をとるらしい。
店先に並ぶプラスチックの容器には
飴やチョコレートが入っていて、
その隣にはコーラやペプシのペットボトルが置かれている。
空中に張られたロープには、スナック菓子の袋がかけられ、
奥には油やトイレットペーパーもある。雑貨屋なのだ。
もちろん初めてみる光景なのだけれども、
なぜか昔、僕の通っていた駄菓子屋に
似ているような懐かしさがあった。
カウンターの向こう側に三歳くらいの子供が座って、
小さな人形で遊んでいる。
その隣には、赤ちゃんを抱いた女性、
店の奥では目つきの鋭い男性が
どっかりと椅子に腰を掛けて茶を飲んでいた。
ショウケースには洗面器が飾られていて、
それだけは意味がわからなかった。
しばらくすると、店の前のテーブルの上に軽食が広げられ、
茶が出された。アルミ製の小さなカップに注がれたのは
スパイスたっぷりのミルクティーだ。チヤという。
この店では水牛のミルクを使っていて、特に美味いらしい。
ところが僕はひどい猫舌なので、熱いものが飲めないのだ。
ずいぶん寒くて、手もかじかんでいるのに、
なかなかチヤを飲めずにぼんやりしていると、
隣にいる幡野さんも、
同じようにカップを手に持ったまま、じっとしている。
「猫舌ですか?」
「猫舌です。あと猫手。熱いものが持てない」
「ああ、僕もです」
どうやら同類らしい。
チヤが冷めるまで待つことにした僕は、
テーブルにカップを置いたまま広場の端まで歩いた。
階段があって、五メートルほど下がったところで数人の
男性が水牛の乳を搾っていた。
その向こうでフリスビーを二枚重ねたような
円盤形の容器をぐるぐると回しているのは、
たぶんバターをつくっているのだろう。
「水牛のミルクを飲むか?」
男たちに話しかけられて、
幡野さんは飲むことにしたようだった。
「これどう飲むの?」
日本語で尋ねる幡野さん。
男たちが寄ってたかって飲み方を説明する。
「え? このまま? このまま飲むの?」
プラスチックのボトルから口に含んで、妙な顔になる。
「まあ、そんなに美味くはないね。日本のほうがいいや」
幡野さんはこういうとき、お世辞めいたことを言わない。
正直といえば正直なのだけれども、
場合によっては相手を傷つけることもあるだろうし、
同時に、正直であることで、
自分自身を傷つけることもあるのだろうなとも思う。
広場のすぐ脇にある山道の向こうから、小さな男の子と
その姉らしき二人連れが歩いてくるのが僕の目に入った。
もうずいぶんと砂にまみれて汚れているけれども、
二人ともグレーの制服を着ている。
「学校?」
僕が声をかけると、男の子は恥ずかしそうに
姉の後ろへ隠れてしまった。
「はい、学校です」
きれいな英語で姉が答える。
「バイバイ」
それ以上、彼女たちに
何を言えばいいのかわからなかったので、
僕はとりあえずさようならをした。
女の子は困ったような顔をして、
それでも「バイバイ」と返事をくれた。
広場の中では鶏が走り回っていた。
どうやら人間の食べこぼしに夢中になっているようだった。
朝食を終えて、みんながあたりをうろうろし始めたので、
僕もその場を離れて、遠くからみんなの様子を
ビデオに収めることにした。
一箇所に人が集まっているとき、
僕はなぜかその場から少し離れたくなる。
離れたところからみんなの様子を見たくなる。
どうにも妙な癖なのだけれど、
これが僕の性分だからしかたがない。
ガラガラと何かを引きずるようなエンジン音とともに、
カーブの向こうから一台の黄色いバスが現れ、
広場の端で停まった。
さっきの妹弟がバスに乗り込むのが見えた。
このバスで、あの子たちは学校へ通うのだろう。
黄色いスクールバスは、広場の端で方向転換をして、
今やって来たばかりの道を戻っていく。
ここがあのバスの最終地点なのだ。
あの子たちがいちばん遠くに住んでいる生徒なのだろう。
それでもここにはバスがある。
これから僕たちの向かうコタンにバスはない。
子供たちは何時間も歩いて学校へ通うのだ。
僕も小・中学生のころは、
一時間ほど歩いて学校へ通っていたのだけれども、
きっとあれとは道のりの険しさがまるで違うはずだ。
まだ写真でしか知らないけれども、
あのネパールの山道を毎日歩いて通うのかと思うと、
ふっと気が遠くなる。
いつのまにかに、みんなの動きが慌ただしくなっていた。
そろそろ出発の時間が近づいているようだった。
僕はあわててみんなの元へ戻る。
すっかり冷めたチヤは、それでも、とても美味かった。