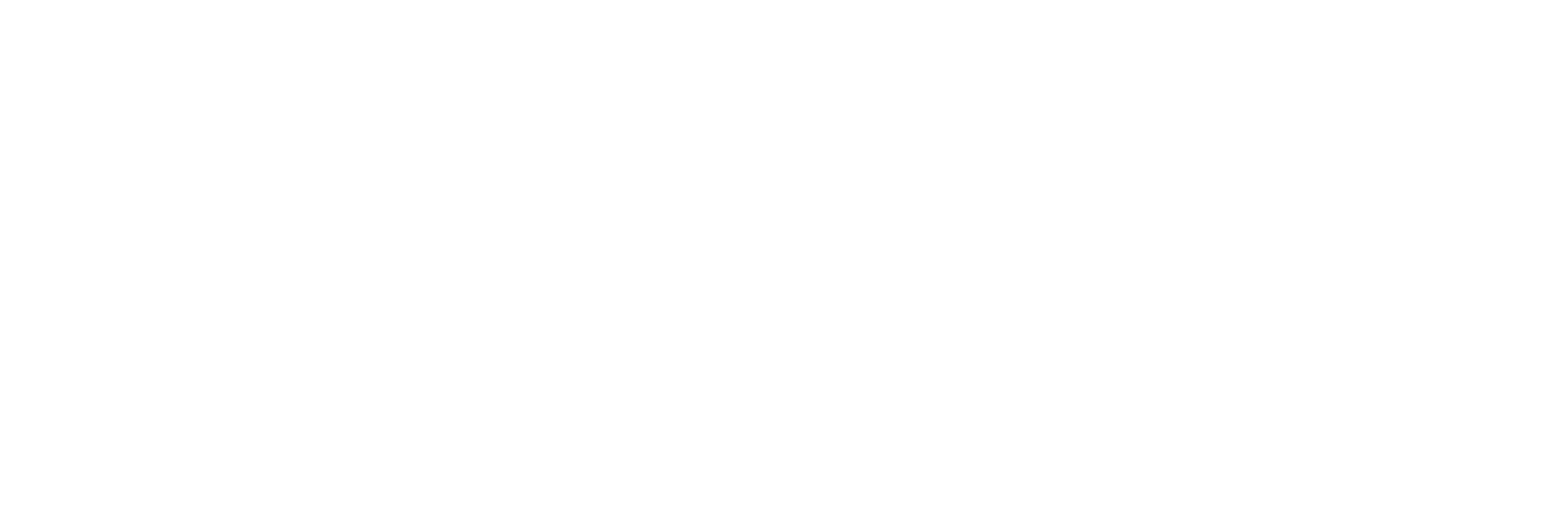登校時間とちょっとバカ
(浅生鴨)
生徒たちの登校する姿を撮影するために
カメラを三脚に置いて待ち受ける僕を見て、
彼らは少し恥ずかしそうに、
それでも大きな声を出して英語で挨拶をしてくれた。
「グッドモーニング、サー」
「グッドモーニング」僕も英語で答える。
ところが、みんながあまりにもきちんと
挨拶してくれるものだから、
どうも自然な登校シーンにならない。
僕はカメラの録画スイッチを入れたまま、
その場を離れることにした。
ただカメラが回っているだけなら、
生徒が挨拶することもない。
もちろんレンズをのぞきこんだり、
カメラに向かって
ふざけてみせたりする子もいるだろうけれど、
それでも挨拶するほどの堅さはないはずだ。
もう一台のカメラを手に持って、
別の方向からやって来る生徒たちに向ける。
「グッドモーニング、サー」
「グッドモーニング」
赤い帽子の生徒たちは、見知らぬ僕にきちんと挨拶をする。
シャラドのやろうとしていることが、
僕にもぼんやりとわかり始めていた。
きっと彼らはここで勉強だけでなく、
人としてのありようを学んでいるのだ。
学校をつくる。それは言葉で聞くのと
実際に見るのとではまるで違っている。
どこかの部屋を借りるのではなく、
山の上に校舎を建てるところから始めてしまうのだから、
シャラドはやっぱりとんでもない男なのだろうし、
そして、ちょっとバカなのだと思う。
普通なら準備に準備を重ねて、
採算だのリスクだのをあれこれ計算したあげくに、
ようやくスタートするようなことを、何というか、
僕の目には気軽にあっさり始めてしまったように映るのだ。
もちろんいくつもの問題やトラブルを乗り越えたからこそ
今の状況まで持ってこられたのだろうし、
そのたびにきっと胃が痛むような思いをしたに違いない。
それでもやっぱり気軽に楽しみながら
プロジェクトを進めているような印象を受けるのは、
やっぱりシャラドがちょっとバカだからだろう。
むしろ、こういうことは、
ちょっとバカじゃなければできない。
何かを為す人というのはたいていちょっとバカだし、
これまでにない新しいものごとを生み出すのは、
きっとバカにしかできない仕事なのだ。
頭のいい人たちが考えに考えて、
余計な心配ごとを積み上げた結果、
そのまま一歩も踏み出せずに躊躇しているすぐその横で、
シャラドはさっさと笑顔で始めてしまう。
心配事の種をあれこれ探す前に、まず体を動かしてしまう。
そうして「ほら、やってごらんよ」と笑顔のまま
周囲をどんどん巻き込んでいくのだ。
シャラドを支える人たちを見れば、
彼がとても尊敬されていることが伝わってくる。
もちろんシャラドのやっていることは、
あまりに大きく長い道のりだし、
たぶんこの先もいろいろな苦労が続くはずだ。
それでもシャラドは一歩ずつ前に進もうとする。
たぶんそれは、この空へ消えていく高い山に生まれ育ち、
何キロも歩き続けてきたシャラドだからこそ
踏み出せる一歩なのだろう。
その一歩の重みを、一歩を積み重ねることの大切さを、
シャラドはきっと誰よりも知っている。
登校する生徒たちの数がしだいに減ってきた。
そろそろ授業開始の時間なのだ。
僕は三脚を置いた場所へ戻った。
自然な登校風景が撮れただろうか。
「グッドモーニング、サー」
なぜか生徒たちはあいかわらず挨拶をしていた。
元気よく声をかけている相手は、
ドライバーのナラヤンだった。
三脚の前でじっと仁王立ちになったナラヤンが、
次々とやってくる生徒たちに向かって手を振っていた。
「あの、ナラヤン、そのカメラで撮影してるんだけど。
カメラの前に立たれると何も映らないんだけど」
そう話しかけた僕をゆっくり振り返ったナラヤンは、
親指と人差し指を丸めてオーケーのサインを出した。
いや、ぜんぜんオーケーじゃないぞ、ナラヤン。