ほぼ日の学校長だよりNo.52
<みどりの季節>の人よ!
10月9日より、ほぼ日の学校第3期「万葉集講座」の受講生募集が始まりました。その予告篇として、漫画家・里中満智子さんのインタビュー「万葉集の魅力」を4回連載しました。このインタビューを読んで、「はじめて『万葉集』が読みたくなりました」と言ってくる乗組員が何人かいました。
私自身、恥ずかしながら、今回初めて『天上の虹』(講談社文庫全11巻)を通読したのです。里中さんが32年の歳月をかけて、2015年にようやく完結させた長編漫画です。第41代天皇で、女帝である持統天皇の57年の生涯を描いた大河ロマンです。『万葉集』の時代を背景に繰り広げられる、さまざまな男女の愛と権力をめぐる一大絵巻物。生き生きと描き出された万葉びとのリアリティに、俄然、好奇心が湧いてきます。

里中さんがおっしゃるように、「万葉集の楽しみはキリがなく、歌から入る、人から入る、時代背景から入る。いろんな切り口がある」と思います。今回の「万葉集講座」もいろいろなアプローチを用意しました。是非この機会に、1300年前の世界にトリップして、『万葉集』の新しい魅力を発見していただければと思います。
さて先日は、その講師の一人であるノンフィクション作家・梯(かけはし)久美子さんをお訪ねし、講義の打合せ、告知用の談話の取材などをしてきました。講座は11月28日スタート(梯さんの登壇は来年5月8日の予定)ですから、「万葉集」のことはまたおいおい触れることにして、今回は梯さんの近著『原民喜――死と愛と孤独の肖像』(岩波新書)について、少し述べたいと思います。
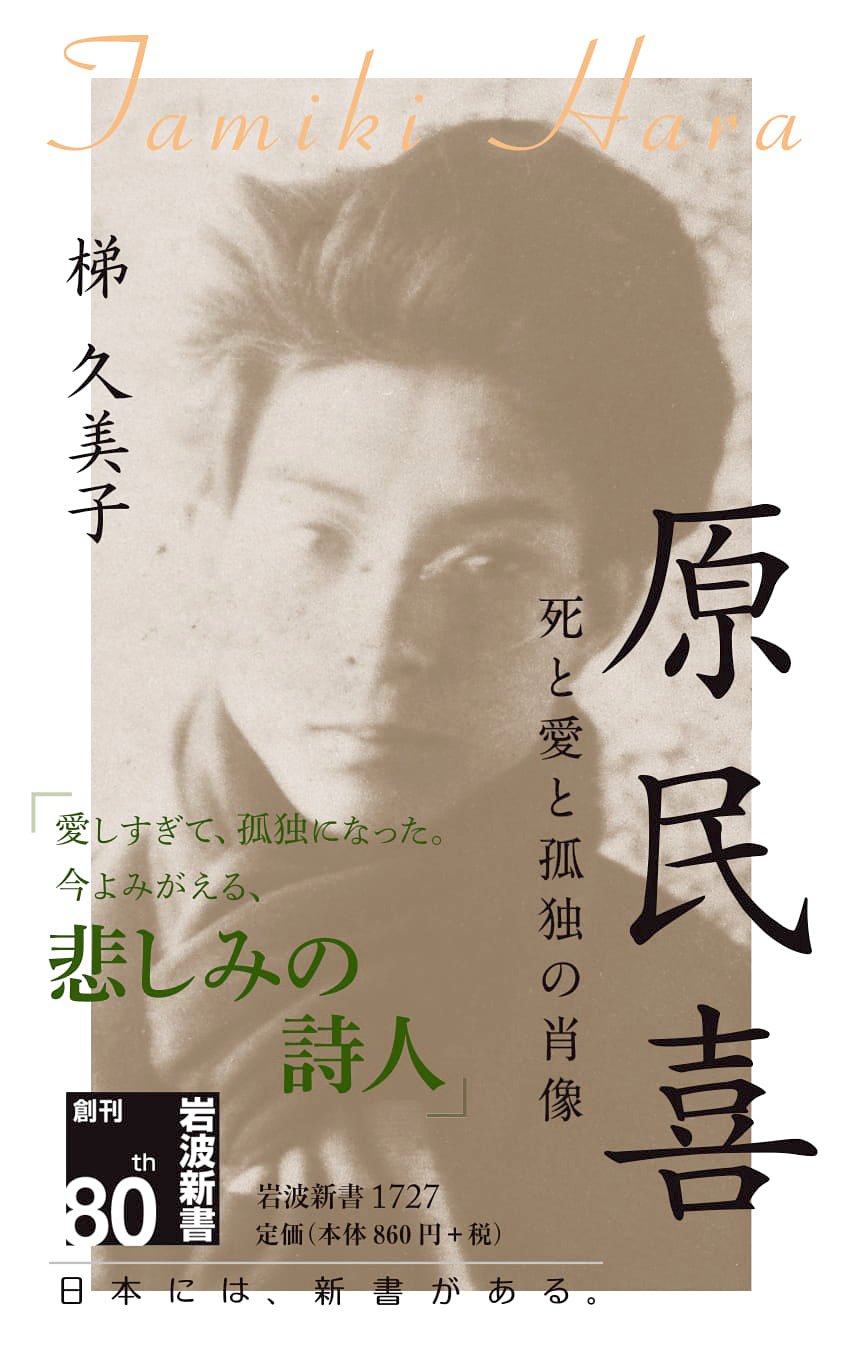
ほぼ日の学校を始めて以来、折々に感じていることをこの本が探り当て、より鮮明に浮き上がらせてくれたからです。
原民喜(はらたみき)という人は、原爆投下直後の広島を描いた名作「夏の花」で知られる作家です。1905年広島市生まれ。慶應義塾大学で英文学を学び、東京で細々と、内省的な心象風景を詩や小説に書いていました。極端に人見知りで、生活能力には乏しく、死の影におびやかされながら、世間から孤絶した暮らしぶりでした。
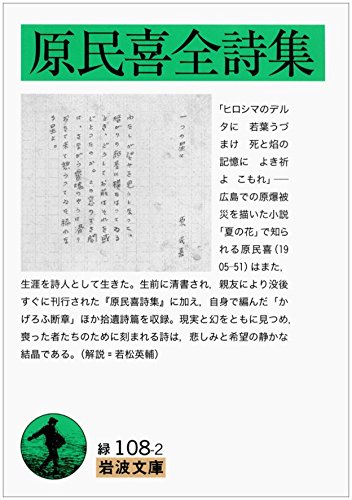

そんな原を支え、彼の人生でもっとも幸福なひと時をもたらすのが、見合い結婚で結ばれた6歳年下の妻です。夫の才能を信じ、「お書きなさい。それはきっといいものが書けます」と励まし、最大の理解者、庇護者になります。ところが、その最愛の人が病に倒れ、数年間の療養生活を経て、亡くなります。結婚12年目、1944年9月のことです。
打ちひしがれて広島に帰郷。翌年、そこで被爆。おびただしい死を目撃します。戦後はふたたび上京して、孤独と困窮に苦しみながら創作活動に励みますが、1951年3月13日、自ら死を選び、45歳の生涯を閉じます。
梯さんは本書の冒頭にこう書いています。
<死の側から照らされたときに初めて、その人の生の輪郭がくっきりと浮かび上がることがある。原は確かにそんな人のうちのひとりだった。>
葬儀の際、弔辞を読んだ作家の埴谷雄高(はにやゆたか)は、「あなたは死によつてのみ生きていた類ひまれな作家でした」と語りかけています。
「死の想念にとらわれた作家」――言葉にすれば、私もそういうイメージを抱いていました。しかし、梯さんがこの本で成し遂げたことは、死にとりつかれた繊細すぎる作家の“短くも美しい人生”をたんに愛惜するのではなく、彼の魂の“強靭さ”を示した点です。
自死という最期に対し、著者は敗北ではなく、原がたどりつかざるを得なかった宿命的な帰結を見ています。「繰り返しよみがえる惨禍の記憶に打ちのめされそうになりながらも、虚無と絶望にあらがって、のちの世を生きる人々に希望を託そうとした」彼の精魂こめた生き方を見届けます。
その意味で、後輩作家である遠藤周作との交わりは象徴的で、いろいろなことを考えさせます。文学的な精神は、ある部分、原から遠藤へとたしかに受け継がれ、死者は生者のなかに生き続けるのです。
留学先のフランスで、原の死を知らされた遠藤は、日記にこう記しています。
「原さん、さようなら。ぼくは生きます。しかし貴方の死は何てきれいなんだ。貴方の生は何てきれいなんだ」
2人の交友には、ひとりの女性が加わります。死の2年前から、不思議な、メルヘンのような3人の関係が生まれます。原42歳、遠藤25歳、女性が21歳。敗戦の焦土から復興へとしゃにむに前に進もうとする荒々しい世相のなかで、3人の奇跡のような交流が始まります。
「原民喜と夢の少女」というエッセイのなかで、遠藤は3人のエピソードを紹介しています。
<私は彼女とある日、映画に行く約束をした。彼女はすなおに美しく「えゝ。」と答えた。
それは夏の暑い午後だった。私は約束した日本橋の喫茶店に一応行ったが、突然、全てが阿呆らしくなって来た。電車が動いている事、人々が忙しげに歩いている事、全てが阿呆らしくなって来た。少女と映画に行く事も阿呆らしくなって来た。私は帰ろうとした。その時、原さんがその喫茶店にあらわれたのだ。
「原さん、何で来たの。」と私は叫んだ。
彼は悲しそうな表情をした。そして
「キミガ、アノヒトヲオイテキボリニスルダロウトオモツタカラ ミニキタンダ。」
突然、私の胸を悲しみとも悔ともつかぬものが一杯にしめつけた。
「大丈夫だよ。原さん、大丈夫だよ。ぼく必ずこゝに居るよ。」
「ソー ソンナラアンシンシタヨ。ボクハカエルヨ。」
そして夏の午後の日本橋の行き交う人群のなかにその肩と肩とを押し合う歩道の流れのなかに原さんはポケットに手を入れ、とぼ、とぼと猫背で消えていった。私はそれを泪をこぼしながら見つめていた。>

遠藤は、この時名状しがたい悩みや葛藤を抱えていました。原はそれに気づいていました。原のことばはカタカナ表記になっていますが、遠藤の耳にはきっと、このように響いて胸に刺さったのだと思います。
多くの死と出会い、喪失の悲しみ、死者の嘆きをことばに刻んでいた原が、若いふたりにどう接していたか。原の資質、人間観、文学者としての使命感までが伝わってくるようなエピソードです。
梯さんは、この時の女性の消息をたどり、89歳になっている彼女を訪ねます。
<彼女は結婚して姓が変わっていた。東京都内の自宅を訪ねると、老女という言葉の似合わない若々しい女性が迎えてくれた。眼に独特の光のある美しい人で、向きあっていると、原が出会った時代の面影が見えるようだった。>
貴重な証言が続きます。
「原さんのお書きになったものを、私は当時、ひとつも読んでいませんでした。境遇についても、原爆に遭われたということはどなたからか聞いたと思いますが、原さんは身の上話などなさらない方で、奥さまのこともお話しになりませんでした」
「遠藤さんはいつもふざけていましたから、傍からはどう見えたかわかりませんが、心から原さんを尊敬し、大切に思っていたのだと思います」
「三人でいると、不思議にほっと息をつくことができた。いま振り返っても、あの時間だけが、ぽっかりと宙に浮いているような‥‥。お互いのことをよく知らず、知る必要もないことが、かえってよかったのかもしれません」
原が自死したことをどう思うか、と訊くと、少し時間をおいて、「‥‥肯定します」と彼女は答えます。
「二十歳そこそこだった私は原さんの苦しみを理解してさしあげることなどできませんでしたし、いまもそうだと思います。でも、どうしてそんなことを? と問うのではなくて、そうですか、そのようになさったんですね、と、そのまま受け止めたいのです」
彼女に寄せて原が書いた小説「永遠のみどり」は、こう締めくくられています。
<十日振りに帰ってみると、東京は雨だった。フランスへ留学するEの送別会の案内状が彼の許へも届いていた。ある雨ぐもりの夕方、神田へ出たついでに、彼は久し振りでU嬢の家を訪ねてみた。玄関先に現れた、お嬢さんは濃い緑色のドレスを着ていたので、彼をハッとさせた。だが、緑色の季節は吉祥寺のそこここにも訪れていた。彼はしきりに少年時代の広島の五月をおもいふけっていた。>(『夏の花・心願の国』新潮文庫より)

遠藤周作は、留学中の日記にこんな記述も残しています。
<原民喜が、その作品の中で描いている、ぼくの像をみると、彼が、ぼくに考えていた事がはっきりわかるのだ。
つまり、ぼくは彼にとって、<みどりの季節>の人間であり、荒涼たる冬を経た彼からバトンを引き渡さるべき人間であったに違いないのである。>
原は無力で、時代の流れにも背を向けて、あくまで死者の側に寄り添おうとする人間でした。「自分のために生きるな。死んだ人たちの嘆きのためにだけ生きよ」――「鎮魂歌」という作品のなかで、原はこのフレーズを繰り返します。
しかし、愛する者たちの死に向き合い、「自分の生涯とそれを育てたもの」にとことん誠実であろうとし続けた原の存在は、終戦直後の寄る辺なき人々に、慰めとあたたかな励ましをもたらします。梯さんがいう原の「強靭さ」とは、まさにこの点です。
そして、新緑への震えるような感動、<みどりの季節>を生きる若い世代への希望、明日の世界への願いと祈りを手放さなかった原を、著者は静かに祝福しています。
<個人の発する弱く小さな声が、意外なほど遠くまで届くこと、そしてそれこそが文学のもつ力であることを、原の作品と人生を通して教わった気がしている。>
「弱く小さな声」に対してオマージュを捧げることで、梯さんはこの作品を締めくくっています。ひと言では言い尽くせない、重いメッセージを読み取ることができ、とても貴重な読書になりました。
2018年10月11日
ほぼ日の学校長












