ほぼ日の学校長だよりNo.125
万葉学者の「死にたまふ母」
「ほぼ日の学校オンライン・クラス」(現在、無料公開中)でも人気絶頂の上野誠さん(奈良大学教授・国文学)が、先日、新著を送ってくださいました。『万葉学者、墓をしまい母を送る』(講談社)という本です。

短いお手紙が添えてあって、冒頭に一首、
春雨の しくしく降るに 高円(たかまと)の 山の桜は いかにあるらむ
という『万葉集』巻8、1440の歌が記されています。河辺朝臣東人(かはへのあそみあづまひと)の歌で、
<春雨がしきりに降りつづいている今頃、高円山の桜はどのようになっているのであろう。もう咲きだしたであろうかな。>(伊藤博『萬葉集釋注四』、集英社文庫ヘリテージシリーズ)
という意です。
<手軽に読んでいただける本を、献本させていただきます。
ただ、‥‥この本が一体なにに当たるのか、私にもわかりません。出来損ないの三文小説、不正確な民俗誌、あまりにも些末な家族史、と考えあぐねています。
ただ、私なりに小さな志もあります。私が書きたかったのは、小さな歴史です。個人が体験し、歩く、見る、聞く、食べる、から構想し得る歴史です。私は民俗学こそ、小さな歴史を記述する学問だと考えています。個人の心性を始発点として、死の歴史を語りたかったのです。おそらく、この本に書いた40年は、家族墓の成立から崩壊の歴史であり、それはとりもなおさず、近代家族の終焉の歴史だと考えています。たぶん、読んでいただければ、馬脚をあらわすと思いますので、先に申し上げますと、フィリップ・アリエスへの極東からのオマージュとなっています。>
フィリップ・アリエス(1914~1984)とは、フランスの中世・近世社会の研究で注目を集めた歴史家です。家族、子供、死をテーマにした『<子供>の誕生』『死と歴史』『死を前にした人間』(いずれも、みすず書房)、『図説 死の文化史――ひとは死をどのように生きたか』(日本エディタースクール出版部)などの著作は、日本でもよく読まれています。
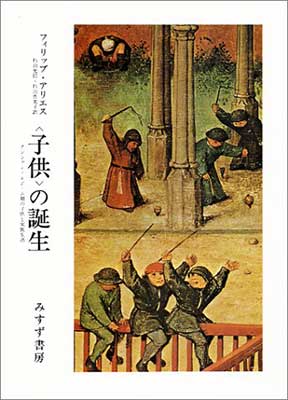
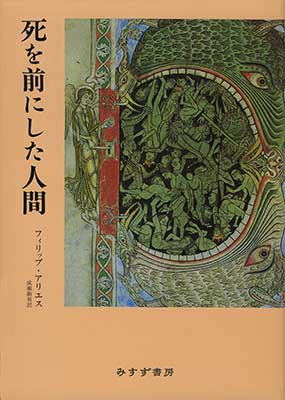
さて、上野さんのいう「小さな歴史」とは、「祖父が死んだ一九七三(昭和四十八)年夏から、母が死んだ二〇一六(平成二十八)年冬の四十三年間の、死と墓をめぐる私自身の体験」を、歴史的な心性の変化として語る試みです。
ほぼ日の学校でもおなじみの語り口! 上野さんの体験談、おもしろくないはずがありません。それを『古事記』や『万葉集』、あるいは歴史学や民俗学などの知見につなげながら軽妙に展開し、死者への愛惜と畏怖、そして現実を生きる私たちの生き方そのものに深く思いをいたす知的エッセイになっています。
始まりは、著者13歳の時の思い出です。病院から自宅に戻ってからのほぼひと月、祖父の“最期”が近づいてゆくさまを少年はかたわらで見続けます。やがて、医師があわただしく呼ばれてその“死”が確認されると、菩提寺の住職が来て、枕経(まくらぎょう)が上げられます。
あい前後して、親類や近所の男衆、女衆がやってきて、家族、親族を中心にした仮通夜、近隣の人々を招いた本通夜、そして一般弔問客をふくめた告別式という流れで葬儀が行われます。
大人たちがバタバタと立ち働きます。女たちは3日間で数百食もの食事を作り、男たちは葬式のやり方――祭壇の大きさだの、焼香の順序だの――をくだくだ、長々と話し合って、「寄り合いの民主主義」で日本的な合意形成をはかっていきます。
驚くのは13歳の記憶力です。「多感な年ごろに、はじめて経験した葬儀であったから」という理由がひとつですが、もうひとつは上野さんの学問的な専門領域にかかわります。
<大学生、大学院生の学者修行の時代、私は万葉挽歌の研究と民俗学の勉強に取り組んでいた。だから、十三歳の記憶を大学生のときから、何度も何度もたどっていたのである。死と葬送の文学である挽歌、そして民俗社会の慣行を考える民俗学を学んでいたから、あの日々のことを、それから何度も思い出しているのである。>
わけても強烈な体験は「湯灌(ゆかん)」です。死者を納棺する前に、お風呂に入れる儀式です。これは、妻や娘、つまり女の仕事であって、男たちは知っていて知らぬふりを決め込みます。
上野さんは13歳。まだ一人前の男とは認められない年齢で、祖母と母親を手伝って、遺体を背負い風呂まで運びます。そして初めて目にする湯灌の光景――死せる祖父を祖母と母が沐浴(もくよく)させる姿――は衝撃でした。
祖母と母は、絶えず祖父に声をかけながら、まるで赤ん坊をあやすかのように、体をきれいに洗うのです。動かなくなった身体を愛撫するかのような姿に、かぎりない愛おしみを感じます。
沐浴が終わると、少年は遺体を浴室から脱衣所に引き上げます。そこで祖父は、あらかじめ用意されていた新しい浴衣を着せられます。
<それから、母たちは、私にはわからない不思議なことをした。祖父の着ていた寝間着を、さっと水洗いし、バケツに入れて、そこに水を注ぎこんだのだ。聞けば、四十九日の法事がすむまでのあいだ、水につけておくのだという。>
祖父を座敷の布団にふたたび寝かしつけると、3人は風呂場を丁寧に洗い流し、それから着ていたものを、下着まですべて着替えます。そして、脱いだ衣服をひとつの袋に入れると、母はそこに☓印をつけ、大きく「焼却」と書きこみます。
<母は私に、湯灌に使ったものは、穢(けが)れているからね、とさらりと言った。>
どうして? この時、疑問に思ったことは、やがて学者として知るところとなります。死者に対する愛惜と畏怖の感情は表裏一体の関係にあります。それは、『古事記』のイザナキとイザナミの国生み神話とともに語られる黄泉行(よみこう)神話に描かれています。

湯灌は、死者が黄泉国(よもつくに)に旅立つための禊(みそ)ぎであり、新生児の産湯に対応する、死者の産湯でもあります。女たちにとっては、死者の肉体を愛おしむ最後のチャンスであり、それはとりもなおさず、死者と生者との今生の別れ――穢れた死者の黄泉の国と、生者の「葦原の中つ国」と、お互いに往き来のできない異界に別れる時なのです。

こうして13歳の脳裡に深く刻まれた「死の手触り」を語り、続いて祖父の建てた巨大な「上野家累代之墓」の「墓じまい」をする話が述べられます。
そして本書の後半は、時が流れ、今度は上野さん自身が、当事者として母を看取り、通夜、告別式、出棺という葬儀の一切を取り仕切るのです。
88年間一度も故郷の博多から離れたことのなかった母親を、
「お母さん。しばらく、奈良に来んね。よか病院のあるとよ。奈良なら、僕も毎日行けるとよ。日本一の親孝行息子が言うとやけん。しばらく、奈良に来て」
と身近に呼び寄せ、7年の介護の後に見送るまでの顛末です。
それまでお兄さんが健在の間は、兄の家族と同居していたお母さんですが、
兄 あんまり、わがままいいよったら、おれんほうが、先に逝くばい。
母 ものには、順序というものがあるとよ。私が死んだ翌日に死にんしゃい。あの世からすぐに迎えに来ちゃるけん。
などと会話していたところ、本当にお兄さんが、2008年に肺がんで先に亡くなります。上野さんの決断がいよいよ迫られます。この母上については、以前、「学校長だより」No.59で紹介しました。福岡の俳壇で活躍していた50代半ばの母上のことが、上野さんの文章に登場します。
<受験の偏差値に苦しんで、やっと東京の私大に滑り込んだ私は、福岡から上京した。そんなある日、とある新聞の俳句の欄が目にとまったのである。
一流に少し外れて入学す
なかなかいい句だなぁー‥‥と思いつつ、うどんをすすっていたのだが、思わず吹き出してしまった。作者のところを見ると「福岡 上野繁子」とあったのである。
そういえば、第一志望の高校に不合格になった日の母の「迷言」を思い出した。「学生食堂も無いような高校に入学しなくてよかった。弁当が大変だ。第二志望でよかった」と。さすが、わが母である。>(上野誠『おもしろ古典教室』、ちくまプリマー新書)

この母にして、この子あり。「ちょっといい話」の典型でしたが、88歳で郷里を離れた奈良での生活はラクなものではありません。
<大腿骨(だいたいこつ)骨折による入退院。誤嚥性(ごえんせい)肺炎による入退院。その合間の介護施設での生活。いくつの病院、いくつの施設にお世話になったのか、数えられない。ぐるぐるめぐる。タライまわしである。>
介護する側も介護される側も、ギリギリのところで耐えますが、「そのたびに、母は小さくなっていった」とあります。
<母は、死ぬ半年前まで、私にこう言った。
「まだ、通帳にぁー、葬式代は残っとるとね。葬式代で、めんどうかけとうはなかばい。葬式はせんでもよかとよ。葬式に来るもんの旅費も払わないといかんばい」
私は、こう答えていた。
「やったら、早よう死ぬわけにもいかんやろが。そげんこつは、死ぬもんが心配することやなかろうがぁー。いまは、家族葬というのがあって、シンプルにできるとやけん。心配せんといて」>
著者にはひとつの哲学がありました。
<死にゆく者を見送るのは、人の人たる義務だ。しかし、送る人の生活の質を低下させることがあってはならないと、と思っている。親を看取る場合、子こそが幸福でなくてはならないとすら思っている。子の幸福こそ、親の希求する最大の幸福ではないのか。>
ここから導かれたのが、まさにシンプルな家族葬。母を看取った後で決めた葬儀は、葬儀場を使わず、葬儀社内の家族室で行う簡素なもの。祭壇も作らず、遺影も作らず、生花、造花も不要。遺体の前に机を置き、アクリル板の写真を5枚と、母の自選句集を飾ります。そして、大学の講義を決して休講にはしない、というきっぱりした決断を下します。
<けっきょく、その日から四日間、母と家族室に寝泊まりし、日中は大学で講義をしていた。折しも、大学の通信制学部のスクーリングの授業があって、三日間朝から晩まで、全国から集った百三十名のスクーリング受講生とともに『古事記』を読んでいたのだ。>
通夜の日に集まった人たち(家族と介護を手伝ってくれた学生=15名)には、それぞれの知っている折り紙を折ってもらい、生花や造花の代わりに遺体の前に飾り、出棺時にそれを棺に入れます。香典はなし、平服参集で、通夜、葬儀の司会も上野さんがやり、会葬の挨拶もなく、「ごくろうさま」のひと言で終わり。
「湯灌」も、葬儀社に依頼して、特別編成の5人のチームに委ねます。これが43年の時を隔てた上野家、2016年の葬礼です。
わずかのあいだに「こんなに変わってしまったのか」という思いが、上野さんの胸に去来します。『古事記』に描かれた神話の世界があり、そこから脈々と受け継がれてきた儀礼があり、時代とともに様式は変化していきます。その時々の人々の生き方を反映しながら、葬送儀礼のありようは、人々が「悩み、あえぎながら」選んできたのではないか、と想像します。

そして、ここから現代人にとっての神話の読み解き、さらには古典といわれる世界への向き合い方に論が及びます。上野さんならではの考察です。
<私たちは、ただ漫然と神話を読んでいるわけではない。なぜ登場する神々は、そういう行動をとったのだろうかと、日々考えながら神話を読んでいる。神話のほうが変わらなくても、読む私たちのほうが、日々刻々と変化しているのだ。そのなかで、私たちは、新しい神話の読み解きを考え、神話の再解釈を続けているのではないのか。読むという行為は、じつに主体的な行為なのである。それは、神話だけでなく、古典、さらに広くいえば文学を読むという行為も同じことだ。古典は、読む側の都合や心のありようによって、解釈も日々刻々と変わるものだ。古典だからといって、動かないわけではない。読むのは、それぞれの時代の人間なのだから。>
上野さんの古典論が思い出されます。
「古典」だからすばらしいのではない。その古典を読んでおもしろいとか、たのしいとか思う「いま」の「自分」がすばらしいのだ。読んだ事柄をどう受け止めるかという「いま」の「自分」こそがもっとも大切なのだ、と。

エピグラフに引かれているのは、『万葉集』巻3の348、349の2首です。大伴旅人「酒を讃むる歌13首」からの意訳です。349を紹介して、締めにしたいと思います。
生ける者(ひと) 遂にも死ぬる ものにあれば この世にある間は 楽しくをあらな
「生きとし生ける者は――
ついには死を迎える
ならばならば、この世にいる間は‥‥
楽しくいきなきゃー ソン!」 (上野誠訳)
2020年5月14日
ほぼ日の学校長
*ほぼ日の学校オンライン・クラスに「ダーウィンの贈りもの I」第6回講義が公開されました。坂口菊恵講師による「人生100年時代:ポスト繁殖年齢をどう生きるか」。だれもが関わるテーマ、必見です!













メルマガに
登録してね。
朝8時にお届けします。