ほぼ日の学校長だよりNo.59
「いまを生きる」
昨晩から、いよいよ「万葉集講座」が始まりました。

今回の講座で中心的な役割を担っていただく上野誠さん(奈良大学文学部教授)に、『おもしろ古典教室』(ちくまプリマー新書)という著書があることを、ごく最近になって知りました。早速開いてみると、

<古典を読むと立派な人になれるというのは間違いだと思います。>
ということばに、いきなり出会います。読書が人格形成に役立つなんて嘘っぱちだ、と。
<古典についていえば、わたしはそういう教養主義的な古典教育が、古典のほんらい持っているたのしさを半減させているとさえ思っています>
<わたしは高校時代の現代国語や古典の授業が嫌いで嫌いでたまりませんでした。そんな高校生だったわたしが、古典の先生としてこの本を書いているのですから、不思議なことです。人生はわからない。>
自らの体験を振り返りながら、ぶっちゃけた話を展開しています。
<では、今なぜ、古典を読むのかと聞かれると、「おもしろいから」としか、答えられません。‥‥わたしの場合、すべては「おもしろい」「たのしい」から出発して、そこがまたゴールになっています。>
こう述べて、ふたつのメッセージを投げかけます。
・「古典」だからすばらしいのではない。その古典を読んでおもしろいとか、たのしいとか思う「今」の「自分」がすばらしいのだ。美味しい料理を味わうには、「今」の「自分」の舌が決め手であるように、読んだ事柄をどう受け止めるのかという「今」の「自分」こそがもっとも大切なのだ。
・「読む」とは、言葉の背後にあるもの――書き手、語り手の心や心情――に思いをはせ、想像することである。そうしてはじめて、言葉を理解したことになり、本を読んだことになる。
なんだ、当たり前のことじゃないか、と思う人がいるかもしれません。けれども、これから「万葉集」をひもとき、万葉歌に詠まれた古代人の心を生き生きと感じ、それをおもしろく読み解くためには、以上のことを改めて強く意識しておくのはけっして無駄ではないと思います。上野さんはこうも述べます。
<わたしは、古代学を次のように分類している。史料を読み解く歴史学は内科とすれば、直接に土を掘る考古学は外科。そして、古代文学研究は、心療内科であると思っている。飛鳥(あすか)の時代を生きた少女の恋心は、掘り出した土器を見てもわからないし、『日本書紀』にも書いてない。新聞は、一面記事が大切だが、読んでおもしろいのは、三面記事。そして、庶民の声を伝えているのも三面である。だから、国文もおもしろいよ!>
この文章を読みながら、よみがえってきた映画があります。日本では1990年3月に公開された「いまを生きる」という作品です。ピーター・ウィアー監督、4年前に亡くなったロビン・ウィリアムズが主演の名作です。
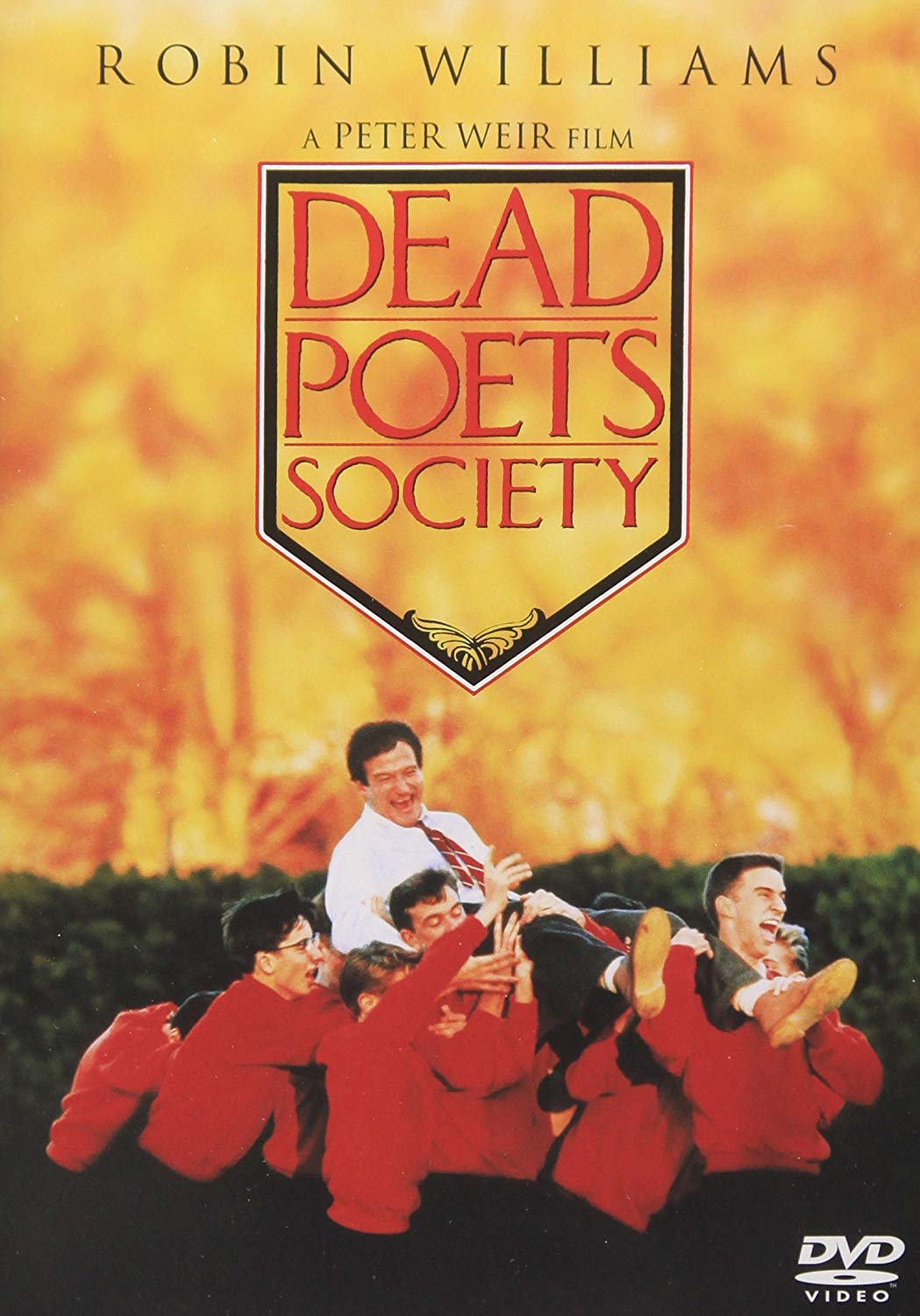
1959年、アメリカの名門進学校ウェルトン・アカデミーに1人の新任英語教師がやってきます。同校OBでもあるジョン・キーティング(ロビン・ウィリアムズ)です。同校の “四柱(four pillars)”――伝統、名誉、規律、美徳――に縛られた厳しい学園生活を送る生徒たちに、キーティングは型破りの授業を行ないます。
口笛を吹きながら最初の授業に現れるなり、生徒たちを教室の外へ連れ出します。そして、ホイットマンの詩などを読みながら、ラテン語の「カーペ・ディエム(Carpe Diem)」ということばを授けます。どういう意味か? “Seize the day(いまを生きろ)”だと教えるのです。
「我々は死ぬ運命なのだ。ここにいる全員、いつか息が止まる日が来て、冷たくなって死ぬ」
次の授業では、学校が採用した英語テキストの冒頭部分、「詩の理解」という概論を、そっくりそのまま「破り捨てろ!」と、生徒に命じて度肝を抜きます。「くそったれ。著者はアホだ。詩はパイプ工事と違う。ヒット・チャートでもない」と。
「自分の力で考えることを学ぶのだ。言葉や表現を味わうことを」
「我々はなぜ詩を読み書くのか。それは我々が人間であるという証なのだ。そして人間は情熱に満ちあふれている。医学、法律、経営、工学は生きるために必要な尊い仕事だ。だが詩や美しさ、ロマンス、愛こそは我々の生きる糧だ」
破天荒な授業ぶりに、最初は「なんだ、こいつ」と戸惑っていた生徒たちも、彼の情熱あふれる指導に次第に魅了されていきます。昔の学生年鑑を探し出した生徒は、そこに在校当時のキーティングを見つけます。サッカー部主将、そして“Dead Poets Society(死せる詩人の会)”を主宰していた、と。
“Dead Poets Society”――それは、寮の近くにある洞窟に集まって、ソローやホイットマンなど古典的な詩人の作品を読み、時には自作の詩を披露しながら、「人生の真髄を吸収する」という会でした。何人かの生徒たちは、この会を復活させようと、深夜、寮を抜け出します。洞窟に集まり、かつての伝統にならって、会の始まりにソローの詩篇を読み上げます。
<私は静かに生きるために森に入った。人生の真髄を吸収するため。命ならざるものは拒んだ。死ぬ時に悔いのないよう生きるため>(*)
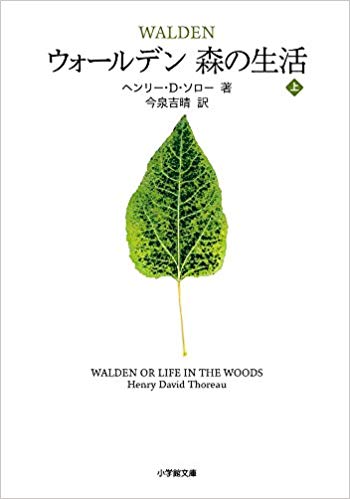
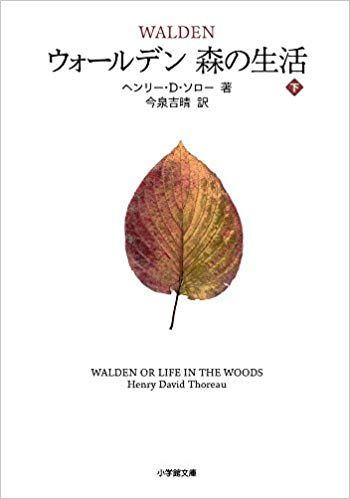
名門大学への進学を最優先する学校や、過大な期待を子どもたちに押しつける親たち。その重圧を息苦しく感じていた生徒たちは、自分の頭で考えること、自分の声に耳を傾けること、物事を常に異なる側面から見直すこと、自分の歩き方を見つけること、というキーティングの教えに目を開かれます。
当然ながら、それはさまざまな摩擦や衝突を招きます。キーティング自身、学校長から「君の教え方はえらく変わっているそうだな」「当校にはカリキュラムがある」とクギを刺されます。「教育とは独立心を養うこと」とキーティングは反論しますが、「彼らの齢ではムリだ。伝統や規律を重んじろ。生徒を大学に進学させればよいのだ」と撥ねつけられます。
そうした中で、俳優の夢を追い始めた生徒が、父親の意志に背いて、シェイクスピア『夏の夜の夢』の舞台に立ちます。主役のパック役を見事に演じ、観客から万雷の拍手を受けたにもかかわらず、父親の逆鱗に触れてしまいます。
なぜ親に逆らうのか? 許すわけにはいかない。明日陸軍学校に転校して、それからハーバードへ行き、医者になれ! お前の可能性を無駄にはさせんぞ。くだらん芝居がいいか? そんなものは忘れてしまえ!
矢継ぎ早に息子を責め立て、追い込みます。そしてその夜、あってはならないことが起きてしまいます。
学校側は事態を重く見て、責任の一切をキーティングに押しつけ、“収拾”を図ります。キーティングは学校を追われ、生徒たちの前から去ることになります。
最後の場面は、真相を知りながら、キーティングに責任を負わせることに“加担”してしまった生徒たちが、去りゆくこの熱血教師に自分たちの思いを伝えようとするシーンです。勇気をふるって、ひとりひとりが師に対する感謝と敬意を、彼らにもっともふさわしい方法で伝えます。“Thank you, boys. Thank you.”――笑顔を浮かべたキーティングが、教室を後にします。
「いまを生きる」という日本語タイトルも、原題の“Dead Poets Society”も、上野さんの本にまっすぐつながります。上野さんの本ではかなりのページ数を割いて、『徒然草』第93段が紹介されています。お気に入りの文章だといいます。
「人、死を憎まば、生(しょう)を愛すべし。存命の喜び、日々に楽しまざらんや」
「人皆(みな)生を楽しまざるは、死を恐れざる故なり。死を恐れざるにはあらず、死の近きことを忘るるなり」
牛の売買の話を手がかりに、吉田兼好が自らの死生観を述べた段です。この話も映画の「カーペ・ディエム(いまを生きよ)」と響き合うものです。『万葉集』や『徒然草』、そして“Dead Poets Society”で愛誦(あいしょう)されるソローやホイットマン。
実は、昨晩の「万葉集講座」初回も、『万葉集』とシェイクスピアとの「掛け合い」に挑む(上野さんとシェイクスピア研究者の河合祥一郎さん)という、かなりアクロバティックな試みをやりました。詳しくは次回の報告に譲りたいと思いますが、1300年前の日本と、400年前の英国の文学との、一種の“マリアージュ(絶妙な組合せ)”に挑んでみました。

さて、「死」ということばが出てくると、どうしても気分が沈んでしまうという方のために、最後に上野さんらしいエピソードを紹介したいと思います。
この本で初めて知ったのですが、上野さんのお母さまは、昔から俳句をやっておられたそうです。一家の歩みを詠んだ俳句が、上野家の記憶のファイルのようになっています。
<受験の偏差値に苦しんで、やっと東京の私大に滑り込んだ私は、福岡から上京した。そんなある日、とある新聞の俳句の欄が目にとまったのである。
一流に少し外れて入学す
なかなかいい句だなぁー‥‥と思いつつ、うどんをすすっていたのだが、思わず吹き出してしまった。作者のところを見ると「福岡 上野繁子」とあったのである。
そういえば、第一志望の高校に不合格になった日の母の「迷言」を思い出した。「学生食堂も無いような高校に入学しなくてよかった。弁当が大変だ。第二志望でよかった」と。さすが、わが母である。>
俳優になる夢を打ち砕かれたウェルトン・アカデミーの生徒とは、何と対照的な親子であることか! かくて「万葉集講座」は、「おもしろい」「たのしい」から出発して、それをゴールにしたいと願います。

2018年11月29日
ほぼ日の学校長
*字幕翻訳・松浦美奈。H・D・ソロー『ウォールデン 森の生活』(今泉吉晴訳、小学館文庫)では、下記のようになっています。
<私が森で暮らしてみようと心に決めたのは、人の生活を作るもとの事実と真正面から向き合いたいと心から望んだからでした。生きるのに大切な事実だけに目を向け、死ぬ時に、じつは本当には生きてはいなかったと知ることのないように、生活が私にもたらすものからしっかり学び取りたかったのです。>












